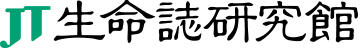常時働く

11歳の頃。弟(左)と。

高校の修学旅行で。(右端:本人)
京大動物学教室へ


Scientist Library:
生命誌30号
『ルイセンコの時代があった 生物学のイデオロギーの時代に』
岡田節人
ホヤとの出会い

白上先生と。京都大学瀬戸臨海実験所の前で。
発生の時間を計る
当時日本ではホヤの初期発生の研究は行われていませんでした。ホヤには群体をつくる仲間があるのですが、そのホヤが2匹出会ったときに融合するかしないかは遺伝的に決まっているとか、あるいは単体のホヤは雌雄同体なのに自家受精しない仕組みがあるというような、自己認識の実験は盛んに行われていたのですが。僕は東北大学の臨海実験所にホヤの扱い方を習いに行き、東北地方を中心に分布するマボヤで発生研究を始めました。

左.成体のマボヤ。 右.研究棟の地下で飼育中のカタユウレイボヤ。

東北大学浅虫臨海実験所での研究集会に来日したホヤ発生学の友人ウィリアム・ジェフェリーと。
学生が広げるホヤ研究の輪

カタユウレイボヤの発生様式。わずか18時間で2,600程度の細胞からなるオタマジャクシ型幼生になる。(写真提供:西方敬人・甲南大学理工学部教授)

1991年、日本動物学会賞受賞記念パーティーにて。
発生と進化をつなぐ
1987年のある日、発生学のライバルである団まりなさん(元大阪市立大学教授、現階層生物学研究ラボ)が『個体発生と系統発生』と題する著作を送ってきてくれました。同封の手紙には、「自分は自分の考えを本にしてきちんと著した。これが本当の生物学者のやることである。おまえのようにくだらない論文を山ほど書いているのはさみしいことだ」とありました。早速読んでみると、序章に「比較発生学や、系統発生と個体発生の問題に興味を持つこと自体が、発生学者としての体質の古さを示すものとされるようになり、この問題は、ついには一種禁句のようになってしまうのである」とあったのです。僕は即座に「全くそうは思わない。問題の大きさに直面して筆を持てないでいるだけ」と反論のメモを書きました。団さんはこれまで行われた発生研究のデータを用いて、さまざまな動物の関係を見るという試みをされたわけだけれど、僕はまだ今の段階ではそれはできないと考えていました。興味はあるけれど、あまりにも大きなテーマで何をすればいいのかわからなかったのです。

団まりなの著書への反論メモ
ウッズホール代理講師
サマースクールの講師を務めた米国ウッズホール海洋生物学研究所。左から3人目はウニの共同研究をしたエリック・デビッドソン博士。(左から2人目:本人)
脊索動物の形づくり

研究室の新歓コンパにて。

試薬棚の前で。朝から晩まで実験三昧。
ホヤゲノムを読む

Scientist Library:
生命誌46号
『DNAのふえ方から見えた生きものの姿』
吉川寛

岡田節人先生(左)の文化勲章受章記念パーティーにて。

ゲノム解読後に開かれたジャンボリーに世界中の研究者が目当ての遺伝子を探しに集合。(前列左から2人目:本人)
ゲノムから発生と進化をさぐる

ホヤ胚の遺伝子ネットワークの概略。
カタユウレイボヤ統合型webデータベースより。

進化発生学の専門誌『Development, Genes and Evolution』2003年6月号。1冊が丸ごと研究室の論文で埋まった。

研究室のメンバーと大学の駅伝大会に参加。(前列左から3人目:本人)

雪国育ちなのでスキーは趣味。
200%の努力



研究について語る。

ホヤの飼育室も兼ねた実験室。75歳くらいまで現役で研究したい。

ホヤとナメクジウオが脊索動物であることを明らかにした先人を記念してつくられたアレキサンダー・コワレフスキーメダル。賞に興味はないけどこれは嬉しい。