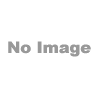「酔いどれ船」を書いたとき、ランボオはまだ海を見たことがなかった。しかし、彼は子供の頃からムーズ河で舟遊びをして、水と波に親しんできた。またシャルルヴィルのマドレーヌ河岸から、毎日のように広いムーズを眺めて、船旅の夢をはぐくんでいたであろう。
また大読書家の少年はすでに、海と航海に関する多くの本を読んでいた。エドガ・ポーの『アーサ・ゴードン・ピムの冒険』、ジゥル・ヴェルヌの『海底二千里』、ボードレールの『旅』、キャプテン・クックの『旅行記』、ヴィクトル・ユゴーの『海の労働者』『諸世紀の伝説』などなど。とりわけ当時の著者たちにひろく愛読されていたフィギエの『大洋の世界』とミッシュレの『海』が、ランボオの想像をかきたてた。
それに自分の家やよその家で読んだ『絵入り雑誌』『世界めぐり』誌などの記事もそれに加えられよう。だが、たとえ「酔いどれ船」に影響を与えた源泉、原典がわかったとしても、それらはただちに「酔いどれ船」を説明するものではない。重要なのは、ランボオがそれらの素材をどのようにおのれの詩に変えたかであって、そこにランボオの天才がかかっている。
また、船という主題はしばしばパルナッス派の詩に現われている。とりわけマラルメの『海の微風』、ディエルクスの『老いた孤独者」などがこの主題を発展させていた。ランボオもふたたびこの主題をとりあげたが、しかし彼はそこに彼自身の強烈な体験をもりこむことによって、独創的な一大傑作をつくりだしたのである。
内容の点からみれば、M・A・リュフの指摘するように、「酔いどれ船」は、その頃の作者ランボオの体験を詩によって告白したものである。つまり作者の体験の詩的表現である。したがって、この詩は根拠のない、気ままな幻想、幻影ではなく、ひとつの自叙伝的な物語である。そこにはランボオの人生を激動させた、あの精神的冒険が歌われているからである。──この点は、「酔いどれ船」の解釈だけでなく、ランボオ理解にとっても重要な意味をもっている。多くの批評家は、「酔いどれ船」をたんなる幻想による、壮大怪異なイメージからなる航海記とみなしている。そうではなくて、ランボオはここでも、それら屈折した怪異なイメージをとおして、おのれの内面生活を歌っているのである。
(つづく)
(新日本新書『ランボオ』)
- 関連記事
-
-
 「酔いどれ船」について (3)
2019/08/28
「酔いどれ船」について (3)
2019/08/28
-
 「酔いどれ船」について (2)
2019/08/27
「酔いどれ船」について (2)
2019/08/27
-
 「酔いどれ船」について
2019/08/26
「酔いどれ船」について
2019/08/26
-
 「酔いどれ船」(2)ヴェルレーヌの手紙
2019/08/23
「酔いどれ船」(2)ヴェルレーヌの手紙
2019/08/23
-
 「酔いどれ船」(1)
2019/08/22
「酔いどれ船」(1)
2019/08/22
-
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)