「井上井月」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
m lk |
||
| 18行目: | 18行目: | ||
[[明治]]2年︵[[1869年]]︶、[[富県村]]︵現[[伊那市]]︶の日枝神社の奉納額を揮毫。翌年には東春近村の五社神社、西春近村の地蔵堂の奉納額を揮毫。この後も、たびたび社寺の奉納額を手がけている。明治5年︵[[1872年]]︶9月、伊那村にて﹁柳廼舎送別書画展覧会﹂が開催され、出席者は113名を数えた。明治7年︵[[1874年]]︶、[[美篶村]]︵現伊那市︶の橋爪玉斎と句画を合作している。明治9年︵1876年︶9月、伊那町の唐木菊園のもとで、﹃菊詠集序﹄を執筆。
|
[[明治]]2年︵[[1869年]]︶、[[富県村]]︵現[[伊那市]]︶の日枝神社の奉納額を揮毫。翌年には東春近村の五社神社、西春近村の地蔵堂の奉納額を揮毫。この後も、たびたび社寺の奉納額を手がけている。明治5年︵[[1872年]]︶9月、伊那村にて﹁柳廼舎送別書画展覧会﹂が開催され、出席者は113名を数えた。明治7年︵[[1874年]]︶、[[美篶村]]︵現伊那市︶の橋爪玉斎と句画を合作している。明治9年︵1876年︶9月、伊那町の唐木菊園のもとで、﹃菊詠集序﹄を執筆。
|
||
明治12年︵[[1879年]]︶3月、[[上水内郡]]︵現[[長野市]][[中条村|中条]]︶の久保田盛斎のもとで、﹃俳諧正風起證﹄を執筆。この頃、当地に庵を立てて定住しようと試みたことが久保田宛の書簡から読み取れる。同書簡中には、新しい庵に移住するため、[[長岡]]で戸籍を取る必要を述べているが、これも井月の出自の論拠となっている。しかし、手続き上に問題があり、定住は叶わず、南信州に帰還した。
|
明治12年︵[[1879年]]︶3月、[[上水内郡]]︵現[[長野市]][[中条村 (長野県)|中条]]︶の久保田盛斎のもとで、﹃俳諧正風起證﹄を執筆。この頃、当地に庵を立てて定住しようと試みたことが久保田宛の書簡から読み取れる。同書簡中には、新しい庵に移住するため、[[長岡]]で戸籍を取る必要を述べているが、これも井月の出自の論拠となっている。しかし、手続き上に問題があり、定住は叶わず、南信州に帰還した。
|
||
明治18年([[1885年]])秋ごろ、句集『余波の水茎(なごりのみづぐき)』を刊行。本書は、井月が集めた諸家の発句をまとめ、井月の弟子であった美篶村の塩原梅関(本名折治)が開板したものである。本書の跋として井月は、後に代表句と評される「'''落栗の座を定むるや窪溜り'''」を、「柳の家」の署名とともに残している。同年、井月の健康を案じた塩原梅関の取り計らいにより塩原家に入籍し、'''塩原清助'''と名乗る。 |
明治18年([[1885年]])秋ごろ、句集『余波の水茎(なごりのみづぐき)』を刊行。本書は、井月が集めた諸家の発句をまとめ、井月の弟子であった美篶村の塩原梅関(本名折治)が開板したものである。本書の跋として井月は、後に代表句と評される「'''落栗の座を定むるや窪溜り'''」を、「柳の家」の署名とともに残している。同年、井月の健康を案じた塩原梅関の取り計らいにより塩原家に入籍し、'''塩原清助'''と名乗る。 |
||
2012年2月24日 (金) 04:00時点における版

| 文学 |
|---|
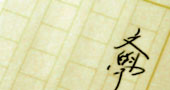 |
| ポータル |
|
各国の文学 記事総覧 出版社・文芸雑誌 文学賞 |
| 作家 |
|
詩人・小説家 その他作家 |
井上 井月︵いのうえ せいげつ、文政5年︵1822年︶? - 明治20年2月16日︵1887年3月10日︶[1]︶は、日本の19世紀中期から末期の俳人。本名は一説に井上克三︵いのうえかつぞう︶。別号に柳の家井月。信州伊那谷を中心に活動し、放浪と漂泊を主題とした俳句を詠み続けた。その作品は、後世の芥川龍之介や種田山頭火をはじめ、つげ義春などに影響を与えた。

下島勲による﹁乞食井月﹂の素描
井月は独特な語彙をよく用いているが、口癖としてもっとも著名なのが﹁千両千両﹂である[6]。
﹁謝辞、賞賛詞、賀詞、感嘆詞として使用するは勿論、今日は、左様ならの挨拶まで、唯この千両千両……を以て済ます﹂[7]という。饗応の際に相好を崩して﹁千両千両﹂と繰り返したという逸話が、数多く言い伝えられている。
井月の酒好きは当時、伊那谷一帯に知れ渡っていた。当然、井月には酒にまつわる句が数多く残されている。秋の新酒を詠んだ﹁親椀につぎ零︵こぼ︶したり今年酒﹂、雪の日に残した﹁別れ端のきげむ直しや玉子酒﹂など、季節それぞれの酒を句にしている。また、新酒が出来たことを知らせる酒屋の杉玉を指す﹁さかばやし﹂を詠み込んだ﹁油断なく残暑見舞やさかばやし﹂﹁朝寒の馬を待たせたさかばやし﹂[8]などの句は、幕末から明治初期の伊那谷の一点景を表している[9]。
井月は接待の酒肴や趣を逐一記録しており、現存する日記などを合わせると、明治16年12月から明治18年4月までの約1年半の、伊那谷における井月の寄食寄宿生活の動向がうかがえる。その中で、おのおのの家造りの濁り酒を﹁手製﹂と呼んで鍾愛している。一方で、家の主人がいなかったため家人に粗末に扱われたり、厄介払いをされた場合は、日記に﹁風情なし﹂﹁粗末﹂、さらには﹁酒なし﹂﹁風呂なし﹂といちいち書き留める性格であった。
また、伊那谷の人士は、俳句作品ばかりでなく、井月の墨書、筆跡も珍重していた。﹁芭蕉に似た趣のあるばかりか、光悦などのある特殊な作をさへ偲ばせる高雅な書品﹂︵下島勲の評︶。特に井月は松尾芭蕉の﹃幻住庵記﹄︵約1300字︶を暗記しており、ある紺屋の店先で、酒を飲みながら唐紙4枚に何の手本も無く、1000字以上をしたためたという。この﹃幻住庵記﹄の筆跡を見た芥川龍之介は﹁入神と称するをも妨げない﹂と評した。
以上のように、芭蕉を慕った井月の句は多数存在する。この点から、月並俳句が横行した幕末・明治初期にかけて、蕉門の再評価を目指した井月の姿勢がうかがわれる。その一方で、﹁鵜﹂の句の例にあるように、物事の全体を捉える芭蕉の感覚に対して、細部のみに収まってしまう井月の句柄の小ささも指摘されている[10]。 また、井月は﹃俳諧雅俗伝﹄という文章を明治8年に染筆しているが、これは甲州の俳人である早川漫々の残した文章の要諦を写したもので、井月が正風俳諧の影響を受けていることが伺える また、井月は同じ幕末期の俳人である小林一茶ともよく比較される︵一茶が65歳で没したとき、井月は5歳︶。特に、一茶の冬の句﹁ともかくもあなた任せの年の暮﹂、新年句﹁目出度さもちう位也おらが春﹂、に対して、井月が﹁目出度さも人任せなり旅の春﹂を残している点が注目される。これらの俳句の比較から、一茶の浄土真宗的な思想[11]と無常観に対して、井月の現世肯定性、楽天性が指摘されている[12]。 また、井月は発句ばかりでなく、連句を巻くことも多かった。﹃井月全集﹄には64篇の連句が残されている。
放浪俳人井月
井月は文政5年︵1822年︶、越後の長岡藩生まれと推測されている。井月の少年期から30代半ばまでの行状は全く不明であるが、巷説によると天保10年︵1839年︶には一旦江戸に出ているという[2]。 嘉永5年︵1852年︶に長野にて版行された、吉村木鵞の母の追悼集に、井月の発句﹁乾く間もなく秋暮れぬ露の袖﹂が見える。また、翌年、同じく長野で開板された吉村木鵞編纂の句集﹃きせ綿﹄に、﹁稲妻や網にこたへし魚の影﹂の句が採られている。従って、この頃には俳人として活動していたと推測される。 安政5年︵1858年︶ごろ、30代後半の壮年であった井月は伊那谷を訪れる。以来約30年の間、死去するまで上伊那を中心に放浪生活を送り続けた。元来、﹁多少好学の風があり、風流風雅を嗜む傾き﹂のある土地[3]であったため、俳諧の師匠として井月は伊那谷の人士に歓迎された。こうして井月は伊那谷の趣味人たちに発句の手ほどきをしたり、連句の席を持ったり、詩文を揮毫する見返りとして、酒食や宿、いくばくかの金銭などの接待を受けつつ、南信州一帯を放浪した。 井月は﹁典型的な酒仙の面影が髣髴とする﹂ほどの酒好きであった。そのため、﹁人の顔さえ見れば酒を勧める﹂、悠長な土地柄であった伊那谷は、ほとんど金銭を持たず、蓄えも無かった井月にとって、いつでも酒の相伴にあずかることの出来る、魅力的な土地であった。体中虱だらけで、直ぐに泥酔しては寝小便をたれたという井月を、土地の女性や子供たちは﹁乞食井月﹂と呼んで忌避したが、俳句を趣味とする富裕層の男性たちが井月を優遇し、中には弟子として師事するものもいた[4]。 文久3年︵1863年︶5月、高遠藩の当時の家老・岡村菊叟と面会し、句集﹃越後獅子﹄の序文を乞う。﹃越後獅子﹄は井月が京都、江戸、大阪をはじめ、各国の俳人の発句を集めた句集であり、書名は菊叟の命名による。また、この序文は、井月が長岡出身と自称していたことを記した最初の記録となる。 元治元年︵1864年︶、善光寺宝勝院の梅塘をたずね、100日間ほど滞在し、﹃家つと集﹄を編集する。 明治2年︵1869年︶、富県村︵現伊那市︶の日枝神社の奉納額を揮毫。翌年には東春近村の五社神社、西春近村の地蔵堂の奉納額を揮毫。この後も、たびたび社寺の奉納額を手がけている。明治5年︵1872年︶9月、伊那村にて﹁柳廼舎送別書画展覧会﹂が開催され、出席者は113名を数えた。明治7年︵1874年︶、美篶村︵現伊那市︶の橋爪玉斎と句画を合作している。明治9年︵1876年︶9月、伊那町の唐木菊園のもとで、﹃菊詠集序﹄を執筆。 明治12年︵1879年︶3月、上水内郡︵現長野市中条︶の久保田盛斎のもとで、﹃俳諧正風起證﹄を執筆。この頃、当地に庵を立てて定住しようと試みたことが久保田宛の書簡から読み取れる。同書簡中には、新しい庵に移住するため、長岡で戸籍を取る必要を述べているが、これも井月の出自の論拠となっている。しかし、手続き上に問題があり、定住は叶わず、南信州に帰還した。 明治18年︵1885年︶秋ごろ、句集﹃余波の水茎︵なごりのみづぐき︶﹄を刊行。本書は、井月が集めた諸家の発句をまとめ、井月の弟子であった美篶村の塩原梅関︵本名折治︶が開板したものである。本書の跋として井月は、後に代表句と評される﹁落栗の座を定むるや窪溜り﹂を、﹁柳の家﹂の署名とともに残している。同年、井月の健康を案じた塩原梅関の取り計らいにより塩原家に入籍し、塩原清助と名乗る。 明治19年︵1886年︶12月末ごろ、伊那村にて病のため道に行き倒れているのを発見される。塩原家に運び込まれ看病を受けるが、翌年の明治20年︵1887年︶2月16日に、66歳にて没する[1]。 大正9年︵1920年︶、塩原家にて三十三回忌が営まれ、句碑が建てられている。出自について
井月の出自については諸説あるが、ほとんど不明である。没年から逆算すると文政5年︵1822年︶生まれとなる。﹁本名が井上克三であり、越後長岡藩出身である﹂ことを、高遠藩家老の岡村菊叟に告げているが、長岡藩の文書が現存していないため確定されていない。他には、世話になった酒屋への書簡一通に﹁井上克三﹂との署名があり、また、塩原家に入籍後、義理の娘に婿養子を斡旋するための口上書に﹁末広侍人井上井月﹂との自署を残している。 また、井月の作品の一部に、越後方言に顕著な﹁イ音﹂と﹁エ音﹂の混同が見られるため、これを越後地方出身の証拠とする論もある[5]。人柄・句柄について

作品について
井月は芭蕉忌に際して﹁我道の神とも拝め翁の日﹂という句を残すほどに、松尾芭蕉を尊敬していた。 芭蕉句 象潟や雨に西施が合歓の花 ほろほろと山吹散るか滝の音 面白うてやがて悲しき鵜舟かな 井月句 象潟の雨なはらしそ合歓の花 山吹に名をよぶ程の滝もがな すくむ鵜に燃くず折るゝかゞり哉以上のように、芭蕉を慕った井月の句は多数存在する。この点から、月並俳句が横行した幕末・明治初期にかけて、蕉門の再評価を目指した井月の姿勢がうかがわれる。その一方で、﹁鵜﹂の句の例にあるように、物事の全体を捉える芭蕉の感覚に対して、細部のみに収まってしまう井月の句柄の小ささも指摘されている[10]。 また、井月は﹃俳諧雅俗伝﹄という文章を明治8年に染筆しているが、これは甲州の俳人である早川漫々の残した文章の要諦を写したもので、井月が正風俳諧の影響を受けていることが伺える また、井月は同じ幕末期の俳人である小林一茶ともよく比較される︵一茶が65歳で没したとき、井月は5歳︶。特に、一茶の冬の句﹁ともかくもあなた任せの年の暮﹂、新年句﹁目出度さもちう位也おらが春﹂、に対して、井月が﹁目出度さも人任せなり旅の春﹂を残している点が注目される。これらの俳句の比較から、一茶の浄土真宗的な思想[11]と無常観に対して、井月の現世肯定性、楽天性が指摘されている[12]。 また、井月は発句ばかりでなく、連句を巻くことも多かった。﹃井月全集﹄には64篇の連句が残されている。
後世への影響
この節の加筆が望まれています。 |
井月は自身の句集は残さなかったが、伊那谷の各地に発句の書き付けを残していた。伊那谷出身の医師であり、自らも年少時に井月を見知っていた下島勲︵俳号‥空谷︶は、井月作品の収集を思い立ち、伊那谷に居住していた実弟の下島五老に調査を依頼。そして大正10年︵1921年︶、﹃井月の句集﹄を出版する。本書の巻頭には、高浜虚子から贈られた﹁丈高き男なりけん木枯らしに﹂の一句が添えられている。この句が松尾芭蕉﹃野ざらし紀行﹄の発句﹁狂句木枯の身は竹斎に似たる哉﹂を踏まえている点から、虚子が井月を芭蕉と比較していたことが分かる[13]。
また、下島が芥川龍之介の主治医であった縁から、﹃井月の句集﹄の跋文は芥川が執筆している。芥川は﹁井月は時代に曳きずられながらも古俳句の大道は忘れなかつた﹂と井月を賞賛している。また、芥川は﹁咲いたのは動いているや蓮の花﹂を井月の最高傑作と称揚しているが、皮肉にもこの俳句は井月の俳友であった橋爪山洲の作品であることが、芥川の没後に判明した[14]。
昭和5年︵1930年︶10月には、下島勲・高津才次郎編集による﹃井月全集﹄が出版される。﹃井月の句集﹄に掲載された虚子らの﹁井月賛﹂俳句と、芥川の序文はこの全集にも再掲され、井月の評価を高める役割を果たした。また、本全集には、井月が残した日記も収録されている。
昭和13︵1938年︶、上伊那郡東部教育会が国語副読本として﹃井月さん﹄を出版する。
昭和31年︵1956年︶、作家の石川淳が伊那市を訪ねて井月の取材を行い、当時﹃文藝春秋﹄に連載していた﹁諸国畸人伝﹂の一篇として﹁信濃国無宿風来俳人井月﹂を執筆。
昭和49年︵1974年︶11月、﹃井月全集﹄の増補復刻版として﹃井上井月全集﹄が伊那毎日新聞社から出版され、決定版とされる。
昭和62年︵1987年︶には、井月没後100年を迎えて﹁井月百年祭﹂が開催され、句碑が3基建立された他、関係図書の復刊や、記念俳句大会などが行われた。
種田山頭火への影響
井上井月に影響を受けた一人に、自由律俳人の種田山頭火が挙げられる。 山頭火日記の﹁昭和5年8月2日﹂の項に﹁樹明兄が借して下さつた﹃井月全集﹄を読む、よい本だつた、今までに読んでゐなければならない本だった、井月の墓は好きだ、書はほんとうにうまい﹂とある通り、山頭火は井月の句を繰り返し読み、思慕の情を持つようになる。昭和9年︵1934年︶3月、52歳の山頭火は井月の墓参を決意し、山口から伊那谷に向けて東上する。しかし、清内路峠付近は雪が深く、4月に信州飯田市に入ったところで肺炎を発症し、2週間緊急入院することとなり、墓参を諦める。 その4年後、昭和14年︵1939年︶3月31日、再び山口を出立し、5月3日、列車で天竜峡駅に着く。その後、伊那谷に向かい、俳人であり伊那高女教諭だった前田若水の家に立ち寄り、若水の案内を得てようやく井月の墓参を果たす。山頭火の﹁風来居日記﹂の5月3日の項には、墓参の様子が100行ほどに渡って記されており、その中に、井月の墓を前にしての即吟を4句残している。井月の墓を前にして ・お墓したしくお酒をそゝぐ ・お墓撫でさすりつゝ、はるばるまゐりました ・駒ヶ根をまへにいつもひとりでしたね ・供へるものとては、野の木瓜の二枝三枝日記の中に﹁私は芭蕉や一茶のことはあまり考えない、いつも考えているのは路通や井月のことである。彼等の酒好きや最後のことである﹂と書きつけている通り、山頭火は井月の作品と生き方に影響を受けたと考えられ、蕉門の乞食僧俳人であった八十村路通などと合わせて、そこに放浪俳人の系譜を見ることもできる[15]。
つげ義春への影響
漫画家のつげ義春は、漫画作品﹃無能の人﹄の最終話である第6話﹁蒸発﹂に、井月を詳しく描いている︵初出は1986年12月、﹁COMIC ばく﹂︶。河原で石を売る主人公が、病人のふりをしながらよたよた歩く無為徒食の古書店主人山井︵病をもじったもの︶からむりやり貸し付けられた﹃漂泊俳人 井月全集﹄を読む。そして、井月の半生をその死まで思い描きつつ、井月に自らや山井の姿を重ね合わせ、感慨にふけるという筋書きになっている。最後は﹁井月も山井も大馬鹿ものだよ……﹂という主人公のセリフで締めくくられる。 ﹁蒸発﹂には以下のような句が引用されている。- 降るとまで 人には見せて 花曇り
- 落栗の 座を定めるや 窪溜り
- 石菖や いつの世よりの 石の肌
- 何処やらに 鶴の声きく かすみかな
脚註
(一)^ ab高津才次郎による、高遠市河南の龍勝寺の過去帳調査から。この過去帳が旧暦で記されているため、あえて旧暦表示で記す。新暦は逆算されたもの︵﹃井月全集﹄参照︶
(二)^ ﹃井上井月全集﹄の記載による
(三)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、26p
(四)^ ﹃井月全集﹄における下島勲の述懐による
(五)^ 例えば、﹁万歳や人が笑ひばしたり顔﹂の﹁ひ﹂など。本来ならば﹁笑へば﹂。宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、14-15p
(六)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、33p
(七)^ ﹃井月全集﹄における高津才次郎の記述
(八)^ どちらの句も﹁さかばやし﹂は本来は漢字1字。穴︵あなかんむり︶の下に巾。
(九)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、45p
(十)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、177p
(11)^ ﹁あなた任せ﹂の﹁あなた﹂とは、阿弥陀如来と解されている。従って、一茶のこの句は、浄土真宗的な他力本願を主題としている
(12)^ 宮脇昌三﹁芭蕉・一茶と井月﹂、﹃井月の俳境﹄所収
(13)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、7-8p
(14)^ 宮脇昌三﹃井月の俳境﹄、鞜青社、1987、11p
(15)^ 中井三好﹃漂泊の俳人 井上井月記﹄他参照
参考文献
- 瓜生卓造『漂鳥のうた 井上井月の生涯』、牧羊社、1982
- 宮脇昌三『井月の俳境』、鞜青社、1987
- 江宮隆之『井上井月伝説』、河出書房新社、2001
- 春日愚良子『井月の風景』、ほおずき書籍、2006
- 中井三好『漂泊の俳人 井上井月記』、彩流社、2007
- つげ義春『無能の人・日の戯れ』、新潮文庫、1998
