弁論術 (アリストテレス)
表示
| アリストテレスの著作 (アリストテレス全集) |
|---|
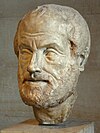 |
| 論理学 |
|
オルガノン: 範疇論 - 命題論 分析論前書 - 分析論後書 トピカ - 詭弁論駁論 |
| 自然学 |
|
自然学 - 天体論 生成消滅論 - 気象論 霊魂論 - 自然学小論集 動物誌 動物部分論 - 動物運動論 動物進行論 - 動物発生論 |
| 形而上学 |
| 形而上学 |
| 倫理学 |
|
ニコマコス倫理学 エウデモス倫理学 |
| 政治学 |
|
政治学 アテナイ人の国制 |
| 制作学 |
| 弁論術 - 詩学 |
| その他 |
| 断片集 - 著作目録 |
| 偽書及びその論争がある書 |
|
宇宙論 - 気息について 小品集 - 問題集 大道徳学 - 徳と悪徳について 経済学 アレクサンドロスに贈る弁論術 |
﹃弁論術﹄︵べんろんじゅつ、古代ギリシャ語: Τέχνη Ῥητορική, Technē Rhētorikē、羅: Ars Rhetorica、英: Art of Rhetoric︶は、アリストテレスによって書かれた弁論術︵レートリケー、レトリック︶についての著作。
古代ギリシャの弁論術を理論的・体系的にまとめ上げた古典の傑作であり[1]、キケロやクインティリアヌスなど、古代ローマにおける弁論術︵修辞学︶の代表人物らによっても言及されている[2][注釈 1]。
アリストテレスの著作では、﹃詩学﹄と共に、制作学︵創作学︶に分類される著作であり、ベッカー版では、﹃詩学﹄︵や﹃アレクサンドロスに贈る弁論術﹄︶と共に最後尾にまとめられている。
ルネサンス期の人文主義者や、19世紀の文献学者によって翻訳・編纂が行われてきたが、20世紀に入り、哲学者や政治学者によって注目されるようになった[4]。
予備知識[編集]
レトリック︵レートリケー︶の意味[編集]
レトリック︵レートリケー︶は、現代日本においては﹁修辞学﹂と訳され、単に言葉を飾り立てるだけの技術ばかりが注目されがちだが[5]、アテナイをはじめとする古代ギリシャにおける元々の意味は、議会、法廷、公衆の面前などにおいて、聴衆を魅了・説得する、あるいは押し切るための、実践的な﹁雄弁術﹂﹁弁論術﹂﹁説得術﹂であり、アリストテレスがこの書で論じているのも、まさにその意味でのレトリック︵レートリケー︶である。 なお、このレートリケー︵弁論術︶は、元々はシケリアの法廷弁論として発達したものであり[6]、その創始者・大成者は、コラクス及びその弟子のテイシアスとされる[7]。弁証術︵ディアレクティケー︶と弁論術︵レートリケー︶[編集]
アリストテレスの師であるプラトンが、弁論術︵レートリケー︶に対して批判的な見解を持っていたことはよく知られており、それは彼の著作である﹃ゴルギアス﹄や﹃パイドロス﹄等で、明確に述べられている。 ﹃ゴルギアス﹄において、プラトンは、弁論術︵レートリケー︶は本来﹁人々の魂︵知見︶を善くする︵ことで国家・社会全体を善くする︶﹂ことを目的としているべき﹁政治術﹂の一部門である﹁司法・裁判の術﹂に寄生しているものであり、対象に対する知識・技術を持ち合わせないまま、人々の短絡的な﹁快﹂につけ込んで無知な人々を釣り、真実や魂を善くすることから彼らを遠ざけ、その目を覆い隠してしまうだけのものであり、ただの﹁熟練の業﹂に過ぎず、醜く劣悪なもので、技術︵テクネー︶と呼べるようなものではなく、﹁化粧法﹂﹁料理法﹂﹁ソフィストの術︵詭弁術/論争術︶﹂と並んで﹁迎合 (追従/へつらい)﹂︵コラケイア︶と呼ぶべきものだとして批判している。 また、﹃パイドロス﹄においても、プラトンは、弁論術︵レートリケー︶が、対象についての真実を知らないまま、相手の魂を事物の真相から逸らして誘導していくことを目的とし、相手がどう考えるかばかりを追求していくだけの、﹁言論︵ロゴス︶の技術︵テクネー︶﹂と呼ぶに値しないものであると批判する。一方、それとは対照的に、定義・綜合・分析︵分割︶を備え、雑多な情報から対象のただ1つの本質的な相を導き出していける弁証術[8]︵弁証法、問答法、ディアレクティケー︶こそが、真に﹁言論︵ロゴス︶の技術︵テクネー︶﹂と呼ぶに値するものであると述べている[9]。彼が対話篇で描く﹁弁論家・ソフィストたちを論破するソクラテス﹂というモチーフは、全てその﹁小手先の弁論術︵レートリケー︶に対する弁証術︵ディアレクティケー︶の優位﹂を表現するためのものである。 さらに、プラトンは、その弁証術︵ディアレクティケー︶を通じた真実の把握は、﹁並々ならぬ労苦﹂を伴うものであり、それがたかだか人間を説得するという﹁矮小な目的﹂の下になされるべきではなく、﹁神々の御心にかなうように﹂、すなわち﹁純粋に真実を恋い慕い、より善い魂を成就する[10]﹂という﹁大きな目的﹂の下になされるべきであると説き、弁論術︵レートリケー︶という営みそのものを拒絶・破棄している[11]。これが彼の考えた﹁哲学者﹂︵愛知者、ピロソポス︶像である。 ︵ただし、﹁次善の国制﹂を模索する現実主義的な性格が強まる後期の作品である﹃政治家﹄においては、プラトンは﹁真の政治家︵王者︶の統治﹂に協力して、﹁正義を実行﹂するように﹁国民を説得・指導﹂する限りにおいて、という条件付きで、﹁弁論術﹂を、﹁戦争術﹂﹁裁判術﹂と並ぶ国家運営上の重要技術として認定し、言及している[12]。︶ それに対して、アリストテレスは、プラトンのように﹁弁論術︵レートリケー︶そのものを拒絶・破棄する﹂ところまではいかず、弁論術︵レートリケー︶を弁証術︵ディアレクティケー︶と相通ずる技術︵テクネー︶として認めている。ただし、基本的な構えとしては、上記のプラトンの考えを継承しており、従来の印象操作的・扇情的な部分ばかりが強調されてきた指南書を批判しつつ、それらとは一線を画し、説得推論︵省略三段論法、エンテュメーマ︶を技術の中心に据え、バランスがとれた形で弁論術︵レートリケー︶に関わる全体像を描き出し、秩序立てようと努めている[13]。 このようにアリストテレスが弁論術に関して、師プラトンとは異なる姿勢を採ることになった大きな原因・背景として、プラトンとライバル関係にあったイソクラテスの影響が、古代から指摘されている[2]。構成[編集]
全3巻から成る。 ●第1巻 - 全15章 ●第1章 - 序論 ︵技術としての弁論術︶ ●第2章 - 弁論術の定義 ●第3章 - 弁論術の種類 ●第4章 - 議会弁論 ●第5章 - 幸福 ●第6章 - 善いもの ●第7章 - より大いなる善・利益 ●第8章 - 国制 ●第9章 - 演説的弁論 ●第10章 - 法廷弁論 ●第11章 - 快楽 ●第12章 - 不正を成す者と被る者 ●第13章 - 不正行為の分類 ●第14章 - より大きな不正行為 ●第15章 - 弁論術に本来属さない説得 ●第2巻 - 全26章 ●第1章 - 聞き手の心への働きかけ ●第2章 - 怒り ●第3章 - 温和 ●第4章 - 友愛と憎しみ ●第5章 - 恐れと大胆さ ●第6章 - 恥と無恥 ●第7章 - 親切と不親切 ●第8章 - 哀れみ ●第9章 - 義憤 ●第10章 - 妬み ●第11章 - 競争心 --- ●第12章 - 年齢による性格1 - 青年 ●第13章 - 年齢による性格2 - 老年 ●第14章 - 年齢による性格3 - 壮年 ●第15章 - 運による性格1 - 家柄の良さ ●第16章 - 運による性格2 - 富 ●第17章 - 運による性格3 - 権力と幸運 --- ●第18章 - 共通の論点1 ●第19章 - 共通の論点2 - 各論 ●第20章 - 共通の説得手段1 - 例証 ●第21章 - 共通の説得手段2 - 格言 ●第22章 - 共通の説得手段3 - 説得推論 ●第23章 - 説得推論の論点 ●第24章 - 見せかけの説得推論 ●第25章 - 説得推論の反駁 ●第26章 - 説得推論の注意事項 ●第3巻 - 全19章 ●第1章 - 第3巻の主題 ●第2章 - 表現の優秀性 ●第3章 - 生彩の無い表現 ●第4章 - 譬え ●第5章 - 表現の良さ ●第6章 - 表現の重厚さ ●第7章 - 表現の適切さ ●第8章 - リズム ●第9章 - 文体表現の構成 ●第10章 - 洗練された表現 ●第11章 - 生き生きとした表現と、味のある表現 ●第12章 - 表現方法の種類 --- ●第13章 - 言論の部分 ●第14章 - 序論 ●第15章 - 抽象 ●第16章 - 陳述 ●第17章 - 説得︵証拠立て︶ ●第18章 - 質問・答え、冗談 ●第19章 - 結びについて要点[編集]
巻別[編集]
本書は三巻から成り、各巻の内容は以下の通りとなっている。 ●第1巻 - 弁論術についての概論、三種の弁論それぞれについての論点の整理。 ●第2巻 - pathos︵感情︶、ethos︵人柄︶、logos︵言論︶/説得推論それぞれの観点からの考察。 ●第3巻 - リズム、文体など表現方法。三種の弁論[編集]
アリストテレスは、弁論を以下の3種類に分類し、それぞれの相違点や共通点を述べている。 ●議会弁論 - 何事かを奨励・慰留させる弁論。 ●演説的弁論 - 人を賞賛・非難する弁論。 ●法廷弁論 - 告訴・弁明する弁論。三種の説得手段[編集]
本書では、説得のあり方について、以下の3つの側面から考察されている。 ●logos︵ロゴス、言論︶ - 理屈による説得。 ●pathos︵パトス、感情︶- 聞き手の感情への訴えかけによる説得。 ●ethos︵エートス、人柄︶- 話し手の人柄による説得。 上記した通り、アリストテレスはこの3つの内、logos︵言論︶を技術の中心に据え、秩序立てようと努めているが、残りのpathos︵感情︶とethos︵人柄︶という2要素も、他者を説得する上では決して無視できない要素であるとして、同程度の文量を割いて考察している。 ︵なお、この分類は、プラトンの魂の三分説における﹁理知(logos)﹂﹁欲望(epithymia)﹂﹁気概(thymos)﹂に概ね対応している。また、近代社会学の父であるマックス・ヴェーバーによって提示された社会支配の三形態、﹁合法的支配﹂﹁伝統的支配﹂﹁カリスマ的支配﹂とも重なる。[要出典]︶弁証術と弁論術の違い[編集]
弁証術︵ディアレクティケー︶と弁論術︵レートリケー︶の関係性/差異は、 ●﹁弁証術︵ディアレクティケー︶による﹁証明﹂は、﹁帰納﹂か﹁推論 (演繹/三段論法)﹂によって行われる﹂ のに対して、それらに類比的︵アナロジカル︶に対応する形で、 ●﹁弁論術︵レートリケー︶による﹁見せかけの証明﹂は、﹁例証﹂か﹁説得推論 (省略三段論法)﹂によって行われる﹂ と表現できる。すなわち、﹁帰納﹂に対して﹁例証﹂が、﹁推論 (演繹/三段論法)﹂に対して﹁説得推論 (省略三段論法)﹂が、それぞれ対応関係を形作ることになる。内容[編集]
第1巻[編集]
第2巻[編集]
第3巻[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
日本語訳[編集]
●﹃世界古典文学全集16アリストテレス 弁論術﹄ 池田美恵訳、筑摩書房 1966年 ●﹃アリストテレス全集16弁論術 アレクサンドロスに贈る弁論術﹄ 山本光雄訳、岩波書店 1968年。後者は斎藤忍随・岩田靖夫訳 ●﹃アリストテレス 弁論術﹄ 戸塚七郎訳、岩波文庫 1992年 ●﹃新版 アリストテレス全集18弁論術 アレクサンドロス宛の弁論術 詩学﹄ 堀尾耕一、野津悌、朴一功訳、岩波書店 2017年注釈[編集]
- ^ ただしキケロに関しては、アリストテレスの論文が再整理され始めたのがロドスのアンドロニコスの時代になってからということもあり、参照できたのはテキスト全体ではなくその「抜粋」であったとする説が有力である。[3][4]
脚注[編集]
- ^ 映像の言語と文法 熊野雅仁
- ^ a b 『イソクラテスの修辞学校』廣川洋一, 講談社学術文庫, 7-4.
- ^ レトリック研究の予備知識 平野敏彦
- ^ a b Aristotle. Art of Rhetoric. Translated by J. H. Freese. Revised by Gisela Striker. Loeb Classical Library 193. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020. (Introduction)
- ^ 修辞とは - 大辞泉/大辞林
- ^ 『プラトン全集 10』 p239 岩波書店
- ^ 『パイドロス』 プラトン/藤沢令夫, 岩波文庫 p181
- ^ プラトンの言う弁証術(ディアレクティケー)は、ゼノンやソクラテスの頃の元々の素朴な「対話」「質疑応答」といった意味に加え、定義・綜合・分析(分割)を備えた「推論」技術という意味も含んだものに変質・拡張されている点に注意が必要 - 『パイドロス』 266B-C (岩波文庫 p111)
- ^ 『パイドロス』 プラトン/藤沢令夫, 岩波文庫 p96-132
- ^ プラトンは、オルペウス教やピタゴラス教団の宗教観に影響を受けており、天上界から堕ちてきて輪廻転生を繰り返す不滅の魂(プシュケー)が、真実を探求して徳を積めば、他の魂より一足早く天上界に帰還できると考えていた。詳しくは、『国家』『パイドロス』等を参照。
- ^ 『パイドロス』 プラトン/藤沢令夫, 岩波文庫 p131-132
- ^ 『政治家』304A-E
- ^ 「弁論術」アリストテレス/戸塚七郎訳 岩波文庫 p22-30
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- Aristotle's Rhetoric (英語) - スタンフォード哲学百科事典「弁論術 (アリストテレス)」の項目。
- 弁論術 - Yahoo!百科事典
