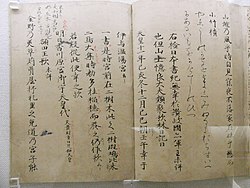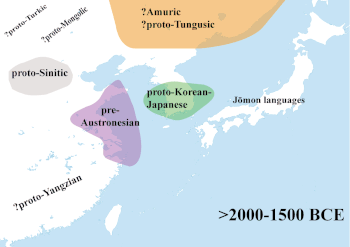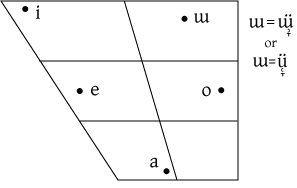日 本 語 ︵ に ほ ん ご 、 に っ ぽ ん ご [ 注 釈 3 ] ︶ は 、 日 本 国 内 や 、 か つ て の 日 本 領 だ っ た 国 、 そ し て 国 外 移 民 や 移 住 者 を 含 む 日 本 人 同 士 の 間 で 使 用 さ れ て い る 言 語 。 日 本 は 法 令 に よ っ て 公 用 語 を 規 定 し て い な い が 、 法 令 そ の 他 の 公 用 文 は 全 て 日 本 語 で 記 述 さ れ 、 各 種 法 令 [ 注 釈 4 ] に お い て 日 本 語 を 用 い る こ と が 規 定 さ れ 、 学 校 教 育 に お い て は ﹁ 国 語 ﹂ の 教 科 と し て 学 習 を 行 う な ど 、 事 実 上 日 本 国 内 に お い て 唯 一 の 公 用 語 と な っ て い る 。
使 用 人 口 に つ い て 正 確 な 統 計 は な い が 、 日 本 国 内 の 人 口 、 及 び 日 本 国 外 に 住 む 日 本 人 や 日 系 人 、 日 本 が か つ て 統 治 し た 地 域 の 一 部 住 民 な ど 、 約 1 億 3 , 0 0 0 万 人 以 上 と 考 え ら れ て い る [ 7 ] 。 統 計 に よ っ て 前 後 す る 場 合 も あ る が 、 こ の 数 は 世 界 の 母 語 話 者 数 で 上 位 10 位 以 内 に 入 る 人 数 で あ る [ 8 ] 。
日 本 語 の 音 韻 は 、 ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ を 除 い て 母 音 で 終 わ る 開 音 節 言 語 の 性 格 が 強 く 、 ま た 標 準 語 ︵ 共 通 語 ︶ を 含 め 多 く の 方 言 が モ ー ラ を 持 つ 。 ア ク セ ン ト は 高 低 ア ク セ ン ト で あ る 。
な お 元 来 の 古 い 大 和 言 葉 で は 、 原 則 と し て
● ﹁ ら 行 ﹂ 音 が 語 頭 に 立 た な い ︵ し り と り で ﹃ ら 行 ﹄ で 始 ま る 言 葉 が 見 つ け に く い の は こ の た め 。 ﹃ ら く ︵ 楽 ︶ ﹄ ﹃ ら っ ぱ ﹄ ﹃ り ん ご ﹄ ﹃ れ い ︵ 礼 ︶ ﹄ な ど は 大 和 言 葉 で な い ︶ ● 濁 音 が 語 頭 に 立 た な い ︵ ﹃ だ ︵ 抱 ︶ く ﹄ ﹃ ど れ ﹄ ﹃ ば ︵ 場 ︶ ﹄ ﹃ ば ら ︵ 薔 薇 ︶ ﹄ な ど は 後 世 の 変 化 ︶ ● 同 一 語 根 内 に 母 音 が 連 続 し な い ︵ ﹃ あ お ︵ 青 ︶ ﹄ ﹃ か い ︵ 貝 ︶ ﹄ は 古 く は ﹃ あ を / a w o / ﹄ , ﹃ か ひ / k a p i / ﹄ ︶ な ど の 特 徴 が あ っ た ︵ ﹁ 系 統 ﹂ お よ び ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
文 は 、 ﹁ 主 語 ・ 修 飾 語 ・ 述 語 ﹂ の 語 順 で 構 成 さ れ る 。 修 飾 語 は 被 修 飾 語 の 前 に 位 置 す る 。 ま た 、 名 詞 の 格 を 示 す た め に は 、 語 順 や 語 尾 を 変 化 さ せ る の で な く 、 文 法 的 な 機 能 を 示 す 機 能 語 ︵ 助 詞 ︶ を 後 ろ に 付 け 加 え る ︵ 膠 着 さ せ る ︶ 。 こ れ ら の こ と か ら 、 言 語 類 型 論 上 は 、 語 順 の 点 で は S O V 型 の 言 語 に 、 形 態 の 点 で は 膠 着 語 に 分 類 さ れ る ︵ ﹁ 文 法 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
語 彙 は 、 古 来 の 大 和 言 葉 ︵ 和 語 ︶ の ほ か 、 漢 語 ︵ 字 音 語 ︶ 、 外 来 語 、 お よ び 、 そ れ ら の 混 ざ っ た 混 種 語 に 分 け ら れ る 。 字 音 語 ︵ 漢 字 の 音 読 み に 由 来 す る 語 の 意 、 一 般 に ﹁ 漢 語 ﹂ と 称 す る ︶ は 現 代 の 語 彙 の 一 部 分 を 占 め て い る 。 ま た 、 ﹁ 絵 / 画 ︵ ゑ ︶ ﹂ な ど 、 も と も と 音 で あ る が 和 語 と 認 識 さ れ て い る も の も あ る 。 さ ら に 近 代 以 降 に は 西 洋 由 来 の 語 を 中 心 と す る 外 来 語 が 増 大 し て い る ︵ ﹁ 語 種 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
待 遇 表 現 の 面 で は 、 文 法 的 ・ 語 彙 的 に 発 達 し た 敬 語 体 系 が あ り 、 叙 述 さ れ る 人 物 ど う し の 微 妙 な 関 係 を 表 現 す る ︵ ﹁ 待 遇 表 現 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
日 本 語 は 地 方 ご と に 多 様 な 方 言 が あ り 、 と り わ け 琉 球 諸 島 で 方 言 差 が 著 し い ︵ ﹁ 方 言 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 近 世 中 期 ま で は 京 都 方 言 が 中 央 語 の 地 位 に あ っ た が 、 近 世 後 期 に は 江 戸 方 言 が 地 位 を 高 め 、 明 治 以 降 の 現 代 日 本 語 で は 東 京 山 の 手 の 中 流 階 級 以 上 の 方 言 ︵ 山 の 手 言 葉 ︶ を 基 盤 に 標 準 語 ︵ 共 通 語 ︶ が 形 成 さ れ た ︵ ﹁ 標 準 語 ﹂ 参 照 ︶ 。
表 記 体 系 は ほ か の 諸 言 語 と 比 べ て 極 め て 複 雑 か つ 柔 軟 性 の 高 さ が 特 徴 で あ る 。 漢 字 ︵ 国 字 を 含 む 。 音 読 み お よ び 訓 読 み で 用 い ら れ る ︶ と 平 仮 名 、 片 仮 名 が 日 本 語 の 主 要 な 文 字 で あ り 、 常 に こ の 3 種 類 の 文 字 を 組 み 合 わ せ て 表 記 す る ︵ ﹁ 字 種 ﹂ の 節 参 照 ︶ [ 注 釈 5 ] 。 表 音 文 字 で 表 記 体 系 を 複 数 持 つ た め 、 当 て 字 を せ ず に 外 来 語 を 表 記 す る こ と が 可 能 だ が 、 ラ テ ン 文 字 ︵ ロ ー マ 字 ︶ や ギ リ シ ャ 文 字 ︵ 医 学 ・ 科 学 用 語 に 多 用 ︶ な ど も し ば し ば 用 い ら れ る 。 ま た 、 縦 書 き と 横 書 き の ど ち ら で も 表 記 す る こ と が 可 能 で あ る ︵ 表 記 体 系 の 詳 細 に つ い て は ﹁ 日 本 語 の 表 記 体 系 ﹂ 参 照 ︶ 。
音 韻 は ﹁ 子 音 + 母 音 ﹂ 音 節 を 基 本 と し 、 母 音 は 5 種 類 し か な い な ど 、 分 か り や す い 構 造 を 持 つ 一 方 、 直 音 と 拗 音 の 対 立 、 ﹁ 1 音 節 2 モ ー ラ ﹂ の 存 在 、 無 声 化 母 音 、 語 の 組 み 立 て に 伴 っ て 移 動 す る 高 さ ア ク セ ン ト な ど の 特 徴 が あ る ︵ ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
成田国際空港 到着ゲートの看板。他言語は日本入国を歓迎する文言になっているのに対し、日本語は「おかえりなさい」と帰国を労う表現となっている。
﹁ 日 本 語 ﹂ の 範 囲 を 本 土 方 言 の み と し た 場 合 、 琉 球 語 が 日 本 語 と 同 系 統 の 言 語 に な り 両 者 は 日 琉 語 族 を 形 成 す る 。
琉 球 列 島 ︵ 旧 琉 球 王 国 領 域 ︶ の 言 葉 は 、 日 本 語 と 系 統 を 同 じ く す る 別 言 語 ︵ 琉 球 語 な い し は 琉 球 諸 語 ︶ と し 、 日 本 語 と ま と め て 日 琉 語 族 と さ れ て い る 。 共 通 点 が 多 い の で ﹁ 日 本 語 の 一 方 言 ︵ 琉 球 方 言 ︶ ﹂ と す る 場 合 も あ り 、 こ の よ う な 場 合 は 日 本 語 は ﹁ 孤 立 し た 言 語 ﹂ と い う 位 置 づ け に さ れ る 。
日本語(族)の系統については明治以来様々な説が議論されてきたが、いずれも他の語族との同系の証明に至っておらず、不明のままである[注釈 12]
アルタイ諸語 の分布
ア ル タ イ 諸 語 に 属 す る と す る 説 は 、 明 治 時 代 末 か ら 特 に 注 目 さ れ て き た [ 29 ] 。 そ の 根 拠 と し て 、 古 代 の 日 本 語 ︵ 大 和 言 葉 ︶ に お い て 語 頭 に r 音 ︵ 流 音 ︶ が 立 た な い こ と 、 一 種 の 母 音 調 和 が 見 ら れ る こ と な ど が 挙 げ ら れ る 。 古 代 日 本 語 に 上 記 の 特 徴 が 見 ら れ る こ と は 、 日 本 語 が 類 型 と し て ﹁ ア ル タ イ 型 ﹂ の 言 語 で あ る [ 31 ] 根 拠 と さ れ る 。 ア ル タ イ 諸 語 に 属 す る と さ れ る そ れ ぞ れ の 言 語 の 親 族 関 係 を 支 持 す る 学 者 の ほ う が ま だ 多 い が 、 最 近 の イ ギ リ ス で は ア ル タ イ 諸 語 の 親 族 関 係 を 否 定 す る 学 者 も 現 れ て い る 。
朝 鮮 語 と は 語 順 や 文 法 構 造 で 類 似 点 が 非 常 に 多 い 。 音 韻 の 面 で も 、 固 有 語 に お い て 語 頭 に 流 音 が 立 た な い こ と 、 一 種 の 母 音 調 和 が 見 ら れ る こ と な ど 、 共 通 の 類 似 点 が あ る ︵ そ の 結 果 、 日 本 語 も 朝 鮮 語 も ア ル タ イ 諸 語 と 分 類 さ れ る 場 合 が あ る ︶ 。 世 界 の 諸 言 語 の 広 く 比 較 し た 場 合 、 広 く ﹁ 朝 鮮 語 は 日 本 語 と 最 も 近 い 言 語 ﹂ と さ れ て い る 。 た だ し 、 閉 音 節 や 子 音 連 結 が 存 在 す る 、 有 声 ・ 無 声 の 区 別 が 無 い 、 と い っ た 相 違 も あ る 。 基 礎 語 彙 は 、 共 通 点 も あ る が 、 か な り 相 違 す る 面 も あ る 。
紀 元 8 世 紀 ま で に 記 録 さ れ た 朝 鮮 半 島 の 地 名 ︵ ﹁ 高 句 麗 地 名 ﹂ を 指 す ︶ の 中 に は 、 満 州 南 部 を 含 む 朝 鮮 半 島 中 部 以 北 に 、 意 味 や 音 韻 で 日 本 語 と 類 似 し た 地 名 を 複 数 見 い だ せ る 。 こ れ を 論 拠 と し て 、 古 代 の 朝 鮮 半 島 で は 朝 鮮 語 と と も に 日 本 語 と 近 縁 の 言 語 で あ る ﹁ 半 島 日 本 語 ﹂ が 話 さ れ て い た と 考 え ら れ て い る [ 34 ] 。
「高句麗地名」より抽出される単語のうち日本語に同根語が見出しうるもの
原語
訓釈
上代日本語
漢字
中古音[注釈 13]
中期朝鮮漢字音[注釈 14]
密
mit
mil
三
mi₁
于次
hju-tshijH
wucha
五
itu
難隱
nan-ʔɨnX
nanun
七
nana
德
tok
tek
十
to₂wo
旦
tanH
tan
谷
tani
頓
twon
twon
吞
then
thon
烏斯含
ʔu-sje-hom
wosaham
兔
usagi₁
那勿
na-mjut
namwul
鉛
namari
買
mɛX
may
水
mi₁(du) <*me [38]
美
mijX
may
彌
mjieX
mi
ま た 、 高 句 麗 語 に 鉛 ︵ な ま り ︶ = 那 勿 ︵ ナ ム ル ︶ 、 泉 ︵ い ず み ︶ = 於 乙 、 土 ︵ つ ち ︶ は 内 、 口 ︵ く ち ︶ は 口 次 と 呼 ん で い た 記 録 が あ り 、 高 句 麗 の 武 将 で あ る 泉 蓋 蘇 文 は 日 本 書 紀 で 伊 梨 柯 須 彌 ︵ イ リ カ ス ミ ︶ と 記 録 さ れ て い て 、 泉 ︵ い ず み ︶ は 高 句 麗 語 で 於 乙 ︵ イ リ ︶ と 呼 ば れ て い た こ と が 分 か る 。 件 の 地 名 が 高 句 麗 の 旧 領 域 内 に 分 布 し て い る こ と か ら 、 多 く の 研 究 は 半 島 日 本 語 は ﹁ 高 句 麗 語 ﹂ で あ る と し て い る 。
U n g e r ( 2 0 1 3 ) [ 40 ] に よ っ て 想 定 さ れ た 日 本 周 辺 の 語 族 分 布 の 変 遷
伊 藤 英 人 は 半 島 日 本 語 ︵ 大 陸 倭 語 ︶ を 高 句 麗 語 と し た 上 で 、 日 本 語 と 半 島 日 本 語 は 同 じ 祖 語 か ら 分 か れ た 同 系 統 の 言 語 で あ り 、 半 島 日 本 語 集 団 か ら 分 か れ た 集 団 が 紀 元 前 9 0 0 年 か ら 紀 元 7 0 0 年 に か け て 水 田 農 耕 を 携 え 日 本 列 島 に 渡 来 し た と 考 え た [ 注 釈 15 ] 。
な お 、 伊 藤 英 人 は 半 島 日 本 語 が 京 阪 式 ア ク セ ン ト と 類 似 し て い る こ と を 指 摘 し て い る 。
中 国 語 と の 関 係 に 関 し て は 、 日 本 語 は 中 国 の 漢 字 を 借 用 語 と し て 広 範 囲 に 取 り 入 れ て お り 、 語 彙 の う ち 漢 字 を 用 い た も の に 関 し て 、 影 響 を 受 け て い る 。 だ が 語 順 も 文 法 も 音 韻 も 大 き く 異 な る の で 、 系 統 論 的 に は 別 系 統 の 言 語 と さ れ る 。
ア イ ヌ 語 は 、 語 順 ︵ S O V 語 順 ︶ に お い て 日 本 語 と 似 る 。 た だ し 、 文 法 ・ 形 態 は 類 型 論 的 に 異 な る 抱 合 語 に 属 し 、 音 韻 構 造 も 有 声 ・ 無 声 の 区 別 が な く 閉 音 節 が 多 い な ど の 相 違 が あ る 。 基 礎 語 彙 の 類 似 に 関 す る 指 摘 [ 47 ] も あ る が 、 例 は 不 充 分 で あ る [ 47 ] 。 一 般 に 似 て い る と さ れ る 語 の 中 に は 、 日 本 語 か ら ア イ ヌ 語 へ の 借 用 語 が 多 く 含 ま れ る と み ら れ る 。
南方系のオーストロネシア語族 とは、音韻体系や語彙に関する類似も指摘されているが、これは偶然一致したものであり、互いに関係があるという根拠はない[注釈 16]
ドラヴィダ語族 との関係を主張する説もあるが、これを認める研究者は少ない。大野晋 は日本語が語彙・文法などの点でタミル語 と共通点を持つとの説を唱える[注釈 17] [注釈 18]
また、レプチャ語 ・ヘブライ語 などとの同系論も過去に存在したが、これに関してはほとんど疑似科学 の範疇に収まる[47]
日 本 語 話 者 は 普 通 、 ﹁ い っ ぽ ん ︵ 一 本 ︶ ﹂ と い う 語 を 、 ﹁ い ・ っ ・ ぽ ・ ん ﹂ の 4 単 位 と 捉 え て い る 。 音 節 ご と に ま と め る な ら ば [ i p ̚ . p o ɴ ] の よ う に 2 単 位 と な る と こ ろ で あ る が 、 音 韻 的 な 捉 え 方 は こ れ と 異 な る 。 音 声 学 上 の 単 位 で あ る 音 節 と は 区 別 し て 、 音 韻 論 で は ﹁ い ・ っ ・ ぽ ・ ん ﹂ の よ う な 単 位 の こ と を モ ー ラ ︵ 拍 ︶ と 称 し て い る 。
日 本 語 の モ ー ラ は 、 大 体 は 仮 名 に 即 し て 体 系 化 す る こ と が で き る 。 ﹁ い っ ぽ ん ﹂ と ﹁ ま っ た く ﹂ は 、 音 声 学 上 は [ i p ̚ p o ɴ ] [ m a t ̚ t a k ɯ ] で あ っ て 共 通 す る 単 音 が な い が 、 日 本 語 話 者 は ﹁ っ ﹂ と い う 共 通 の モ ー ラ を 見 出 す 。 ま た 、 ﹁ ん ﹂ は 、 音 声 学 上 は 後 続 の 音 に よ っ て [ ɴ ] [ m ] [ n ] [ ŋ ] な ど と 変 化 す る が 、 日 本 語 の 話 者 自 ら は 同 一 音 と 認 識 し て い る の で 、 音 韻 論 上 は 1 種 類 の モ ー ラ と な る 。
日 本 語 で は 、 ほ と ん ど の モ ー ラ が 母 音 で 終 わ っ て い る 。 そ れ ゆ え に 日 本 語 は 開 音 節 言 語 の 性 格 が 強 い と い う こ と が で き る 。 も っ と も 、 特 殊 モ ー ラ の ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ に は 母 音 が 含 ま れ な い 。
モ ー ラ の 種 類 は 、 以 下 に 示 す よ う に 1 1 1 程 度 存 在 す る 。 た だ し 、 研 究 者 に よ り 数 え 方 が 少 し ず つ 異 な る 。 ﹁ が 行 ﹂ の 音 は 、 語 中 語 尾 で は 鼻 音 ︵ い わ ゆ る 鼻 濁 音 ︶ の ﹁ か ゚ 行 ﹂ 音 と な る 場 合 が あ る が 、 ﹁ が 行 ﹂ と ﹁ か ゚ 行 ﹂ と の 違 い は 何 ら 弁 別 の 機 能 を 提 供 せ ず 、 単 な る 異 音 ど う し に 過 ぎ な い 。 そ こ で 、 ﹁ か ゚ 行 ﹂ を 除 外 し て 数 え る 場 合 、 モ ー ラ の 数 は 1 0 3 程 度 と な る 。 こ れ 以 外 に 、 ﹁ 外 来 語 の 表 記 ﹂ 第 1 表 に も あ る ﹁ シ ェ ﹂ ﹁ チ ェ ﹂ ﹁ ツ ァ ・ ツ ェ ・ ツ ォ ﹂ ﹁ テ ィ ﹂ ﹁ フ ァ ・ フ ィ ・ フ ェ ・ フ ォ ﹂ そ の 他 の 外 来 音 を 含 め る 場 合 は 、 さ ら に ま た 数 が 変 わ っ て く る [ 注 釈 19 ] 。 こ の ほ か 、 外 来 語 の 表 記 に お い て 用 い ら れ る ﹁ ヴ ァ ・ ヴ ィ ・ ヴ ・ ヴ ェ ・ ヴ ォ ﹂ に つ い て は 、 バ 行 と し て 発 音 さ れ る こ と が 多 い も の の 、 独 立 し た 音 韻 と し て 発 音 さ れ る こ と も あ り 、 こ れ ら を 含 め る と さ ら に 増 え る こ と と な る 。
なお、五十音図 は、音韻体系の説明に使われることがしばしばあるが、上記の日本語モーラ表と比べてみると、少なからず異なる部分がある。五十音図の成立は平安時代にさかのぼるものであり、現代語の音韻体系を反映するものではないことに注意が必要である(「日本語研究史 」の節の「江戸時代以前 」を参照)。
基 本 5 母 音 の 調 音 位 置 左 側 を 向 い た 人 の 口 の 中 を 模 式 的 に 示 し た も の 。 左 へ 行 く ほ ど 舌 が 前 に 出 、 上 へ 行 く ほ ど 口 が 狭 ま る こ と を 表 す 。 な お 、 [ o ] の と き は 唇 の 丸 め を 伴 う 。
母 音 は 、 ﹁ あ ・ い ・ う ・ え ・ お ﹂ の 文 字 で 表 さ れ る 。 音 韻 論 上 は 、 日 本 語 の 母 音 は こ の 文 字 で 表 さ れ る 5 個 で あ り 、 音 素 記 号 で は 以 下 の よ う に 記 さ れ る 。
● / a / , / i / , / u / , / e / , / o / 一 方 、 音 声 学 上 は 、 基 本 の 5 母 音 は 、 そ れ ぞ れ
● [ ä ] 、 [ i ̠ ] 、 [ u ̜ ] ま た は [ ɯ ̹ ] 、 [ e ̞ ] ま た は [ ɛ ̝ ] 、 [ o ̜ ̞ ] ま た は [ ɔ ̜ ̝ ] に 近 い 発 音 と 捉 え ら れ る 。 ̈ は 中 舌 寄 り 、 ̠ は 後 寄 り 、 ̜ は 弱 め の 円 唇 、 ̹ は 強 め の 円 唇 、 ˕ は 下 寄 り 、 ˔ は 上 寄 り を 示 す 補 助 記 号 で あ る 。
日 本 語 の ﹁ あ ﹂ は 、 国 際 音 声 記 号 ( I P A ) で は 前 舌 母 音 [ a ] と 後 舌 母 音 [ ɑ ] の 中 間 音 [ ä ] に 当 た る 。 ﹁ い ﹂ は 少 し 後 寄 り で あ り [ i ̠ ] が 近 い 。 ﹁ え ﹂ は 半 狭 母 音 [ e ] と 半 広 母 音 [ ɛ ] の 中 間 音 で あ り 、 ﹁ お ﹂ は 半 狭 母 音 [ o ] と 半 広 母 音 [ ɔ ] の 中 間 音 で あ る 。
日 本 語 の ﹁ う ﹂ は 、 東 京 方 言 で は 、 英 語 な ど の [ u ] の よ う な 円 唇 後 舌 母 音 よ り 、 少 し 中 舌 よ り で 、 そ れ に 伴 い 円 唇 性 が 弱 ま り 、 中 舌 母 音 の よ う な 張 唇 で も 円 唇 で も な い ニ ュ ー ト ラ ル な 唇 か 、 そ れ よ り ほ ん の 僅 か に 前 に 突 き 出 し た 唇 で 発 音 さ れ る 、 半 後 舌 微 円 唇 狭 母 音 で あ る 。 こ れ は 舌 と 唇 の 動 き の 連 関 で 、 前 舌 母 音 は 張 唇 、 中 舌 母 音 は 平 唇 ・ ニ ュ ー ト ラ ル ︵ た だ し ニ ュ ー ト ラ ル は 、 現 行 の I P A 表 記 で は 非 円 唇 と し て 、 張 唇 と 同 じ カ テ ゴ リ ー に 入 れ ら れ て い る ︶ 、 後 舌 母 音 は 円 唇 と な る の が 自 然 で あ る と い う 法 則 に 適 っ て い る 。 し か し ﹁ う ﹂ は 母 音 融 合 な ど で 見 ら れ る よ う に 、 音 韻 上 は 未 だ に 円 唇 後 舌 狭 母 音 と し て 機 能 す る 。 ま た 、 [ ɯ ᵝ ] と い う 表 記 も 行 わ れ る [ 要 出 典 ] 。
円 唇 性 の 弱 さ を 強 調 す る た め に 、 [ ɯ ] を 使 う こ と も あ る が 、 こ れ は 本 来 朝 鮮 語 に 見 ら れ る 、 i の よ う な 完 全 な 張 唇 で あ り な が ら 、 u の よ う に 後 舌 の 狭 母 音 を 表 す 記 号 で あ り 、 円 唇 性 が 減 衰 し つ つ も 残 存 し 、 か つ 後 舌 よ り や や 前 よ り で あ る 日 本 語 の 母 音 ﹁ う ﹂ の 音 声 と は 違 い を 有 す る 。 ま た こ の 種 の 母 音 は 、 唇 と 舌 の 連 関 か ら 外 れ る た め 、 母 音 数 5 以 上 の 言 語 で な い 限 り 、 発 生 す る の は 稀 で あ る 。 ﹁ う ﹂ は 唇 音 の 後 で は よ り 完 全 な 円 唇 母 音 に 近 づ く ︵ 発 音 の 詳 細 は そ れ ぞ れ の 文 字 の 項 目 を 参 照 ︶ 。 一 方 、 西 日 本 方 言 で は ﹁ う ﹂ は 東 京 方 言 よ り も 奥 舌 で 、 唇 も 丸 め て 発 音 し 、 [ u ] に 近 い 。
音 韻 論 上 、 ﹁ コ ー ヒ ー ﹂ ﹁ ひ い ひ い ﹂ な ど 、 ﹁ ー ﹂ や ﹁ あ 行 ﹂ の 仮 名 で 表 す 長 音 と い う 単 位 が 存 在 す る ︵ 音 素 記 号 で は / R / ︶ 。 こ れ は 、 ﹁ 直 前 の 母 音 を 1 モ ー ラ 分 引 く ﹂ と い う 方 法 で 発 音 さ れ る 独 立 し た 特 殊 モ ー ラ で あ る [ 56 ] 。 ﹁ 鳥 ﹂ ︵ ト リ ︶ と ﹁ 通 り ﹂ ︵ ト ー リ ︶ の よ う に 、 長 音 の 有 無 に よ り 意 味 を 弁 別 す る こ と も 多 い 。 た だ し 、 音 声 と し て は ﹁ 長 音 ﹂ と い う 特 定 の 音 が あ る わ け で は な く 、 長 母 音 [ ä ː ] [ i ̠ ː ] [ u ̜ ̟ ː ] [ e ̞ ː ] [ o ̜ ̞ ː ] の 後 半 部 分 に 相 当 す る も の で あ る 。
﹁ え い ﹂ ﹁ お う ﹂ と 書 か れ る 文 字 は 、 発 音 上 は ﹁ え え ﹂ ﹁ お お ﹂ と 同 じ く 長 母 音 [ e ̞ ː ] [ o ̜ ̞ ː ] と し て 発 音 さ れ る こ と が 一 般 的 で あ る ︵ ﹁ け い ﹂ ﹁ こ う ﹂ な ど 、 頭 子 音 が 付 い た 場 合 も 同 様 ︶ 。 す な わ ち 、 ﹁ 衛 星 ﹂ ﹁ 応 答 ﹂ ﹁ 政 党 ﹂ は ﹁ エ ー セ ー ﹂ ﹁ オ ー ト ー ﹂ ﹁ セ ー ト ー ﹂ の よ う に 発 音 さ れ る 。 た だ し 、 九 州 や 四 国 南 部 ・ 西 部 、 紀 伊 半 島 南 部 な ど で は ﹁ え い ﹂ を [ e ̞ i ] と 発 音 す る [ 57 ] 。 ﹁ 思 う ﹂ [ o m o ɯ ᵝ ] 、 ﹁ 問 う ﹂ [ t o ɯ ᵝ ] な ど の 単 語 は 必 ず 二 重 母 音 と な り 、 ま た 軟 骨 魚 の エ イ な ど 、 語 彙 に よ っ て 二 重 母 音 に な る 場 合 も あ る が 、 こ れ に は 個 人 差 が あ る 。 1 文 字 1 文 字 丁 寧 に 発 話 す る 場 合 に は ﹁ え い ﹂ を [ e ̞ i ] と 発 音 す る 話 者 も 多 い 。
単 語 末 や 無 声 子 音 の 間 に 挟 ま れ た 位 置 に お い て 、 ﹁ イ ﹂ や ﹁ ウ ﹂ な ど の 狭 母 音 は し ば し ば 無 声 化 す る 。 た と え ば 、 ﹁ で す ﹂ ﹁ ま す ﹂ は [ d e ̞ s u ̜ ̟ ̥ ] [ m ä s u ̜ ̟ ̥ ] の よ う に 発 音 さ れ る し 、 ﹁ 菊 ﹂ ﹁ 力 ﹂ ﹁ 深 い ﹂ ﹁ 放 つ ﹂ ﹁ 秋 ﹂ な ど は そ れ ぞ れ [ k ʲ i ̠ ̥ k u ̜ ̟ ] [ ʨ i ̠ ̥ k ä ɾ ä ] [ ɸ u ̜ ̟ ̥ k ä i ̠ ] [ h ä n ä ʦ u ̜ ̟ ̥ ] [ ä k ʲ i ̠ ̥ ] と 発 音 さ れ る こ と が あ る 。 た だ し ア ク セ ン ト 核 が あ る 拍 は 無 声 化 し に く い 。 個 人 差 も あ り 、 発 話 の 環 境 や 速 さ 、 丁 寧 さ に よ っ て も 異 な る 。 ま た 方 言 差 も 大 き く 、 た と え ば 近 畿 方 言 で は ほ と ん ど 母 音 の 無 声 化 が 起 こ ら な い 。
﹁ ん ﹂ の 前 の 母 音 は 鼻 音 化 す る 傾 向 が あ る 。 ま た 、 母 音 の 前 の ﹁ ん ﹂ は 前 後 の 母 音 に 近 似 の 鼻 母 音 に な る 。
子 音 は 、 音 韻 論 上 区 別 さ れ て い る も の と し て は 、 現 在 の 主 流 学 説 に よ れ ば ﹁ か ・ さ ・ た ・ な ・ は ・ ま ・ や ・ ら ・ わ 行 ﹂ の 子 音 、 濁 音 ﹁ が ・ ざ ・ だ ・ ば 行 ﹂ の 子 音 、 半 濁 音 ﹁ ぱ 行 ﹂ の 子 音 で あ る 。 音 素 記 号 で は 以 下 の よ う に 記 さ れ る 。 ワ 行 と ヤ 行 の 語 頭 子 音 は 、 音 素 u と 音 素 i の 音 節 内 の 位 置 に 応 じ た 変 音 で あ る と す る 解 釈 も あ る 。 特 殊 モ ー ラ の ﹁ ん ﹂ と ﹁ っ ﹂ は 、 音 韻 上 独 立 の 音 素 で あ る と い う 説 と 、 ﹁ ん ﹂ は ナ 行 語 頭 子 音 n の 音 節 内 の 位 置 に 応 じ た 変 音 、 ﹁ っ ﹂ は 単 な る 二 重 子 音 化 で あ る と し て 音 韻 上 独 立 の 音 素 で は な い と い う 説 の 両 方 が あ る 。
● / k / , / s / , / t / , / h / ︵ 清 音 ︶ ● / ɡ / , / z / , / d / , / b / ︵ 濁 音 ︶ ● / p / ︵ 半 濁 音 ︶ ● / n / , / m / , / r / ● / j / , / w / ︵ 半 母 音 と も 呼 ば れ る ︶ 一 方 、 音 声 学 上 は 、 子 音 体 系 は い っ そ う 複 雑 な 様 相 を 呈 す る 。 主 に 用 い ら れ る 子 音 を 以 下 に 示 す ︵ 後 述 す る 口 蓋 化 音 は 省 略 ︶ 。
基 本 的 に ﹁ か 行 ﹂ は [ k ] 、 ﹁ さ 行 ﹂ は [ s ] ︵ [ θ ] を 用 い る 地 方 ・ 話 者 も あ る [ 57 ] ︶ 、 ﹁ た 行 ﹂ は [ t ] 、 ﹁ な 行 ﹂ は [ n ] 、 ﹁ は 行 ﹂ は [ h ] 、 ﹁ ま 行 ﹂ は [ m ] 、 ﹁ や 行 ﹂ は [ j ] 、 ﹁ だ 行 ﹂ は [ d ] 、 ﹁ ば 行 ﹂ は [ b ] 、 ﹁ ぱ 行 ﹂ は [ p ] を 用 い る 。
﹁ ら 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 で は [ ɺ ] 、 ﹁ ん ﹂ の 後 の ら 行 は 英 語 の [ l ] に 近 い 音 を 用 い る 話 者 も あ る 。 一 方 、 ﹁ あ ら っ ? ﹂ と い う と き の よ う に 、 語 中 語 尾 に 現 れ る 場 合 は 、 舌 を は じ く [ ɾ ] も し く は [ ɽ ] と な る 。
標 準 日 本 語 お よ び そ れ の 母 体 で あ る 首 都 圏 方 言 ︵ 共 通 語 ︶ に お い て 、 ﹁ わ 行 ﹂ の 子 音 は 、 上 で 挙 げ た 同 言 語 の ﹁ う ﹂ と 基 本 的 な 性 質 を 共 有 し 、 も う 少 し 空 気 の 通 り 道 の 狭 い 接 近 音 で あ る 。 こ の た め 、 [ u ] に 対 応 す る 接 近 音 [ w ] と 、 [ ɯ ] に 対 応 す る 接 近 音 [ ɰ ] の 中 間 、 も し く は 微 円 唇 と い う 点 で 僅 か に [ w ] に 近 い と 言 え 、 軟 口 蓋 ︵ 後 舌 母 音 の 舌 の 位 置 ︶ の 少 し 前 よ り の 部 分 を 主 な 調 音 点 と し 、 両 唇 も 僅 か に 使 っ て 調 音 す る 二 重 調 音 の 接 近 音 と い え る 。 こ の た め 、 五 十 音 図 の 配 列 で は 、 ワ 行 は 唇 音 に 入 れ ら れ て い る ︵ ﹁ 日 本 語 ﹂ の 項 目 で は 、 特 別 の 必 要 の な い 場 合 は [ w ] で 表 現 す る ︶ 。 外 来 音 ﹁ ウ ィ ﹂ ﹁ ウ ェ ﹂ ﹁ ウ ォ ﹂ に も 同 じ 音 が 用 い ら れ る が 、 ﹁ ウ イ ﹂ ﹁ ウ エ ﹂ ﹁ ウ オ ﹂ と 2 モ ー ラ で 発 音 す る 話 者 も 多 い 。
﹁ が 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 で は 破 裂 音 の [ g ] を 用 い る が 、 語 中 で は 鼻 音 の [ ŋ ] ︵ ﹁ が 行 ﹂ 鼻 音 、 い わ ゆ る 鼻 濁 音 ︶ を 用 い る こ と が 一 般 的 だ っ た 。 現 在 で は 、 こ の [ ŋ ] を 用 い る 話 者 は 減 少 し つ つ あ り 、 代 わ り に 語 頭 と 同 じ く 破 裂 音 を 用 い る か 、 摩 擦 音 の [ ɣ ] を 用 い る 話 者 が 増 え て い る 。
﹁ ざ 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 や ﹁ ん ﹂ の 後 で は 破 擦 音 ︵ 破 裂 音 と 摩 擦 音 を 合 わ せ た [ d ͡ z ] な ど の 音 ︶ を 用 い る が 、 語 中 で は 摩 擦 音 ︵ [ z ] な ど ︶ を 用 い る 場 合 が 多 い 。 い つ で も 破 擦 音 を 用 い る 話 者 も あ る が 、 ﹁ 手 術 ︵ し ゅ じ ゅ つ ︶ ﹂ な ど の 語 で は 発 音 が 難 し い た め 摩 擦 音 に す る ケ ー ス が 多 い 。 な お 、 ﹁ だ 行 ﹂ の ﹁ ぢ ﹂ ﹁ づ ﹂ は 、 一 部 方 言 を 除 い て ﹁ ざ 行 ﹂ の ﹁ じ ﹂ ﹁ ず ﹂ と 同 音 に 帰 し て お り 、 発 音 方 法 は 同 じ で あ る 。
母 音 ﹁ い ﹂ が 後 続 す る 子 音 は 、 独 特 の 音 色 を 呈 す る 。 い く つ か の 子 音 で は 、 前 舌 面 を 硬 口 蓋 に 近 づ け る 口 蓋 化 が 起 こ る 。 た と え ば 、 ﹁ か 行 ﹂ の 子 音 は 一 般 に [ k ] を 用 い る が 、 ﹁ き ﹂ だ け は [ k ʲ ] を 用 い る と い っ た 具 合 で あ る 。 口 蓋 化 し た 子 音 の 後 ろ に 母 音 ﹁ あ ﹂ ﹁ う ﹂ ﹁ お ﹂ が 来 る と き は 、 表 記 上 は ﹁ い 段 ﹂ の 仮 名 の 後 ろ に ﹁ ゃ ﹂ ﹁ ゅ ﹂ ﹁ ょ ﹂ の 仮 名 を 用 い て ﹁ き ゃ ﹂ ﹁ き ゅ ﹂ ﹁ き ょ ﹂ 、 ﹁ み ゃ ﹂ ﹁ み ゅ ﹂ ﹁ み ょ ﹂ の よ う に 記 す 。 後 ろ に 母 音 ﹁ え ﹂ が 来 る と き は ﹁ ぇ ﹂ の 仮 名 を 用 い て ﹁ き ぇ ﹂ の よ う に 記 す が 、 外 来 語 な ど に し か 使 わ れ な い 。
﹁ さ 行 ﹂ ﹁ ざ 行 ﹂ ﹁ た 行 ﹂ ﹁ は 行 ﹂ の ﹁ い 段 ﹂ 音 の 子 音 も 独 特 の 音 色 で あ る が 、 こ れ は 単 な る 口 蓋 化 で な く 、 調 音 点 が 硬 口 蓋 に 移 動 し た 音 で あ る 。 ﹁ し ﹂ ﹁ ち ﹂ の 子 音 は [ ɕ ] [ ʨ ] を 用 い る 。 外 来 音 ﹁ ス ィ ﹂ ﹁ テ ィ ﹂ の 子 音 は 口 蓋 化 し た [ s ʲ ] [ t ʲ ] を 用 い る 。 ﹁ じ ﹂ ﹁ ぢ ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 お よ び ﹁ ん ﹂ の 後 ろ で は [ d ͡ ʑ ] 、 語 中 で は [ ʑ ] を 用 い る 。 外 来 音 ﹁ デ ィ ﹂ ﹁ ズ ィ ﹂ の 子 音 は 口 蓋 化 し た [ d ʲ ] [ d ͡ ʑ ʲ ] お よ び [ z ʲ ] を 用 い る 。 ﹁ ひ ﹂ の 子 音 は [ h ] で は な く 硬 口 蓋 音 [ ç ] で あ る 。
ま た 、 ﹁ に ﹂ の 子 音 は 多 く は 口 蓋 化 し た [ n ʲ ] で 発 音 さ れ る が 、 硬 口 蓋 鼻 音 [ ɲ ] を 用 い る 話 者 も あ る 。 同 様 に 、 ﹁ り ﹂ に 硬 口 蓋 は じ き 音 を 用 い る 話 者 や 、 ﹁ ち ﹂ に 無 声 硬 口 蓋 破 裂 音 [ c ] を 用 い る 話 者 も あ る 。
そ の ほ か 、 ﹁ は 行 ﹂ で は ﹁ ふ ﹂ の 子 音 の み 無 声 両 唇 摩 擦 音 [ ɸ ] を 用 い る が 、 こ れ は ﹁ は 行 ﹂ 子 音 が [ p ] → [ ɸ ] → [ h ] と 変 化 し て き た 名 残 り で あ る 。 五 十 音 図 で は 、 奈 良 時 代 に 音 韻 ・ 音 声 で p 、 平 安 時 代 に [ ɸ ] で あ っ た 名 残 で 、 両 唇 音 の カ テ ゴ リ ー に 入 っ て い る 。 外 来 語 に は [ f ] を 用 い る 話 者 も あ る 。 こ れ に 関 し て 、 現 代 日 本 語 で ﹁ っ ﹂ の 後 ろ や 、 漢 語 で ﹁ ん ﹂ の 後 ろ に ハ 行 が 来 た と き 、 パ 行 ( p ) の 音 が 現 れ 、 連 濁 で も バ 行 ( b ) に 変 わ り 、 有 音 声 門 摩 擦 音 [ ɦ ] で は な い こ と か ら 、 現 代 日 本 語 で も 語 種 を 和 語 や 前 近 代 の 漢 語 等 の 借 用 語 に 限 れ ば ︵ ハ 行 に 由 来 し な い パ 行 は 近 代 以 降 の も の ︶ 、 ハ 行 の 音 素 は h で な く p で あ り 、 摩 擦 音 化 規 則 で 上 に 挙 げ た 場 合 以 外 は h に 変 わ る の だ と い う 解 釈 も あ る 。 現 代 日 本 語 母 語 話 者 の 直 感 に は 反 す る が 、 ハ 行 の 連 濁 や ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ の 後 ろ で の ハ 行 の 音 の 変 化 を よ り 体 系 的 ・ 合 理 的 に 表 し う る [ 60 ] 。
ま た 、 ﹁ た 行 ﹂ で は ﹁ つ ﹂ の 子 音 の み [ t ͡ s ] を 用 い る 。 こ れ ら の 子 音 に 母 音 ﹁ あ ﹂ ﹁ い ﹂ ﹁ え ﹂ ﹁ お ﹂ が 続 く の は 主 と し て 外 来 語 の 場 合 で あ り 、 仮 名 で は ﹁ ァ ﹂ ﹁ ィ ﹂ ﹁ ェ ﹂ ﹁ ォ ﹂ を 添 え て ﹁ フ ァ ﹂ ﹁ ツ ァ ﹂ の よ う に 記 す ︵ ﹁ ツ ァ ﹂ は ﹁ お と っ つ ぁ ん ﹂ ﹁ ご っ つ ぁ ん ﹂ な ど で も 用 い る ︶ 。 ﹁ フ ィ ﹂ ﹁ ツ ィ ﹂ は 子 音 に 口 蓋 化 が 起 こ る 。 ま た ﹁ ツ ィ ﹂ は 多 く ﹁ チ ﹂ な ど に 言 い 換 え ら れ る 。 ﹁ ト ゥ ﹂ ﹁ ド ゥ ﹂ ︵ [ t ɯ ] [ d ɯ ] ︶ は 、 外 来 語 で 用 い る こ と が あ る 。
促 音 ﹁ っ ﹂ ︵ 音 素 記 号 で は / Q / ︶ お よ び 撥 音 ﹁ ん ﹂ ︵ / N / ︶ と 呼 ば れ る 音 は 、 音 韻 論 上 の 概 念 で あ っ て 、 前 節 で 述 べ た 長 音 と 併 せ て 特 殊 モ ー ラ と 扱 う 。 実 際 の 音 声 と し て は 、 ﹁ っ ﹂ は [ - k ̚ k - ] [ - s ̚ s - ] [ - ɕ ̚ ɕ - ] [ - t ̚ t - ] [ - t ̚ ʦ - ] [ - t ̚ ʨ - ] [ - p ̚ p - ] な ど の 子 音 連 続 と な る 。 た だ し ﹁ あ っ ﹂ の よ う に 、 単 独 で 出 現 す る こ と も あ り 、 そ の と き は 声 門 閉 鎖 音 と な る 。 ま た 、 ﹁ ん ﹂ は 、 後 続 の 音 に よ っ て [ ɴ ] [ m ] [ n ] [ ŋ ] な ど の 子 音 と な る ︵ た だ し 、 母 音 の 前 で は 鼻 母 音 と な る ︶ 。 文 末 な ど で は [ ɴ ] を 用 い る 話 者 が 多 い 。
日 本 語 は 、 一 部 の 方 言 を 除 い て 、 音 ︵ ピ ッ チ ︶ の 上 下 に よ る 高 低 ア ク セ ン ト を 持 っ て い る 。 ア ク セ ン ト は 語 ご と に 決 ま っ て お り 、 モ ー ラ ︵ 拍 ︶ 単 位 で 高 低 が 定 ま る 。 同 音 語 を ア ク セ ン ト に よ っ て 区 別 で き る 場 合 も 少 な く な い 。 た と え ば 東 京 方 言 の 場 合 、 ﹁ 雨 ﹂ ﹁ 飴 ﹂ は そ れ ぞ れ ﹁ ア \ メ ﹂ ︵ 頭 高 型 ︶ 、 ﹁ ア / メ ﹂ ︵ 平 板 型 ︶ と 異 な っ た ア ク セ ン ト で 発 音 さ れ る ︵ / を 音 の 上 昇 、 \ を 音 の 下 降 と す る ︶ 。 ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 助 詞 は 固 有 の ア ク セ ン ト が な く 、 直 前 に 来 る 名 詞 に よ っ て 助 詞 の 高 低 が 決 ま る 。 た と え ば ﹁ 箸 ﹂ ﹁ 橋 ﹂ ﹁ 端 ﹂ は 、 単 独 で は そ れ ぞ れ ﹁ ハ \ シ ﹂ ﹁ ハ / シ ﹂ ﹁ ハ / シ ﹂ と な る が 、 後 ろ に ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 助 詞 が 付 く 場 合 、 そ れ ぞ れ ﹁ ハ \ シ ガ ﹂ ﹁ ハ / シ \ ガ ﹂ ﹁ ハ / シ ガ ﹂ と な る 。
共 通 語 の ア ク セ ン ト で は 、 単 語 の 中 で 音 の 下 が る 場 所 が あ る か 、 あ る な ら ば 何 モ ー ラ 目 の 直 後 に 下 が る か を 弁 別 す る 。 音 が 下 が る と こ ろ を 下 が り 目 ま た は ア ク セ ン ト の 滝 と い い 、 音 が 下 が る 直 前 の モ ー ラ を ア ク セ ン ト 核 [ 注 釈 20 ] ま た は 下 げ 核 と い う 。 た と え ば ﹁ 箸 ﹂ は 第 1 拍 、 ﹁ 橋 ﹂ は 第 2 拍 に ア ク セ ン ト 核 が あ り 、 ﹁ 端 ﹂ に は ア ク セ ン ト 核 が な い 。 ア ク セ ン ト 核 は 1 つ の 単 語 に は 1 箇 所 も な い か 1 箇 所 だ け あ る か の い ず れ か で あ り 、 一 度 下 が っ た 場 合 は 単 語 内 で 再 び 上 が る こ と は な い 。 ア ク セ ン ト 核 を ○ で 表 す と 、 2 拍 語 に は ○ ○ ︵ 核 な し ︶ 、 ○ ○ 、 ○ ○ の 3 種 類 、 3 拍 語 に は ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ の 4 種 類 の ア ク セ ン ト が あ り 、 拍 数 が 増 え る に つ れ て ア ク セ ン ト の 型 の 種 類 も 増 え る 。 ア ク セ ン ト 核 が 存 在 し な い も の を 平 板 型 と い い 、 第 1 拍 に ア ク セ ン ト 核 が あ る も の を 頭 高 型 、 最 後 の 拍 に あ る も の を 尾 高 型 、 第 1 拍 と 最 後 の 拍 の 間 に あ る も の を 中 高 型 と い う 。 頭 高 型 ・ 中 高 型 ・ 尾 高 型 を ま と め て 起 伏 式 ま た は 有 核 型 と 呼 び 、 平 板 型 を 平 板 式 ま た は 無 核 型 と 呼 ん で 区 別 す る こ と も あ る 。
ま た 共 通 語 の ア ク セ ン ト で は 、 単 語 や 文 節 の み の 形 で 発 音 し た 場 合 、 ﹁ し / る し が ﹂ ﹁ た / ま \ ご が ﹂ の よ う に 1 拍 目 か ら 2 拍 目 に か け て 音 の 上 昇 が あ る ︵ 頭 高 型 を 除 く ︶ 。 し か し こ の 上 昇 は 単 語 に 固 有 の も の で は な く 、 文 中 で は ﹁ あ / か い し る し が ﹂ ﹁ こ / の た ま \ ご が ﹂ の よ う に 、 区 切 ら ず に 発 音 し た ひ と ま と ま り ︵ ﹁ 句 ﹂ と 呼 ぶ ︶ の 始 め に 上 昇 が 現 れ る 。 こ の 上 昇 を 句 音 調 と 言 い 、 句 と 句 の 切 れ 目 を 分 か り や す く す る 機 能 を 担 っ て い る 。 一 方 、 ア ク セ ン ト 核 は 単 語 に 固 定 さ れ て お り 、 ﹁ た ま ご ﹂ の ﹁ ま ﹂ の 後 の 下 が り 目 は な く な る こ と が な い 。 共 通 語 の 音 調 は 、 句 の 2 拍 目 か ら 上 昇 し ︵ 句 の 最 初 の 単 語 が 頭 高 型 の 場 合 は 1 拍 目 か ら 上 昇 す る ︶ 、 ア ク セ ン ト 核 ま で 平 ら に 進 み 、 核 の 後 で 下 が る 。 従 っ て 、 句 頭 で ﹁ 低 低 高 高 … ﹂ や ﹁ 高 高 高 高 … ﹂ の よ う な 音 調 は 現 れ な い 。 ア ク セ ン ト 辞 典 な ど で は 、 ア ク セ ン ト を ﹁ し る し が ﹂ ﹁ た ま ご が ﹂ の よ う に 表 記 す る 場 合 が あ る が 、 こ れ は 1 文 節 を 1 つ の 句 と し て 発 音 す る と き の も の で 、 句 音 調 と ア ク セ ン ト 核 の 両 方 を 同 時 に 表 記 し た も の で あ る 。
日本語 は膠着語 の性質を持ち、主語+目的語+動詞(SOV )を語順とする構成的言語 である。言語分類学上、日本語はほとんどのヨーロッパ言語とはかけ離れた文法構造をしており、句では主要部終端型、複文では左枝分かれの構造をしている。このような言語は多く存在するが、ヨーロッパでは希少である。主題優勢言語 である。
日本語の文の例上の文は、橋本進吉の説に基づき主述構造の文として説明したもの。下の文は、主述構造をなすとは説明しがたいもの。三上章はこれを題述構造の文と捉えている。
日 本 語 で は ﹁ 私 は 本 を 読 む 。 ﹂ と い う 語 順 で 文 を 作 る 。 英 語 で ﹁ I r e a d a b o o k . ﹂ と い う 語 順 を S V O 型 ︵ 主 語 ・ 動 詞 ・ 目 的 語 ︶ と 称 す る 説 明 に な ら っ て い え ば 、 日 本 語 の 文 は S O V 型 と い う こ と に な る 。 も っ と も 、 厳 密 に い え ば 、 英 語 の 文 に 動 詞 が 必 須 で あ る の に 対 し て 、 日 本 語 文 は 動 詞 で 終 わ る こ と も あ れ ば 、 形 容 詞 や 名 詞 + 助 動 詞 で 終 わ る こ と も あ る 。 そ こ で 、 日 本 語 文 の 基 本 的 な 構 造 は 、 ﹁ S ︵ 主 語 ︶ ‐ V ︵ 動 詞 ︶ ﹂ と い う よ り は 、 ﹁ S ︵ 主 語 ︶ ‐ P ︵ 述 語 ︶ ﹂ と い う ﹁ 主 述 構 造 ﹂ と 考 え る ほ う が 、 よ り 適 当 で あ る 。
(一) 私 は ︵ が ︶ 社 長 だ (二) 私 は ︵ が ︶ 行 く 。 (三) 私 は ︵ が ︶ 嬉 し い 。 上 記 の 文 は 、 い ず れ も ﹁ S ‐ P ﹂ 構 造 、 す な わ ち 主 述 構 造 を な す 同 一 の 文 型 で あ る 。 英 語 な ど で は 、 そ れ ぞ れ ﹁ S V C ﹂ ﹁ SV ﹂ ﹁ S V C ﹂ の 文 型 に な る と こ ろ で あ る か ら 、 そ れ に な ら っ て 、 1 を 名 詞 文 、 2 を 動 詞 文 、 3 を 形 容 詞 文 と 分 け る こ と も あ る 。 し か し 、 日 本 語 で は こ れ ら の 文 型 に 本 質 的 な 違 い は な い 。 そ の た め 、 日 本 語 話 者 の 英 語 初 学 者 な ど は 、 ﹁ I a m a p r e s i d e n t . ﹂ ﹁ I a m h a p p y . ﹂ と 同 じ 調 子 で ﹁ I a m g o . ﹂ と 誤 っ た 作 文 を す る こ と が あ る 。
ま た 、 日 本 語 文 で は 、 主 述 構 造 と は 別 に 、 ﹁ 題 目 ‐ 述 部 ﹂ か ら な る ﹁ 題 述 構 造 ﹂ を 採 る こ と が き わ め て 多 い 。 題 目 と は 、 話 の テ ー マ ︵ 主 題 ︶ を 明 示 す る も の で あ る ︵ 三 上 章 は ﹁ what we are talking about ﹂ と 説 明 す る ︶ 。 よ く 主 語 と 混 同 さ れ る が 、 別 概 念 で あ る 。 主 語 は 多 く ﹁ が ﹂ に よ っ て 表 さ れ 、 動 作 や 作 用 の 主 体 を 表 す も の で あ る が 、 題 目 は 多 く ﹁ は ﹂ に よ っ て 表 さ れ 、 そ の 文 が ﹁ こ れ か ら 何 に つ い て 述 べ る の か ﹂ を 明 ら か に す る も の で あ る 。 主 語 に ﹁ は ﹂ が 付 い て い る よ う に 見 え る 文 も 多 い が 、 そ れ は そ の 文 が 動 作 や 作 用 の 主 体 に つ い て 述 べ る 文 、 す な わ ち 題 目 が 同 時 に 主 語 で も あ る 文 だ か ら で あ る 。 そ の よ う な 文 で は 、 題 目 に ﹁ は ﹂ が 付 く こ と に よ り 結 果 的 に 主 語 に ﹁ は ﹂ が 付 く 。 一 方 、 動 作 や 作 用 の 客 体 に つ い て 述 べ る 文 、 す な わ ち 題 目 が 同 時 に 目 的 語 で も あ る 文 で は 、 題 目 に ﹁ は ﹂ が 付 く こ と に よ り 結 果 的 に 目 的 語 に ﹁ は ﹂ が 付 く 。 た と え ば 、
● 4 . 象 は 大 き い 。 ● 5 . 象 は お り に 入 れ た 。 ● 6 . 象 は え さ を や っ た 。 ● 7 . 象 は 鼻 が 長 い 。 な ど の 文 で は 、 ﹁ 象 は ﹂ は い ず れ も 題 目 を 示 し て い る 。 4 の ﹁ 象 は ﹂ は ﹁ 象 が ﹂ に 言 い 換 え ら れ る も の で 、 事 実 上 は 文 の 主 語 を 兼 ね る 。 し か し 、 5 以 下 は ﹁ 象 が ﹂ に は 言 い 換 え ら れ な い 。 5 は ﹁ 象 を ﹂ の こ と で あ り 、 6 は ﹁ 象 に ﹂ の こ と で あ る 。 さ ら に 、 7 の ﹁ 象 は ﹂ は 何 と も 言 い 換 え ら れ な い も の で あ る ︵ ﹁ 象 の ﹂ に 言 い 換 え ら れ る と も い う ︶ 。 こ れ ら の ﹁ 象 は ﹂ と い う 題 目 は 、 ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 特 定 の 格 を 表 す も の で は な く 、 ﹁ 私 は 象 に つ い て 述 べ る ﹂ と い う こ と だ け を ま ず 明 示 す る 役 目 を 持 つ も の で あ る 。
こ れ ら の 文 で は 、 題 目 ﹁ 象 は ﹂ に 続 く 部 分 全 体 が ﹁ 述 部 ﹂ で あ る [ 注 釈 21 ] 。
大 野 晋 は 、 ﹁ が ﹂ と ﹁ は ﹂ は そ れ ぞ れ 未 知 と 既 知 を 表 す と 主 張 し た 。 た と え ば
● 私 が 佐 藤 で す ● 私 は 佐 藤 で す に お い て は 、 前 者 は ﹁ 佐 藤 は ど の 人 物 か と 言 え ば ︵ そ れ ま で 未 知 で あ っ た ︶ 私 が 佐 藤 で す ﹂ を 意 味 し 、 後 者 は ﹁ ︵ す で に 既 知 で あ る ︶ 私 は 誰 か と 言 え ば ︵ 田 中 で は な く ︶ 佐 藤 で す ﹂ と な る 。 し た が っ て ﹁ 何 ﹂ ﹁ ど こ ﹂ ﹁ い つ ﹂ な ど の 疑 問 詞 は 常 に 未 知 を 意 味 す る か ら ﹁ 何 が ﹂ ﹁ ど こ が ﹂ ﹁ い つ が ﹂ と な り 、 ﹁ 何 は ﹂ ﹁ ど こ は ﹂ ﹁ い つ は ﹂ と は 言 え な い 。
ジ ョ ー ゼ フ ・ グ リ ー ン バ ー グ に よ る 構 成 素 順 ︵ ﹁ 語 順 ﹂ ︶ の 現 代 理 論 は 、 言 語 に よ っ て 、 句 が 何 種 類 か 存 在 す る こ と を 認 識 し て い る 。 そ れ ぞ れ の 句 に は 主 要 部 が あ り 、 場 合 に よ っ て は 修 飾 語 が 同 句 に 含 ま れ る 。 句 の 主 要 部 は 、 修 飾 語 の 前 ︵ 主 要 部 先 導 型 ︶ か 後 ろ ︵ 主 要 部 終 端 型 ︶ に 位 置 す る 。 英 語 で の 句 の 構 成 を 例 示 す る と 以 下 の よ う に な る ︵ 太 字 は そ れ ぞ れ の 句 の 主 要 部 ︶ 。
● 属 句 ︵ 例 ‥ 他 の 名 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 ︶ ― " t h e c o v e r o f t h e b o o k " 、 " t h e b o o k ' s c o v e r " な ど ● 接 置 詞 に 支 配 さ れ た 名 詞 ― " on t h e t a b l e " 、 " u n d e r n e a t h t h e t a b l e " ● 比 較 ー " [ X i s ] b i g g e r t h a n Y " 、 例 ‥ " c o m p a r e d t o Y , X i s b i g " ● 形 容 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 ― " b l a c k c a t " 主 要 部 先 導 型 と 主 要 部 終 端 型 の 混 合 に よ っ て 、 構 成 素 順 が 不 規 則 で あ る 言 語 も 存 在 す る 。 例 え ば 、 上 記 の 句 の リ ス ト を 見 る と 、 英 語 で は 大 抵 が 主 要 部 先 導 型 で あ る が 、 名 詞 は 修 飾 す る 形 容 詞 後 の 後 に 位 置 し て い る 。 し か も 、 属 句 で は 主 要 部 先 導 型 と 主 要 部 終 端 型 の い ず れ も 存 在 し 得 る 。 こ れ と は 対 照 的 に 、 日 本 語 は 主 要 部 終 端 型 言 語 の 典 型 で あ る 。
● 属 句 : ﹁ 猫 の 色 ﹂ ● 接 置 詞 に 支 配 さ れ た 名 詞 ‥ ﹁ 日 本 に ﹂ ● 比 較 : ﹁ Y よ り 大 き い ﹂ ● 形 容 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 : ﹁ 黒 い 猫 ﹂ 日 本 語 の 主 要 部 終 端 型 の 性 質 は 、 複 文 な ど の 文 章 単 位 で の 構 成 に お い て も 見 ら れ る 。 文 章 を 構 成 素 と し た 文 章 で は 、 従 属 節 が 常 に 先 行 す る 。 こ れ は 、 従 属 節 が 修 飾 部 で あ り 、 修 飾 す る 文 が 統 語 的 に 句 の 主 要 部 を 擁 し て い る か ら で あ る 。 例 え ば 、 英 語 と 比 較 し た 場 合 、 次 の 英 文 ﹁ t h e m a n w h o w a s w a l k i n g d o w n t h e s t r e e t ﹂ を 日 本 語 に 訳 す 時 、 英 語 の 従 属 節 ︵ 関 係 代 名 詞 節 ︶ で あ る ﹁ ( w h o ) w a s w a l k i n g d o w n t h e s t r e e t ﹂ を 主 要 部 で あ る ﹁ t h e m a n ﹂ の 前 に 位 置 さ せ な け れ ば 、 自 然 な 日 本 語 の 文 章 に は な ら な い 。
ま た 、 主 要 部 終 端 型 の 性 質 は 重 文 で も 見 ら れ る 。 他 言 語 で は 、 一 般 的 に 重 文 構 造 に お い て 、 構 成 節 の 繰 り 返 し を 避 け る 傾 向 に あ る 。 例 え ば 、 英 語 の 場 合 、 ﹁ B o b b o u g h t h i s m o t h e r s o m e f l o w e r s a n d b o u g h t h i s f a t h e r a t i e ﹂ の 文 を 2 番 目 の ﹁ b o u g h t ﹂ を 省 略 し 、 ﹁ B o b b o u g h t h i s m o t h e r s o m e f l o w e r s a n d h i s f a t h e r a t i e ﹂ と す る こ と が 一 般 的 で あ る 。 し か し 、 日 本 語 で は 、 ﹁ ボ ブ は お 母 さ ん に 花 を 買 い 、 お 父 さ ん に ネ ク タ イ を 買 い ま し た ﹂ で あ る と こ ろ を ﹁ ボ ブ は お 母 さ ん に 花 を 、 お 父 さ ん に ネ ク タ イ を 買 い ま し た ﹂ と い う よ う に 初 め の 動 詞 を 省 略 す る 傾 向 に あ る 。 こ れ は 、 日 本 語 の 文 章 が 常 に 動 詞 で 終 わ る 性 質 を 持 つ か ら で あ る 。 ︵ 倒 置 文 や 考 え た 後 で の 後 付 け 文 な ど は 除 く 。 ︶
日本語・英語の構文の違い
三 上 説 に よ れ ば 、 日 本 語 の 文 は 、 ﹁ 紹 介 シ ﹂ の 部 分 に ﹁ ガ ﹂ ﹁ ニ ﹂ ﹁ ヲ ﹂ が 同 等 に 係 る 。 英 語 式 の 文 は 、 ﹁ 甲 ︵ ガ ︶ ﹂ と い う 主 語 だ け が 述 語 ﹁ 紹 介 シ タ ﹂ と 対 立 す る 。 上 述 の ﹁ 象 は 鼻 が 長 い 。 ﹂ の よ う に 、 ﹁ 主 語 ‐ 述 語 ﹂ の 代 わ り に ﹁ 題 目 ‐ 述 部 ﹂ と 捉 え る べ き 文 が 非 常 に 多 い こ と を 考 え る と 、 日 本 語 の 文 に は そ も そ も 主 語 は 必 須 で な い と い う 見 方 も 成 り 立 つ 。 三 上 章 は 、 こ こ か ら ﹁ 主 語 廃 止 論 ﹂ ︵ 主 語 と い う 文 法 用 語 を や め る 提 案 ︶ を 唱 え た 。 三 上 に よ れ ば 、
● 甲 ガ 乙 ニ 丙 ヲ 紹 介 シ タ 。 と い う 文 に お い て 、 ﹁ 甲 ガ ﹂ ﹁ 乙 ニ ﹂ ﹁ 丙 ヲ ﹂ は い ず れ も ﹁ 紹 介 シ ﹂ と い う 行 為 を 説 明 す る た め に 必 要 な 要 素 で あ り 、 優 劣 は な い 。 重 要 な の は 、 そ れ ら を ま と め る 述 語 ﹁ 紹 介 シ タ ﹂ の 部 分 で あ る 。 ﹁ 甲 ガ ﹂ ﹁ 乙 ニ ﹂ ﹁ 丙 ヲ ﹂ は す べ て 述 語 を 補 足 す る 語 ︵ 補 語 ︶ と な る 。 い っ ぽ う 、 英 語 な ど で の 文 で 主 語 は 、 述 語 と 人 称 な ど の 点 で 呼 応 し て お り 、 特 別 の 存 在 で あ る 。
こ の 考 え 方 に 従 え ば 、 英 語 式 の 観 点 か ら は ﹁ 主 語 が 省 略 さ れ て い る ﹂ と し か い い よ う が な い 文 を う ま く 説 明 す る こ と が で き る 。 た と え ば 、
● ハ マ チ の 成 長 し た も の を ブ リ と い う 。 ● こ こ で ニ ュ ー ス を お 伝 え し ま す 。 ● 日 一 日 と 暖 か く な っ て き ま し た 。 な ど は 、 い わ ゆ る 主 語 の な い 文 で あ る 。 し か し 、 日 本 語 の 文 で は 述 語 に 中 心 が あ り 、 補 語 を 必 要 に 応 じ て 付 け 足 す と 考 え れ ば 、 上 記 の い ず れ も 、 省 略 の な い 完 全 な 文 と 見 な し て 差 し 支 え な い 。
今 日 の 文 法 学 説 で は 、 主 語 と い う 用 語 ・ 概 念 は 、 作 業 仮 説 と し て 有 用 な 面 も あ る た め 、 な お 一 般 に 用 い ら れ て い る 。 一 般 的 に は 格 助 詞 ﹁ ガ ﹂ を 伴 う 文 法 項 を 主 語 と 見 な す 。 た だ し 、 三 上 の 説 に 対 す る 形 で 日 本 語 の 文 に 主 語 が 必 須 で あ る と 主 張 す る 学 説 は 、 生 成 文 法 や 鈴 木 重 幸 ら の 言 語 学 研 究 会 グ ル ー プ な ど 、 主 語 に 統 語 上 の 重 要 な 役 割 を 認 め る 学 派 を 除 い て 、 少 数 派 で あ る 。 森 重 敏 は 、 日 本 語 の 文 に お い て も 主 述 関 係 が 骨 子 で あ る と の 立 場 を 採 る が 、 こ の 場 合 の 主 語 ・ 述 語 も 、 一 般 に 言 わ れ る も の と は か な り 様 相 を 異 に し て い る 。 現 在 一 般 的 に 行 わ れ て い る 学 校 教 育 に お け る 文 法 ︵ 学 校 文 法 ︶ で は 、 主 語 ・ 述 語 を 基 本 と し た 伝 統 的 な 文 法 用 語 を 用 い る の が 普 通 だ が 、 教 科 書 に よ っ て は 主 語 を 特 別 扱 い し な い も の も あ る [ 注 釈 22 ] 。
こ の 節 に は 複 数 の 問 題 が あ り ま す 。 改 善 や ノ ー ト ペ ー ジ で の 議 論 に ご 協 力 く だ さ い 。
● 出 典 が ま っ た く 示 さ れ て い な い か 不 十 分 で す 。 内 容 に 関 す る 文 献 や 情 報 源 が 必 要 で す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶ ● 独 自 研 究 が 含 ま れ て い る お そ れ が あ り ま す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶
文 を 主 語 ・ 述 語 か ら 成 り 立 つ と 捉 え る 立 場 で も 、 こ の 2 要 素 だ け で は 文 の 構 造 を 十 分 に 説 明 で き な い 。 主 語 ・ 述 語 に は 、 さ ら に 修 飾 語 な ど の 要 素 が 付 け 加 わ っ て 、 よ り 複 雑 な 文 が 形 成 さ れ る 。 文 を 成 り 立 た せ る こ れ ら の 要 素 を ﹁ 文 の 成 分 ﹂ と 称 す る 。
学 校 文 法 ︵ 中 学 校 の 国 語 教 科 書 ︶ で は 、 文 の 成 分 と し て ﹁ 主 語 ﹂ ﹁ 述 語 ﹂ ﹁ 修 飾 語 ﹂ ︵ 連 用 修 飾 語 ・ 連 体 修 飾 語 ︶ ﹁ 接 続 語 ﹂ ﹁ 独 立 語 ﹂ の 5 つ を 挙 げ て い る [ 要 出 典 ] 。 ﹁ 並 立 語 ︵ 並 立 の 関 係 に あ る 文 節 / 連 文 節 ど う し ︶ ﹂ や ﹁ 補 助 語 ・ 被 補 助 語 ︵ 補 助 の 関 係 に あ る 文 節 / 連 文 節 ど う し ︶ は 文 の 成 分 ︵ あ る い は そ れ を 示 す 用 語 ︶ で は な く 、 文 節 / 連 文 節 ど う し の 関 係 を 表 し た 概 念 で あ っ て 、 常 に 連 文 節 と な っ て 上 記 五 つ の 成 分 に な る と い う 立 場 に 学 校 文 法 は 立 っ て い る 。 し た が っ て 、 ﹁ 並 立 の 関 係 ﹂ ﹁ 補 助 の 関 係 ﹂ と い う 用 語 ︵ 概 念 ︶ を 教 科 書 で は 採 用 し て お り 、 ﹁ 並 立 語 ﹂ ﹁ 補 助 語 ﹂ と い う 用 語 ︵ 概 念 ︶ に つ い て は 載 せ て い な い 教 科 書 が 主 流 で あ る [ 要 出 典 ] 。 な お ﹁ 連 体 修 飾 語 ﹂ も 厳 密 に い え ば そ れ だ け で は 成 分 に は な り 得 ず 、 常 に 被 修 飾 語 と 連 文 節 を 構 成 し て 文 の 成 分 に な る 。
学 校 図 書 を 除 く 四 社 の 教 科 書 で は 、 単 文 節 で で き て い る も の を ﹁ 主 語 ﹂ の よ う に ﹁ - 語 ﹂ と 呼 び 、 連 文 節 で で き て い る も の を ﹁ 主 部 ﹂ の よ う に ﹁ - 部 ﹂ と 呼 ん で い る 。 そ れ に 対 し 学 校 図 書 だ け は 、 文 節 / 連 文 節 ど う し の 関 係 概 念 を ﹁ - 語 ﹂ と 呼 び 、 い わ ゆ る 成 分 ︵ 文 を 構 成 す る 個 々 の 最 大 要 素 ︶ を ﹁ - 部 ﹂ と 呼 ん で い る [ 要 出 典 ] 。
以下、学校文法の区分に従いつつ、それぞれの文の成分の種類と役割とについて述べる。
文を成り立たせる基本的な成分である。ことに述語は、文をまとめる重要な役割を果たす。「雨が降る。」「本が多い。」「私は学生だ。」などは、いずれも主語・述語から成り立っている。教科書によっては、述語を文のまとめ役として最も重視する一方、主語については修飾語と併せて説明するものもある(前節「主語廃止論 」参照)。
用 言 に 係 る 修 飾 語 で あ る ︵ 用 言 に つ い て は ﹁ 自 立 語 ﹂ の 節 を 参 照 ︶ 。 ﹁ 兄 が 弟 に 算 数 を 教 え る 。 ﹂ と い う 文 で ﹁ 弟 に ﹂ ﹁ 算 数 を ﹂ な ど 格 を 表 す 部 分 は 、 述 語 の 動 詞 ﹁ 教 え る ﹂ に か か る 連 用 修 飾 語 と い う こ と に な る 。 ま た 、 ﹁ 算 数 を み っ ち り 教 え る 。 ﹂ ﹁ 算 数 を 熱 心 に 教 え る 。 ﹂ と い う 文 の ﹁ み っ ち り ﹂ ﹁ 熱 心 に ﹂ な ど も 、 ﹁ 教 え る ﹂ に か か る 連 用 修 飾 語 で あ る 。 た だ し 、 ﹁ 弟 に ﹂ ﹁ 算 数 を ﹂ な ど の 成 分 を 欠 く と 、 基 本 的 な 事 実 関 係 が 伝 わ ら な い の に 対 し 、 ﹁ み っ ち り ﹂ ﹁ 熱 心 に ﹂ な ど の 成 分 は 、 欠 い て も そ れ ほ ど 事 実 の 伝 達 に 支 障 が な い 。 こ こ か ら 、 前 者 は 文 の 根 幹 を な す と し て 補 充 成 分 と 称 し 、 後 者 に 限 っ て 修 飾 成 分 と 称 す る 説 も あ る 。 国 語 教 科 書 で も こ の 2 者 を 区 別 し て 説 明 す る も の が あ る 。
体言に係る修飾語である(体言については「自立語 」の節を参照)。「私の本」「動く歩道」「赤い髪飾り」「大きな瞳」の「私の」「動く」「赤い」「大きな」は連体修飾語である。鈴木重幸 ・鈴木康之 ・高橋太郎 ・鈴木泰 らは、ものを表す文の成分に特徴を付与し、そのものがどんなものであるかを規定(限定)する文の成分であるとして、連体修飾語を「規定語 」(または「連体規定語 」)と呼んでいる。
﹁ 疲 れ た の で 、 動 け な い 。 ﹂ ﹁ 買 い た い が 、 金 が な い 。 ﹂ の ﹁ 疲 れ た の で ﹂ ﹁ 買 い た い が ﹂ の よ う に 、 あ と の 部 分 と の 論 理 関 係 を 示 す も の で あ る 。 ま た 、 ﹁ 今 日 は 晴 れ た 。 だ か ら 、 ピ ク ニ ッ ク に 行 こ う 。 ﹂ ﹁ 君 は 若 い 。 な の に 、 な ぜ 絶 望 す る の か 。 ﹂ に お け る ﹁ だ か ら ﹂ ﹁ な の に ﹂ の よ う に 、 前 の 文 と そ の 文 と を つ な ぐ 成 分 も 接 続 語 で あ る 。 品 詞 分 類 で は 、 常 に 接 続 語 と な る 品 詞 を 接 続 詞 と す る 。
﹁ は い 、 分 か り ま し た 。 ﹂ ﹁ 姉 さ ん 、 ど こ へ 行 く の 。 ﹂ ﹁ 新 鮮 、 そ れ が 命 で す 。 ﹂ の ﹁ は い ﹂ ﹁ 姉 さ ん ﹂ ﹁ 新 鮮 ﹂ の よ う に 、 他 の 部 分 に 係 っ た り 、 他 の 部 分 を 受 け た り す る こ と が な い も の で あ る 。 係 り 受 け の 観 点 か ら 定 義 す る と 、 結 果 的 に 、 独 立 語 に は 感 動 ・ 呼 び か け ・ 応 答 ・ 提 示 な ど を 表 す 語 が 該 当 す る こ と に な る 。 品 詞 分 類 で は 、 独 立 語 と し て の み 用 い ら れ る 品 詞 は 感 動 詞 と さ れ る 。 名 詞 や 形 容 動 詞 語 幹 な ど も 独 立 語 と し て 用 い ら れ る 。
﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を 買 う 。 ﹂ ﹁ 琵 琶 湖 の 冬 は 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ の ﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を ﹂ や 、 ﹁ 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ の よ う に 並 立 関 係 で ま と ま っ て い る 成 分 で あ る 。 全 体 と し て の 働 き は 、 ﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を ﹂ の 場 合 は 連 用 修 飾 部 に 相 当 し 、 ﹁ 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ は 述 部 に 相 当 す る 。
現 行 の 学 校 文 法 で は 、 英 語 に あ る よ う な ﹁ 目 的 語 ﹂ ﹁ 補 語 ﹂ な ど の 成 分 は な い と す る 。 英 語 文 法 で は ﹁ I read a book. ﹂ の ﹁ a book ﹂ は S V O 文 型 の 一 部 を な す 目 的 語 で あ り 、 ま た ﹁ I go to the library. ﹂ の ﹁ the library ﹂ は 前 置 詞 と と も に 付 け 加 え ら れ た 修 飾 語 と 考 え ら れ る 。 一 方 、 日 本 語 で は 、
● 私 は 本 を 読 む 。 ● 私 は 図 書 館 へ 行 く 。 の よ う に 、 ﹁ 本 を ﹂ ﹁ 図 書 館 へ ﹂ は ど ち ら も ﹁ 名 詞 + 格 助 詞 ﹂ で 表 現 さ れ る の で あ っ て 、 そ の 限 り で は 区 別 が な い 。 こ れ ら は 、 文 の 成 分 と し て は い ず れ も ﹁ 連 用 修 飾 語 ﹂ と さ れ る 。 こ こ か ら 、 学 校 文 法 に 従 え ば 、 ﹁ 私 は 本 を 読 む 。 ﹂ は 、 ﹁ 主 語 ‐ 目 的 語 ‐ 動 詞 ﹂ ( S O V ) 文 型 と い う よ り は 、 ﹁ 主 語 ‐ 修 飾 語 ‐ 述 語 ﹂ 文 型 で あ る と 解 釈 さ れ る 。
鈴木重幸 ・鈴木康之 らは、「連用修飾語」のうち、「目的語」に当たる語は、述語の表す動きや状態の成立に加わる対象を表す「対象語」であるとし、文の基本成分として認めている。高橋太郎 ・鈴木泰 ・工藤真由美 らは「対象語」と同じ文の成分を、主語・述語が表す事柄の組み立てを明示するために、その成り立ちに参加する物を補うという文中における機能の観点から、「補語」と呼んでいる。
﹁ 明 日 、 学 校 で 運 動 会 が あ る 。 ﹂ の ﹁ 明 日 ﹂ ﹁ 学 校 で ﹂ な ど 、 出 来 事 や 有 様 の 成 り 立 つ 状 況 を 述 べ る た め に 時 や 場 所 、 原 因 や 目 的 ︵ ﹁ 雨 だ か ら ﹂ ︵ ﹁ 体 力 向 上 の た め に ﹂ な ど ︶ を 示 す 文 の 成 分 の こ と を ﹁ 状 況 語 ﹂ と も 言 う [ 注 釈 23 ] 。 学 校 文 法 で は ﹁ 連 用 修 飾 語 ﹂ に 含 ん で い る が 、 ︵ 連 用 ︶ 修 飾 語 が 、 述 語 の 表 す 内 的 な 属 性 を 表 す の に 対 し て 、 状 況 語 は 外 的 状 況 を 表 す ﹁ と り ま き ﹂ な い し は ﹁ 額 縁 ﹂ の 役 目 を 果 た し て い る 。 状 況 語 は 、 出 来 事 や 有 様 を 表 す 部 分 の 前 に 置 か れ る の が 普 通 で あ り 、 主 語 の 前 に 置 か れ る こ と も あ る 。 な お 、 ﹁ 状 況 語 ﹂ と い う 用 語 は ロ シ ア 語 ・ ス ペ イ ン 語 ・ 中 国 語 ︵ 中 国 語 で は ﹁ 状 語 ﹂ と 言 う ︶ な ど に も あ る が 、 日 本 語 の ﹁ 状 況 語 ﹂ と 必 ず し も 概 念 が 一 致 し て い る わ け で は な く 、 修 飾 語 を 含 ん だ 概 念 で あ る 。
日本語では、修飾語はつねに被修飾語の前に位置する。「ぐんぐん進む」「白い雲」の「ぐんぐん」「白い」はそれぞれ「進む」「雲」の修飾語である。修飾語が長大になっても位置関係は同じで、たとえば、
ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲
と い う 短 歌 は 、 冒 頭 か ら ﹁ ひ と ひ ら の ﹂ ま で が ﹁ 雲 ﹂ に 係 る 長 い 修 飾 語 で あ る 。
法 律 文 や 翻 訳 文 な ど で も 、 長 い 修 飾 語 を 主 語 ・ 述 語 の 間 に 挟 み 、 文 意 を 取 り に く く し て い る こ と が し ば し ば あ る 。 た と え ば 、 日 本 国 憲 法 前 文 の 一 節 に 、
わ れ ら は 、 い づ れ の 国 家 も 、 自 国 の こ と の み に 専 念 し て 他 国 を 無 視 し て は な ら な い の で あ つ て 、 政 治 道 徳 の 法 則 は 、 普 遍 的 な も の で あ り 、 こ の 法 則 に 従 ふ こ と は 、 自 国 の 主 権 を 維 持 し 、 他 国 と 対 等 関 係 に 立 た う と す る 各 国 の 責 務 で あ る と 信 ず る 。 と あ る が 、 主 語 ︵ 題 目 ︶ の ﹁ わ れ ら ﹂ 、 述 語 の ﹁ 信 ず る ﹂ の 間 に ﹁ い づ れ の 国 家 も … … で あ る と ﹂ と い う 長 い 修 飾 語 が 介 在 し て い る 。 こ の 種 の 文 を 読 み 慣 れ た 人 で な け れ ば 分 か り に く い 。 英 訳 で " W e h o l d … " ︵ わ れ ら は 信 ず る ︶ と 主 語 ・ 述 語 が 隣 り 合 う の と は 対 照 的 で あ る 。
も っ と も 、 修 飾 語 が 後 置 さ れ る 英 語 で も 、 修 飾 関 係 の 分 か り に く い 文 が 現 れ る こ と が あ る 。 次 の よ う な 文 は ﹁ 袋 小 路 文 ﹂ と 呼 ば れ る 。
T h e h o r s e r a c e d p a s t t h e b a r n f e l l . ︵ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た 馬 が 倒 れ た 。 ︶ こ の 場 合 、 日 本 語 の 文 で は ﹁ 馬 ﹂ に 係 る 連 体 修 飾 語 ﹁ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た ﹂ が 前 に 来 て い る た め に 文 構 造 が わ か り や す い が 、 英 語 で は ﹁ The horse ﹂ を 修 飾 す る ﹁ raced past the barn ﹂ が あ と に 来 て い る た め に 、 構 造 が 把 握 し づ ら く な っ て い る 。 具 体 的 に は 、 こ の 英 文 の 途 中 ﹁ The horse raced past the barn ﹂ ま で し か 読 ん で い な い 状 況 で は 、 文 の 成 分 と し て の 動 詞 ︵ 主 語 は ﹁ The horse ﹂ ︶ は ﹁ raced ﹂ で あ る よ う に 感 じ ら れ る が 、 ﹁ fell ﹂ ま で 行 き 着 く と 、 文 の 成 分 と し て の 動 詞 は 、 文 法 上 、 こ れ ま で 唯 一 の 候 補 だ っ た ( 1 ) ﹁ raced ﹂ に 加 え 、 ( 2 ) ﹁ fell ﹂ が 出 て く る こ と に な り 、 そ れ ぞ れ の 候 補 ご と に ( 1 ) ﹁ ︻ ︵ 習 慣 的 に 、 ま た は 一 般 法 則 に 従 っ て [ 注 釈 24 ] ︶ ︼ 崩 れ る 納 屋 の そ ば を 馬 が 素 早 く 走 り 抜 け た ﹂ な の か ( 2 ) ﹁ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た 馬 が 倒 れ た ﹂ な の か を 検 討 し な け れ ば な ら な く な る 。
学校文法の品詞体系元の図は、 橋本進吉「国語法要説」に掲載。上図および現在の国語教科書では微修正を加えている。
名 詞 や 動 詞 、 形 容 詞 と い っ た ﹁ 品 詞 ﹂ の 概 念 は 、 上 述 し た ﹁ 文 の 成 分 ﹂ の 概 念 と は 分 け て 考 え る 必 要 が あ る 。 名 詞 ﹁ 犬 ﹂ は 、 文 の 成 分 と し て は 主 語 に も な れ ば 修 飾 語 に も な り 、 ﹁ 犬 だ ﹂ の よ う に 助 動 詞 ﹁ だ ﹂ を 付 け て 述 語 に も な る 。 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 も 、 修 飾 語 に も な れ ば 述 語 に も な る 。 も っ と も 、 副 詞 は 多 く 連 用 修 飾 語 と し て 用 い ら れ 、 ま た 、 連 体 詞 は 連 体 修 飾 語 に 、 接 続 詞 は 接 続 語 に 、 感 動 詞 は 独 立 語 に も っ ぱ ら 用 い ら れ る が 、 必 ず し も 、 特 定 の 品 詞 が 特 定 の 文 の 成 分 に 1 対 1 で 対 応 し て い る わ け で は な い 。
で は 、 そ れ ぞ れ の 品 詞 の 特 徴 を 形 作 る も の は 何 か と い う こ と が 問 題 に な る が 、 こ れ に つ い て は 、 さ ま ざ ま な 説 明 が あ り 、 一 定 し な い 。 俗 に 、 事 物 を 表 す 単 語 が 名 詞 、 動 き を 表 す 単 語 が 動 詞 、 様 子 を 表 す 単 語 が 形 容 詞 な ど と い わ れ る こ と が あ る が 、 例 外 が い く ら で も 挙 が り 、 定 義 と し て は 成 立 し な い 。
橋 本 進 吉 は 、 品 詞 を 分 類 す る に あ た り 、 単 語 の 表 す 意 味 ︵ 動 き を 表 す か 様 子 を 表 す か な ど ︶ に は 踏 み 込 ま ず 、 主 と し て 形 式 的 特 徴 に よ っ て 品 詞 分 類 を 行 っ て い る 。 橋 本 の 考 え 方 は 初 学 者 に も 分 か り や す い た め 、 学 校 文 法 も そ の 考 え 方 に 基 づ い て い る 。
学 校 文 法 で は 、 語 の う ち 、 ﹁ 太 陽 ﹂ ﹁ 輝 く ﹂ ﹁ 赤 い ﹂ ﹁ ぎ ら ぎ ら ﹂ な ど 、 そ れ だ け で 文 節 を 作 り 得 る も の を 自 立 語 ︵ 詞 ︶ と し 、 ﹁ よ う だ ﹂ ﹁ で す ﹂ ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ な ど 、 単 独 で 文 節 を 作 り 得 ず 、 自 立 語 に 付 属 し て 用 い ら れ る も の を 付 属 語 ︵ 辞 ︶ と す る 。 な お 、 日 本 語 で は 、 自 立 語 の 後 に 接 辞 や 付 属 語 を 次 々 に つ け 足 し て 文 法 的 な 役 割 な ど を 示 す た め 、 言 語 類 型 論 上 は 膠 着 語 に 分 類 さ れ る 。
自 立 語 は 、 活 用 の な い も の と 、 活 用 の あ る も の と に 分 け ら れ る 。
自 立 語 で 活 用 の な い も の の う ち 、 主 語 に な る も の を 名 詞 と す る 。 名 詞 の う ち 、 代 名 詞 ・ 数 詞 を 独 立 さ せ る 考 え 方 も あ る 。 一 方 、 主 語 に な ら ず 、 単 独 で 連 用 修 飾 語 に な る も の を 副 詞 、 連 体 修 飾 語 に な る も の を 連 体 詞 ︵ 副 体 詞 ︶ 、 接 続 語 に な る も の を 接 続 詞 、 独 立 語 と し て の み 用 い ら れ る も の を 感 動 詞 と す る 。 副 詞 ・ 連 体 詞 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 一 品 詞 と す べ き か ど う か に つ い て 議 論 が あ り 、 さ ら に 細 分 化 す る 考 え 方 [ 68 ] や 、 他 の 品 詞 に 吸 収 さ せ る 考 え 方 な ど が あ る 。
自 立 語 で 活 用 の あ る も の の う ち 、 命 令 形 の あ る も の を 動 詞 、 命 令 形 が な く 終 止 ・ 連 体 形 が ﹁ い ﹂ で 終 わ る も の を 形 容 詞 ︵ 日 本 語 教 育 で は ﹁ イ 形 容 詞 ﹂ ︶ 、 連 体 形 が ﹁ な ﹂ で 終 わ る も の を 形 容 動 詞 ︵ 日 本 語 教 育 で は ﹁ ナ 形 容 詞 ﹂ ︶ と す る 。 形 容 動 詞 を 一 品 詞 と し て 認 め る こ と に つ い て は 、 時 枝 誠 記 や 鈴 木 重 幸 な ど 、 否 定 的 な 見 方 を す る 研 究 者 も い る 。
な お 、 ﹁ 名 詞 ﹂ お よ び ﹁ 体 言 ﹂ と い う 用 語 は 、 し ば し ば 混 同 さ れ る 。 古 来 、 こ と ば を 分 類 す る に あ た り 、 活 用 の な い 語 を ﹁ 体 言 ﹂ ︵ 体 ︶ 、 活 用 の あ る 語 を ﹁ 用 言 ﹂ ︵ 用 ︶ 、 そ の ほ か 、 助 詞 ・ 助 動 詞 の 類 を ﹁ て に を は ﹂ と 大 ざ っ ぱ に 称 す る こ と が 多 か っ た 。 現 在 の 学 校 文 法 で は 、 ﹁ 用 言 ﹂ は 活 用 の あ る 自 立 語 の 意 味 で 用 い ら れ ︵ 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 を 指 す ︶ 、 ﹁ 体 言 ﹂ は 活 用 の な い 自 立 語 の 中 で も 名 詞 ︵ お よ び 代 名 詞 ・ 数 詞 ︶ を 指 す よ う に な っ た 。 つ ま り 、 現 在 で は ﹁ 体 言 ﹂ と ﹁ 名 詞 ﹂ と は 同 一 物 と 見 て も 差 し 支 え は な い が 、 活 用 し な い 語 と い う 点 に 着 目 し て い う 場 合 は ﹁ 体 言 ﹂ 、 文 の 成 分 の う ち 主 語 に な り う る と い う 点 に 着 目 し て い う 場 合 は ﹁ 名 詞 ﹂ と 称 す る 。
付 属 語 も 、 活 用 の な い も の と 、 活 用 の あ る も の と に 分 け ら れ る 。
付 属 語 で 活 用 の な い も の を 助 詞 と 称 す る 。 ﹁ 春 が 来 た ﹂ ﹁ 買 っ て く る ﹂ ﹁ や る し か な い ﹂ ﹁ 分 か っ た か ﹂ な ど の 太 字 部 分 は す べ て 助 詞 で あ る 。 助 詞 は 、 名 詞 に つ い て 述 語 と の 関 係 ︵ 格 関 係 ︶ を 表 す 格 助 詞 ︵ ﹁ 名 詞 の 格 ﹂ の 節 参 照 ︶ 、 活 用 す る 語 に つ い て 後 続 部 分 と の 接 続 関 係 を 表 す 接 続 助 詞 、 種 々 の 語 に つ い て 、 程 度 や 限 定 な ど の 意 味 を 添 え つ つ 後 続 の 用 言 な ど を 修 飾 す る 副 助 詞 、 文 の 終 わ り に 来 て 疑 問 や 詠 嘆 ・ 感 動 ・ 禁 止 と い っ た 気 分 や 意 図 を 表 す 終 助 詞 に 分 け ら れ る 。 鈴 木 重 幸 ・ 高 橋 太 郎 他 ・ 鈴 木 康 之 ら は 助 詞 を 単 語 と は 認 め ず 、 付 属 辞 ︵ ﹁ く っ つ き ﹂ ︶ と し て 、 単 語 の 一 部 と す る 。 ︵ 格 助 詞 ・ 並 立 助 詞 ・ 係 助 詞 ・ 副 助 詞 ・ 終 助 詞 の 全 部 お よ び 接 続 助 詞 の う ち ﹁ し ﹂ ﹁ が ﹂ ﹁ け れ ど も ﹂ ﹁ か ら ﹂ ﹁ の で ﹂ ﹁ の に ﹂ に つ い て ︶ ま た は 語 尾 ︵ 接 続 助 詞 の う ち ﹁ て ︵ で ︶ ﹂ 、 条 件 の 形 の ﹁ ば ﹂ 、 並 べ 立 て る と き の ﹁ た り ︵ だ り ︶ ﹂ に つ い て ︶ 。
付 属 語 で 活 用 の あ る も の を 助 動 詞 と 称 す る 。 ﹁ 気 を 引 か れ る ﹂ ﹁ 私 は 泣 か な い ﹂ ﹁ 花 が 笑 っ た ﹂ ﹁ さ あ 、 出 か け よ う ﹂ ﹁ 今 日 は 来 な い そ う だ ﹂ ﹁ も う す ぐ 春 で す ﹂ な ど の 太 字 部 分 は す べ て 助 動 詞 で あ る 。 助 動 詞 の 最 も 主 要 な 役 割 は 、 動 詞 ︵ お よ び 助 動 詞 ︶ に 付 属 し て 以 下 の よ う な 情 報 を 加 え る こ と で あ る 。 す な わ ち 、 動 詞 の 態 ︵ 特 に 受 け 身 ・ 使 役 ・ 可 能 な ど 。 ヴ ォ イ ス ︶ ・ 極 性 ︵ 肯 定 ・ 否 定 の 決 定 。 ポ ラ リ テ ィ ︶ ・ 時 制 ︵ テ ン ス ︶ ・ 相 ︵ ア ス ペ ク ト ︶ ・ 法 ︵ 推 量 ・ 断 定 ・ 意 志 な ど 。 ム ー ド ︶ な ど を 示 す 役 割 を 持 つ 。 山 田 孝 雄 は 、 助 動 詞 を 認 め ず 、 動 詞 か ら 分 出 さ れ る 語 尾 ︵ 複 語 尾 ︶ と 見 な し て い る 。 ま た 時 枝 誠 記 は 、 ﹁ れ る ︵ ら れ る ︶ ﹂ ﹁ せ る ︵ さ せ る ︶ ﹂ を 助 動 詞 と せ ず 、 動 詞 の 接 尾 語 と し て い る 。 鈴 木 重 幸 ・ 鈴 木 康 之 ・ 高 橋 太 郎 ら は 大 部 分 の 助 動 詞 を 単 語 と は 認 め な い 。 ﹁ た ︵ だ ︶ ﹂ ﹁ う ︵ よ う ︶ は 、 動 詞 の 語 尾 で あ る と し 、 ﹁ な い ﹂ ﹁ よ う ﹂ ﹁ ま す ﹂ ﹁ れ る ﹂ ﹁ ら れ る ﹂ ﹁ せ る ﹂ ﹁ さ せ る ﹂ ﹁ た い ﹂ ﹁ そ う だ ﹂ ﹁ よ う だ ﹂ は 、 接 尾 辞 で あ る と し て 、 単 語 の 一 部 と す る 。 ︵ ﹁ よ う だ ﹂ ﹁ ら し い ﹂ ﹁ そ う だ ﹂ に 関 し て は 、 ﹁ む す び ﹂ ま た は ﹁ コ ピ ュ ラ ﹂ ﹁ 繋 辞 ﹂ で あ る と す る 。 ︶
名 詞 お よ び 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 は 、 そ れ が 文 中 で ど の よ う な 成 分 を 担 っ て い る か を 特 別 の 形 式 に よ っ て 表 示 す る 。
名 詞 の 場 合 、 ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ に ﹂ な ど の 格 助 詞 を 後 置 す る こ と で 動 詞 と の 関 係 ︵ 格 ︶ を 示 す 。 語 順 に よ っ て 格 を 示 す 言 語 で は な い た め 、 日 本 語 は 語 順 が 比 較 的 自 由 で あ る 。 す な わ ち 、
● 桃 太 郎 が 犬 に き び だ ん ご を や り ま し た 。 ● 犬 に 桃 太 郎 が き び だ ん ご を や り ま し た 。 ● き び だ ん ご を 桃 太 郎 が 犬 に や り ま し た 。 な ど は 、 強 調 さ れ る 語 は 異 な る が 、 い ず れ も 同 一 の 内 容 を 表 す 文 で 、 し か も 正 し い 文 で あ る 。
主 な 格 助 詞 と そ の 典 型 的 な 機 能 は 次 の 通 り で あ る 。
助詞
機能
使用例
が
動作・作用の主体を表す。
例:「空が青い」、「犬がいる」
の
連体修飾を表す。
「私の本」、「理想の家庭」
を
動作・作用の対象を表す。
「本を読む」、「人を教える」
に
動作・作用の到達点を表す。
「駅に着く」、「人に教える」
へ
動作・作用の及ぶ方向を表す。
「駅へ向かう」、「学校へ出かける」
と
動作・作用をともに行う相手を表す。
「友人と帰る」、「車とぶつかる」
から
動作・作用の起点を表す。
「旅先から戻る」、「6時から始める」
より
動作・作用の起点や、比較の対象を表す。
「旅先より戻る」、「花より美しい」
で
動作・作用の行われる場所を表す。
「川で洗濯する」、「風呂で寝る」
こ の よ う に 、 格 助 詞 は 、 述 語 を 連 用 修 飾 す る 名 詞 が 述 語 と ど の よ う な 関 係 に あ る か を 示 す ︵ た だ し 、 ﹁ の ﹂ だ け は 連 体 修 飾 に 使 わ れ 、 名 詞 同 士 の 関 係 を 示 す ︶ 。 な お 、 上 記 は あ く ま で も 典 型 的 な 機 能 で あ り 、 主 体 を 表 さ な い ﹁ が ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 水 が 飲 み た い ﹂ ︶ 、 対 象 を 表 さ な い ﹁ を ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 日 本 を 発 っ た ﹂ ︶ 、 到 達 点 を 表 さ な い ﹁ に ﹂ ︵ 例 、 受 動 動 作 の 主 体 ﹁ 先 生 に ほ め ら れ た ﹂ 、 地 位 の 所 在 ﹁ 今 上 天 皇 に あ ら せ ら れ る ﹂ ︶ 、 主 体 を 表 す ﹁ の ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 私 は 彼 の 急 い で 走 っ て い る の を 見 た ﹂ ︶ な ど 、 上 記 に 収 ま ら な い 機 能 を 担 う 場 合 も 多 い 。
格 助 詞 の う ち 、 ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ に ﹂ は 、 話 し 言 葉 に お い て は 脱 落 す る こ と が 多 い 。 そ の 場 合 、 文 脈 の 助 け が な け れ ば 、 最 初 に 来 る 部 分 は ﹁ が ﹂ 格 に 相 当 す る と 見 な さ れ る 。 ﹁ く じ ら を お 父 さ ん が 食 べ て し ま っ た 。 ﹂ を ﹁ く じ ら 、 お 父 さ ん 食 べ ち ゃ っ た 。 ﹂ と 助 詞 を 抜 か し て 言 っ た 場 合 は 、 ﹁ く じ ら ﹂ が ﹁ が ﹂ 格 相 当 と と ら え ら れ る た め 、 誤 解 の 元 に な る 。 ﹁ チ ョ コ レ ー ト を 私 が 食 べ て し ま っ た 。 ﹂ を ﹁ チ ョ コ レ ー ト 、 私 食 べ ち ゃ っ た 。 ﹂ と 言 っ た 場 合 は 、 文 脈 の 助 け に よ っ て 誤 解 は 避 け ら れ る 。 な お 、 ﹁ へ ﹂ ﹁ と ﹂ ﹁ か ら ﹂ ﹁ よ り ﹂ ﹁ で ﹂ な ど の 格 助 詞 は 、 話 し 言 葉 に お い て も 脱 落 し な い 。
題 述 構 造 の 文 ︵ ﹁ 文 の 構 造 ﹂ の 節 参 照 ︶ で は 、 特 定 の 格 助 詞 が ﹁ は ﹂ に 置 き 換 わ る 。 た と え ば 、 ﹁ 空 が 青 い 。 ﹂ と い う 文 は 、 ﹁ 空 ﹂ を 題 目 化 す る と ﹁ 空 は 青 い 。 ﹂ と な る 。 題 目 化 の 際 の ﹁ は ﹂ の 付 き 方 は 、 以 下 の よ う に そ れ ぞ れ の 格 助 詞 に よ っ て 異 な る 。
無題の文
題述構造の文
空が 青い。
空は 青い。
本を 読む。
本は 読む。
学校に 行く。
学校は 行く。(学校には 行く。)
駅へ 向かう。
駅へは 向かう。
友人と 帰る。
友人とは 帰る。
旅先から 戻る。
旅先からは 戻る。
川で 洗濯する。
川では 洗濯する。
格 助 詞 は 、 下 に 来 る 動 詞 が 何 で あ る か に 応 じ て 、 必 要 と さ れ る 種 類 と 数 が 変 わ っ て く る 。 た と え ば 、 ﹁ 走 る ﹂ と い う 動 詞 で 終 わ る 文 に 必 要 な の は ﹁ が ﹂ 格 で あ り 、 ﹁ 馬 が 走 る 。 ﹂ と す れ ば 完 全 な 文 に な る 。 と こ ろ が 、 ﹁ 教 え る ﹂ の 場 合 は 、 ﹁ が ﹂ 格 を 加 え て ﹁ 兄 が 教 え て い ま す 。 ﹂ と し た だ け で は 不 完 全 な 文 で あ る 。 さ ら に ﹁ で ﹂ 格 を 加 え 、 ﹁ 兄 が 小 学 校 で 教 え て い ま す ︵ = 教 壇 に 立 っ て い ま す ︶ 。 ﹂ と す れ ば 完 全 に な る 。 つ ま り 、 ﹁ 教 え る ﹂ は 、 ﹁ が ・ で ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。
と こ ろ が 、 ﹁ 兄 が 部 屋 で 教 え て い ま す 。 ﹂ と い う 文 の 場 合 、 ﹁ が ・ で ﹂ 格 が あ る に も か か わ ら ず 、 な お 完 全 な 文 と い う 感 じ が し な い 。 ﹁ 兄 が 部 屋 で 弟 に 算 数 を 教 え て い ま す 。 ﹂ の よ う に ﹁ が ・ に ・ を ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。 む し ろ 、 ﹁ で ﹂ 格 は な く と も 文 は 不 完 全 な 印 象 は な い 。
す な わ ち 、 同 じ ﹁ 教 え る ﹂ で も 、 ﹁ 教 壇 に 立 つ ﹂ と い う 意 味 の ﹁ 教 え る ﹂ は ﹁ が ・ で ﹂ 格 が 必 要 で あ り 、 ﹁ 説 明 し て 分 か る よ う に さ せ る ﹂ と い う 意 味 の ﹁ 教 え る ﹂ で は ﹁ が ・ に ・ を ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。 こ の よ う に 、 そ れ ぞ れ の 文 を 成 り 立 た せ る の に 必 要 な 格 を ﹁ 必 須 格 ﹂ と い う 。
名 詞 が 格 助 詞 を 伴 っ て さ ま ざ ま な 格 を 示 す の に 対 し 、 用 言 ︵ 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 ︶ お よ び 助 動 詞 は 、 語 尾 を 変 化 さ せ る こ と に よ っ て 、 文 中 の ど の 成 分 を 担 っ て い る か を 示 し た り 、 時 制 ・ 相 な ど の 情 報 や 文 の 切 れ 続 き の 別 な ど を 示 し た り す る 。 こ の 語 尾 変 化 を ﹁ 活 用 ﹂ と い い 、 活 用 す る 語 を 総 称 し て ﹁ 活 用 語 ﹂ と い う 。
学 校 文 法 で は 、 口 語 の 活 用 語 に つ い て 、 6 つ の 活 用 形 を 認 め て い る 。 以 下 、 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 の 活 用 形 を 例 に 挙 げ る ︵ 太 字 部 分 ︶ 。
活用形
動詞
形容詞
形容動詞
未然形
打た ない打と う強かろ う勇敢だろ う
連用形
打ち ます打っ た強かっ た強く なる強う ございます勇敢だっ た勇敢で ある勇敢に なる
終止形
打つ 。強い 。勇敢だ 。
連体形
打つ こと強い こと勇敢な こと
仮定形
打て ば強けれ ば勇敢なら ば
命令形
打て 。○
○
一 般 に 、 終 止 形 は 述 語 に 用 い ら れ る 。 ﹁ ︵ 選 手 が 球 を ︶ 打 つ 。 ﹂ ﹁ ︵ こ の 子 は ︶ 強 い 。 ﹂ ﹁ ︵ 消 防 士 は ︶ 勇 敢 だ 。 ﹂ な ど 。
連 用 形 は 、 文 字 通 り 連 用 修 飾 語 に も 用 い ら れ る 。 ﹁ 強 く ︵ 生 き る 。 ︶ ﹂ ﹁ 勇 敢 に ︵ 突 入 す る 。 ︶ ﹂ な ど 。 た だ し 、 ﹁ 選 手 が 球 を 打 ち ま し た 。 ﹂ の ﹁ 打 ち ﹂ は 連 用 形 で あ る が 、 連 用 修 飾 語 で は な く 、 こ の 場 合 は 述 語 の 一 部 で あ る 。 こ の よ う に 、 活 用 形 と 文 中 で の 役 割 は 、 1 対 1 で 対 応 し て い る わ け で は な い 。
仮 定 形 は 、 文 語 で は 已 然 形 と 称 す る 。 口 語 の ﹁ 打 て ば ﹂ は 仮 定 を 表 す が 、 文 語 の ﹁ 打 て ば ﹂ は ﹁ 已 ︵ す で ︶ に 打 っ た の で ﹂ の 意 味 を 表 す か ら で あ る 。 ま た 、 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 は 、 口 語 で は 命 令 形 が な い が 、 文 語 で は ﹁ 稽 古 は 強 か れ 。 ﹂ ︵ 風 姿 花 伝 ︶ の ご と く 命 令 形 が 存 在 す る 。
動 詞 の 活 用 は 種 類 が 分 か れ て い る 。 口 語 の 場 合 は 、 五 段 活 用 ・ 上 一 段 活 用 ・ 下 一 段 活 用 ・ カ 行 変 格 活 用 ︵ カ 変 ︶ ・ サ 行 変 格 活 用 ︵ サ 変 ︶ の 5 種 類 で あ る 。
動詞の種類
特徴
例
五段動詞
未然形活用語尾が「あ段 音」で終わるもの
「買う」「畳む」
上一段動詞
未然形活用語尾が「い段 音」で終わるもの
「見る」「借りる」
下一段動詞
未然形活用語尾が「え段 音」で終わるもの
「出る」「受ける」
カ変動詞
「来る」および「来る」を語末要素とするもの
「来る」
サ変動詞
「する」および「する」を語末要素とするもの
「する」
あ る 言 語 の 語 彙 体 系 を 見 渡 し て 、 特 定 の 分 野 の 語 彙 が 豊 富 で あ る と か 、 別 の 分 野 の 語 彙 が 貧 弱 で あ る と か を 決 め つ け る こ と は 、 一 概 に は で き な い 。 日 本 語 で も 、 た と え ば ﹁ 自 然 を 表 す 語 彙 が 多 い と い う の が 定 評 ﹂ と い わ れ る が 、 こ れ は 人 々 の 直 感 か ら 来 る 評 判 と い う 意 味 以 上 の も の で は な い 。
実 際 に 、 旧 版 ﹃ 分 類 語 彙 表 ﹄ に よ っ て 分 野 ご と の 語 彙 量 の 多 寡 を 比 べ た 結 果 に よ れ ば 、 名 詞 ︵ 体 の 類 ︶ の う ち ﹁ 人 間 活 動 ― 精 神 お よ び 行 為 ﹂ に 属 す る も の が 2 7 . 0 % 、 ﹁ 抽 象 的 関 係 ﹂ が 1 8 . 3 % 、 ﹁ 自 然 物 お よ び 自 然 現 象 ﹂ が 1 0 . 0 % な ど と な っ て い て 、 こ の 限 り で は ﹁ 自 然 ﹂ よ り も ﹁ 精 神 ﹂ や ﹁ 行 為 ﹂ な ど を 表 す 語 彙 の ほ う が 多 い こ と に な る 。 た だ し 、 こ れ も 、 他 の 言 語 と 比 較 し て 多 い と い う こ と で は な く 、 こ の 結 果 が た だ ち に 日 本 語 の 語 彙 の 特 徴 を 示 す こ と に は な ら な い 。
日 本 語 の 人 称 は あ ま り 固 定 化 し て い な い 。 現 代 語 ・ 標 準 語 の 範 疇 と し て は 、 一 人 称 は ﹁ わ た く し ・ わ た し ・ あ た し ・ ぼ く ・ お れ ・ う ち ・ 自 分 ・ 我 々 ﹂ な ど 、 二 人 称 は ﹁ あ な た ・ あ ん た ・ お ま え ・ お め え ・ て め え ・ き み ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。 方 言 ・ 近 代 語 ・ 古 語 ま で 含 め る と こ の 限 り で は な く 、 文 献 上 で は 他 に も ﹁ あ た く し ・ あ た い ・ わ し ・ わ い ・ わ て ・ 我 が 輩 ・ お れ 様 ・ お い ら ・ わ れ ・ わ ー ・ わ ん ・ 朕 ・ わ っ し ・ こ ち と ら ・ て ま え ・ 小 生 ・ そ れ が し ・ 拙 者 ・ お ら ﹂ な ど の 一 人 称 、 ﹁ お ま え さ ん ・ て め え ・ 貴 様 ・ お の れ ・ わ れ ・ お 宅 ・ な ん じ ・ お ぬ し ・ そ の 方 ・ 貴 君 ・ 貴 兄 ・ 貴 下 ・ 足 下 ・ 貴 公 ・ 貴 女 ・ 貴 殿 ・ 貴 方 ︵ き ほ う ︶ ﹂ な ど の 二 人 称 が 見 つ か る 。
上 の 事 実 は 、 現 代 英 語 の 一 人 称 ・ 二 人 称 代 名 詞 が ほ ぼ " I " と " y o u " の み で あ り 、 フ ラ ン ス 語 の 一 人 称 代 名 詞 が " j e " 、 二 人 称 代 名 詞 が " t u " " v o u s " の み 、 ま た ド イ ツ 語 の 一 人 称 代 名 詞 が " i c h " 、 二 人 称 代 名 詞 が " d u " " S i e " " i h r " の み で あ る こ と と 比 較 す れ ば 、 特 徴 的 と い う こ と が で き る 。 も っ と も 、 日 本 語 に お い て も 、 本 来 の 人 称 代 名 詞 は 、 一 人 称 に ﹁ ワ ︵ レ ︶ ﹂ ﹁ ア ︵ レ ︶ ﹂ 、 二 人 称 に ﹁ ナ ︵ レ ︶ ﹂ が あ る の み で あ る ︵ 但 し ﹃ ナ ﹄ は も と 一 人 称 と も 見 ら れ 、 後 述 の こ と と も 関 係 が あ る が ︶ 。 今 日 、 一 ・ 二 人 称 同 様 に 用 い ら れ る 語 は 、 そ の 大 部 分 が 一 般 名 詞 か ら の 転 用 で あ る [ 76 ] 。 一 人 称 を 示 す ﹁ ぼ く ﹂ や 三 人 称 を 示 す ﹁ 彼 女 ﹂ な ど を 、 ﹁ ぼ く 、 何 歳 ? ﹂ ﹁ 彼 女 、 ど こ 行 く の ? ﹂ の よ う に 二 人 称 に 転 用 す る こ と が 可 能 で あ る の も 、 日 本 語 の 人 称 語 彙 が 一 般 名 詞 的 で あ る こ と の 現 れ で あ る 。
な お 、 敬 意 表 現 の 観 点 か ら 、 目 上 に 対 し て は 二 人 称 代 名 詞 の 使 用 が 避 け ら れ る 傾 向 が あ る 。 た と え ば 、 ﹁ あ な た は 何 時 に 出 か け ま す か ﹂ と は 言 わ ず 、 ﹁ 何 時 に い ら っ し ゃ い ま す か ﹂ の よ う に 言 う こ と が 普 通 で あ る 。
﹁ 親 族 語 彙 の 体 系 ﹂ の 節 も 参 照 。
ま た 、 音 象 徴 語 、 い わ ゆ る オ ノ マ ト ペ の 語 彙 量 も 日 本 語 に は 豊 富 で あ る ︵ オ ノ マ ト ペ の 定 義 は 一 定 し な い が 、 こ こ で は 、 擬 声 語 ・ 擬 音 語 の よ う に 耳 に 聞 こ え る も の を 写 し た 語 と 、 擬 態 語 の よ う に 耳 に 聞 こ え な い 状 態 ・ 様 子 な ど を 写 し た 語 の 総 称 と し て 用 い る ︶ 。
擬 声 語 は 、 人 や 動 物 が 立 て る 声 を 写 し た も の で あ る ︵ 例 、 お ぎ ゃ あ ・ が お う ・ げ ら げ ら ・ に ゃ あ に ゃ あ ︶ 。 擬 音 語 は 、 物 音 を 写 し た も の で あ る ︵ 例 、 が た が た ・ が ん が ん ・ ば ん ば ん ・ ど ん ど ん ︶ 。 擬 態 語 は 、 も の ご と の 様 子 や 心 理 の 動 き な ど を 表 し た も の で あ る ︵ 例 、 き ょ ろ き ょ ろ ・ す い す い ・ い ら い ら ・ わ く わ く ︶ 。 擬 態 語 の 中 で 、 心 理 を 表 す 語 を 特 に 擬 情 語 と 称 す る こ と も あ る 。
オ ノ マ ト ペ 自 体 は 多 く の 言 語 に 存 在 す る 。 た と え ば 猫 の 鳴 き 声 は 、 英 語 で ﹁ m e w ﹂ 、 ド イ ツ 語 で ﹁ m i a u ﹂ 、 フ ラ ン ス 語 で ﹁ m i a o u ﹂ 、 ロ シ ア 語 で ﹁ м я у ﹂ [ 注 釈 25 ] 、 中 国 語 で ﹁ 喵 喵 ﹂ [ 注 釈 26 ] 、 朝 鮮 語 で ﹁ 야 옹 야 옹 ﹂ [ 注 釈 27 ] な ど で あ る [ 77 ] 。 し か し な が ら 、 そ の 語 彙 量 は 言 語 に よ っ て 異 な る 。 日 本 語 の オ ノ マ ト ペ は 欧 米 語 や 中 国 語 の 3 倍 か ら 5 倍 存 在 す る と い わ れ る 。 英 語 な ど と 比 べ る と 、 と り わ け 擬 態 語 が 多 く 使 わ れ る と さ れ る 。
新 た な オ ノ マ ト ペ が 作 ら れ る こ と も あ る 。 ﹁ ︵ 心 臓 が ︶ ば く ば く ﹂ ﹁ が っ つ り ︵ 食 べ る ︶ ﹂ な ど は 、 近 年 に 作 ら れ た ︵ 広 ま っ た ︶ オ ノ マ ト ペ の 例 で あ る 。
漫 画 な ど の 媒 体 で は 、 と り わ け 自 由 に オ ノ マ ト ペ が 作 ら れ る 。 漫 画 家 の 手 塚 治 虫 は 、 漫 画 を 英 訳 し て も ら っ た と こ ろ 、 ﹁ ド ギ ュ ー ン ﹂ ﹁ シ ー ン ﹂ な ど の 語 に 翻 訳 者 が ﹁ お 手 あ げ に な っ て し ま っ た ﹂ と 記 し て い る 。 ま た 、 漫 画 出 版 社 社 長 の 堀 淵 清 治 も 、 ア メ リ カ で 日 本 漫 画 を 売 る に 当 た り 、 独 特 の 擬 音 を 訳 す の に ス タ ッ フ が 悩 ん だ こ と を 述 べ て い る 。
日 本 語 の 語 彙 を 品 詞 ご と に み る と 、 圧 倒 的 に 多 い も の は 名 詞 で あ る 。 そ の 残 り の う ち で 比 較 的 多 い も の は 動 詞 で あ る 。 ﹃ 新 選 国 語 辞 典 ﹄ の 収 録 語 の 場 合 、 名 詞 が 8 2 . 3 7 % 、 動 詞 が 9 . 0 9 % 、 副 詞 が 2 . 4 6 % 、 形 容 動 詞 が 2 . 0 2 % 、 形 容 詞 が 1 . 2 4 % と な っ て い る [ 82 ] 。
こ の う ち 、 と り わ け 目 を 引 く の は 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 の 少 な さ で あ る 。 か つ て 柳 田 國 男 は こ の 点 を 指 摘 し て ﹁ 形 容 詞 饑 饉 ﹂ と 称 し た [ 83 ] 。 英 語 の 場 合 、 ﹃ オ ッ ク ス フ ォ ー ド 英 語 辞 典 ﹄ 第 2 版 で は 、 半 分 以 上 が 名 詞 、 約 4 分 の 1 が 形 容 詞 、 約 7 分 の 1 が 動 詞 と い う こ と で あ り [ 84 ] 、 英 語 と の 比 較 の 上 か ら は 、 日 本 語 の 形 容 詞 が 僅 少 で あ る こ と は 特 徴 的 と い え る 。
た だ し 、 こ れ は 日 本 語 で 物 事 を 形 容 す る こ と が 難 し い こ と を 意 味 す る も の で は な く 、 他 の 形 式 に よ る 形 容 表 現 が 多 く 存 在 す る 。 例 え ば ﹁ 初 歩 ︵ の ︶ ﹂ ﹁ 酸 性 ︵ の ︶ ﹂ な ど ﹁ 名 詞 ︵ + の ︶ ﹂ の 形 式 、 ﹁ 目 立 つ ︵ 色 ︶ ﹂ ﹁ と が っ た ︵ 針 ︶ ﹂ ﹁ は や っ て い る ︵ 店 ︶ ﹂ な ど 動 詞 を 基 に し た 形 式 、 ﹁ つ ま ら な い ﹂ ﹁ に え き ら な い ﹂ な ど 否 定 助 動 詞 ﹁ な い ﹂ を 伴 う 形 式 な ど が 形 容 表 現 に 用 い ら れ る 。
も と も と 少 な い 形 容 詞 を 補 う 主 要 な 形 式 は 形 容 動 詞 で あ る 。 漢 語 ・ 外 来 語 の 輸 入 に よ っ て 、 ﹁ 正 確 だ ﹂ ﹁ ス マ ー ト だ ﹂ の よ う な 、 漢 語 ・ 外 来 語 + ﹁ だ ﹂ の 形 式 の 形 容 動 詞 が 増 大 し た 。 上 掲 の ﹃ 新 選 国 語 辞 典 ﹄ で 名 詞 扱 い に な っ て い る 漢 語 ・ 外 来 語 の う ち に も 、 形 容 動 詞 の 用 法 を 含 む も の が 多 数 存 在 す る 。 現 代 の 二 字 漢 語 ︵ ﹁ 世 界 ﹂ ﹁ 研 究 ﹂ ﹁ 豊 富 ﹂ な ど ︶ 約 2 万 1 千 語 を 調 査 し た 結 果 に よ れ ば 、 全 体 の 6 3 . 7 % が 事 物 類 ︵ 名 詞 に 相 当 ︶ 、 2 9 . 9 % が 動 態 類 ︵ 動 詞 に 相 当 ︶ 、 7 . 3 % が 様 態 類 ︵ 形 容 動 詞 に 相 当 ︶ 、 1 . 1 % が 副 用 類 ︵ 副 詞 に 相 当 ︶ で あ り 、 二 字 漢 語 の 7 % 程 度 が 形 容 動 詞 と し て 用 い ら れ て い る こ と が 分 か る 。
﹁ 語 彙 の 増 加 と 品 詞 ﹂ の 節 も 参 照 。
そ れ ぞ れ の 語 は 、 ば ら ば ら に 存 在 し て い る の で は な く 、 意 味 ・ 用 法 な ど の 点 で 互 い に 関 連 を も っ た グ ル ー プ を 形 成 し て い る 。 こ れ を 語 彙 体 系 と 称 す る [ 86 ] 。 日 本 語 の 語 彙 自 体 、 一 つ の 大 き な 語 彙 体 系 と い え る が 、 そ の 中 に は さ ら に 無 数 の 語 彙 体 系 が 含 ま れ て い る 。
以 下 、 体 系 を な す 語 彙 の 典 型 的 な 例 と し て 、 指 示 語 ・ 色 彩 語 彙 ・ 親 族 語 彙 を 取 り 上 げ て 論 じ る 。
日 本 語 で は 、 も の を 指 示 す る た め に 用 い る 語 彙 は 、 一 般 に ﹁ こ そ あ ど ﹂ と 呼 ば れ る 4 系 列 を な し て い る 。 こ れ ら の 指 示 語 ︵ 指 示 詞 ︶ は 、 主 と し て 名 詞 ︵ ﹁ こ れ ・ こ こ ・ こ な た ・ こ っ ち ﹂ な ど ︶ で あ る た め 、 概 説 書 の 類 で は 名 詞 ︵ 代 名 詞 ︶ の 説 明 の な か で 扱 わ れ て い る 場 合 も 多 い 。 し か し 、 実 際 に は 副 詞 ︵ ﹁ こ う ﹂ な ど ︶ ・ 連 体 詞 ︵ ﹁ こ の ﹂ な ど ︶ ・ 形 容 動 詞 ︵ ﹁ こ ん な だ ﹂ な ど ︶ に ま た が る た め 、 こ こ で は 語 彙 体 系 の 問 題 と し て 論 じ る 。
﹁ こ そ あ ど ﹂ の 体 系 は 、 伝 統 的 に は ﹁ 近 称 ・ 中 称 ・ 遠 称 ・ 不 定 ︵ ふ じ ょ う 、 ふ て い ︶ 称 ﹂ の 名 で 呼 ば れ た 。 明 治 時 代 に 、 大 槻 文 彦 は 以 下 の よ う な 表 を 示 し て い る [ 87 ] 。
\
近称
中称
遠称
不定称
事物
これ こ
それ そ
あれ あ
いづれ(どれ) なに
地位
ここ
そこ
あしこ あそこ
いづこ(どこ) いづく
方向
こなた
そなた
あなた
いづかた(どなた)
こち
そち
あち
いづち(どち)
こ こ で 、 ﹁ 近 称 ﹂ は 最 も 近 い も の 、 ﹁ 中 称 ﹂ は や や 離 れ た も の 、 ﹁ 遠 称 ﹂ は 遠 い も の を 指 す と さ れ た 。 と こ ろ が 、 ﹁ そ こ ﹂ な ど を ﹁ や や 離 れ た も の ﹂ を 指 す と 考 え る と 、 遠 く に い る 人 に 向 か っ て ﹁ そ こ で 待 っ て い て く れ ﹂ と 言 う よ う な 場 合 を 説 明 し が た い 。 ま た 、 自 分 の 腕 の よ う に 近 く に あ る も の を 指 し て 、 人 に ﹁ そ こ を さ す っ て く だ さ い ﹂ と 言 う こ と も 説 明 し が た い な ど の 欠 点 が あ る 。 佐 久 間 鼎 は 、 こ の 点 を 改 め 、 ﹁ こ ﹂ は ﹁ わ ︵ = 自 分 ︶ の な わ ば り ﹂ に 属 す る も の 、 ﹁ そ ﹂ は ﹁ な ︵ = あ な た ︶ の な わ ば り ﹂ に 属 す る も の 、 ﹁ あ ﹂ は そ れ 以 外 の 範 囲 に 属 す る も の を 指 す と し た [ 88 ] 。 す な わ ち 、 体 系 は 下 記 の よ う に ま と め ら れ た 。
\
指示されるもの
対話者の層
所属事物の層
話し手
(話し手自身)
(話し手所属のもの)
相手
(話しかけの目標)
(相手所属のもの)
はたの
(第三者)(アノヒト)
(はたのもの)
不定
ドナタ ダレ
ド系
こ の よ う に 整 理 す れ ば 、 上 述 の ﹁ そ こ で 待 っ て い て く れ ﹂ ﹁ そ こ を さ す っ て く だ さ い ﹂ の よ う な 言 い 方 は う ま く 説 明 さ れ る 。 相 手 側 に 属 す る も の は 、 遠 近 を 問 わ ず ﹁ そ ﹂ で 表 さ れ る こ と に な る 。 こ の 説 明 方 法 は 、 現 在 の 学 校 教 育 の 国 語 で も 取 り 入 れ ら れ て い る 。
と は い え 、 す べ て の 場 合 を 佐 久 間 説 で 割 り 切 れ る わ け で も な い 。 た と え ば 、 道 で ﹁ ど ち ら に 行 か れ ま す か ﹂ と 問 わ れ て 、 ﹁ ち ょ っ と そ こ ま で ﹂ と 答 え た と き 、 こ れ は ﹁ そ れ ほ ど 遠 く な い と こ ろ ま で 行 く ﹂ と い う 意 味 で あ る か ら 、 大 槻 文 彦 の い う ﹁ 中 称 ﹂ の 説 明 の ほ う が ふ さ わ し い 。 も の を 無 く し た と き 、 ﹁ ち ょ っ と そ の へ ん を 探 し て み る よ ﹂ と 言 う と き も 同 様 で あ る 。
ま た 、 目 の 前 に あ る も の を 直 接 指 示 す る 場 合 ︵ 現 場 指 示 ︶ と 、 文 章 の 中 で 前 に 出 た 語 句 を 指 示 す る 場 合 ︵ 文 脈 指 示 ︶ と で も 、 事 情 が 変 わ っ て く る 。 ﹁ 生 か 死 か 、 そ れ が 問 題 だ ﹂ の ﹁ そ れ ﹂ は 、 ﹁ 中 称 ﹂ ︵ や や 離 れ た も の ︶ と も 、 ﹁ 相 手 所 属 の も の ﹂ と も 解 釈 し が た い 。 直 前 の 内 容 を ﹁ そ れ ﹂ で 示 す も の で あ る 。 こ の よ う に 、 指 示 語 の 意 味 体 系 は 、 詳 細 に 見 れ ば 、 な お 研 究 の 余 地 が 多 く 残 さ れ て い る 。
な お 、 指 示 の 体 系 は 言 語 に よ っ て 異 な る 。 不 定 称 を 除 い た 場 合 、 3 系 列 を な す 言 語 は 日 本 語 ︵ こ 、 そ 、 あ ︶ や 朝 鮮 語 ︵ 이 、 그 、 저 ︶ な ど が あ る 。 一 方 、 英 語 ︵ t h i s 、 t h a t ︶ や 中 国 語 ︵ 这 、 那 ︶ な ど は 2 系 列 を な す 。 日 本 人 の 英 語 学 習 者 が ﹁ こ れ 、 そ れ 、 あ れ ﹂ に ﹁ t h i s 、 it 、 t h a t ﹂ を 当 て は め て 考 え る こ と が あ る が 、 ﹁ it ﹂ は 文 脈 指 示 の 代 名 詞 で 系 列 が 異 な る た め 、 混 用 す る こ と は で き な い 。
日 本 語 で 色 彩 を 表 す 語 彙 ︵ 色 彩 語 彙 ︶ は 、 古 来 、 ﹁ ア カ ﹂ ﹁ シ ロ ﹂ ﹁ ア ヲ ﹂ ﹁ ク ロ ﹂ の 4 語 が 基 礎 と な っ て い る 。 ﹁ ア カ ﹂ は 明 る い 色 ︵ 明 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ シ ロ ﹂ は 顕 ︵ あ き ︶ ら か な 色 ︵ 白 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ ア ヲ ﹂ は 漠 然 と し た 色 ︵ 淡 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ ク ロ ﹂ は 暗 い 色 ︵ 暗 し の 語 源 か ︶ を 総 称 し た 。 今 日 で も こ の 体 系 は 基 本 的 に 変 わ っ て い な い 。 葉 の 色 ・ 空 の 色 ・ 顔 色 な ど を い ず れ も ﹁ ア オ ﹂ と 表 現 す る の は こ こ に 理 由 が あ る 。
文 化 人 類 学 者 の バ ー リ ン と ケ イ の 研 究 に よ れ ば 、 種 々 の 言 語 で 最 も 広 範 に 用 い ら れ て い る 基 礎 的 な 色 彩 語 彙 は ﹁ 白 ﹂ と ﹁ 黒 ﹂ で あ り 、 以 下 、 ﹁ 赤 ﹂ ﹁ 緑 ﹂ が 順 次 加 わ る と い う [ 91 ] 。 日 本 語 の 色 彩 語 彙 も ほ ぼ こ の 法 則 に 合 っ て い る と い っ て よ い 。
こ の こ と は 、 日 本 語 を 話 す 人 々 が 4 色 し か 識 別 し な い と い う こ と で は な い 。 特 別 の 色 を 表 す 場 合 に は 、 ﹁ 黄 色 ︵ 語 源 は ﹁ 木 ﹂ か と い う [ 92 ] ︶ ﹂ ﹁ 紫 色 ﹂ ﹁ 茶 色 ﹂ ﹁ 蘇 芳 色 ﹂ ﹁ 浅 葱 色 ﹂ な ど 、 植 物 そ の 他 の 一 般 名 称 を 必 要 に 応 じ て 転 用 す る 。 た だ し 、 こ れ ら は 基 礎 的 な 色 彩 語 彙 で は な い 。
日 本 語 の 親 族 語 彙 [ 94 ] は 、 比 較 的 単 純 な 体 系 を な し て い る 。 英 語 の 基 礎 語 彙 で 、 同 じ 親 か ら 生 ま れ た 者 を ﹁ b r o t h e r ﹂ ﹁ s i s t e r ﹂ の 2 語 の み で 区 別 す る の に 比 べ れ ば 、 日 本 語 で は 、 男 女 ・ 長 幼 に よ っ て ﹁ ア ニ ﹂ ﹁ ア ネ ﹂ ﹁ オ ト ウ ト ﹂ ﹁ イ モ ウ ト ﹂ の 4 語 を 区 別 し 、 よ り 詳 し い 体 系 で あ る と い え る ︵ 古 代 に は 、 年 上 の み ﹁ ア ニ ﹂ ﹁ ア ネ ﹂ と 区 別 し 、 年 下 は ﹁ オ ト ﹂ と 一 括 し た ︶ 。 し か し な が ら 、 た と え ば 中 国 語 の 親 族 語 彙 と 比 較 す れ ば 、 は る か に 単 純 で あ る 。 中 国 語 で は 、 父 親 の 父 母 を ﹁ 祖 父 ﹂ ﹁ 祖 母 ﹂ 、 母 親 の 父 母 を ﹁ 外 祖 父 ﹂ ﹁ 外 祖 母 ﹂ と 呼 び 分 け る が 、 日 本 語 で は ﹁ ジ ジ ﹂ ﹁ バ バ ﹂ の 区 別 し か な い 。 中 国 語 で は 父 の 兄 弟 を ﹁ 伯 ﹂ ﹁ 叔 ﹂ 、 父 の 姉 妹 を ﹁ 姑 ﹂ 、 母 の 兄 弟 を ﹁ 舅 ﹂ 、 母 の 姉 妹 を ﹁ 姨 ﹂ な ど と い う が 、 日 本 語 で は ﹁ オ ジ ﹂ ﹁ オ バ ﹂ の み で あ る 。 ﹁ オ ジ ﹂ ﹁ オ バ ﹂ の 子 は い ず れ も ﹁ イ ト コ ﹂ の 名 で 呼 ば れ る 。 日 本 語 で も 、 ﹁ 伯 父 ︵ は く ふ ︶ ﹂ ﹁ 叔 父 ︵ し ゅ く ふ ︶ ﹂ ﹁ 従 兄 ︵ じ ゅ う け い ︶ ﹂ ﹁ 従 姉 ︵ じ ゅ う し ︶ ﹂ な ど の 語 を 文 章 語 と し て 用 い る こ と も あ る が 、 こ れ ら は 中 国 語 か ら の 借 用 語 で あ る 。
親 族 語 彙 を 他 人 に 転 用 す る 虚 構 的 用 法 [ 注 釈 28 ] が 多 く の 言 語 に 存 在 す る 。 例 え ば 、 朝 鮮 語 ︵ ﹁ 아 버 님 ﹂ お 父 様 ︶ ・ モ ン ゴ ル 語 ︵ ﹁ a a b ﹂ 父 ︶ で は 尊 敬 す る 年 配 男 性 に 用 い る 。 英 語 で も 議 会 な ど の 長 老 や カ ト リ ッ ク 教 会 の 神 父 を ﹁ f a t h e r ︵ 父 ︶ ﹂ 、 寮 母 を ﹁ m o t h e r ︵ 母 ︶ ﹂ 、 男 の 親 友 や 同 一 宗 派 の 男 性 を ﹁ b r o t h e r ︵ 兄 弟 ︶ ﹂ 、 女 の 親 友 や 修 道 女 や 見 知 ら ぬ 女 性 を ﹁ s i s t e r ﹂ ︵ 姉 妹 ︶ と 呼 ぶ 。 中 国 語 で は 見 知 ら ぬ 若 い 男 性 ・ 女 性 に ﹁ 老 兄 ﹂ ︵ お 兄 さ ん ︶ ﹁ 大 姐 ﹂ ︵ お 姉 さ ん ︶ と 呼 び か け る 、 そ し て 年 長 者 で は 男 性 ・ 女 性 に ﹁ 大 爺 ﹂ ︵ 旦 那 さ ん ︶ ﹁ 大 媽 ﹂ ︵ 伯 母 さ ん ︶ と 呼 び か け る 。 日 本 語 に も こ の 用 法 が あ り 、 赤 の 他 人 を ﹁ お 父 さ ん ﹂ ﹁ お 母 さ ん ﹂ と 呼 ぶ こ と が あ る 。 た と え ば 、 店 員 が 中 年 の 男 性 客 に ﹁ お 父 さ ん 、 さ あ 買 っ て く だ さ い ﹂ の よ う に 言 う 。 フ ラ ン ス 語 ・ イ タ リ ア 語 ・ デ ン マ ー ク 語 ・ チ ェ コ 語 な ど の ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 で 他 人 で あ る 男 性 を こ の よ う に 呼 ぶ こ と は 、 日 本 語 で 赤 の 他 人 を ﹁ お 父 さ ん ﹂ と 呼 ぶ の が 失 礼 に な り う る の と 同 じ く 、 失 礼 に さ え な る と い う 。
一 族 内 で 一 番 若 い 世 代 か ら 見 た 名 称 で 自 分 や 他 者 を 呼 ぶ こ と が あ る の も 各 国 語 に 見 ら れ る 用 法 で あ る 。 例 え ば 、 父 親 が 自 分 自 身 を 指 し て ﹁ お 父 さ ん ﹂ と 言 っ た り ︵ ﹁ お 父 さ ん が や っ て あ げ よ う ﹂ ︶ 、 自 分 の 母 を 子 か ら 見 た 名 称 で ﹁ お ば あ ち ゃ ん ﹂ と 呼 ん だ り す る 用 法 で あ る 。 こ の 用 法 は 、 中 国 語 ・ 朝 鮮 語 ・ モ ン ゴ ル 語 ・ 英 語 ・ フ ラ ン ス 語 ・ イ タ リ ア 語 ・ デ ン マ ー ク 語 ・ チ ェ コ 語 な ど を 含 め 諸 言 語 に あ る 。
日 本 語 の 語 彙 を 出 自 か ら 分 類 す れ ば 、 大 き く 、 和 語 ・ 漢 語 ・ 外 来 語 、 お よ び そ れ ら が 混 ざ っ た 混 種 語 に 分 け ら れ る 。 こ の よ う に 、 出 自 に よ っ て 分 け た 言 葉 の 種 類 を ﹁ 語 種 ﹂ と い う 。 和 語 は 日 本 古 来 の 大 和 言 葉 、 漢 語 は 中 国 渡 来 の 漢 字 の 音 を 用 い た 言 葉 、 外 来 語 は 中 国 以 外 の 他 言 語 か ら 取 り 入 れ た 言 葉 で あ る 。 ︵ ﹁ 語 彙 史 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。
和 語 は 日 本 語 の 語 彙 の 中 核 部 分 を 占 め る 。 ﹁ こ れ ﹂ ﹁ そ れ ﹂ ﹁ き ょ う ﹂ ﹁ あ す ﹂ ﹁ わ た し ﹂ ﹁ あ な た ﹂ ﹁ 行 く ﹂ ﹁ 来 る ﹂ ﹁ 良 い ﹂ ﹁ 悪 い ﹂ な ど の い わ ゆ る 基 礎 語 彙 は ほ と ん ど 和 語 で あ る 。 ま た 、 ﹁ て ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ は ﹂ な ど の 助 詞 や 、 助 動 詞 の 大 部 分 な ど 、 文 を 組 み 立 て る た め に 必 要 な 付 属 語 も 和 語 で あ る 。
一 方 、 抽 象 的 な 概 念 や 、 社 会 の 発 展 に 伴 っ て 新 た に 発 生 し た 概 念 を 表 す た め に は 、 漢 語 や 外 来 語 が 多 く 用 い ら れ る 。 和 語 の 名 称 が す で に あ る 事 物 を 漢 語 や 外 来 語 で 言 い 換 え る こ と も あ る 。 ﹁ め し ﹂ を ﹁ 御 飯 ﹂ ﹁ ラ イ ス ﹂ 、 ﹁ や ど や ﹂ を ﹁ 旅 館 ﹂ ﹁ ホ テ ル ﹂ な ど と 称 す る の は そ の 例 で あ る [ 95 ] 。 こ の よ う な 語 種 の 異 な る 同 義 語 に は 、 微 妙 な 意 味 ・ ニ ュ ア ン ス の 差 異 が 生 ま れ 、 と り わ け 和 語 に は 易 し い 、 ま た は 卑 俗 な 印 象 、 漢 語 に は 公 的 で 重 々 し い 印 象 、 外 来 語 に は 新 し い 印 象 が 含 ま れ る こ と が 多 い 。
一 般 に 、 和 語 の 意 味 は 広 く 、 漢 語 の 意 味 は 狭 い と い わ れ る 。 た と え ば 、 ﹁ し づ む ︵ し ず め る ︶ ﹂ と い う 1 語 の 和 語 に 、 ﹁ 沈 ﹂ ﹁ 鎮 ﹂ ﹁ 静 ﹂ な ど 複 数 の 漢 語 の 造 語 成 分 が 相 当 す る 。 ﹁ し づ む ﹂ の 含 む 多 様 な 意 味 は 、 ﹁ 沈 む ﹂ ﹁ 鎮 む ﹂ ﹁ 静 む ﹂ な ど と 漢 字 を 用 い て 書 き 分 け る よ う に な り 、 そ の 結 果 、 こ れ ら の ﹁ し づ む ﹂ が 別 々 の 語 と 意 識 さ れ る ま で に な っ た 。 2 字 以 上 の 漢 字 が 組 み 合 わ さ っ た 漢 語 の 表 す 意 味 は と り わ け 分 析 的 で あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 弱 ﹂ と い う 造 語 成 分 は 、 ﹁ 脆 ﹂ ﹁ 貧 ﹂ ﹁ 軟 ﹂ ﹁ 薄 ﹂ な ど の 成 分 と 結 合 す る こ と に よ り 、 ﹁ 脆 弱 ﹂ ﹁ 貧 弱 ﹂ ﹁ 軟 弱 ﹂ ﹁ 薄 弱 ﹂ の よ う に 分 析 的 ・ 説 明 的 な 単 語 を 作 る ︵ ﹁ 語 彙 史 ﹂ の 節 の ﹁ 漢 語 の 勢 力 拡 大 ﹂ お よ び ﹁ 語 彙 の 増 加 と 品 詞 ﹂ を 参 照 ︶ 。
漢 語 は 、 ﹁ 学 問 ﹂ ﹁ 世 界 ﹂ ﹁ 博 士 ﹂ な ど の よ う に 、 古 く 中 国 か ら 入 っ て き た 語 彙 が 大 部 分 を 占 め る の は 無 論 で あ る が 、 日 本 人 が 作 っ た 漢 語 ︵ 和 製 漢 語 ︶ も 古 来 多 い 。 現 代 語 と し て も 、 ﹁ 国 立 ﹂ ﹁ 改 札 ﹂ ﹁ 着 席 ﹂ ﹁ 挙 式 ﹂ ﹁ 即 答 ﹂ ﹁ 熱 演 ﹂ な ど 多 く の 和 製 漢 語 が 用 い ら れ て い る [ 注 釈 29 ] 。 漢 語 は 音 読 み で 読 ま れ る こ と か ら 、 字 音 語 と 呼 ば れ る 場 合 も あ る 。
外 来 語 は 、 も と の 言 語 の 意 味 の ま ま で 用 い ら れ る も の 以 外 に 、 日 本 語 に 入 っ て か ら 独 自 の 意 味 変 化 を 遂 げ る も の が 少 な く な い 。 英 語 の " c l a i m " は ﹁ 当 然 の 権 利 と し て 要 求 す る ﹂ の 意 で あ る が 、 日 本 語 の ﹁ ク レ ー ム ﹂ は ﹁ 文 句 ﹂ の 意 で あ る 。 英 語 の " l u n c h " は 昼 食 の 意 で あ る が 、 日 本 の 食 堂 で ﹁ ラ ン チ ﹂ と い え ば 料 理 の 種 類 を 指 す [ 97 ] 。
外 来 語 を 組 み 合 わ せ て 、 ﹁ ア イ ス キ ャ ン デ ー ﹂ ﹁ サ イ ド ミ ラ ー ﹂ ﹁ テ ー ブ ル ス ピ ー チ ﹂ の よ う に 日 本 語 独 自 の 語 が 作 ら れ る こ と が あ る 。 ま た 、 当 該 の 語 形 が 外 国 語 に な い ﹁ パ ネ ラ ー ﹂ ︵ パ ネ リ ス ト の 意 ︶ ﹁ プ レ ゼ ン テ ー タ ー ﹂ ︵ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を す る 人 。 プ レ ゼ ン タ ー ︶ な ど の 語 形 が 作 ら れ る こ と も あ る 。 こ れ ら を 総 称 し て ﹁ 和 製 洋 語 ﹂ 、 英 語 系 の 語 を 特 に ﹁ 和 製 英 語 ﹂ と 言 う 。
日 本 語 の 語 彙 は 、 語 構 成 の 面 か ら は 単 純 語 と 複 合 語 に 分 け る こ と が で き る 。 単 純 語 は 、 ﹁ あ た ま ﹂ ﹁ か お ﹂ ﹁ う え ﹂ ﹁ し た ﹂ ﹁ い ぬ ﹂ ﹁ ね こ ﹂ の よ う に 、 そ れ 以 上 分 け ら れ な い と 意 識 さ れ る 語 で あ る 。 複 合 語 は 、 ﹁ あ た ま か ず ﹂ ﹁ か お な じ み ﹂ ﹁ う わ く ち び る ﹂ ﹁ い ぬ ず き ﹂ の よ う に 、 い く つ か の 単 純 語 が 合 わ さ っ て で き て い る と 意 識 さ れ る 語 で あ る 。 な お 、 熟 語 と 総 称 さ れ る 漢 語 は 、 本 来 漢 字 の 字 音 を 複 合 さ せ た も の で あ る が 、 ﹁ え ん ぴ つ ︵ 鉛 筆 ︶ ﹂ ﹁ せ か い ︵ 世 界 ︶ ﹂ な ど 、 日 本 語 に お い て 単 純 語 と 認 識 さ れ る 語 も 多 い 。 ﹁ 語 種 ﹂ の 節 で 触 れ た 混 種 語 、 す な わ ち 、 ﹁ プ ロ 野 球 ﹂ ﹁ 草 野 球 ﹂ ﹁ 日 本 シ リ ー ズ ﹂ の よ う に 複 数 の 語 種 が 合 わ さ っ た 語 は 、 語 構 成 の 面 か ら は す べ て 複 合 語 と い う こ と に な る 。
日 本 語 で は 、 限 り な く 長 い 複 合 語 を 作 る こ と が 可 能 で あ る 。 ﹁ 平 成 十 六 年 新 潟 県 中 越 地 震 非 常 災 害 対 策 本 部 ﹂ ﹁ 服 部 四 郎 先 生 定 年 退 官 記 念 論 文 集 編 集 委 員 会 ﹂ と い っ た 類 も 、 ひ と つ の 長 い 複 合 語 で あ る 。 国 際 協 定 の 関 税 及 び 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 は 、 英 語 で は ﹁ G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ﹂ ︵ 関 税 と 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ︶ で あ り 、 ひ と つ の 句 で あ る が 、 日 本 の 新 聞 で は ﹁ 関 税 貿 易 一 般 協 定 ﹂ と 複 合 語 で 表 現 す る こ と が あ る 。 こ れ は 漢 字 の 結 合 力 に よ る と こ ろ が 大 き く 、 中 国 語 ・ 朝 鮮 語 な ど で も 同 様 の 長 い 複 合 語 を 作 る 。 な お 、 ヨ ー ロ ッ パ 語 を 見 る と 、 ロ シ ア 語 で は ﹁ ч е л о в е к о н е н а в и с т н и ч е с т в о ﹂ ︵ 人 間 嫌 い ︶ 、 ド イ ツ 語 で は ﹁ N a t u r f a r b e n p h o t o g r a p h i e ﹂ ︵ 天 然 色 写 真 ︶ な ど の 長 い 語 の 例 を 比 較 的 多 く 有 し 、 英 語 で も ﹁ a n t i d i s e s t a b l i s h m e n t a r i a n i s m ﹂ ︵ 国 教 廃 止 条 例 反 対 論 。 英 首 相 グ ラ ッ ド ス ト ン の 造 語 と い う [ 99 ] ︶ な ど の 語 例 が ま れ に あ る 。
接 辞 は 、 複 合 語 を 作 る た め に 威 力 を 発 揮 す る 。 た と え ば 、 ﹁ 感 ﹂ は 、 ﹁ 音 感 ﹂ ﹁ 語 感 ﹂ ﹁ 距 離 感 ﹂ ﹁ 不 安 感 ﹂ な ど 漢 字 2 字 ・ 3 字 か ら な る 複 合 語 の み な ら ず 、 最 近 で は ﹁ 透 け 感 ﹂ ﹁ 懐 か し 感 ﹂ ﹁ し ゃ き っ と 感 ﹂ ﹁ き ち ん と 感 ﹂ な ど 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 副 詞 と の 複 合 語 を 作 り 、 さ ら に は ﹁ ﹃ 昔 の 名 前 で 出 て い ま す ﹄ 感 ﹂ ︵ = 昔 の 名 前 で 出 て い る と い う 感 じ ︶ の よ う に 文 で あ っ た も の に 下 接 し て 長 い 複 合 語 を 作 る こ と も あ る 。
日 本 語 の 複 合 語 は 、 難 し い 語 で も 、 表 記 を 見 れ ば 意 味 が 分 か る 場 合 が 多 い 。 た と え ば 、 英 語 の ﹁ a p i v o r o u s ﹂ は 生 物 学 者 に し か 分 か ら な い の に 対 し 、 日 本 語 の ﹁ 蜂 食 性 ﹂ は ﹁ 蜂 を 食 べ る 性 質 ﹂ で あ る と 推 測 で き る 。 こ れ は 表 記 に 漢 字 を 用 い る 言 語 の 特 徴 で あ る 。
現代の日本語は、平仮名 (ひらがな)・片仮名 (カタカナ)・漢字 を用いて、現代仮名遣い ・常用漢字 に基づいて表記されることが一般的である。アラビア数字 やローマ字(ラテン文字) なども必要に応じて併用される。
正書法の必要性を説く主張[101] [102]
平仮名・片仮名は、2017年9月現在では以下の46字ずつが使われる。
名称
字形
平仮名
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん
片仮名
ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン
こ の う ち 、 ﹁ ゛ ﹂ ︵ 濁 音 符 ︶ お よ び ﹁ ゜ ﹂ ︵ 半 濁 音 符 ︶ を 付 け て 濁 音 ・ 半 濁 音 を 表 す 仮 名 も あ る ︵ ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 拗 音 は 小 書 き の ﹁ ゃ ﹂ ﹁ ゅ ﹂ ﹁ ょ ﹂ を 添 え て 表 し 、 促 音 は 小 書 き の ﹁ っ ﹂ で 表 す 。 ﹁ つ ぁ ﹂ ﹁ フ ァ ﹂ の よ う に 、 小 書 き の ﹁ ぁ ﹂ ﹁ ぃ ﹂ ﹁ ぅ ﹂ ﹁ ぇ ﹂ ﹁ ぉ ﹂ を 添 え て 表 す 音 も あ り 、 補 助 符 号 と し て 長 音 を 表 す ﹁ ー ﹂ が あ る 。 歴 史 的 仮 名 遣 い で は 上 記 の ほ か 、 表 音 は 同 じ で も 表 記 の 違 う 、 平 仮 名 ﹁ ゐ ﹂ ﹁ ゑ ﹂ お よ び 片 仮 名 ﹁ ヰ ﹂ ﹁ ヱ ﹂ の 字 が 存 在 し 、 そ の 他 に も 変 体 仮 名 が あ る 。
漢 字 は 、 日 常 生 活 に お い て 必 要 と さ れ る 2 1 3 6 字 の 常 用 漢 字 と 、 子 の 名 づ け に 用 い ら れ る 8 6 1 字 の 人 名 用 漢 字 が 、 法 で 定 め ら れ て い る 。 実 際 に は こ れ ら 以 外 に も 一 般 に 通 用 す る 漢 字 の 数 は 多 い と さ れ 、 日 本 産 業 規 格 ︵ J I S ︶ は J I S X 0 2 0 8 ︵ 通 称 J I S 漢 字 ︶ と し て 約 6 3 0 0 字 を 電 算 処 理 可 能 な 漢 字 と し て 挙 げ て い る 。 な お 、 漢 字 の 本 家 で あ る 中 国 に お い て も 同 様 の 基 準 は 存 在 し 、 現 代 漢 語 常 用 字 表 に よ り 、 ﹁ 常 用 字 ﹂ と し て 2 5 0 0 字 、 ﹁ 次 常 用 字 ﹂ と し て 1 0 0 0 字 が 定 め ら れ て い る 。 こ れ に 加 え 、 現 代 漢 語 通 用 字 表 で は さ ら に 3 5 0 0 字 が 追 加 さ れ て い る 。
一 般 的 な 文 章 で は 、 上 記 の 漢 字 ・ 平 仮 名 ・ 片 仮 名 を 交 え て 記 す ほ か 、 ア ラ ビ ア 数 字 ・ ロ ー マ 字 な ど も 必 要 に 応 じ て 併 用 す る 。 基 本 的 に は 、 漢 語 に は 漢 字 を 、 和 語 の う ち 概 念 を 表 す 部 分 ︵ 名 詞 や 用 言 語 幹 な ど ︶ に は 漢 字 を 、 形 式 的 要 素 ︵ 助 詞 ・ 助 動 詞 な ど ︶ や 副 詞 ・ 接 続 詞 の 一 部 に は 平 仮 名 を 、 外 来 語 ︵ 漢 語 以 外 ︶ に は 片 仮 名 を 用 い る 場 合 が 多 い 。 公 的 な 文 書 で は 特 に 表 記 法 を 規 定 し て い る 場 合 も あ り [ 注 釈 30 ] 、 民 間 で も こ れ に 倣 う こ と が あ る 。 た だ し 、 厳 密 な 正 書 法 は な く 、 表 記 の ゆ れ は 広 く 許 容 さ れ て い る 。 文 章 の 種 類 や 目 的 に よ っ て 、
● さ く ら の は な が さ く / サ ク ラ の 花 が 咲 く / 桜 の 花 が 咲 く な ど の 表 記 が あ り う る 。
多 様 な 文 字 体 系 を 交 え て 記 す 利 点 と し て 、 単 語 の ま と ま り が 把 握 し や す く 、 速 読 性 に 優 れ る な ど の 点 が 指 摘 さ れ る 。 日 本 語 の 単 純 な 音 節 構 造 に 由 来 す る 同 音 異 義 語 が 漢 字 に よ っ て 区 別 さ れ 、 か つ 字 数 も 節 約 さ れ る と い う 利 点 も あ る 。 計 算 機 科 学 者 の 村 島 定 行 は 、 日 本 語 で は 、 表 意 文 字 と 表 音 文 字 の 二 重 の 文 章 表 現 が で き る た め 、 記 憶 し た り 、 想 起 し た り す る の に 手 が か り が 多 く 、 言 語 と し て の 機 能 が 高 い と 指 摘 し て い る 。 一 方 で 中 国 文 学 者 の 高 島 俊 男 は 、 漢 字 の 表 意 性 に 過 度 に 依 存 し た 日 本 語 の 文 章 は 、 他 の 自 然 言 語 に 類 を 見 な い ほ ど の 同 音 異 義 語 を 用 い ざ る を 得 な く な り 、 し ば し ば 実 用 の 上 で 支 障 を 来 た す こ と か ら 、 言 語 と し て ﹁ 顚 倒 し て い る ﹂ と 評 し て い る 。 歴 史 上 、 漢 字 を 廃 止 し て 、 仮 名 ま た は ロ ー マ 字 を 国 字 化 し よ う と い う 主 張 も あ っ た が 、 広 く 実 行 さ れ る こ と は な か っ た [ 1 0 5 ] ︵ ﹁ 国 語 国 字 問 題 ﹂ 参 照 ︶ 。 今 日 で は 漢 字 ・ 平 仮 名 ・ 片 仮 名 の 交 ぜ 書 き が 標 準 的 表 記 の 地 位 を え て い る 。
日 本 語 の 表 記 体 系 は 中 央 語 を 書 き 表 す た め に 発 達 し た も の で あ り 、 方 言 の 音 韻 を 表 記 す る た め に は 必 ず し も 適 し て い な い 。 た と え ば 、 東 北 地 方 で は ﹁ 柿 ﹂ を [ k a g ɨ ] 、 ﹁ 鍵 ﹂ を [ k ã ŋ ɨ ] の よ う に 発 音 す る が 、 こ の 両 語 を 通 常 の 仮 名 で は 書 き 分 け ら れ な い ︵ ア ク セ ン ト 辞 典 な ど で 用 い る 表 記 に よ っ て 近 似 的 に 記 せ ば 、 ﹁ カ ギ ﹂ と ﹁ カ ン キ ゚ ﹂ の よ う に な る ︶ 。 そ の た め 、 方 言 を 正 確 に 文 字 に 書 き 表 す こ と が で き ず 、 方 言 を 書 き 言 葉 と し て 用 い る こ と が 少 な く な っ て い る 。
岩 手 県 気 仙 方 言 ︵ ケ セ ン 語 ︶ に つ い て 、 山 浦 玄 嗣 に よ り 、 文 法 形 式 を 踏 ま え た 正 書 法 が 試 み ら れ て い る と い う よ う な 例 も あ る [ 1 0 7 ] 。 た だ し 、 こ れ は 実 用 の た め の も の と い う よ り は 、 学 術 的 な 試 み の ひ と つ で あ る 。
琉 球 語 ︵ ﹁ 系 統 ﹂ 参 照 ︶ の 表 記 体 系 も そ れ を 準 用 し て い る 。 た と え ば 、 琉 歌 ﹁ て ん さ ご の 花 ﹂ ︵ て ぃ ん さ ぐ ぬ 花 ︶ は 、 伝 統 的 な 表 記 法 で は 次 の よ う に 記 す 。
て ん さ ご の 花 や 爪 先 に 染 め て 親 の 寄 せ ご と や 肝 に 染 め れ —
こ の 表 記 法 で は 、 た と え ば 、 ﹁ ぐ ﹂ ﹁ ご ﹂ が ど ち ら も [ gu ] と 発 音 さ れ る よ う に 、 か な 表 記 と 発 音 が 一 対 一 で 対 応 し な い 場 合 が 多 々 あ る 。 表 音 的 に 記 せ ば 、 [ t i ɴ ʃ a g u n u h a n a j a ʦ i m i ʣ a ʧ i ɲ i s u m i t i , ʔ u j a n u j u ʃ i g u t u j a ʧ i m u ɲ i s u m i r i ] の よ う に な る と こ ろ で あ る [ 注 釈 31 ] 。
漢 字 表 記 の 面 で は 、 地 域 文 字 と い う べ き も の が 各 地 に 存 在 す る 。 た と え ば 、 名 古 屋 市 の 地 名 ﹁ 杁 中 ︵ い り な か ︶ ﹂ な ど に 使 わ れ る ﹁ 杁 ﹂ は 、 名 古 屋 と 関 係 あ る 地 域 の ﹁ 地 域 文 字 ﹂ で あ る 。 ま た 、 ﹁ 垰 ﹂ は ﹁ た お ﹂ ﹁ た わ ﹂ な ど と 読 ま れ る 国 字 で 、 中 国 地 方 ほ か で 定 着 し て い る と い う 。
文 は 、 目 的 や 場 面 な ど に 応 じ て 、 さ ま ざ ま な 異 な っ た 様 式 を 採 る 。 こ の 様 式 の こ と を 、 書 き 言 葉 ︵ 文 章 ︶ で は ﹁ 文 体 ﹂ と 称 し 、 話 し 言 葉 ︵ 談 話 ︶ で は ﹁ 話 体 ﹂ [ 1 1 0 ] と 称 す る 。
日 本 語 で は 、 と り わ け 文 末 の 助 動 詞 ・ 助 詞 な ど に 文 体 差 が 顕 著 に 現 れ る 。 こ の こ と は 、 ﹁ で す ま す 体 ﹂ ﹁ で ご ざ い ま す 体 ﹂ ﹁ だ 体 ﹂ ﹁ で あ る 体 ﹂ ﹁ あ り ん す 言 葉 ﹂ ︵ 江 戸 ・ 新 吉 原 の 遊 女 の 言 葉 ︶ ﹁ て よ だ わ 言 葉 ﹂ ︵ 明 治 中 期 か ら 流 行 し た 若 い 女 性 の 言 葉 ︶ な ど の 名 称 に 典 型 的 に 表 れ て い る 。 そ れ ぞ れ の 文 体 ・ 話 体 の 差 は 大 き い が 、 日 本 語 話 者 は 、 複 数 の 文 体 ・ 話 体 を 常 に 切 り 替 え な が ら 使 用 し て い る 。
な お 、 ﹁ 文 体 ﹂ の 用 語 は 、 書 か れ た 文 章 だ け で は な く 談 話 に つ い て も 適 用 さ れ る た め 、 以 下 で は ﹁ 文 体 ﹂ に ﹁ 話 体 ﹂ も 含 め て 述 べ る 。 ま た 、 文 語 文 ・ 口 語 文 な ど に つ い て は ﹁ 文 体 史 ﹂ の 節 に 譲 る 。
日本語の文体は、大きく普通体(常体)および丁寧体(敬体)の2種類に分かれる。日本語話者は日常生活で両文体を適宜使い分ける。日本語学習者は、初めに丁寧体を、次に普通体を順次学習することが一般的である。普通体は相手を意識しないかのような文体であるため独語体と称し、丁寧体は相手を意識する文体であるため対話体と称することもある[112]
普通体と丁寧体の違いは次のように現れる。
\
普通体
丁寧体
名詞文
もうすぐ春だ (春である )。
もうすぐ春です 。
形容動詞文
ここは静かだ (静かである )。
ここは静かです 。
形容詞文
野山の花が美しい。
(野山の花が美しいです 。)
動詞文
鳥が空を飛ぶ。
鳥が空を飛びます 。
普 通 体 で は 、 文 末 に 名 詞 ・ 形 容 動 詞 ・ 副 詞 な ど が 来 る 場 合 に は 、 ﹁ だ ﹂ ま た は ﹁ で あ る ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 前 者 を 特 に ﹁ だ 体 ﹂ 、 後 者 を 特 に ﹁ で あ る 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。
丁 寧 体 で は 、 文 末 に 名 詞 ・ 形 容 動 詞 ・ 副 詞 な ど が 来 る 場 合 に は 、 助 動 詞 ﹁ で す ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 動 詞 が 来 る 場 合 に は ﹁ ま す ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 こ こ か ら 、 丁 寧 体 を ﹁ で す ま す 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。 丁 寧 の 度 合 い を よ り 強 め 、 ﹁ で す ﹂ の 代 わ り に ﹁ で ご ざ い ま す ﹂ を 用 い た 文 体 を 、 特 に ﹁ で ご ざ い ま す 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。 丁 寧 体 は 、 敬 語 の 面 か ら い え ば 丁 寧 語 を 用 い た 文 体 の こ と で あ る 。 な お 、 文 末 に 形 容 詞 が 来 る 場 合 に も ﹁ で す ﹂ で 結 ぶ こ と は で き る が ﹁ 花 が 美 し く 咲 い て い ま す ﹂ ﹁ 花 が 美 し ゅ う ご ざ い ま す ﹂ な ど と 言 い 、 ﹁ で す ﹂ を 避 け る こ と が あ る 。
談 話 の 文 体 ︵ 話 体 ︶ は 、 話 し 手 の 性 別 ・ 年 齢 ・ 職 業 ・ 場 面 な ど 、 位 相 の 違 い に よ っ て 左 右 さ れ る 部 分 が 大 き い 。 ﹁ ご は ん を 食 べ て き ま し た ﹂ と い う 丁 寧 体 は 、 話 し 手 の 属 性 に よ っ て 、 た と え ば 、 次 の よ う な 変 容 が あ る 。
● ご は ん 食 べ て き た よ 。 ︵ 子 ど も や 一 般 人 の く だ け た 文 体 ︶ ● め し 食 っ て き た ぜ 。 ︵ S N S や 学 生 の 粗 野 な 文 体 ︶ ● 食 事 を 取 っ て ま い り ま し た 。 ︵ 成 人 の 改 ま っ た 文 体 ︶ こ の よ う に 異 な る 言 葉 遣 い の そ れ ぞ れ を 位 相 語 と 言 い 、 そ れ ぞ れ の 差 を 位 相 差 と い う 。
物 語 作 品 や メ デ ィ ア に お い て 、 位 相 が 極 端 に ス テ レ オ タ イ プ 化 さ れ て 現 実 と 乖 離 し た り 、 あ る い は 書 き 手 な ど が 仮 想 的 ︵ バ ー チ ャ ル ︶ な 位 相 を 意 図 的 に 作 り 出 し た り す る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 言 葉 遣 い を ﹁ 役 割 語 ﹂ と 称 す る こ と が あ る 。 例 え ば 以 下 の 文 体 は 、 実 際 の 性 別 ・ 博 士 ・ 令 嬢 ・ 地 方 出 身 者 な ど の 一 般 的 な 位 相 を 反 映 し た も の で は な い も の の 、 小 説 ・ 漫 画 ・ ア ニ メ ・ ド ラ マ な ど で 、 仮 想 的 に そ れ ら し い 感 じ を 与 え る 文 体 と し て 広 く 観 察 さ れ る 。 こ れ は 現 代 に 始 ま っ た も の で は な く 、 近 世 や 近 代 の 文 献 に も 役 割 語 の 例 が 認 め ら れ る ︵ 仮 名 垣 魯 文 ﹃ 西 洋 道 中 膝 栗 毛 ﹄ に 現 れ る 外 国 人 ら し い 言 葉 遣 い な ど ︶ 。
● ご は ん 食 べ て き た わ よ 。 ︵ 目 上 の 女 性 ︶ ● わ し は 、 食 事 を し て き た の じ ゃ 。 ︵ 博 士 風 ︶ ● わ た く し 、 お 食 事 を い た だ い て ま い り ま し て よ 。 ︵ お 嬢 様 風 ︶ ● お ら 、 め し 食 っ て き た だ よ 。 ︵ 田 舎 者 風 ︶ ● ワ タ シ 、 ご は ん 食 べ て き た ア ル ヨ 。 ︵ 中 国 人 風 。 協 和 語 を 参 照 ︶
日 本 語 で は 、 待 遇 表 現 が 文 法 的 ・ 語 彙 的 な 体 系 を 形 作 っ て い る 。 と り わ け 、 相 手 に 敬 意 を 示 す 言 葉 ︵ 敬 語 ︶ に お い て 顕 著 で あ る 。
﹁ 敬 語 は 日 本 に し か な い ﹂ と 言 わ れ る こ と が あ る が 、 日 本 と 同 様 に 敬 語 が 文 法 的 ・ 語 彙 的 体 系 を 形 作 っ て い る 言 語 と し て は 、 朝 鮮 語 ・ ジ ャ ワ 語 ・ ベ ト ナ ム 語 ・ チ ベ ッ ト 語 ・ ベ ン ガ ル 語 ・ タ ミ ル 語 な ど が あ り 、 尊 敬 ・ 謙 譲 ・ 丁 寧 の 区 別 も あ る 。 朝 鮮 語 で は た と え ば 動 詞 ﹁ 내 다 ︵ ネ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 す ︶ は 、 敬 語 形 ﹁ 내 시 다 ︵ ネ シ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 さ れ る ︶ ・ ﹁ 냅 니 다 ︵ ネ ム ニ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 し ま す ︶ の 形 を 持 つ 。
敬 語 体 系 は 無 く と も 、 敬 意 を 示 す 表 現 自 体 は 、 さ ま ざ ま な 言 語 に 広 く 観 察 さ れ る 。 相 手 を 敬 い 、 物 を 丁 寧 に 言 う こ と は 、 発 達 し た 社 会 な ら ば ど こ で も 必 要 と さ れ る 。 そ う し た 言 い 方 を 習 得 す る こ と は 、 ど の 言 語 で も 容 易 で な い 。
金 田 一 京 助 な ど に よ れ ば 、 現 代 日 本 語 の 敬 語 に 特 徴 的 な の は 次 の 2 点 で あ る 。
● 相 対 敬 語 で あ る ● 文 法 体 系 と な っ て い る 朝 鮮 語 な ど 他 の 言 語 の 敬 語 で は 、 た と え ば 自 分 の 父 親 は い か な る 状 況 で も 敬 意 表 現 の 対 象 で あ り 、 他 人 に 彼 の こ と を 話 す 場 合 も ﹁ 私 の お 父 様 は … ﹂ と い う 絶 対 的 敬 語 を 用 い る が 、 日 本 語 で は 自 分 の 身 内 に 対 す る 敬 意 を 他 人 に 表 現 す る こ と は 憚 ら れ 、 ﹁ 私 の 父 は … ﹂ の よ う に 表 現 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 皇 室 で は 絶 対 敬 語 が 存 在 し 、 皇 太 子 は 自 分 の 父 親 の こ と を ﹁ 天 皇 陛 下 は … ﹂ と 表 現 す る 。
ど ん な 言 語 も 敬 意 を 表 す 表 現 を 持 っ て い る が 、 日 本 語 や 朝 鮮 語 な ど は そ れ が 文 法 体 系 と な っ て い る た め 、 表 現 ・ 言 語 行 動 の あ ら ゆ る 部 分 に 、 高 度 に 組 織 立 っ た 体 系 が 出 来 上 が っ て い る 。 そ の た め 、 敬 意 の 種 類 や 度 合 い に 応 じ た 表 現 の 選 択 肢 が 予 め 用 意 さ れ て お り 、 常 に そ れ ら の 中 か ら 適 切 な 表 現 を 選 ば な く て は な ら な い 。
以 下 、 日 本 語 の 敬 語 体 系 お よ び 敬 意 表 現 に つ い て 述 べ る 。
日本語の敬語体系は、一般に、大きく尊敬語 謙譲語 丁寧語 文化審議会 国語分科会は、2007年2月に「敬語の指針」を答申し、これに丁重語 美化語 [116]
尊 敬 語 は 、 動 作 の 主 体 を 高 め る こ と で 、 主 体 へ の 敬 意 を 表 す 言 い 方 で あ る 。 動 詞 に ﹁ お ︵ ご ︶ 〜 に な る ﹂ を 付 け た 形 、 ま た 、 助 動 詞 ﹁ ︵ ら ︶ れ る ﹂ を 付 け た 形 な ど が 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 動 詞 ﹁ 取 る ﹂ の 尊 敬 形 と し て 、 ﹁ ︵ 先 生 が ︶ お 取 り に な る ﹂ ﹁ ︵ 先 生 が ︶ 取 ら れ る ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。
語 に よ っ て は 、 特 定 の 尊 敬 語 が 対 応 す る も の も あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 言 う ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ お っ し ゃ る ﹂ 、 ﹁ 食 べ る ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ 召 し 上 が る ﹂ 、 ﹁ 行 く ・ 来 る ・ い る ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ い ら っ し ゃ る ﹂ で あ る 。
謙 譲 語 は 、 古 代 か ら 基 本 的 に 動 作 の 客 体 へ の 敬 意 を 表 す 言 い 方 で あ り 、 現 代 で は ﹁ 動 作 の 主 体 を 低 め る ﹂ と 解 釈 す る ほ う が よ い 場 合 が あ る 。 動 詞 に ﹁ お 〜 す る ﹂ ﹁ お 〜 い た し ま す ﹂ ︵ 謙 譲 語 + 丁 寧 語 ︶ を つ け た 形 な ど が 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 ﹁ 取 る ﹂ の 謙 譲 形 と し て 、 ﹁ お 取 り す る ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。
語 に よ っ て は 、 特 定 の 謙 譲 語 が 対 応 す る も の も あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 言 う ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ 申 し 上 げ る ﹂ 、 ﹁ 食 べ る ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ い た だ く ﹂ 、 ﹁ ︵ 相 手 の 所 に ︶ 行 く ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ 伺 う ﹂ ﹁ 参 上 す る ﹂ ﹁ ま い る ﹂ で あ る 。
な お 、 ﹁ 夜 も 更 け て ま い り ま し た ﹂ の ﹁ ま い り ﹂ な ど 、 謙 譲 表 現 の よ う で あ り な が ら 、 誰 か を 低 め て い る わ け で は な い 表 現 が あ る 。 こ れ は 、 ﹁ 夜 も 更 け て き た ﹂ と い う 話 題 を 丁 重 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 聞 き 手 へ の 敬 意 を 表 す も の で あ る 。 宮 地 裕 は 、 こ の 表 現 に 使 わ れ る 語 を 、 特 に ﹁ 丁 重 語 ﹂ と 称 し て い る 。 丁 重 語 に は ほ か に ﹁ い た し ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 申 し ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 存 じ ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 小 生 ﹂ ﹁ 小 社 ﹂ ﹁ 弊 社 ﹂ な ど が あ る 。 文 化 審 議 会 の ﹁ 敬 語 の 指 針 ﹂ で も 、 ﹁ 明 日 か ら 海 外 へ ま い り ま す ﹂ の ﹁ ま い り ﹂ の よ う に 、 相 手 と は 関 り の な い 自 分 側 の 動 作 を 表 現 す る 言 い 方 を 丁 重 語 と し て い る 。
丁 寧 語 は 、 文 末 を 丁 寧 に す る こ と で 、 聞 き 手 へ の 敬 意 を 表 す も の で あ る 。 動 詞 ・ 形 容 詞 の 終 止 形 で 終 わ る 常 体 に 対 し て 、 名 詞 ・ 形 容 動 詞 語 幹 な ど に ﹁ で す ﹂ を 付 け た 形 ︵ ﹁ 学 生 で す ﹂ ﹁ き れ い で す ﹂ ︶ や 、 動 詞 に ﹁ ま す ﹂ を つ け た 形 ︵ ﹁ 行 き ま す ﹂ ﹁ 分 か り ま し た ﹂ ︶ 等 の 丁 寧 語 を 用 い た 文 体 を 敬 体 と い う 。
一 般 に 、 目 上 の 人 に は 丁 寧 語 を 用 い 、 同 等 ・ 目 下 の 人 に は 丁 寧 語 を 用 い な い と い わ れ る 。 し か し 、 実 際 の 言 語 生 活 に 照 ら し て 考 え れ ば 、 こ れ は 事 実 で は な い 。 母 が 子 を 叱 る と き 、 ﹁ お 母 さ ん は も う 知 り ま せ ん よ ﹂ と 丁 寧 語 を 用 い る 場 合 も あ る 。 丁 寧 語 が 用 い ら れ る 多 く の 場 合 は 、 敬 意 や 謝 意 の 表 現 と さ れ る が 、 稀 に 一 歩 引 い た 心 理 的 な 距 離 を と ろ う と す る 場 合 も あ る 。
﹁ お 弁 当 ﹂ ﹁ ご 飯 ﹂ な ど の ﹁ お ﹂ ﹁ ご ﹂ も 、 広 い 意 味 で は 丁 寧 語 に 含 ま れ る が 、 宮 地 裕 は 特 に ﹁ 美 化 語 ﹂ と 称 し て 区 別 す る 。 相 手 へ の 丁 寧 の 意 を 示 す と い う よ り は 、 話 し 手 が 自 分 の 言 葉 遣 い に 配 慮 し た 表 現 で あ る 。 し た が っ て 、 ﹁ お 弁 当 食 べ よ う よ 。 ﹂ の よ う に 、 丁 寧 体 で な い 文 で も 美 化 語 を 用 い る こ と が あ る 。 文 化 審 議 会 の ﹁ 敬 語 の 指 針 ﹂ で も ﹁ 美 化 語 ﹂ を 設 け て い る 。
こ の 節 に は 独 自 研 究 が 含 ま れ て い る お そ れ が あ り ま す 。 問 題 箇 所 を 検 証 し 出 典 を 追 加 し て 、 記 事 の 改 善 に ご 協 力 く だ さ い 。 議 論 は ノ ー ト を 参 照 し て く だ さ い 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶
日 本 語 で 敬 意 を 表 現 す る た め に は 、 文 法 ・ 語 彙 の 敬 語 要 素 を 知 っ て い る だ け で は な お 不 十 分 で あ り 、 時 や 場 合 な ど 種 々 の 要 素 に 配 慮 し た 適 切 な 表 現 が 必 要 で あ る 。 こ れ を 敬 意 表 現 ︵ 敬 語 表 現 ︶ と い う こ と が あ る 。
た と え ば 、 ﹁ 課 長 も コ ー ヒ ー を お 飲 み に な り た い で す か ﹂ は 、 尊 敬 表 現 ﹁ お 飲 み に な る ﹂ を 用 い て い る が 、 敬 意 表 現 と し て は 適 切 で な い 。 日 本 語 で は 相 手 の 意 向 を 直 接 的 に 聞 く こ と は 失 礼 に 当 た る か ら で あ る 。 ﹁ コ ー ヒ ー は い か が で す か ﹂ の よ う に 言 う の が 適 切 で あ る 。 第 22 期 国 語 審 議 会 ︵ 2 0 0 0 年 ︶ は 、 こ の よ う な 敬 意 表 現 の 重 要 性 を 踏 ま え て 、 ﹁ 現 代 社 会 に お け る 敬 意 表 現 ﹂ を 答 申 し た 。
婉 曲 表 現 の 一 部 は 、 敬 意 表 現 と し て も 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 相 手 に 窓 を 開 け て ほ し い 場 合 は 、 命 令 表 現 に よ ら ず に 、 ﹁ 窓 を 開 け て く れ る ? ﹂ な ど と 問 い か け 表 現 を 用 い る 。 あ る い は 、 ﹁ 今 日 は 暑 い ね え ﹂ と だ け 言 っ て 、 窓 を 開 け て ほ し い 気 持 ち を 含 意 す る こ と も あ る 。
日 本 人 が 商 取 引 で ﹁ 考 え さ せ て も ら い ま す ﹂ と い う 場 合 は 拒 絶 の 意 味 で あ る と 言 わ れ る 。 英 語 で も " T h a n k y o u f o r i n v i t i n g m e . " ︵ 誘 っ て く れ て あ り が と う ︶ と は 誘 い を 断 る 表 現 で あ る 。 ま た 、 京 都 で は 、 京 都 弁 で 帰 り が け の 客 に そ の 気 が な い の に ﹁ ぶ ぶ づ け ︵ お 茶 漬 け ︶ で も あ が っ て お い き や す ﹂ と 愛 想 を 言 う と さ れ る ︵ 出 典 は 落 語 ﹁ 京 の ぶ ぶ づ け ﹂ ﹁ 京 の 茶 漬 け ﹂ よ る と い う ︶ 。 こ れ ら は 、 相 手 の 気 分 を 害 さ な い よ う に 工 夫 し た 表 現 と い う 意 味 で は 、 広 義 の 敬 意 表 現 と 呼 ぶ べ き も の で あ る が 、 そ の 呼 吸 が 分 か ら な い 人 と の 間 に 誤 解 を 招 く お そ れ も あ る 。
日本語には多様な方言 がみられ、それらはいくつかの方言圏にまとめることができる。どのような方言圏を想定するかは、区画するために用いる指標によって少なからず異なる。
1 9 6 7 年 の 相 互 理 解 可 能 性 の 調 査 よ り 、 関 東 地 方 出 身 者 に 最 も 理 解 し に く い 方 言 は ︵ 琉 球 諸 語 と 東 北 方 言 を 除 く ︶ 、 富 山 県 氷 見 方 言 ︵ 正 解 率 4 . 1 % ︶ 、 長 野 県 木 曽 方 言 ︵ 正 解 率 1 3 . 3 % ︶ 、 鹿 児 島 方 言 ︵ 正 解 率 1 7 . 6 % ︶ 、 岡 山 県 真 庭 方 言 ︵ 正 解 率 2 4 . 7 % ︶ だ っ た 。 [ 1 2 1 ] こ の 調 査 は 、 12 〜 20 秒 の 長 さ 、 1 3 5 〜 2 4 4 の 音 素 の 老 人 の 録 音 に 基 づ い て お り 、 42 名 若 者 が 聞 い て 翻 訳 し た 。 受 験 者 は 関 東 地 方 で 育 っ た 慶 應 大 学 の 学 生 で あ っ た 。 [ 1 2 1 ]
日本語の方言区分の一例。大きな方言境界ほど太い線で示している。
東 条 操 は 、 全 国 で 話 さ れ て い る 言 葉 を 大 き く 東 部 方 言 ・ 西 部 方 言 ・ 九 州 方 言 お よ び 琉 球 方 言 に 分 け て い る 。 ま た そ れ ら は 、 北 海 道 ・ 東 北 ・ 関 東 ・ 八 丈 島 ・ 東 海 東 山 ・ 北 陸 ・ 近 畿 ・ 中 国 ・ 雲 伯 ︵ 出 雲 ・ 伯 耆 ︶ ・ 四 国 ・ 豊 日 ︵ 豊 前 ・ 豊 後 ・ 日 向 ︶ ・ 肥 筑 ︵ 筑 紫 ・ 肥 前 ・ 肥 後 ︶ ・ 薩 隅 ︵ 薩 摩 ・ 大 隅 ︶ ・ 奄 美 群 島 ・ 沖 縄 諸 島 ・ 先 島 諸 島 に 区 画 さ れ た 。 こ れ ら の 分 類 は 、 今 日 で も な お 一 般 的 に 用 い ら れ る 。 な お 、 こ の う ち 奄 美 ・ 沖 縄 ・ 先 島 の 言 葉 は 、 日 本 語 の 一 方 言 ︵ 琉 球 方 言 ︶ と す る 立 場 と 、 独 立 言 語 と し て 琉 球 語 と す る 立 場 と が あ る 。
ま た 、 金 田 一 春 彦 は 、 近 畿 ・ 四 国 を 主 と す る 内 輪 方 言 、 関 東 ・ 中 部 ・ 中 国 ・ 九 州 北 部 の 一 部 を 主 と す る 中 輪 方 言 、 北 海 道 ・ 東 北 ・ 九 州 の 大 部 分 を 主 と す る 外 輪 方 言 、 沖 縄 地 方 を 主 と す る 南 島 方 言 に 分 類 し た 。 こ の 分 類 は 、 ア ク セ ン ト や 音 韻 、 文 法 の 特 徴 が 畿 内 を 中 心 に 輪 を 描 く こ と に 着 目 し た も の で あ る 。 こ の ほ か 、 幾 人 か の 研 究 者 に よ り 方 言 区 画 案 が 示 さ れ て い る 。
一 つ の 方 言 区 画 の 内 部 も 変 化 に 富 ん で い る 。 た と え ば 、 奈 良 県 は 近 畿 方 言 の 地 域 に 属 す る が 、 十 津 川 村 や 下 北 山 村 周 辺 で は そ の 地 域 だ け 東 京 式 ア ク セ ン ト が 使 わ れ 、 さ ら に 下 北 山 村 池 原 に は ま た 別 体 系 の ア ク セ ン ト が あ っ て 東 京 式 の 地 域 に 取 り 囲 ま れ て い る 。 香 川 県 観 音 寺 市 伊 吹 町 ︵ 伊 吹 島 ︶ で は 、 平 安 時 代 の ア ク セ ン ト 体 系 が 残 存 し て い る と い わ れ る ︵ 異 説 も あ る ︶ 。 こ れ ら は 特 に 顕 著 な 特 徴 を 示 す 例 で あ る が 、 ど の よ う な 狭 い 地 域 に も 、 そ の 土 地 と し て の 言 葉 の 体 系 が あ る 。 し た が っ て 、 ﹁ ど の 地 点 の こ と ば も 、 等 し く 記 録 に 価 す る ﹂ も の で あ る 。
一 般 に 、 方 言 差 が 話 題 に な る と き に は 、 文 法 の 東 西 の 差 異 が 取 り 上 げ ら れ る こ と が 多 い 。 東 部 方 言 と 西 部 方 言 と の 間 に は 、 お よ そ 次 の よ う な 違 い が あ る 。
否 定 辞 に 東 で ﹁ ナ イ ﹂ 、 西 で ﹁ ン ﹂ を 用 い る 。 完 了 形 に は 、 東 で ﹁ テ ル ﹂ を 、 西 で ﹁ ト ル ﹂ を 用 い る 。 断 定 に は 、 東 で ﹁ ダ ﹂ を 、 西 で ﹁ ジ ャ ﹂ ま た は ﹁ ヤ ﹂ を 用 い る 。 ア ワ 行 五 段 活 用 の 動 詞 連 用 形 は 、 東 で は ﹁ カ ッ タ ︵ 買 ︶ ﹂ と 促 音 便 に 、 西 で は ﹁ コ ー タ ﹂ と ウ 音 便 に な る 。 形 容 詞 連 用 形 は 、 東 で は ﹁ ハ ヤ ク ︵ ナ ル ︶ ﹂ の よ う に 非 音 便 形 を 用 い る が 、 西 で は ﹁ ハ ヨ ー ︵ ナ ル ︶ ﹂ の よ う に ウ 音 便 形 を 用 い る な ど で あ る 。
方 言 の 東 西 対 立 の 境 界 は 、 画 然 と 引 け る も の で は な く 、 ど の 特 徴 を 取 り 上 げ る か に よ っ て 少 な か ら ず 変 わ っ て く る 。 し か し 、 お お む ね 、 日 本 海 側 は 新 潟 県 西 端 の 糸 魚 川 市 、 太 平 洋 側 は 静 岡 県 浜 名 湖 が 境 界 線 ︵ 糸 魚 川 ・ 浜 名 湖 線 ︶ と さ れ る こ と が 多 い 。 糸 魚 川 西 方 に は 難 所 親 不 知 が あ り 、 そ の 南 に は 日 本 ア ル プ ス が 連 な っ て 東 西 の 交 通 を 妨 げ て い た こ と が 、 東 西 方 言 を 形 成 し た 一 因 と み ら れ る 。
日本語のアクセント分布
日 本 語 の ア ク セ ン ト は 、 方 言 ご と の 違 い が 大 き い 。 日 本 語 の ア ク セ ン ト 体 系 は い く つ か の 種 類 に 分 け ら れ る が 、 特 に 広 範 囲 で 話 さ れ 話 者 数 も 多 い の は 東 京 式 ア ク セ ン ト と 京 阪 式 ア ク セ ン ト の 2 つ で あ る 。 東 京 式 ア ク セ ン ト は 下 が り 目 の 位 置 の み を 弁 別 す る が 、 京 阪 式 ア ク セ ン ト は 下 が り 目 の 位 置 に 加 え て 第 1 拍 の 高 低 を 弁 別 す る 。 一 般 に は ア ク セ ン ト の 違 い は 日 本 語 の 東 西 の 違 い と し て 語 ら れ る こ と が 多 い が 、 実 際 の 分 布 は 単 純 な 東 西 対 立 で は な く 、 東 京 式 ア ク セ ン ト は 概 ね 北 海 道 、 東 北 地 方 北 部 、 関 東 地 方 西 部 、 甲 信 越 地 方 、 東 海 地 方 の 大 部 分 、 中 国 地 方 、 四 国 地 方 南 西 部 、 九 州 北 東 部 に 分 布 し て お り 、 京 阪 式 ア ク セ ン ト は 近 畿 地 方 ・ 四 国 地 方 の そ れ ぞ れ 大 部 分 と 北 陸 地 方 の 一 部 に 分 布 し て い る 。 す な わ ち 、 近 畿 地 方 を 中 心 と し た 地 域 に 京 阪 式 ア ク セ ン ト 地 帯 が 広 が り 、 そ の 東 西 を 東 京 式 ア ク セ ン ト 地 域 が 挟 む 形 に な っ て い る 。 日 本 語 の 標 準 語 ・ 共 通 語 の ア ク セ ン ト は 、 東 京 の 山 の 手 言 葉 の も の を 基 盤 に し て い る た め 東 京 式 ア ク セ ン ト で あ る 。
九 州 西 南 部 や 沖 縄 の 一 部 に は 型 の 種 類 が 2 種 類 に な っ て い る 二 型 ア ク セ ン ト が 分 布 し 、 宮 崎 県 都 城 市 な ど に は 型 の 種 類 が 1 種 類 に な っ て い る 一 型 ア ク セ ン ト が 分 布 す る 。 ま た 、 岩 手 県 雫 石 町 や 山 梨 県 早 川 町 奈 良 田 な ど の ア ク セ ン ト は 、 音 の 下 が り 目 で は な く 上 が り 目 を 弁 別 す る 。 こ れ ら 有 ア ク セ ン ト の 方 言 に 対 し 、 東 北 地 方 南 部 か ら 関 東 地 方 北 東 部 に か け て の 地 域 や 、 九 州 の 東 京 式 ア ク セ ン ト 地 帯 と 二 型 ア ク セ ン ト 地 帯 に 挟 ま れ た 地 域 な ど に は 、 話 者 に ア ク セ ン ト の 知 覚 が な く 、 ど こ を 高 く す る と い う 決 ま り が な い 無 ア ク セ ン ト ︵ 崩 壊 ア ク セ ン ト ︶ の 地 域 が あ る 。 こ れ ら の ア ク セ ン ト 大 区 分 の 中 に も 様 々 な 変 種 が あ り 、 さ ら に そ れ ぞ れ の 体 系 の 中 間 型 や 別 派 な ど も 存 在 す る 。
﹁ 花 が ﹂ が 東 京 で ﹁ 低 高 低 ﹂ 、 京 都 で ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 さ れ る よ う に 、 単 語 の ア ク セ ン ト は 地 方 に よ っ て 異 な る 。 た だ し 、 そ れ ぞ れ の 地 方 の ア ク セ ン ト 体 系 は 互 い に ま っ た く 無 関 係 に 成 り 立 っ て い る の で は な い 。 多 く の 場 合 に お い て 規 則 的 な 対 応 が 見 ら れ る 。 た と え ば 、 ﹁ 花 が ﹂ ﹁ 山 が ﹂ ﹁ 池 が ﹂ を 東 京 で は い ず れ も ﹁ 低 高 低 ﹂ と 発 音 す る が 、 京 都 で は い ず れ も ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 し 、 ﹁ 水 が ﹂ ﹁ 鳥 が ﹂ ﹁ 風 が ﹂ は 東 京 で は い ず れ も ﹁ 低 高 高 ﹂ と 発 音 す る の に 対 し て 京 都 で は い ず れ も ﹁ 高 高 高 ﹂ と 発 音 す る 。 ま た 、 ﹁ 松 が ﹂ ﹁ 空 が ﹂ ﹁ 海 が ﹂ は 東 京 で は い ず れ も ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 さ れ る の に 対 し 、 京 都 で は い ず れ も ﹁ 低 低 高 ﹂ と 発 音 さ れ る 。 こ の よ う に 、 あ る 地 方 で 同 じ ア ク セ ン ト の 型 に ま と め ら れ る 語 群 ︵ 類 と 呼 ぶ ︶ は 、 他 の 地 方 で も 同 じ 型 に 属 す る こ と が 一 般 的 に 観 察 さ れ る 。
こ の 事 実 は 、 日 本 の 方 言 ア ク セ ン ト が 、 過 去 の 同 一 の ア ク セ ン ト 体 系 か ら 分 か れ 出 た こ と を 意 味 す る 。 服 部 四 郎 は こ れ を 原 始 日 本 語 の ア ク セ ン ト と 称 し 、 こ れ が 分 岐 し 互 い に 反 対 の 方 向 に 変 化 し て 、 東 京 式 と 京 阪 式 を 生 じ た と 考 え た 。 現 在 有 力 な 説 は 、 院 政 期 の 京 阪 式 ア ク セ ン ト ︵ 名 義 抄 式 ア ク セ ン ト ︶ が 日 本 語 ア ク セ ン ト の 祖 体 系 で 、 現 在 の 諸 方 言 ア ク セ ン ト の ほ と ん ど は こ れ が 順 次 変 化 を 起 こ し た 結 果 生 じ た と す る も の で あ る [ 注 釈 32 ] 。 一 方 で 、 地 方 の 無 ア ク セ ン ト と 中 央 の 京 阪 式 ア ク セ ン ト の 接 触 で 諸 方 言 の ア ク セ ン ト が 生 じ た と す る 説 も あ る 。
発 音 の 特 徴 に よ っ て 本 土 方 言 を 大 き く 区 分 す る と 、 表 日 本 方 言 、 裏 日 本 方 言 、 薩 隅 ︵ 鹿 児 島 ︶ 式 方 言 に 分 け る こ と が で き る [ 1 3 2 ] 。 表 日 本 方 言 は 共 通 語 に 近 い 音 韻 体 系 を 持 つ 。 裏 日 本 式 の 音 韻 体 系 は 、 東 北 地 方 を 中 心 に 、 北 海 道 沿 岸 部 や 新 潟 県 越 後 北 部 、 関 東 北 東 部 ︵ 茨 城 県 ・ 栃 木 県 ︶ と 、 と ん で 島 根 県 出 雲 地 方 を 中 心 と し た 地 域 に 分 布 す る 。 そ の 特 徴 は 、 イ 段 と ウ 段 の 母 音 に 中 舌 母 音 を 用 い る こ と と 、 エ が 狭 く イ に 近 い こ と で あ る 。 関 東 の う ち 千 葉 県 や 埼 玉 県 東 部 な ど と 、 越 後 中 部 ・ 佐 渡 ・ 富 山 県 ・ 石 川 県 能 登 の 方 言 は 裏 日 本 式 と 表 日 本 式 の 中 間 で あ る 。 ま た 薩 隅 式 方 言 は 、 大 量 の 母 音 脱 落 に よ り 閉 音 節 を 多 く 持 っ て い る 点 で 他 方 言 と 対 立 し て い る 。 薩 隅 方 言 以 外 の 九 州 の 方 言 は 、 薩 隅 式 と 表 日 本 式 の 中 間 で あ る 。
音 韻 の 面 で は 、 母 音 の ﹁ う ﹂ を 、 東 日 本 、 北 陸 、 出 雲 付 近 で は 中 舌 寄 り で 非 円 唇 母 音 ︵ 唇 を 丸 め な い ︶ の [ ɯ ] ま た は [ ɯ ̈ ] で 、 西 日 本 一 般 で は 奥 舌 で 円 唇 母 音 の [ u ] で 発 音 す る 。 ま た 、 母 音 は 、 東 日 本 や 北 陸 、 出 雲 付 近 、 九 州 で 無 声 化 し や す く 、 東 海 、 近 畿 、 中 国 、 四 国 で は 無 声 化 し に く い [ 1 3 3 ] 。
ま た こ れ と は 別 に 、 近 畿 ・ 四 国 ︵ ・ 北 陸 ︶ と そ れ 以 外 で の 対 立 が あ る 。 前 者 は 京 阪 式 ア ク セ ン ト の 地 域 で あ る が 、 こ の 地 域 で は ア ク セ ン ト 以 外 に も 、 ﹁ 木 ﹂ を ﹁ き い ﹂ 、 ﹁ 目 ﹂ を ﹁ め え ﹂ の よ う に 一 音 節 語 を 伸 ば し て 二 拍 に 発 音 し 、 ま た ﹁ 赤 い ﹂ → ﹁ あ け ー ﹂ の よ う な 連 母 音 の 融 合 が 起 こ ら な い と い う 共 通 点 が あ る 。 ま た 、 西 日 本 ︵ 九 州 ・ 山 陰 ・ 北 陸 除 く ︶ は 母 音 を 強 く 子 音 を 弱 く 発 音 し 、 東 日 本 や 九 州 は 子 音 を 強 く 母 音 を 弱 く 発 音 す る 傾 向 が あ る 。
日本語の歴史は一般的に「日本語史 」(または「国語史 」)と呼ばれる[注釈 33]
母 音 の 数 は 、 奈 良 時 代 お よ び そ れ 以 前 に は 現 在 よ り も 多 か っ た と 考 え ら れ る 。 橋 本 進 吉 は 、 江 戸 時 代 の 上 代 特 殊 仮 名 遣 の 研 究 を 再 評 価 し [ 1 3 4 ] 、 記 紀 や ﹃ 万 葉 集 ﹄ な ど の 万 葉 仮 名 に お い て ﹁ き ・ ひ ・ み ・ け ・ へ ・ め ・ こ ・ そ ・ と ・ の ・ も ・ よ ・ ろ ﹂ の 表 記 に 2 種 類 の 仮 名 が 存 在 す る こ と を 指 摘 し た ︵ 甲 類 ・ 乙 類 と 称 す る 。 ﹁ も ﹂ は ﹃ 古 事 記 ﹄ の み で 区 別 さ れ る ︶ 。 橋 本 は 、 こ れ ら の 仮 名 の 区 別 は 音 韻 上 の 区 別 に 基 づ く も の で 、 特 に 母 音 の 差 に よ る も の と 考 え た [ 1 3 5 ] 。 橋 本 の 説 は 、 後 続 の 研 究 者 ら に よ っ て 、 ﹁ 母 音 の 数 が ア イ ウ エ オ 五 つ で な く 、 合 計 八 を 数 え る も の ﹂ と い う 8 母 音 説 と 受 け 取 ら れ 、 定 説 化 し た [ 注 釈 34 ] 。 8 母 音 の 区 別 は 平 安 時 代 に は な く な り 、 現 在 の よ う に 5 母 音 に な っ た と み ら れ る 。 な お 、 上 代 日 本 語 の 語 彙 で は 、 母 音 の 出 現 の 仕 方 が ウ ラ ル 語 族 や ア ル タ イ 語 族 の 母 音 調 和 の 法 則 に 類 似 し て い る と さ れ る 。
﹁ は 行 ﹂ の 子 音 は 、 奈 良 時 代 以 前 に は [ p ] で あ っ た と み ら れ る 。 す な わ ち 、 ﹁ は な ︵ 花 ︶ ﹂ は [ p a n a ] ︵ パ ナ ︶ の よ う に 発 音 さ れ た 可 能 性 が あ る 。 [ p ] は 遅 く と も 平 安 時 代 初 期 に は 無 声 両 唇 摩 擦 音 [ ɸ ] に 変 化 し て い た [ 1 3 7 ] 。 す な わ ち 、 ﹁ は な ﹂ は [ ɸ a n a ] ︵ フ ァ ナ ︶ と な っ て い た 。 中 世 末 期 に 、 ロ ー マ 字 で 当 時 の 日 本 語 を 記 述 し た キ リ シ タ ン 資 料 が 多 く 残 さ れ て い る が 、 そ こ で は ﹁ は 行 ﹂ の 文 字 が ﹁ f a , f i , f u , f e , f o ﹂ で 転 写 さ れ て お り 、 当 時 の ﹁ は 行 ﹂ は ﹁ フ ァ 、 フ ィ 、 フ 、 フ ェ 、 フ ォ ﹂ に 近 い 発 音 で あ っ た こ と が 分 か る 。 中 世 末 期 か ら 江 戸 時 代 に か け て 、 ﹁ は 行 ﹂ の 子 音 は [ ɸ ] か ら [ h ] へ 移 行 し た 。 た だ し 、 ﹁ ふ ﹂ は [ ɸ ] の ま ま に 、 ﹁ ひ ﹂ は [ ç i ] に な っ た 。 現 代 で も 引 き 続 き こ の よ う に 発 音 さ れ て い る 。
平 安 時 代 以 降 、 語 中 ・ 語 尾 の ﹁ は 行 ﹂ 音 が ﹁ わ 行 ﹂ 音 に 変 化 す る ハ 行 転 呼 が 起 こ っ た 。 た と え ば 、 ﹁ か は ︵ 川 ︶ ﹂ ﹁ か ひ ︵ 貝 ︶ ﹂ ﹁ か ふ ︵ 買 ︶ ﹂ ﹁ か へ ︵ 替 ︶ ﹂ ﹁ か ほ ︵ 顔 ︶ ﹂ は 、 そ れ ま で [ k a ɸ a ] [ k a ɸ i ] [ k a ɸ u ] [ k a ɸ e ] [ k a ɸ o ] で あ っ た も の が 、 [ k a w a ] [ k a w i ] [ k a u ] [ k a w e ] [ k a w o ] に な っ た 。 ﹁ は は ︵ 母 ︶ ﹂ も 、 キ リ シ タ ン 資 料 で は ﹁ f a u a ﹂ ︵ ハ ワ ︶ と 記 さ れ た 例 が あ る な ど 、 他 の 語 と 同 様 に ハ 行 転 呼 が 起 こ っ て い た こ と が 知 ら れ る 。
こ の よ う に 、 ﹁ は 行 ﹂ 子 音 は 語 頭 で お お む ね [ p ] → [ ɸ ] → [ h ] 、 語 中 で [ p ] → [ ɸ ] → [ w ] と 唇 音 が 衰 退 す る 方 向 で 推 移 し た 。 ま た 、 関 西 で ﹁ う ﹂ を 唇 を 丸 め て 発 音 す る ︵ 円 唇 母 音 ︶ の に 対 し 、 関 東 で は 唇 を 丸 め ず に 発 音 す る が 、 こ れ も 唇 音 退 化 の 例 と と ら え る こ と が で き る 。
﹁ や 行 ﹂ の ﹁ え ﹂ ( [ je ] ) の 音 が 古 代 に 存 在 し た こ と は 、 ﹁ あ 行 ﹂ の ﹁ え ﹂ の 仮 名 と 別 の 文 字 で 書 き 分 け ら れ て い た こ と か ら 明 ら か で あ る 。 平 安 時 代 初 期 に 成 立 し た と 見 ら れ る ﹁ 天 地 の 詞 ﹂ に は ﹁ え ﹂ が 2 つ 含 ま れ て お り 、 ﹁ あ 行 ﹂ と ﹁ や 行 ﹂ の 区 別 を 示 す も の と 考 え ら れ る 。 こ の 区 別 は 10 世 紀 の 頃 に は な く な っ て い た と み ら れ 、 9 7 0 年 成 立 の ﹃ 口 遊 ﹄ に 収 録 さ れ る ﹁ 大 為 爾 の 歌 ﹂ で は ﹁ あ 行 ﹂ の ﹁ え ﹂ し か な い 。 こ の 頃 に は ﹁ あ 行 ﹂ と ﹁ や 行 ﹂ の ﹁ え ﹂ の 発 音 は と も に [ je ] に な っ て い た 。
﹁ わ 行 ﹂ は 、 ﹁ わ ﹂ を 除 い て ﹁ あ 行 ﹂ と の 合 流 が 起 き た 。
平 安 時 代 末 頃 に は 、
(一) ﹁ い ﹂ と ﹁ ゐ ﹂ ︵ お よ び 語 中 ・ 語 尾 の ﹁ ひ ﹂ ︶ (二) ﹁ え ﹂ と ﹁ ゑ ﹂ ︵ お よ び 語 中 ・ 語 尾 の ﹁ へ ﹂ ︶ (三) ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ ︵ お よ び 語 中 ・ 語 尾 の ﹁ ほ ﹂ ︶ が 同 一 に 帰 し た 。 3 が 同 音 に な っ た の は 11 世 紀 末 頃 、 1 と 2 が 同 音 に な っ た の は 12 世 紀 末 頃 と 考 え ら れ て い る 。 藤 原 定 家 の ﹃ 下 官 集 ﹄ ︵ 13 世 紀 ︶ で は ﹁ お ﹂ ・ ﹁ を ﹂ 、 ﹁ い ﹂ ・ ﹁ ゐ ﹂ ・ ﹁ ひ ﹂ 、 ﹁ え ﹂ ・ ﹁ ゑ ﹂ ・ ﹁ へ ﹂ の 仮 名 の 書 き 分 け が 問 題 に な っ て い る 。
当 時 の 発 音 は 、 1 は 現 在 の [ i ] ︵ イ ︶ 、 2 は [ je ] ︵ イ ェ ︶ 、 3 は [ wo ] ︵ ウ ォ ︶ の よ う で あ っ た 。
3 が 現 在 の よ う に [ o ] ︵ オ ︶ に な っ た の は 江 戸 時 代 で あ っ た と み ら れ る 。 18 世 紀 の ﹃ 音 曲 玉 淵 集 ﹄ で は 、 ﹁ お ﹂ ﹁ を ﹂ を ﹁ ウ ォ ﹂ と 発 音 し な い よ う に 説 い て い る 。
2 が 現 在 の よ う に [ e ] ︵ エ ︶ に な っ た の は 、 新 井 白 石 ﹃ 東 雅 ﹄ 総 論 の 記 述 か ら す れ ば 早 く と も 元 禄 享 保 頃 ︵ 17 世 紀 末 か ら 18 世 紀 初 頭 ︶ 以 降 [ 1 4 1 ] 、 ﹃ 謳 曲 英 華 抄 ﹄ の 記 述 か ら す れ ば 18 世 紀 中 葉 頃 と み ら れ る 。
﹁ が 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 中 ・ 語 尾 で は い わ ゆ る 鼻 濁 音 ︵ ガ 行 鼻 音 ︶ の [ ŋ ] で あ っ た 。 鼻 濁 音 は 、 近 代 に 入 っ て 急 速 に 勢 力 を 失 い 、 語 頭 と 同 じ 破 裂 音 の [ ɡ ] ま た は 摩 擦 音 の [ ɣ ] に 取 っ て 代 わ ら れ つ つ あ る 。 今 日 、 鼻 濁 音 を 表 記 す る 時 は 、 ﹁ か 行 ﹂ の 文 字 に 半 濁 点 を 付 し て ﹁ カ カ ゚ ミ ︵ 鏡 ︶ ﹂ の よ う に 書 く こ と も あ る 。
﹁ じ ・ ぢ ﹂ ﹁ ず ・ づ ﹂ の 四 つ 仮 名 は 、 室 町 時 代 前 期 の 京 都 で は そ れ ぞ れ [ ʑ i ] , [ d ʲ i ] , [ zu ] , [ du ] と 発 音 さ れ て い た が 、 16 世 紀 初 め 頃 に ﹁ ち ﹂ ﹁ ぢ ﹂ が 口 蓋 化 し 、 ﹁ つ ﹂ ﹁ づ ﹂ が 破 擦 音 化 し た 結 果 、 ﹁ ぢ ﹂ ﹁ づ ﹂ の 発 音 が そ れ ぞ れ [ ʥ i ] , [ ʣ u ] と な り 、 ﹁ じ ﹂ ﹁ ず ﹂ の 音 に 近 づ い た 。 16 世 紀 末 の キ リ シ タ ン 資 料 で は そ れ ぞ れ ﹁ ji ・ gi ﹂ ﹁ zu ・ z z u ﹂ な ど 異 な る ロ ー マ 字 で 表 さ れ て お り 、 当 時 は ま だ 発 音 の 区 別 が あ っ た こ と が 分 か る が 、 当 時 既 に 混 同 が 始 ま っ て い た こ と も 記 録 さ れ て い る 。 17 世 紀 末 頃 に は 発 音 の 区 別 は 京 都 で は ほ ぼ 消 滅 し た と 考 え ら れ て い る ︵ 今 も 区 別 し て い る 方 言 も あ る [ 57 ] ︶ 。 ﹁ せ ・ ぜ ﹂ は ﹁ xe ・ je ﹂ で 表 記 さ れ て お り 、 現 在 の ﹁ シ ェ ・ ジ ェ ﹂ に 当 た る [ ɕ e ] , [ ʑ e ] で あ っ た こ と も 分 か っ て い る 。 関 東 で は 室 町 時 代 末 に す で に [ se ] , [ ze ] の 発 音 で あ っ た が 、 こ れ は や が て 西 日 本 に も 広 が り 、 19 世 紀 中 頃 に は 京 都 で も 一 般 化 し た 。 現 在 は 東 北 や 九 州 な ど の 一 部 に [ ɕ e ] , [ ʑ e ] が 残 っ て い る 。
平 安 時 代 か ら 、 発 音 を 簡 便 に す る た め に 単 語 の 音 を 変 え る 音 便 現 象 が 少 し ず つ 見 ら れ る よ う に な っ た 。 ﹁ 次 ︵ つ ︶ ぎ て ﹂ を ﹁ 次 い で ﹂ と す る な ど の イ 音 便 、 ﹁ 詳 ︵ く は ︶ し く す ﹂ を ﹁ 詳 し う す ﹂ と す る な ど の ウ 音 便 、 ﹁ 発 ︵ た ︶ ち て ﹂ を ﹁ 発 っ て ﹂ と す る な ど の 促 音 便 、 ﹁ 飛 び て ﹂ を ﹁ 飛 ん で ﹂ と す る な ど の 撥 音 便 が 現 れ た 。 ﹃ 源 氏 物 語 ﹄ に も 、 ﹁ い み じ く ﹂ を ﹁ い み じ う ﹂ と す る な ど の ウ 音 便 が 多 く 、 ま た 、 少 数 な が ら ﹁ 苦 し き ﹂ を ﹁ 苦 し い ﹂ と す る な ど の イ 音 便 の 例 も 見 出 さ れ る 。 鎌 倉 時 代 以 降 に な る と 、 音 便 は 口 語 で は 盛 ん に 用 い ら れ る よ う に な っ た 。
中 世 に は 、 ﹁ 差 し て ﹂ を ﹁ 差 い て ﹂ 、 ﹁ 挟 み て ﹂ を ﹁ 挟 う で ﹂ 、 ﹁ 及 び て ﹂ を ﹁ 及 う で ﹂ な ど の よ う に 、 今 の 共 通 語 に は な い 音 便 形 も 見 ら れ た 。 こ れ ら の 形 は 、 今 日 で も 各 地 に 残 っ て い る 。 [ 要 出 典 ]
鎌 倉 時 代 ・ 室 町 時 代 に は 連 声 ︵ れ ん じ ょ う ︶ の 傾 向 が 盛 ん に な っ た 。 撥 音 ま た は 促 音 の 次 に 来 た 母 音 ・ 半 母 音 が ﹁ な 行 ﹂ 音 ・ ﹁ ま 行 ﹂ 音 ・ ﹁ た 行 ﹂ 音 に 変 わ る 現 象 で 、 た と え ば 、 銀 杏 は ﹁ ギ ン ﹂ + ﹁ ア ン ﹂ で ﹁ ギ ン ナ ン ﹂ 、 雪 隠 は ﹁ セ ッ ﹂ + ﹁ イ ン ﹂ で ﹁ セ ッ チ ン ﹂ と な る 。 助 詞 ﹁ は ﹂ ︵ ワ ︶ と 前 の 部 分 と が 連 声 を 起 こ す と 、 ﹁ 人 間 は ﹂ → ﹁ ニ ン ゲ ン ナ ﹂ 、 ﹁ 今 日 は ﹂ → ﹁ コ ン ニ ッ タ ﹂ と な っ た 。
ま た 、 こ の 時 代 に は 、 ﹁ 中 央 ﹂ の ﹁ 央 ﹂ な ど ﹁ ア ウ ﹂ [ au ] の 音 が 合 し て 長 母 音 [ ɔ ː ] に な り 、 ﹁ 応 対 ﹂ の ﹁ 応 ﹂ な ど ﹁ オ ウ ﹂ [ ou ] の 音 が [ o ː ] に な っ た ︵ ﹁ カ ウ ﹂ ﹁ コ ウ ﹂ な ど 頭 子 音 が 付 い た 場 合 も 同 様 ︶ 。 口 を や や 開 け る 前 者 を 開 音 、 口 を す ぼ め る 後 者 を 合 音 と 呼 ぶ 。 ま た 、 ﹁ イ ウ ﹂ [ iu ] 、 ﹁ エ ウ ﹂ [ eu ] な ど の 二 重 母 音 は 、 [ j u ː ] 、 [ j o ː ] と い う 拗 長 音 に 変 化 し た 。 ﹁ 開 合 ﹂ の 区 別 は 次 第 に 乱 れ 、 江 戸 時 代 に は 合 一 し て 今 日 の [ o ː ] ︵ オ ー ︶ に な っ た 。 京 都 で は 、 一 般 の 話 し 言 葉 で は 17 世 紀 に 開 合 の 区 別 は 失 わ れ た 。 し か し 方 言 に よ っ て は 今 も 開 合 の 区 別 が 残 っ て い る も の も あ る [ 57 ] 。
漢 語 が 日 本 で 用 い ら れ る よ う に な る と 、 古 来 の 日 本 に 無 か っ た 合 拗 音 ﹁ ク ヮ ・ グ ヮ ﹂ ﹁ ク ヰ ・ グ ヰ ﹂ ﹁ ク ヱ ・ グ ヱ ﹂ の 音 が 発 音 さ れ る よ う に な っ た 。 こ れ ら は [ k w a ] [ ɡ w e ] な ど と い う 発 音 で あ り 、 ﹁ キ ク ヮ イ ︵ 奇 怪 ︶ ﹂ ﹁ ホ ン グ ヮ ン ︵ 本 願 ︶ ﹂ ﹁ ヘ ン グ ヱ ︵ 変 化 ︶ ﹂ の よ う に 用 い ら れ た 。 当 初 は 外 来 音 の 意 識 が 強 か っ た が 、 平 安 時 代 以 降 は 普 段 の 日 本 語 に 用 い ら れ る よ う に な っ た と み ら れ る [ 1 4 4 ] 。 た だ し ﹁ ク ヰ ・ グ ヰ ﹂ ﹁ ク ヱ ・ グ ヱ ﹂ の 寿 命 は 短 く 、 13 世 紀 に は ﹁ キ ・ ギ ﹂ ﹁ ケ ・ ゲ ﹂ に 統 合 さ れ た 。 ﹁ ク ヮ ﹂ ﹁ グ ヮ ﹂ は 中 世 を 通 じ て 使 わ れ て い た が 、 室 町 時 代 に は す で に ﹁ カ ・ ガ ﹂ と の 間 で 混 同 が 始 ま っ て い た 。 江 戸 時 代 に は 混 同 が 進 ん で い き 、 江 戸 で は 18 世 紀 中 頃 に は 直 音 の ﹁ カ ・ ガ ﹂ が 一 般 化 し た 。 た だ し 一 部 の 方 言 に は 今 も 残 っ て い る [ 57 ] 。
漢 語 は 平 安 時 代 頃 ま で は 原 語 で あ る 中 国 語 に 近 く 発 音 さ れ 、 日 本 語 の 音 韻 体 系 と は 別 個 の も の と 意 識 さ れ て い た 。 入 声 韻 尾 の [ - k ] , [ - t ] , [ - p ] , 鼻 音 韻 尾 の [ - m ] , [ - n ] , [ - ŋ ] な ど も 原 音 に か な り 忠 実 に 発 音 さ れ て い た と 見 ら れ る 。 鎌 倉 時 代 に は 漢 字 音 の 日 本 語 化 が 進 行 し 、 [ ŋ ] は ウ に 統 合 さ れ 、 韻 尾 の [ - m ] と [ - n ] の 混 同 も 13 世 紀 に 一 般 化 し 、 撥 音 の / ɴ / に 統 合 さ れ た 。 入 声 韻 尾 の [ - k ] は 開 音 節 化 し て キ 、 ク と 発 音 さ れ る よ う に な り 、 [ - p ] も [ - ɸ u ] ︵ フ ︶ を 経 て ウ で 発 音 さ れ る よ う に な っ た 。 [ - t ] は 開 音 節 化 し た チ 、 ツ の 形 も 現 れ た が 、 子 音 終 わ り の [ - t ] の 形 も 17 世 紀 末 ま で 並 存 し て 使 わ れ て い た 。 室 町 時 代 末 期 の キ リ シ タ ン 資 料 に は 、 ﹁ b u t m e t ﹂ ︵ 仏 滅 ︶ 、 ﹁ b a t ﹂ ︵ 罰 ︶ な ど の 語 形 が 記 録 さ れ て い る 。 江 戸 時 代 に 入 る と 開 音 節 の 形 が 完 全 に 一 般 化 し た 。
近 代 以 降 に は 、 外 国 語 ︵ 特 に 英 語 ︶ の 音 の 影 響 で 新 し い 音 が 使 わ れ 始 め た 。 比 較 的 一 般 化 し た ﹁ シ ェ ・ チ ェ ・ ツ ァ ・ ツ ェ ・ ツ ォ ・ テ ィ ・ フ ァ ・ フ ィ ・ フ ェ ・ フ ォ ・ ジ ェ ・ デ ィ ・ デ ュ ﹂ な ど の 音 に 加 え 、 場 合 に よ っ て は 、 ﹁ イ ェ ・ ウ ィ ・ ウ ェ ・ ウ ォ ・ ク ァ ・ ク ィ ・ ク ェ ・ ク ォ ・ ツ ィ ・ ト ゥ ・ グ ァ ・ ド ゥ ・ テ ュ ・ フ ュ ﹂ な ど の 音 も 使 わ れ る [ 1 4 5 ] 。 こ れ ら は 、 子 音 ・ 母 音 の そ れ ぞ れ を 取 っ て み れ ば 、 従 来 の 日 本 語 に あ っ た も の で あ る 。 ﹁ ヴ ァ ・ ヴ ィ ・ ヴ ・ ヴ ェ ・ ヴ ォ ・ ヴ ュ ﹂ の よ う に 、 こ れ ま で 無 か っ た 音 は 、 書 き 言 葉 で は 書 き 分 け て も 、 実 際 に 発 音 さ れ る こ と は 少 な い 。
動 詞 の 活 用 種 類 は 、 平 安 時 代 に は 9 種 類 で あ っ た 。 す な わ ち 、 四 段 ・ 上 一 段 ・ 上 二 段 ・ 下 一 段 ・ 下 二 段 ・ カ 変 ・ サ 変 ・ ナ 変 ・ ラ 変 に 分 か れ て い た 。 こ れ が 時 代 と と も に 統 合 さ れ 、 江 戸 時 代 に は 5 種 類 に 減 っ た 。 上 二 段 は 上 一 段 に 、 下 二 段 は 下 一 段 に そ れ ぞ れ 統 合 さ れ 、 ナ 変 ︵ ﹁ 死 ぬ ﹂ な ど ︶ ・ ラ 変 ︵ ﹁ 有 り ﹂ な ど ︶ は 四 段 に 統 合 さ れ た 。 こ れ ら の 変 化 は 、 古 代 か ら 中 世 に か け て 個 別 的 に 起 こ っ た 例 も あ る が 、 顕 著 に な っ た の は 江 戸 時 代 に 入 っ て か ら の こ と で あ る 。 た だ し 、 ナ 変 は 近 代 に 入 っ て も な お 使 用 さ れ る こ と が あ っ た 。
こ の う ち 、 最 も 規 模 の 大 き な 変 化 は 二 段 活 用 の 一 段 化 で あ る 。 二 段 → 一 段 の 統 合 は 、 室 町 時 代 末 期 の 京 阪 地 方 で は 、 ま だ ま れ で あ っ た ︵ 関 東 で は 比 較 的 早 く 完 了 し た ︶ 。 そ れ で も 、 江 戸 時 代 前 期 に は 京 阪 で も 見 ら れ る よ う に な り 、 後 期 に は 一 般 化 し た 。 す な わ ち 、 今 日 の ﹁ 起 き る ﹂ は 、 平 安 時 代 に は ﹁ き ・ き ・ く ・ く る ・ く れ ・ き よ ﹂ の よ う に ﹁ き ・ く ﹂ の 2 段 に 活 用 し た が 、 江 戸 時 代 に は ﹁ き ・ き ・ き る ・ き る ・ き れ ・ き よ ︵ き ろ ︶ ﹂ の よ う に ﹁ き ﹂ の 1 段 だ け で 活 用 す る よ う に な っ た 。 ま た 、 今 日 の ﹁ 明 け る ﹂ は 、 平 安 時 代 に は ﹁ け ・ く ﹂ の 2 段 に 活 用 し た が 、 江 戸 時 代 に は ﹁ け ﹂ の 1 段 だ け で 活 用 す る よ う に な っ た 。 し か も 、 こ の 変 化 の 過 程 で は 、 終 止 ・ 連 体 形 の 合 一 が 起 こ っ て い る た め 、 鎌 倉 ・ 室 町 時 代 頃 に は 、 前 後 の 時 代 と は 異 な っ た 活 用 の 仕 方 に な っ て い る 。 次 に 時 代 ご と の 活 用 を 対 照 し た 表 を 掲 げ る 。
現代の語形
時代
語幹
未然
連用
終止
連体
已然
命令
起きる
平安
お
き
き
く
くる
くれ
きよ
室町
き
き
くる
くる
くれ
きよ
江戸
き
き
きる
きる
きれ
きよ(きろ)
明ける
平安
あ
け
け
く
くる
くれ
けよ
室町
け
け
くる
くる
くれ
けよ
江戸
け
け
ける
ける
けれ
けよ(けろ)
死ぬ
平安
し
な
に
ぬ
ぬる
ぬれ
ね
室町
な
に
ぬる
ぬる
ぬれ
ね
な
に
ぬ
ぬ
ね
ね
有る
平安
あ
ら
り
り
る
れ
れ
室町
ら
り
る
る
れ
れ
江戸
ら
り
る
る
れ
れ
形 容 詞 は 、 平 安 時 代 に は ﹁ く ・ く ・ し ・ き ・ け れ ︵ か ら ・ か り ・ か る ・ か れ ︶ ﹂ の よ う に 活 用 し た ク 活 用 と 、 ﹁ し く ・ し く ・ し ・ し き ・ し け れ ︵ し か ら ・ し か り ・ し か る ・ し か れ ︶ ﹂ の シ ク 活 用 が 存 在 し た 。 こ の 区 別 は 、 終 止 ・ 連 体 形 の 合 一 と と も に 消 滅 し 、 形 容 詞 の 活 用 種 類 は 一 つ に な っ た 。
今 日 で は 、 文 法 用 語 の 上 で 、 四 段 活 用 が 五 段 活 用 ︵ 実 質 的 に は 同 じ ︶ と 称 さ れ 、 已 然 形 が 仮 定 形 と 称 さ れ る よ う に な っ た も の の 、 活 用 の 種 類 お よ び 活 用 形 は 基 本 的 に 江 戸 時 代 と 同 様 で あ る 。
この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? "日本語" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年10月
か つ て の 日 本 語 に は 、 係 り 結 び と 称 さ れ る 文 法 規 則 が あ っ た 。 文 中 の 特 定 の 語 を ﹁ ぞ ﹂ ﹁ な む ﹂ ﹁ や ﹂ ﹁ か ﹂ ﹁ こ そ ﹂ な ど の 係 助 詞 で 受 け 、 か つ ま た 、 文 末 を 連 体 形 ︵ ﹁ ぞ ﹂ ﹁ な む ﹂ ﹁ や ﹂ ﹁ か ﹂ の 場 合 ︶ ま た は 已 然 形 ︵ ﹁ こ そ ﹂ の 場 合 ︶ で 結 ぶ も の で あ る ︵ 奈 良 時 代 に は 、 ﹁ こ そ ﹂ も 連 体 形 で 結 ん だ ︶ 。
係 り 結 び を ど う 用 い る か に よ っ て 、 文 全 体 の 意 味 に 明 確 な 違 い が 出 た 。 た と え ば 、 ﹁ 山 里 は 、 冬 、 寂 し さ 増 さ り け り ﹂ と い う 文 に お い て 、 ﹁ 冬 ﹂ と い う 語 を ﹁ ぞ ﹂ で 受 け る と 、 ﹁ 山 里 は 冬 ぞ 寂 し さ 増 さ り け る ﹂ ︵ ﹃ 古 今 集 ﹄ ︶ と い う 形 に な り 、 ﹁ 山 里 で 寂 し さ が 増 す の は 、 ほ か で も な い 冬 だ ﹂ と 告 知 す る 文 に な る 。 ま た 仮 に 、 ﹁ 山 里 ﹂ を ﹁ ぞ ﹂ で 受 け る と 、 ﹁ 山 里 ぞ 冬 は 寂 し さ 増 さ り け る ﹂ と い う 形 に な り 、 ﹁ 冬 に 寂 し さ が 増 す の は 、 ほ か で も な い 山 里 だ ﹂ と 告 知 す る 文 に な る 。
と こ ろ が 、 中 世 に は 、 ﹁ ぞ ﹂ ﹁ こ そ ﹂ な ど の 係 助 詞 は 次 第 に 形 式 化 の 度 合 い を 強 め 、 単 に 上 の 語 を 強 調 す る 意 味 し か 持 た な く な っ た 。 そ う な る と 、 係 助 詞 を 使 っ て も 、 文 末 を 連 体 形 ま た は 已 然 形 で 結 ば な い 例 も 見 ら れ る よ う に な る 。 ま た 、 逆 に 、 係 助 詞 を 使 わ な い の に 、 文 末 が 連 体 形 で 結 ば れ る 例 も 多 く な っ て く る 。 こ う し て 、 係 り 結 び は 次 第 に 崩 壊 し て い っ た 。
今 日 の 口 語 文 に は 、 規 則 的 な 係 り 結 び は 存 在 し な い 。 た だ し 、 ﹁ 貧 乏 で こ そ あ れ 、 彼 は 辛 抱 強 い ﹂ ﹁ 進 む 道 こ そ 違 え 、 考 え 方 は 同 じ ﹂ の よ う な 形 で 化 石 的 に 残 っ て い る 。
活 用 語 の う ち 、 四 段 活 用 以 外 の 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 お よ び 多 く の 助 動 詞 は 、 平 安 時 代 に は 、 終 止 形 と 連 体 形 と が 異 な る 形 態 を 採 っ て い た 。 た と え ば 、 動 詞 は ﹁ 対 面 す 。 ﹂ ︵ 終 止 形 ︶ と ﹁ 対 面 す る ︵ と き ︶ ﹂ ︵ 連 体 形 ︶ の よ う で あ っ た 。 と こ ろ が 、 係 り 結 び の 形 式 化 と と も に 、 上 に 係 助 詞 が な い の に 文 末 を 連 体 形 止 め ︵ ﹁ 対 面 す る 。 ﹂ ︶ に す る 例 が 多 く 見 ら れ る よ う に な っ た 。 た と え ば 、 ﹃ 源 氏 物 語 ﹄ に は 、
す こ し 立 ち 出 で つ つ 見 わ た し た ま へ ば 、 高 き 所 に て 、 こ こ か し こ 、 僧 坊 ど も あ ら は に 見 お ろ さ る る 。
な ど の 言 い 方 が あ る が 、 本 来 な ら ば ﹁ 見 お ろ さ る ﹂ の 形 で 終 止 す べ き も の で あ る 。
こ の よ う な 例 は 、 中 世 に は 一 般 化 し た 。 そ の 結 果 、 動 詞 ・ 形 容 詞 お よ び 助 動 詞 は 、 形 態 上 、 連 体 形 と 終 止 形 と の 区 別 が な く な っ た 。
形 容 動 詞 は 、 終 止 形 ・ 連 体 形 活 用 語 尾 が と も に ﹁ な る ﹂ に な り 、 さ ら に 語 形 変 化 を 起 こ し て ﹁ な ﹂ と な っ た 。 た と え ば 、 ﹁ 辛 労 な り ﹂ は 、 終 止 形 ・ 連 体 形 と も ﹁ 辛 労 な ﹂ と な っ た 。 も っ と も 、 終 止 形 に は 、 む し ろ ﹁ に て あ る ﹂ か ら 来 た ﹁ ぢ や ﹂ が 用 い ら れ る こ と が 普 通 で あ っ た 。 し た が っ て 、 終 止 形 は ﹁ 辛 労 ぢ や ﹂ 、 連 体 形 は ﹁ 辛 労 な ﹂ の よ う に な っ た 。 ﹁ ぢ や ﹂ は 主 と し て 上 方 で 用 い ら れ 、 東 国 で は ﹁ だ ﹂ が 用 い ら れ た 。 今 日 の 共 通 語 も 東 国 語 の 系 統 を 引 い て お り 、 終 止 形 語 尾 は ﹁ だ ﹂ 、 連 体 形 語 尾 は ﹁ な ﹂ と な っ て い る 。 こ の こ と は 、 用 言 の 活 用 に 連 体 形 ・ 終 止 形 の 両 形 を 区 別 す べ き 根 拠 の 一 つ と な っ て い る 。
文 語 の 終 止 形 が 化 石 的 に 残 っ て い る 場 合 も あ る 。 文 語 の 助 動 詞 ﹁ た り ﹂ ﹁ な り ﹂ の 終 止 形 は 、 今 日 で も 並 立 助 詞 と し て 残 り 、 ﹁ 行 っ た り 来 た り ﹂ ﹁ 大 な り 小 な り ﹂ と い っ た 形 で 使 わ れ て い る 。
今 日 、 ﹁ 漢 字 が 書 け る ﹂ ﹁ 酒 が 飲 め る ﹂ な ど と 用 い る 、 い わ ゆ る 可 能 動 詞 は 、 室 町 時 代 に は 発 生 し て い た 。 こ の 時 期 に は 、 ﹁ 読 む ﹂ か ら ﹁ 読 む る ﹂ ︵ = 読 む こ と が で き る ︶ が 、 ﹁ 持 つ ﹂ か ら ﹁ 持 つ る ﹂ ︵ = 持 つ こ と が で き る ︶ が 作 ら れ る な ど 、 四 段 活 用 の 動 詞 を 元 に し て 、 可 能 を 表 す 下 二 段 活 用 の 動 詞 が 作 ら れ 始 め た 。 こ れ ら の 動 詞 は 、 や が て 一 段 化 し て 、 ﹁ 読 め る ﹂ ﹁ 持 て る ﹂ の よ う な 語 形 で 用 い ら れ る よ う に な っ た [ 注 釈 35 ] 。 こ れ ら の 可 能 動 詞 は 、 江 戸 時 代 前 期 の 上 方 で も 用 い ら れ 、 後 期 の 江 戸 で は 普 通 に 使 わ れ る よ う に な っ た 。
従 来 の 日 本 語 に も 、 ﹁ ︵ 刀 を ︶ 抜 く 時 ﹂ に 対 し て ﹁ ︵ 刀 が 自 然 に ︶ 抜 く る 時 ︵ 抜 け る 時 ︶ ﹂ の よ う に 、 四 段 動 詞 の ﹁ 抜 く ﹂ と 下 二 段 動 詞 の ﹁ 抜 く ﹂ ︵ 抜 け る ︶ と が 対 応 す る 例 は 多 く 存 在 し た 。 こ の 場 合 、 後 者 は 、 ﹁ 自 然 に そ う な る ﹂ と い う 自 然 生 起 ︵ 自 発 ︶ を 表 し た 。 そ こ か ら 類 推 し た 結 果 、 ﹁ 文 字 を 読 む ﹂ に 対 し て ﹁ 文 字 が 読 む る ︵ 読 め る ︶ ﹂ な ど の 可 能 動 詞 が 出 来 上 が っ た も の と 考 え ら れ る 。
近 代 以 降 、 と り わ け 大 正 時 代 以 降 に は 、 こ の 語 法 を 四 段 動 詞 の み な ら ず 一 段 動 詞 に も 及 ぼ す 、 い わ ゆ る ﹁ ら 抜 き 言 葉 ﹂ が 広 が り 始 め た [ 注 釈 36 ] 。 ﹁ 見 ら れ る ﹂ を ﹁ 見 れ る ﹂ 、 ﹁ 食 べ ら れ る ﹂ を ﹁ 食 べ れ る ﹂ 、 ﹁ 来 ら れ る ﹂ を ﹁ 来 れ る ﹂ 、 ﹁ 居 ︵ い ︶ ら れ る ﹂ を ﹁ 居 ︵ い ︶ れ る ﹂ と い う 類 で あ る 。 こ の 語 法 は 、 地 方 に よ っ て は 早 く 一 般 化 し 、 第 二 次 世 界 大 戦 後 に は 全 国 的 に 顕 著 に な っ て い る 。
受 け 身 の 表 現 に お い て 、 人 物 以 外 が 主 語 に な る 例 は 、 近 代 以 前 に は 乏 し い 。 も と も と 、 日 本 語 の 受 け 身 表 現 は 、 自 分 の 意 志 で は ど う に も な ら な い ﹁ 自 然 生 起 ﹂ の 用 法 の 一 種 で あ っ た 。 し た が っ て 、 物 が 受 け 身 表 現 の 主 語 に な る こ と は ほ と ん ど な か っ た 。 ﹃ 枕 草 子 ﹄ の ﹁ に く き も の ﹂ に
す ず り に 髪 の 入 り て す ら れ た る 。 ︵ す ず り に 髪 が 入 っ て す ら れ て い る ︶
と あ る 例 な ど は 、 受 け 身 表 現 と 解 す る こ と も で き る が 、 む し ろ 自 然 の 状 態 を 観 察 し て 述 べ た も の と い う べ き も の で あ る 。 一 方 、 ﹁ こ の 橋 は 多 く の 人 々 に よ っ て 造 ら れ た ﹂ ﹁ 源 氏 物 語 は 紫 式 部 に よ っ て 書 か れ た ﹂ の よ う な 言 い 方 は 、 古 く は 存 在 し な か っ た と 見 ら れ る 。 こ れ ら の 受 け 身 は 、 状 態 を 表 す も の で は な く 、 事 物 が 人 か ら 働 き 掛 け を 受 け た こ と を 表 す も の で あ る 。
﹁ こ の 橋 は 多 く の 人 々 に よ っ て 造 ら れ た ﹂ 式 の 受 け 身 は 、 英 語 な ど の 欧 文 脈 を 取 り 入 れ る 中 で 広 く 用 い ら れ る よ う に な っ た と 見 ら れ る 。 明 治 時 代 に は
民 子 の 墓 の 周 囲 に は 野 菊 が 一 面 に 植 え ら れ た 。
のような欧文風の受け身が用いられている。
漢 字 ︵ 中 国 語 の 語 彙 ︶ が 日 本 語 の 中 に 入 り 始 め た の は か な り 古 く 、 文 献 の 時 代 に さ か の ぼ る と 考 え ら れ る 。 今 日 和 語 と 扱 わ れ る ﹁ ウ メ ︵ 梅 ︶ ﹂ ﹁ ウ マ ︵ 馬 ︶ ﹂ な ど も 、 元 々 は 漢 語 か ら の 借 用 語 で あ っ た 可 能 性 も あ る が 、 上 古 漢 字 の 場 合 、 馬 と 梅 の 発 音 は 違 う 。 異 民 族 が 中 国 を よ く 支 配 し て か ら 漢 語 の 発 音 は 変 わ っ て い た 。
中 国 の 文 物 ・ 思 想 の 流 入 や 仏 教 の 普 及 な ど に つ れ て 、 漢 語 は 徐 々 に 一 般 の 日 本 語 に 取 り 入 れ ら れ て い っ た 。 鎌 倉 時 代 最 末 期 の ﹃ 徒 然 草 ﹄ で は 、 漢 語 及 び 混 種 語 ︵ 漢 語 と 和 語 の 混 交 ︶ は 、 異 な り 語 数 ︵ 文 中 の 同 一 語 を 一 度 し か カ ウ ン ト し な い ︶ で 全 体 の 3 1 % を 占 め る に 至 っ て い る 。 た だ し 、 延 べ 語 数 ︵ 同 一 語 を 何 度 で も カ ウ ン ト す る ︶ で は 1 3 % に 過 ぎ ず 、 語 彙 の 大 多 数 は 和 語 が 占 め る [ 1 5 2 ] 。 幕 末 の 和 英 辞 典 ﹃ 和 英 語 林 集 成 ﹄ の 見 出 し 語 で も 、 漢 語 は な お 2 5 % ほ ど に 止 ま っ て い る 。
漢 字 が よ く 使 わ れ る よ う に な っ た の は 幕 末 か ら 明 治 時 代 に か け て で あ る 。 ﹁ 電 信 ﹂ ﹁ 鉄 道 ﹂ ﹁ 政 党 ﹂ ﹁ 主 義 ﹂ ﹁ 哲 学 ﹂ そ の 他 、 西 洋 の 文 物 を 漢 語 に よ り 翻 訳 し た ︵ 新 漢 語 。 古 典 中 国 語 に な い 語 を 特 に 和 製 漢 語 と い う ︶ 。 幕 末 の ﹃ 都 鄙 新 聞 ﹄ の 記 事 に よ れ ば 、 京 都 祇 園 の 芸 者 も 漢 語 を 好 み 、 ﹁ 霖 雨 ニ 盆 池 ノ 金 魚 ガ 脱 走 シ 、 火 鉢 ガ 因 循 シ テ ヰ ル ﹂ ︵ 長 雨 で 池 が あ ふ れ て 金 魚 が ど こ か へ 行 っ た 、 火 鉢 の 火 が な か な か つ か な い ︶ な ど と 言 っ て い た と い う [ 1 5 4 ] 。
漢 字 は 今 も 多 く 使 わ れ て い る 。 雑 誌 調 査 で は 、 延 べ 語 数 ・ 異 な り 語 数 と も に 和 語 を 上 回 り 、 全 体 の 半 数 近 く に 及 ぶ ま で に な っ て い る ︵ ﹁ 語 種 ﹂ 参 照 ︶ 。
漢 字 を 除 き 、 他 言 語 の 語 彙 を 借 用 す る こ と は 、 古 代 に は そ れ ほ ど 多 く な か っ た 。 こ の う ち 、 梵 語 の 語 彙 は 、 多 く 漢 語 に 取 り 入 れ ら れ た 後 に 、 仏 教 と 共 に 日 本 に 伝 え ら れ た 。 ﹁ 娑 婆 ﹂ ﹁ 檀 那 ﹂ ﹁ 曼 荼 羅 ﹂ な ど が そ の 例 で あ る 。 ま た 、 今 日 で は 和 語 と 扱 わ れ る ﹁ ほ と け ︵ 仏 ︶ ﹂ ﹁ か わ ら ︵ 瓦 ︶ ﹂ な ど も 梵 語 由 来 で あ る と さ れ る 。
西 洋 語 が 輸 入 さ れ 始 め た の は 、 中 世 に キ リ シ タ ン 宣 教 師 が 来 日 し た 時 期 以 降 で あ る 。 室 町 時 代 に は 、 ポ ル ト ガ ル 語 か ら ﹁ カ ス テ ラ ﹂ ﹁ コ ン ペ イ ト ウ ﹂ ﹁ サ ラ サ ﹂ ﹁ ジ ュ バ ン ﹂ ﹁ タ バ コ ﹂ ﹁ バ テ レ ン ﹂ ﹁ ビ ロ ー ド ﹂ な ど の 語 が 取 り 入 れ ら れ た 。 ﹁ メ リ ヤ ス ﹂ な ど 一 部 ス ペ イ ン 語 も 用 い ら れ た 。 江 戸 時 代 に も 、 ﹁ カ ッ パ ︵ 合 羽 ︶ ﹂ ﹁ カ ル タ ﹂ ﹁ チ ョ ッ キ ﹂ ﹁ パ ン ﹂ ﹁ ボ タ ン ﹂ な ど の ポ ル ト ガ ル 語 、 ﹁ エ ニ シ ダ ﹂ な ど の ス ペ イ ン 語 が 用 い ら れ る よ う に な っ た 。
ま た 、 江 戸 時 代 に は 、 蘭 学 な ど の 興 隆 と と も に 、 ﹁ ア ル コ ー ル ﹂ ﹁ エ レ キ ﹂ ﹁ ガ ラ ス ﹂ ﹁ コ ー ヒ ー ﹂ ﹁ ソ ー ダ ﹂ ﹁ ド ン タ ク ﹂ な ど の オ ラ ン ダ 語 が 伝 え ら れ た [ 1 5 7 ] 。
幕 末 か ら 明 治 時 代 以 後 に は 、 英 語 を 中 心 と す る 外 来 語 が 急 増 し た 。 ﹁ ス テ ン シ ョ ン ︵ 駅 ︶ ﹂ ﹁ テ レ ガ ラ フ ︵ 電 信 ︶ ﹂ な ど 、 今 日 で は 普 通 使 わ れ な い 語 で 、 当 時 一 般 に 使 わ れ て い た も の も あ っ た 。 坪 内 逍 遥 ﹃ 当 世 書 生 気 質 ﹄ ( 1 8 8 5 ) に は 書 生 の せ り ふ の 中 に ﹁ 我 輩 の 時 計 ︵ ウ オ ツ チ ︶ で は ま だ 十 分 ︵ テ ン ミ ニ ツ ︶ 位 あ る か ら 、 急 い て 行 き よ つ た ら 、 大 丈 夫 ぢ ゃ ら う ﹂ ﹁ 想 ふ に 又 貸 と は 遁 辞 ︵ プ レ テ キ ス ト ︶ で 、 七 ︵ セ ブ ン ︶ ︹ = 質 屋 ︺ へ 典 ︵ ポ ウ ン ︶ し た 歟 ︵ か ︶ 、 売 ︵ セ ル ︶ し た に 相 違 な い ﹂ な ど と い う 英 語 が 多 く 出 て く る 。 こ の よ う な 語 の う ち 、 日 本 語 と し て 定 着 し た 語 も 多 い 。
第 二 次 世 界 大 戦 が 激 し く な る に つ れ て 、 外 来 語 を 禁 止 ま た は 自 粛 す る 風 潮 も 起 こ っ た が 、 戦 後 は ア メ リ カ 発 の 外 来 語 が 爆 発 的 に 多 く な っ た 。 現 在 で は 、 報 道 ・ 交 通 機 関 ・ 通 信 技 術 の 発 達 に よ り 、 新 し い 外 来 語 が 瞬 時 に 広 ま る 状 況 が 生 ま れ て い る 。 雑 誌 調 査 で は 、 異 な り 語 数 で 外 来 語 が 3 0 % を 超 え る と い う 結 果 が 出 て お り 、 現 代 語 彙 の 中 で 欠 く こ と の で き な い 存 在 と な っ て い る ︵ ﹁ 語 種 ﹂ 参 照 ︶ 。
源氏物語 (12世紀)
漢 語 が 日 本 語 に 取 り 入 れ ら れ た 結 果 、 名 詞 ・ サ 変 動 詞 ・ 形 容 動 詞 の 語 彙 が 特 に 増 大 す る こ と に な っ た 。 漢 語 は 活 用 し な い 語 で あ り 、 本 質 的 に は 体 言 ︵ 名 詞 ︶ と し て 取 り 入 れ ら れ た が [ 1 5 8 ] 、 ﹁ す ﹂ を つ け れ ば サ 変 動 詞 ︵ 例 、 祈 念 す ︶ 、 ﹁ な り ﹂ を つ け れ ば 形 容 動 詞 ︵ 例 、 神 妙 な り ︶ と し て 用 い る こ と が で き た 。
漢 語 に よ り 、 厳 密 な 概 念 を 簡 潔 に 表 現 す る こ と が 可 能 に な っ た 。 一 般 に 、 和 語 は 一 語 が 広 い 意 味 で 使 わ れ る [ 1 5 9 ] 。 た と え ば 、 ﹁ と る ﹂ と い う 動 詞 は 、 ﹁ 資 格 を と る ﹂ ﹁ 栄 養 を と る ﹂ ﹁ 血 液 を と る ﹂ ﹁ 新 人 を と る ﹂ ﹁ 映 画 を と る ﹂ の よ う に 用 い ら れ る 。 と こ ろ が 、 漢 語 を 用 い て 、 ﹁ 取 得 す る ︵ 取 得 す ︶ ﹂ ﹁ 摂 取 す る ﹂ ﹁ 採 取 す る ﹂ ﹁ 採 用 す る ﹂ ﹁ 撮 影 す る ﹂ な ど と 、 さ ま ざ ま な サ 変 動 詞 で 区 別 し て 表 現 す る こ と が で き る よ う に な っ た 。 ま た 、 日 本 語 の ﹁ き よ い ︵ き よ し ︶ ﹂ と い う 形 容 詞 は 意 味 が 広 い が 、 漢 語 を 用 い て 、 ﹁ 清 潔 だ ︵ 清 潔 な り ︶ ﹂ ﹁ 清 浄 だ ﹂ ﹁ 清 澄 だ ﹂ ﹁ 清 冽 だ ﹂ ﹁ 清 純 だ ﹂ な ど の 形 容 動 詞 に よ っ て 厳 密 に 表 現 す る こ と が で き る よ う に な っ た 。
外 来 語 は 、 漢 語 ほ ど 高 い 造 語 力 を 持 た な い も の の 、 漢 語 と 同 様 に 、 特 に 名 詞 ・ サ 変 動 詞 ・ 形 容 動 詞 の 部 分 で 日 本 語 の 語 彙 を 豊 富 に し た 。 ﹁ イ ン キ ﹂ ﹁ バ ケ ツ ﹂ ﹁ テ ー ブ ル ﹂ な ど 名 詞 と し て 用 い ら れ る ほ か 、 ﹁ す る ﹂ を 付 け て ﹁ ス ケ ッ チ す る ﹂ ﹁ サ ー ビ ス す る ﹂ な ど の サ 変 動 詞 と し て 、 ま た 、 ﹁ だ ﹂ を つ け て ﹁ ロ マ ン チ ッ ク だ ﹂ ﹁ セ ン チ メ ン タ ル だ ﹂ な ど の 形 容 動 詞 と し て 用 い ら れ る よ う に な っ た 。
漢 語 ・ 外 来 語 の 増 加 に よ っ て 、 形 容 詞 と 形 容 動 詞 の 勢 力 が 逆 転 し た 。 元 来 、 和 語 に は 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 と も に 少 な か っ た が 、 数 の 上 で は 、 形 容 詞 が 形 容 表 現 の 中 心 で あ り 、 形 容 動 詞 が そ れ を 補 う 形 で あ っ た 。 ﹃ 万 葉 集 ﹄ で は 名 詞 5 9 . 7 % 、 動 詞 3 1 . 5 % 、 形 容 詞 3 . 3 % 、 形 容 動 詞 0 . 5 % で あ り 、 ﹃ 源 氏 物 語 ﹄ で も 名 詞 4 2 . 5 % 、 動 詞 4 4 . 6 % 、 形 容 詞 5 . 3 % 、 形 容 動 詞 5 . 1 % で あ っ た ︵ い ず れ も 異 な り 語 数 ︶ [ 1 5 2 ] 。 と こ ろ が 、 漢 語 ・ 外 来 語 を 語 幹 と し た 形 容 動 詞 が 漸 増 し た た め 、 現 代 語 で は 形 容 動 詞 が 形 容 詞 を 上 回 る に 至 っ て い る ︵ ﹁ 品 詞 ご と の 語 彙 量 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 た だ し 、 一 方 で 漢 語 ・ 外 来 語 に 由 来 す る 名 詞 ・ サ 変 動 詞 な ど も 増 え て い る た め 、 語 彙 全 体 か ら 見 れ ば な お 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 の 割 合 は 少 な い 。
形 容 詞 の 造 語 力 は 今 日 で は ほ と ん ど 失 わ れ て お り 、 近 代 以 降 の み 確 例 の あ る 新 し い 形 容 詞 は ﹁ 甘 酸 っ ぱ い ﹂ ﹁ 黄 色 い ﹂ ﹁ 四 角 い ﹂ ﹁ 粘 っ こ い ﹂ な ど わ ず か に す ぎ な い [ 注 釈 37 ] 。 一 方 、 形 容 動 詞 は 今 日 に 至 る ま で 高 い 造 語 力 を 保 っ て い る 。 特 に 、 ﹁ 科 学 的 だ ﹂ ﹁ 人 間 的 だ ﹂ な ど 接 尾 語 ﹁ 的 ﹂ を 付 け た 語 の 大 多 数 や 、 ﹁ エ レ ガ ン ト だ ﹂ ﹁ ク リ ー ン だ ﹂ な ど 外 来 語 に 由 来 す る も の は 近 代 以 降 の 新 語 で あ る 。 し か も 、 新 し い 形 容 動 詞 の 多 く は 漢 語 ・ 外 来 語 を 語 幹 と す る も の で あ る 。 現 代 雑 誌 の 調 査 に よ れ ば 、 形 容 動 詞 で 語 種 の は っ き り し て い る も の の う ち 、 和 語 は 2 割 ほ ど で あ り 、 漢 語 は 3 割 強 、 外 来 語 は 4 割 強 と い う 状 況 で あ る 。
元 来 、 日 本 に 文 字 と 呼 べ る も の は な く 、 言 葉 を 表 記 す る た め に は 中 国 渡 来 の 漢 字 を 用 い た ︵ い わ ゆ る 神 代 文 字 は 後 世 の 偽 作 と さ れ て い る [ 1 6 1 ] ︶ 。 漢 字 の 記 さ れ た 遺 物 の 例 と し て は 、 1 世 紀 の も の と さ れ る 福 岡 市 出 土 の ﹁ 漢 委 奴 国 王 印 ﹂ な ど も あ る が 、 本 格 的 に 使 用 さ れ た の は よ り 後 年 と み ら れ る 。 ﹃ 古 事 記 ﹄ に よ れ ば 、 応 神 天 皇 の 時 代 に 百 済 の 学 者 王 仁 が ﹁ 論 語 十 巻 、 千 字 文 一 巻 ﹂ を 携 え て 来 日 し た と あ る 。 稲 荷 山 古 墳 出 土 の 鉄 剣 銘 ︵ 5 世 紀 ︶ に は 、 雄 略 天 皇 と 目 さ れ る 人 名 を 含 む 漢 字 が 刻 ま れ て い る 。 ﹁ 隅 田 八 幡 神 社 鏡 銘 ﹂ ︵ 6 世 紀 ︶ は 純 漢 文 で 記 さ れ て い る 。 こ の よ う な 史 料 か ら 、 大 和 政 権 の 勢 力 伸 長 と と も に 漢 字 使 用 域 も 拡 大 さ れ た こ と が 推 測 さ れ る 。 6 世 紀 〜 7 世 紀 に な る と 儒 教 、 仏 教 、 道 教 な ど に つ い て 漢 文 を 読 む 必 要 が 出 て き た た め 識 字 層 が 広 が っ た [ 1 6 2 ] 。
漢 字 で 和 歌 な ど の 大 和 言 葉 を 記 す 際 、 ﹁ 波 都 波 流 能 ︵ は つ は る の ︶ ﹂ の よ う に 日 本 語 の 1 音 1 音 を 漢 字 の 音 ︵ ま た は 訓 ︶ を 借 り て 写 す こ と が あ っ た 。 こ の 表 記 方 式 を 用 い た 資 料 の 代 表 が ﹃ 万 葉 集 ﹄ ︵ 8 世 紀 ︶ で あ る た め 、 こ の 表 記 の こ と を ﹁ 万 葉 仮 名 ﹂ と い う ︵ す で に 7 世 紀 中 頃 の 木 簡 に 例 が 見 ら れ る [ 注 釈 38 ] ︶ 。
9 世 紀 に は 万 葉 仮 名 の 字 体 を よ り 崩 し た ﹁ 草 仮 名 ﹂ が 生 ま れ ︵ ﹃ 讃 岐 国 戸 籍 帳 ﹄ の ﹁ 藤 原 有 年 申 文 ﹂ な ど ︶ 、 さ ら に 、 草 仮 名 を よ り 崩 し た 平 仮 名 の 誕 生 を み る に 至 っ た 。 こ れ に よ っ て 、 初 め て 日 本 語 を 自 由 に 記 す こ と が 可 能 に な っ た 。 平 仮 名 を 自 在 に 操 っ た 王 朝 文 学 は 、 10 世 紀 初 頭 の ﹃ 古 今 和 歌 集 ﹄ な ど に 始 ま り 、 11 世 紀 の ﹃ 源 氏 物 語 ﹄ な ど の 物 語 作 品 群 で 頂 点 を 迎 え た 。
僧 侶 や 学 者 ら が 漢 文 を 訓 読 す る 際 に は 、 漢 字 の 隅 に 点 を 打 ち 、 そ の 位 置 に よ っ て ﹁ て ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ は ﹂ な ど の 助 詞 そ の 他 を 表 す こ と が あ っ た ︵ ヲ コ ト 点 ︶ 。 し か し 、 次 第 に 万 葉 仮 名 を 添 え て 助 詞 な ど を 示 す こ と が 一 般 化 し た 。 や が て 、 そ れ ら は 、 字 画 の 省 か れ た 簡 略 な 片 仮 名 に な っ た 。
平 仮 名 も 、 片 仮 名 も 、 発 生 当 初 か ら 、 1 つ の 音 価 に 対 し て 複 数 の 文 字 が 使 わ れ て い た 。 た と え ば 、 / h a / ︵ 当 時 の 発 音 は [ ɸ a ] ︶ に 当 た る 平 仮 名 と し て は 、 ﹁ 波 ﹂ ﹁ 者 ﹂ ﹁ 八 ﹂ な ど を 字 源 と す る も の が あ っ た 。 1 9 0 0 年 ︵ 明 治 33 年 ︶ に ﹁ 小 学 校 令 施 行 規 則 ﹂ が 出 さ れ 、 小 学 校 で 教 え る 仮 名 は 1 字 1 音 に 整 理 さ れ た 。 こ れ 以 降 使 わ れ な く な っ た 仮 名 を 、 今 日 で は 変 体 仮 名 と 呼 ん で い る 。 変 体 仮 名 は 、 現 在 で も 料 理 屋 の 名 な ど に 使 わ れ る こ と が あ る 。
平 安 時 代 ま で は 、 発 音 と 仮 名 は ほ ぼ 一 致 し て い た 。 そ の 後 、 発 音 の 変 化 に 伴 っ て 、 発 音 と 仮 名 と が 1 対 1 の 対 応 を し な く な っ た 。 た と え ば 、 ﹁ は な ︵ 花 ︶ ﹂ の ﹁ は ﹂ と ﹁ か は ︵ 川 ︶ ﹂ の ﹁ は ﹂ の 発 音 は 、 平 安 時 代 初 期 に は い ず れ も ﹁ フ ァ ﹂ ( [ ɸ a ] ) で あ っ た と み ら れ る が 、 平 安 時 代 に 起 こ っ た ハ 行 転 呼 に よ り 、 ﹁ か は ︵ 川 ︶ ﹂ な ど 語 中 語 尾 の ﹁ は ﹂ は ﹁ ワ ﹂ と 発 音 す る よ う に な っ た 。 と こ ろ が 、 ﹁ ワ ﹂ と 読 む 文 字 に は 別 に ﹁ わ ﹂ も あ る た め 、 ﹁ カ ワ ﹂ と い う 発 音 を 表 記 す る と き 、 ﹁ か わ ﹂ ﹁ か は ﹂ の い ず れ に す べ き か 、 判 断 の 基 準 が 不 明 に な っ て し ま っ た 。 こ こ に 、 仮 名 を ど う 使 う か と い う 仮 名 遣 い の 問 題 が 発 生 し た 。
そ の 時 々 の 知 識 人 は 、 仮 名 遣 い に つ い て の 規 範 を 示 す こ と も あ っ た が ︵ 藤 原 定 家 ﹃ 下 官 集 ﹄ な ど ︶ 、 必 ず し も 古 い 仮 名 遣 い に 忠 実 な も の ば か り で は な か っ た ︵ ﹁ 日 本 語 研 究 史 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 ま た 、 従 う 者 も 、 歌 人 、 国 学 者 な ど 、 あ る 種 の グ ル ー プ に 限 ら れ て い た 。 万 人 に 用 い ら れ る 仮 名 遣 い 規 範 は 、 明 治 に 学 校 教 育 が 始 ま る ま で 待 た な け れ ば な ら な か っ た 。
漢 字 の 字 数 ・ 字 体 お よ び 仮 名 遣 い に つ い て は 、 近 代 以 降 、 た び た び 改 定 が 議 論 さ れ 、 ま た 実 施 に 移 さ れ て き た [ 1 0 5 ] 。
仮 名 遣 い に つ い て は 、 早 く 小 学 校 令 施 行 規 則 ︵ 1 9 0 0 年 ︶ に お い て 、 ﹁ に ん ぎ や う ︵ 人 形 ︶ ﹂ を ﹁ に ん ぎ ょ ー ﹂ と す る な ど 、 漢 字 音 を 発 音 通 り に す る 、 い わ ゆ る ﹁ 棒 引 き 仮 名 遣 い ﹂ が 採 用 さ れ た こ と が あ っ た 。 1 9 0 4 年 か ら 使 用 の ﹃ 尋 常 小 学 読 本 ﹄ ︵ 第 1 期 ︶ は こ の 棒 引 き 仮 名 遣 い に 従 っ た 。 し か し 、 こ れ は 評 判 が 悪 く 、 規 則 の 改 正 と と も に 、 次 期 1 9 1 0 年 の 教 科 書 か ら 元 の 仮 名 遣 い に 戻 っ た 。
第 二 次 世 界 大 戦 後 の 1 9 4 6 年 に は 、 ﹁ 当 用 漢 字 表 ﹂ ﹁ 現 代 か な づ か い ﹂ が 内 閣 告 示 さ れ た 。 こ れ に 伴 い 、 一 部 の 漢 字 の 字 体 に 略 字 体 が 採 用 さ れ 、 そ れ ま で の 歴 史 的 仮 名 遣 い に よ る 学 校 教 育 は 廃 止 さ れ た 。
1 9 4 6 年 お よ び 1 9 5 0 年 の 米 教 育 使 節 団 報 告 書 で は 、 国 字 の ロ ー マ 字 化 に つ い て 勧 告 お よ び 示 唆 が 行 わ れ [ 注 釈 39 ] 、 国 語 審 議 会 で も 議 論 さ れ た が 、 実 現 し な か っ た 。 1 9 4 8 年 に は 、 G H Q の 民 間 情 報 教 育 局 ( C I E ) の 指 示 に よ る 読 み 書 き 能 力 調 査 が 行 わ れ た 。 漢 字 が 日 本 人 の 識 字 率 を 抑 え て い る と の 考 え 方 に 基 づ く 調 査 で あ っ た が 、 そ の 結 果 は 、 調 査 者 の 予 想 に 反 し て 日 本 人 の 識 字 率 は 高 水 準 で あ っ た こ と が 判 明 し た 。
1 9 8 1 年 に は 、 当 用 漢 字 表 ・ 現 代 か な づ か い の 制 限 色 を 薄 め た ﹁ 常 用 漢 字 表 ﹂ お よ び 改 訂 ﹁ 現 代 仮 名 遣 い ﹂ が 内 閣 告 示 さ れ た 。 ま た 、 送 り 仮 名 に 関 し て は 、 数 次 に わ た る 議 論 を 経 て 、 1 9 7 3 年 に ﹁ 送 り 仮 名 の 付 け 方 ﹂ が 内 閣 告 示 さ れ 、 今 日 に 至 っ て い る 。 戦 後 の 国 語 政 策 は 、 必 ず し も 定 見 に 支 え ら れ て い た と は い え ず 、 今 に 至 る ま で 議 論 が 続 い て い る 。
平 安 時 代 ま で は 、 朝 廷 で 用 い る 公 の 書 き 言 葉 は 漢 文 で あ っ た 。 こ れ は ベ ト ナ ム ・ 朝 鮮 半 島 な ど と 同 様 で あ る 。 当 初 漢 文 は 中 国 語 音 で 読 ま れ た と み ら れ る が 、 日 本 語 と 中 国 語 の 音 韻 体 系 は 相 違 が 大 き い た め 、 こ の 方 法 は や が て 廃 れ 、 日 本 語 の 文 法 ・ 語 彙 を 当 て は め て 訓 読 さ れ る よ う に な っ た 。 い わ ば 、 漢 文 を 日 本 語 に 直 訳 し な が ら 読 む も の で あ っ た 。
漢 文 訓 読 の 習 慣 に 伴 い 、 漢 文 に 日 本 語 特 有 の ﹁ 賜 ﹂ ︵ … た ま ふ ︶ や ﹁ 坐 ﹂ ︵ … ま す ︶ の よ う な 語 句 を 混 ぜ た り 、 一 部 を 日 本 語 の 語 順 で 記 し た り し た ﹁ 和 化 漢 文 ﹂ と い う べ き も の が 生 じ た ︵ 6 世 紀 の 法 隆 寺 薬 師 仏 光 背 銘 な ど に 見 ら れ る ︶ 。 さ ら に は ﹁ 王 等 臣 等 乃 中 尓 ﹂ ︵ ﹃ 続 日 本 紀 ﹄ ︶ の よ う に 、 ﹁ 乃 ︵ の ︶ ﹂ ﹁ 尓 ︵ に ︶ ﹂ と い っ た 助 詞 な ど を 小 書 き に し て 添 え る 文 体 が 現 れ た 。 こ の 文 体 は 祝 詞 ︵ の り と ︶ ・ 宣 命 ︵ せ ん み ょ う ︶ な ど に 見 ら れ る た め 、 ﹁ 宣 命 書 き ﹂ と 呼 ば れ る 。
漢 文 の 読 み 添 え に は 片 仮 名 が 用 い ら れ る よ う に な り 、 や が て こ れ が 本 文 中 に 進 出 し て 、 漢 文 訓 読 体 を 元 に し た ﹁ 漢 字 片 仮 名 交 じ り 文 ﹂ を 形 成 し た 。 最 古 の 例 は ﹃ 東 大 寺 諷 誦 文 稿 ﹄ ︵ 9 世 紀 ︶ と さ れ る 。 漢 字 片 仮 名 交 じ り 文 で は 、 漢 語 が 多 用 さ れ る ば か り で な く 、 言 い 回 し も ﹁ 甚 ︵ は な は ︶ ダ 広 ク シ テ ﹂ ﹁ 何 ︵ な ん ︶ ゾ 言 ハ ザ ル ﹂ の よ う に 、 漢 文 訓 読 に 用 い ら れ る も の が 多 い こ と が 特 徴 で あ る 。
一 方 、 平 安 時 代 の 宮 廷 文 学 の 文 体 ︵ 和 文 ︶ は 、 基 本 的 に 和 語 を 用 い る も の で あ っ て 、 漢 語 は 少 な い 。 ま た 、 漢 文 訓 読 に 使 う 言 い 回 し も あ ま り な い 。 た と え ば 、 漢 文 訓 読 ふ う の ﹁ 甚 ダ 広 ク シ テ ﹂ ﹁ 何 ゾ 言 ハ ザ ル ﹂ は 、 和 文 で は ﹁ い と 広 う ﹂ ﹁ な ど か の た ま は ぬ ﹂ と な る 。 和 文 は 、 表 記 法 か ら 見 れ ば 、 平 仮 名 に と こ ろ ど こ ろ 漢 字 の 交 じ る ﹁ 平 仮 名 漢 字 交 じ り 文 ﹂ で あ る 。 ﹁ 春 は あ け ぼ の 。 や う や う し ろ く 成 行 山 ぎ は す こ し あ か り て … … ﹂ で 始 ま る ﹃ 枕 草 子 ﹄ の 文 体 は 典 型 例 の 一 つ で あ る 。
両 者 の 文 体 は 、 や が て 合 わ さ り 、 ﹃ 平 家 物 語 ﹄ に 見 ら れ る よ う な 和 漢 混 淆 文 が 完 成 し た 。
強 呉 ︵ き ゃ う ご ︶ 忽 ︵ た ち ま ち ︶ に ほ ろ び て 、 姑 蘇 台 ︵ こ そ た い ︶ の 露 荊 棘 ︵ け い き ょ く ︶ に う つ り 、 暴 秦 ︵ ぼ う し ん ︶ す で に 衰 へ て 、 咸 陽 宮 ︵ か ん や う き う ︶ の 煙 埤 堄 ︵ へ い け い ︶ を 隠 し け ん も 、 か く や と お ぼ え て 哀 れ な り 。
こ こ で は 、 ﹁ 強 呉 ﹂ ﹁ 荊 棘 ﹂ と い っ た 漢 語 、 ﹁ す で に ﹂ と い っ た 漢 文 訓 読 の 言 い 回 し が あ る 一 方 、 ﹁ か く や と お ぼ え て 哀 れ な り ﹂ と い っ た 和 文 の 語 彙 ・ 言 い 回 し も 使 わ れ て い る 。
今 日 、 最 も 普 通 に 用 い ら れ る 文 章 は 、 和 語 と 漢 語 を 適 度 に 交 え た 一 種 の 和 漢 混 淆 文 で あ る 。 ﹁ 先 日 、 友 人 と 同 道 し て 郊 外 を 散 策 し た ﹂ と い う よ う な 漢 語 の 多 い 文 章 と 、 ﹁ こ の 間 、 友 だ ち と 連 れ だ っ て 町 は ず れ を ぶ ら ぶ ら 歩 い た ﹂ と い う よ う な 和 語 の 多 い 文 章 と を 、 適 宜 混 ぜ 合 わ せ 、 あ る い は 使 い 分 け な が ら 文 章 を 綴 っ て い る 。
話 し 言 葉 は 、 時 代 と 共 に き わ め て 大 き な 変 化 を 遂 げ る が 、 そ れ に 比 べ て 、 書 き 言 葉 は 変 化 の 度 合 い が 少 な い 。 そ の た め 、 何 百 年 と い う 間 に は 、 話 し 言 葉 と 書 き 言 葉 の 差 が 生 ま れ る 。
日 本 語 の 書 き 言 葉 が ひ と ま ず 成 熟 し た の は 平 安 時 代 中 期 で あ り 、 そ の 頃 は 書 き 言 葉 ・ 話 し 言 葉 の 差 は 大 き く な か っ た と 考 え ら れ る 。 し か し な が ら 、 中 世 の キ リ シ タ ン 資 料 の う ち 、 語 り 口 調 で 書 か れ て い る も の を 見 る と 、 書 き 言 葉 と 話 し 言 葉 と に は す で に 大 き な 開 き が 生 ま れ て い た こ と が 窺 え る 。 江 戸 時 代 の 洒 落 本 ・ 滑 稽 本 の 類 で は 、 会 話 部 分 は 当 時 の 話 し 言 葉 が 強 く 反 映 さ れ 、 地 の 部 分 の 書 き 言 葉 で は 古 来 の 文 法 に 従 お う と し た 文 体 が 用 い ら れ て い る 。 両 者 の 違 い は 明 ら か で あ る 。
明 治 時 代 の 書 き 言 葉 は 、 依 然 と し て 古 典 文 法 に 従 お う と し て い た が 、 単 語 に は 日 常 語 を 用 い た 文 章 も 現 れ た 。 こ う し た 書 き 言 葉 は 、 一 般 に ﹁ 普 通 文 ﹂ と 称 さ れ た 。 普 通 文 は 、 以 下 の よ う に 小 学 校 の 読 本 で も 用 い ら れ た 。
ワ ガ 国 ノ 人 ハ 、 手 ヲ 用 フ ル 工 業 ニ 、 タ ク ミ ナ レ バ 、 ソ ノ 製 作 品 ノ 精 巧 ナ ル コ ト 、 他 ニ 、 ク ラ ブ ベ キ 国 少 シ 。 —『国定読本』第1期 1904
普 通 文 は 、 厳 密 に は 、 古 典 文 法 そ の ま ま で は な く 、 新 し い 言 い 方 も 多 く 混 じ っ て い た 。 た と え ば 、 ﹁ 解 釈 せ ら る ﹂ と い う べ き と こ ろ を ﹁ 解 釈 さ る ﹂ 、 ﹁ 就 学 せ し む る 義 務 ﹂ を ﹁ 就 学 せ し む る の 義 務 ﹂ な ど と 言 う こ と が あ っ た 。 そ こ で 、 文 部 省 は 新 し い 語 法 の う ち 一 部 慣 用 の 久 し い も の を 認 め 、 ﹁ 文 法 上 許 容 ス ベ キ 事 項 ﹂ ︵ 1 9 0 5 年 ・ 明 治 38 年 ︶ 16 条 を 告 示 し た 。
一 方 、 明 治 20 年 代 頃 か ら 、 二 葉 亭 四 迷 ・ 山 田 美 妙 ら 文 学 者 を 中 心 に 、 書 き 言 葉 を 話 し 言 葉 に 近 づ け よ う と す る 努 力 が 重 ね ら れ た ︵ 言 文 一 致 運 動 ︶ 。 二 葉 亭 は ﹁ だ ﹂ 体 、 美 妙 は ﹁ で す ﹂ 体 、 尾 崎 紅 葉 は ﹁ で あ る ﹂ 体 と い わ れ る 文 章 を そ れ ぞ れ 試 み た 。 こ の よ う な 試 み が 広 ま る 中 で 、 新 聞 ・ 雑 誌 の 記 事 な ど も 話 し 言 葉 に 近 い 文 体 が 多 く な っ て い く 。 古 来 の 伝 統 的 文 法 に 従 っ た 文 章 を 文 語 文 、 話 し 言 葉 を 反 映 し た 文 章 を 口 語 文 と い う 。 第 二 次 世 界 大 戦 後 は 、 法 律 文 な ど の 公 文 書 も も っ ぱ ら 口 語 文 で 書 か れ る よ う に な り 、 文 語 文 は 日 常 生 活 の 場 か ら 遠 の い た 。
こ の 節 に は 複 数 の 問 題 が あ り ま す 。 改 善 や ノ ー ト ペ ー ジ で の 議 論 に ご 協 力 く だ さ い 。
● 出 典 が ま っ た く 示 さ れ て い な い か 不 十 分 で す 。 内 容 に 関 す る 文 献 や 情 報 源 が 必 要 で す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶ ● 独 自 研 究 が 含 ま れ て い る お そ れ が あ り ま す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶
日 本 語 は 、 文 献 時 代 に 入 っ た と き に は す で に 方 言 差 が あ っ た 。 ﹃ 万 葉 集 ﹄ の 巻 14 ﹁ 東 歌 ﹂ や 巻 20 ﹁ 防 人 歌 ﹂ に は 当 時 の 東 国 方 言 に よ る 歌 が 記 録 さ れ て い る [ 注 釈 40 ] 。 8 2 0 年 頃 成 立 の ﹃ 東 大 寺 諷 誦 文 稿 ﹄ に は ﹁ 此 当 国 方 言 、 毛 人 方 言 、 飛 騨 方 言 、 東 国 方 言 ﹂ と い う 記 述 が 見 え 、 こ れ が 国 内 文 献 で 用 い ら れ た ﹁ 方 言 ﹂ と い う 語 の 最 古 例 と さ れ る 。 平 安 初 期 の 中 央 の 人 々 の 方 言 観 が 窺 え る 貴 重 な 記 録 で あ る 。
平 安 時 代 か ら 鎌 倉 時 代 に か け て は 、 中 央 の 文 化 的 影 響 力 が 圧 倒 的 で あ っ た た め 、 方 言 に 関 す る 記 述 は 断 片 的 な も の に と ど ま っ た が 、 室 町 時 代 、 と り わ け 戦 国 時 代 に は 中 央 の 支 配 力 が 弱 ま り 地 方 の 力 が 強 ま っ た 結 果 、 地 方 文 献 に 方 言 を 反 映 し た も の が し ば し ば 現 わ れ る よ う に な っ た 。 洞 門 抄 物 と 呼 ば れ る 東 国 系 の 文 献 が 有 名 で あ る が 、 古 文 書 類 に も し ば し ば 方 言 が 登 場 す る よ う に な る 。
安 土 桃 山 時 代 か ら 江 戸 時 代 極 初 期 に か け て は 、 ポ ル ト ガ ル 人 の 宣 教 師 が 数 多 く の キ リ シ タ ン 資 料 を 残 し て い る が 、 そ の 中 に 各 地 の 方 言 を 記 録 し た も の が あ る 。 京 都 の こ と ば を 中 心 に 据 え な が ら も 九 州 方 言 を 多 数 採 録 し た ﹃ 日 葡 辞 書 ﹄ ︵ 1 6 0 3 年 〜 1 6 0 4 年 ︶ や 、 筑 前 や 備 前 な ど 各 地 の 方 言 の 言 語 的 特 徴 を 記 し た ﹃ ロ ド リ ゲ ス 日 本 大 文 典 ﹄ ︵ 1 6 0 4 年 〜 1 6 0 8 年 ︶ は そ の 代 表 で あ る 。
こ の 時 期 に は 琉 球 方 言 ︵ 琉 球 語 ︶ の 資 料 も 登 場 す る 。 最 古 期 に 属 す る も の と し て は 、 中 国 資 料 の ﹃ 琉 球 館 訳 語 ﹄ ︵ 16 世 紀 前 半 成 立 ︶ が あ り 、 琉 球 の 言 葉 を 音 訳 表 記 に よ っ て 多 数 記 録 し て い る 。 ま た 、 1 6 0 9 年 の 島 津 侵 攻 事 件 で 琉 球 王 国 を 支 配 下 に 置 い た 薩 摩 藩 も 、 記 録 類 に 琉 球 の 言 葉 を 断 片 的 に 記 録 し て い る が 、 語 史 の 資 料 と し て 見 た 場 合 、 琉 球 諸 島 に 伝 わ る 古 代 歌 謡 ・ ウ ム イ を 集 め た ﹃ お も ろ さ う し ﹄ ︵ 1 5 3 1 年 〜 1 6 2 3 年 ︶ が 、 質 ・ 量 と も に 他 を 圧 倒 し て い る 。
奈 良 時 代 以 来 、 江 戸 幕 府 が 成 立 す る ま で 、 近 畿 方 言 が 中 央 語 の 地 位 に あ っ た 。 朝 廷 か ら 徳 川 家 へ 征 夷 大 将 軍 の 宣 下 が な さ れ て 以 降 、 江 戸 文 化 が 開 花 す る と と も に 、 江 戸 語 の 地 位 が 高 ま り 、 明 治 時 代 に は 東 京 語 が 日 本 語 の 標 準 語 と 見 な さ れ る よ う に な っ た 。
明 治 政 府 の 成 立 後 は 、 政 治 的 ・ 社 会 的 に 全 国 的 な 統 一 を 図 る た め 、 ま た 、 近 代 国 家 と し て 外 国 に 対 す る た め 、 言 葉 の 統 一 ・ 標 準 化 が 求 め ら れ る よ う に な っ た 。 学 校 教 育 で は ﹁ 東 京 の 中 流 社 会 ﹂ の 言 葉 が 採 用 さ れ [ 注 釈 41 ] 、 放 送 で も 同 様 の 言 葉 が ﹁ 共 通 用 語 ﹂ ︵ 共 通 語 ︶ と さ れ た [ 注 釈 42 ] 。 こ う し て 標 準 語 の 規 範 意 識 が 確 立 し て い く に つ れ 、 方 言 を 矯 正 し よ う と す る 動 き が 広 が っ た 。 教 育 家 の 伊 沢 修 二 は 、 教 員 向 け に 書 物 を 著 し て 東 北 方 言 の 矯 正 法 を 説 い た 。 地 方 の 学 校 で は 方 言 を 話 し た 者 に 首 か ら ﹁ 方 言 札 ﹂ を 下 げ さ せ る な ど の 罰 則 も 行 わ れ た [ 注 釈 43 ] 。 軍 隊 で は 命 令 伝 達 に 支 障 を 来 さ な い よ う 、 初 等 教 育 の 段 階 で 共 通 語 の 使 用 が 指 導 さ れ た [ 注 釈 44 ] 。
一 方 、 戦 後 に な る と 各 地 の 方 言 が 失 わ れ つ つ あ る こ と が 危 惧 さ れ る よ う に な っ た 。 N H K 放 送 文 化 研 究 所 は 、 ︵ 昭 和 20 年 代 の 時 点 で ︶ 各 地 の 純 粋 な 方 言 は 80 歳 以 上 の 老 人 の 間 で の み 使 わ れ て い る に す ぎ な い と し て 、 1 9 5 3 年 か ら 5 年 計 画 で 全 国 の 方 言 の 録 音 を 行 っ た 。 こ の 録 音 調 査 に は 、 柳 田 邦 夫 、 東 条 操 、 岩 淵 悦 太 郎 、 金 田 一 春 彦 な ど 言 語 学 者 ら が 指 導 に あ た っ た [ 1 6 9 ] 。
た だ し 、 戦 後 し ば ら く は 共 通 語 の 取 得 に 力 点 を 置 い た 国 語 教 育 が 初 等 教 育 の 現 場 で 続 き 、 昭 和 22 年 ︵ 1 9 4 7 年 ︶ の 学 習 指 導 要 領 国 語 科 編 ︵ 試 案 ︶ で は 、 ﹁ な る べ く 、 方 言 や 、 な ま り 、 舌 の も つ れ を な お し て 、 標 準 語 に 近 づ け る ﹂ ﹁ で き る だ け 、 語 法 の 正 し い こ と ば を つ か い 、 俗 語 ま た は 方 言 を さ け る よ う に す る ﹂ と の 記 載 が 見 ら れ る 。 ま た 、 昭 和 33 年 ︵ 1 9 5 8 年 ︶ の 小 学 校 学 習 指 導 要 領 で も 、 ﹁ 小 学 校 の 第 六 学 年 を 終 了 す る ま で に , ど の よ う な 地 域 に お い て も , 全 国 に 通 用 す る こ と ば で , 一 応 聞 い た り 話 し た り す る こ と が で き る よ う に す る ﹂ と の 記 述 が あ る [ 1 7 1 ] 。
ま た 、 経 済 成 長 と と も に 地 方 か ら 都 市 へ の 人 口 流 入 が 始 ま る と 、 標 準 語 と 方 言 の 軋 轢 が 顕 在 化 し た 。 1 9 5 0 年 代 後 半 か ら 、 地 方 出 身 者 が 自 分 の 言 葉 を 笑 わ れ た こ と に よ る 自 殺 ・ 事 件 が 相 次 い だ [ 注 釈 45 ] 。 こ の よ う な 情 勢 を 受 け て 、 方 言 の 矯 正 教 育 も な お 続 け ら れ た 。 鎌 倉 市 立 腰 越 小 学 校 で は 、 1 9 6 0 年 代 に 、 ﹁ ネ サ ヨ 運 動 ﹂ と 称 し て 、 語 尾 に ﹁ 〜 ね ﹂ ﹁ 〜 さ ﹂ ﹁ 〜 よ ﹂ な ど 関 東 方 言 特 有 の 語 尾 を つ け な い よ う に し よ う と す る 運 動 が 始 め ら れ た 。 同 趣 の 運 動 は 全 国 に 広 が っ た 。
高 度 成 長 後 に な る と 、 方 言 に 対 す る 意 識 に 変 化 が 見 ら れ る よ う に な っ た 。 1 9 8 0 年 代 初 め の ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 ﹁ 方 言 を 残 し て お き た い ﹂ と 回 答 す る 者 が 9 0 % 以 上 に 達 す る 結 果 が 出 て い る [ 1 7 4 ] 。 方 言 の 共 通 語 化 が 進 む と と も に 、 い わ ゆ る ﹁ 方 言 コ ン プ レ ッ ク ス ﹂ が 解 消 に 向 か い 、 方 言 を 大 切 に し よ う と い う 気 運 が 盛 り 上 が っ た 。
1 9 9 0 年 代 以 降 は 、 若 者 が 言 葉 遊 び の 感 覚 で 方 言 を 使 う こ と に 注 目 が 集 ま る よ う に な っ た 。 1 9 9 5 年 に は ラ ッ プ ﹁ D A . Y O . N E ﹂ の 関 西 版 ﹁ S O . Y A . N A ﹂ な ど の 方 言 替 え 歌 が 話 題 を 呼 び 、 報 道 記 事 に も 取 り 上 げ ら れ た [ 1 7 5 ] 。 首 都 圏 出 身 の 都 内 大 学 生 を 対 象 と し た 調 査 で は 、 東 京 の 若 者 の 間 に も 関 西 方 言 が 浸 透 し て い る こ と が 観 察 さ れ る と い う [ 1 7 6 ] 。 2 0 0 5 年 頃 に は 、 東 京 の 女 子 高 生 た ち の 間 で も ﹁ で ら ︵ と て も ︶ か わ い い ー ! ﹂ ﹁ い く べ ﹂ な ど と 各 地 の 方 言 を 会 話 に 織 り 交 ぜ て 使 う こ と が 流 行 し 始 め [ 1 7 7 ] 、 女 子 高 生 の た め の 方 言 参 考 書 の 類 も 現 れ た [ 1 7 8 ] 。 ﹁ 超 お も し ろ い ﹂ な ど ﹁ 超 ﹂ の 新 用 法 も 、 も と も と 静 岡 県 で 発 生 し て 東 京 に 入 っ た と さ れ る が 、 若 者 言 葉 や 新 語 の 発 信 地 が 東 京 に 限 ら な い 状 況 に な っ て い る ︵ ﹁ 方 言 由 来 の 若 者 言 葉 ﹂ を 参 照 ︶ 。
方 言 学 の 世 界 で は 、 か つ て は 、 標 準 語 の 確 立 に 資 す る た め の 研 究 が 盛 ん で あ っ た が [ 注 釈 46 ] 、 今 日 の 方 言 研 究 は 、 必 ず し も そ の よ う な 視 点 の み に よ っ て 行 わ れ て は い な い 。 中 央 語 の 古 形 が 方 言 に 残 る こ と は 多 く 、 方 言 研 究 が 中 央 語 の 史 的 研 究 に 資 す る こ と は い う ま で も な い [ 注 釈 47 ] 。 し か し 、 そ れ に と ど ま ら ず 、 個 々 の 方 言 の 研 究 は 、 そ れ 自 体 、 独 立 し た 学 問 と 捉 え る こ と が で き る 。 山 浦 玄 嗣 の ﹁ ケ セ ン 語 ﹂ 研 究 に 見 ら れ る よ う に [ 1 0 7 ] 、 研 究 者 が 自 ら の 方 言 に 誇 り を 持 ち 、 日 本 語 と は 別 個 の 言 語 と し て 研 究 す る と い う 立 場 も 生 ま れ て い る 。
日 本 人 自 身 が 日 本 語 に 関 心 を 寄 せ て き た 歴 史 は 長 く 、 ﹃ 古 事 記 ﹄ や ﹃ 万 葉 集 ﹄ の 記 述 に も 語 源 ・ 用 字 法 ・ 助 字 な ど に つ い て の 関 心 が 垣 間 見 ら れ る よ う に 、 古 来 、 さ ま ざ ま な 分 野 の 人 々 に よ っ て 日 本 語 研 究 が 行 わ れ て き た が 、 と り わ け 江 戸 時 代 に 入 っ て か ら は 、 秘 伝 に こ だ わ ら な い 自 由 な 学 風 が 起 こ り 、 客 観 的 ・ 実 証 的 な 研 究 が 深 め ら れ た 。 近 代 に 西 洋 の 言 語 学 が 輸 入 さ れ る 以 前 に 、 日 本 語 の 基 本 的 な 性 質 は ほ ぼ 明 ら か に な っ て い た と い っ て も 過 言 で は な い 。
こ の よ う に ﹁ こ れ ま で 日 本 語 を ど の よ う に 捉 え て き た か ﹂ を 明 ら か に す る 分 野 は 、 一 般 的 に ﹁ 日 本 語 学 史 ﹂ ︵ ま た は ﹁ 国 語 学 史 ﹂ ︶ と 呼 ば れ る 。 以 下 で は 、 江 戸 時 代 以 前 ・ 以 後 に 分 け て 概 説 し 、 さ ら に 近 代 に つ い て 付 説 す る 。
江 戸 時 代 以 前 の 日 本 語 研 究 の 流 れ は 、 大 き く 分 け て 3 分 野 あ っ た 。 中 国 語 ︵ 漢 語 ︶ 学 者 に よ る 研 究 、 悉 曇 学 者 に よ る 研 究 、 歌 学 者 に よ る 研 究 で あ る 。
中 国 語 と の 接 触 、 す な わ ち 漢 字 の 音 節 構 造 に つ い て 学 習 す る こ と に よ り 、 日 本 語 の 相 対 的 な 特 徴 が 意 識 さ れ る よ う に な っ た 。 ﹃ 古 事 記 ﹄ に は ﹁ 淤 能 碁 呂 嶋 自 淤 以 下 四 字 以 音 ﹂ ︵ オ ノ ゴ ロ 嶋 ︿ 淤 よ り 以 下 の 四 字 は 音 を 以 ゐ よ ﹀ ︶ の よ う な 音 注 が し ば し ば 付 け ら れ て い る が 、 こ れ は 漢 字 を 借 字 と し て 用 い 、 中 国 語 で 表 せ な い 日 本 語 の 固 有 語 を 1 音 節 ず つ 漢 字 で 表 記 し た も の で あ る 。 こ う し た 表 記 法 を 通 じ て 、 日 本 語 の 音 節 構 造 が 自 覚 さ れ る よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。 ま た 漢 文 の 訓 読 に よ り 、 中 国 語 に な い 助 詞 ・ 助 動 詞 の 要 素 が 意 識 さ れ る よ う に な り 、 漢 文 を 読 み 下 す 際 に 必 要 な ﹁ て ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ は ﹂ な ど の 要 素 は 、 当 初 は 点 を 漢 字 に 添 え る こ と で 表 現 し て い た の が ︵ ヲ コ ト 点 ︶ 、 後 に 借 字 、 さ ら に 片 仮 名 が 用 い ら れ る よ う に な っ た 。 こ れ ら の 要 素 は ﹁ て に を は ﹂ の 名 で 一 括 さ れ 、 後 に 一 つ の 研 究 分 野 と な っ た 。
日 本 語 の 1 音 1 音 を 借 字 で 記 す よ う に な っ た 当 初 は 、 音 韻 組 織 全 体 に 対 す る 意 識 は ま だ 弱 か っ た が 、 後 に あ ら ゆ る 仮 名 を 1 回 ず つ 集 め て 誦 文 に し た も の が 成 立 し て い る 。 平 安 時 代 初 期 に ﹁ 天 地 の 詞 ﹂ が 、 平 安 時 代 中 期 に は ﹁ い ろ は 歌 ﹂ が 現 れ た 。 こ れ ら は ほ ん ら い 漢 字 音 の ア ク セ ン ト 習 得 の た め に 使 わ れ た と み ら れ る が 、 の ち に い ろ は 歌 は 文 脈 が あ っ て 内 容 を 覚 え や す い こ と か ら 、 ﹃ 色 葉 字 類 抄 ﹄ ︵ 12 世 紀 ︶ な ど 物 の 順 番 を 示 す ﹁ い ろ は 順 ﹂ と し て 用 い ら れ 、 ま た 仮 名 の 手 本 と し て も 人 々 の 間 に 一 般 化 し て い る 。
一 方 、 悉 曇 学 の 研 究 に よ り 、 梵 語 ︵ サ ン ス ク リ ッ ト ︶ に 整 然 と し た 音 韻 組 織 が 存 在 す る こ と が 知 ら れ る よ う に な っ た 。 平 安 時 代 末 期 に 成 立 し た と 見 ら れ る ﹁ 五 十 音 図 ﹂ は 、 ﹁ あ ・ か ・ さ ・ た ・ な … … ﹂ の 行 の 並 び 方 が 梵 語 の 悉 曇 章 ︵ 字 母 表 ︶ の 順 に 酷 似 し て お り 、 悉 曇 学 を 通 じ て 日 本 語 の 音 韻 組 織 の 研 究 が 進 ん だ こ と を う か が わ せ る 。 も っ と も 、 五 十 音 図 作 成 の 目 的 は 、 一 方 で は 、 中 国 音 韻 学 の 反 切 を 理 解 す る た め で も あ っ た 。 当 初 、 そ の 配 列 は か な り 自 由 で あ っ た ︵ ほ ぼ 現 在 に 近 い 配 列 が 定 着 し た の は 室 町 時 代 以 後 ︶ 。 最 古 の 五 十 音 図 は 、 平 安 時 代 末 期 の 悉 曇 学 者 明 覚 の ﹃ 反 音 作 法 ﹄ に 見 ら れ る 。 明 覚 は ま た 、 ﹃ 悉 曇 要 訣 ﹄ に お い て 、 梵 語 の 発 音 を 説 明 す る た め に 日 本 語 の 例 を 多 く 引 用 し 、 日 本 語 の 音 韻 組 織 へ の 関 心 を 見 せ て い る 。
歌 学 は 平 安 時 代 以 降 、 大 い に 興 隆 し た 。 和 歌 の 実 作 お よ び 批 評 の た め の 学 問 で あ っ た が 、 正 当 な 語 彙 ・ 語 法 を 使 用 す る こ と へ の 要 求 か ら 、 日 本 語 の 古 語 に 関 す る 研 究 や 、 ﹁ て に を は ﹂ の 研 究 、 さ ら に 仮 名 遣 い へ の 研 究 に 繋 が っ た 。
こ の う ち 、 古 語 の 研 究 で は 、 語 と 語 の 関 係 を 音 韻 論 的 に 説 明 す る こ と が 試 み ら れ た 。 た と え ば 、 顕 昭 の ﹃ 袖 中 抄 ﹄ で は 、 ﹁ 七 夕 つ 女 ︵ た な ば た つ め ︶ ﹂ の 語 源 は ﹁ た な ば た つ ま ﹂ だ と し て ︵ こ れ 自 体 は 誤 り ︶ 、 ﹁ ﹃ ま ﹄ と ﹃ め ﹄ と は 同 じ 五 音 ︵ = 五 十 音 の 同 じ 行 ︶ な る 故 也 ﹂ [ 1 8 7 ] と 説 明 し て い る 。 こ の よ う に 、 ﹁ 五 音 相 通 ︵ 五 十 音 の 同 じ 行 で 音 が 相 通 ず る こ と ︶ ﹂ や ﹁ 同 韻 相 通 ︵ 五 十 音 の 同 じ 段 で 音 が 相 通 ず る こ と ︶ ﹂ な ど の 説 明 が 多 用 さ れ る よ う に な っ た 。
﹁ て に を は ﹂ の 本 格 的 研 究 は 、 鎌 倉 時 代 末 期 か ら 室 町 時 代 初 期 に 成 立 し た ﹃ 手 爾 葉 大 概 抄 ﹄ と い う 短 い 文 章 に よ っ て 端 緒 が 付 け ら れ た 。 こ の 文 章 で は ﹁ 名 詞 ・ 動 詞 な ど の 自 立 語 ︵ 詞 ︶ が 寺 社 で あ る と す れ ば 、 ﹃ て に を は ﹄ は そ の 荘 厳 さ に 相 当 す る も の だ ﹂ と 規 定 し た 上 で 、 係 助 詞 ﹁ ぞ ﹂ ﹁ こ そ ﹂ と そ の 結 び の 関 係 を 論 じ る な ど 、 ﹁ て に を は ﹂ に つ い て ご く 概 略 的 に 述 べ て い る 。 ま た 、 室 町 時 代 に は ﹃ 姉 小 路 式 ﹄ が 著 さ れ 、 係 助 詞 ﹁ ぞ ﹂ ﹁ こ そ ﹂ ﹁ や ﹂ ﹁ か ﹂ の ほ か 終 助 詞 ﹁ か な ﹂ な ど の ﹁ て に を は ﹂ の 用 法 を よ り 詳 細 に 論 じ て い る 。
仮 名 遣 い に つ い て は 、 鎌 倉 時 代 の 初 め 頃 に 藤 原 定 家 が こ れ を 問 題 と し 、 定 家 は そ の 著 作 ﹃ 下 官 集 ﹄ に お い て 、 仮 名 遣 い の 基 準 を 前 代 の 平 安 時 代 末 期 の 草 子 類 の 仮 名 表 記 に 求 め 、 規 範 を 示 そ う と し た 。 と こ ろ が ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ の 区 別 に つ い て は 、 平 安 時 代 末 期 に は す で に い ず れ も [ wo ] の 音 と な り 発 音 上 の 区 別 が 無 く な っ て い た こ と に よ り 、 相 当 な 表 記 の 揺 れ が あ り 、 格 助 詞 の ﹁ を ﹂ を 除 き 前 例 に よ る 基 準 を 見 出 す こ と が で き な か っ た 。 そ こ で ﹃ 下 官 集 ﹄ で は ア ク セ ン ト が 高 い 言 葉 を ﹁ を ﹂ で 、 ア ク セ ン ト が 低 い 言 葉 を ﹁ お ﹂ で 記 し て い る が 、 こ の ア ク セ ン ト の 高 低 に よ り ﹁ を ﹂ と ﹁ お ﹂ の 使 い 分 け を す る こ と は 、 す で に ﹃ 色 葉 字 類 抄 ﹄ に も 見 ら れ る 。 南 北 朝 時 代 に は 行 阿 が こ れ を 増 補 し て ﹃ 仮 名 文 字 遣 ﹄ を 著 し 、 こ れ が 後 に ﹁ 定 家 仮 名 遣 ﹂ と 呼 ば れ る 。 行 阿 の 姿 勢 も 基 準 を 古 書 に 求 め る と い う も の で 、 ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ の 区 別 に つ い て も 定 家 仮 名 遣 の 原 則 を 踏 襲 し て い る 。 し か し 行 阿 が ﹃ 仮 名 文 字 遣 ﹄ を 著 し た 頃 、 日 本 語 に ア ク セ ン ト の 一 大 変 化 が あ り 、 [ wo ] の 音 を 含 む 語 彙 に 関 し て も 定 家 の 時 代 と は ア ク セ ン ト の 高 低 が 異 な っ て し ま っ た 。 そ の 結 果 ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ の 仮 名 遣 い に つ い て は 、 定 家 が 示 し た も の と は 齟 齬 を 生 じ て い る 。
な お 、 ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ の 発 音 上 の 区 別 が 無 く な っ て い た こ と で 、 五 十 音 図 に お い て も 鎌 倉 時 代 以 来 ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ と は 位 置 が 逆 転 し た 誤 っ た 図 が 用 い ら れ て い た ︵ す な わ ち 、 ﹁ あ い う え を ﹂ ﹁ わ ゐ う ゑ お ﹂ と な っ て い た ︶ 。 こ れ が 正 さ れ る の は 、 江 戸 時 代 に 本 居 宣 長 が 登 場 し て か ら の こ と で あ る 。
外 国 人 に よ る 日 本 語 研 究 も 、 中 世 末 期 か ら 近 世 前 期 に か け て 多 く 行 わ れ た 。 イ エ ズ ス 会 で は 日 本 語 と ポ ル ト ガ ル 語 の 辞 書 ﹃ 日 葡 辞 書 ﹄ ︵ 1 6 0 3 年 ︶ が 編 纂 さ れ 、 同 会 の ロ ド リ ゲ ス に よ る 文 法 書 ﹃ 日 本 大 文 典 ﹄ ︵ 1 6 0 8 年 ︶ お よ び ﹃ 日 本 小 文 典 ﹄ ︵ 1 6 2 0 年 ︶ は 、 ラ テ ン 語 の 文 法 書 の 伝 統 に 基 づ い て 日 本 語 を 分 析 し た も の で 、 い ず れ も 価 値 が 高 い 。 一 方 、 中 国 で は ﹃ 日 本 館 訳 語 ﹄ ︵ 1 5 4 9 年 頃 ︶ 、 李 氏 朝 鮮 で は ﹃ 捷 解 新 語 ﹄ ︵ 1 6 7 6 年 ︶ と い っ た 日 本 語 学 習 書 が 編 纂 さ れ た 。
日 本 語 の 研 究 が 高 い 客 観 性 ・ 実 証 性 を 備 え る よ う に な っ た の は 、 江 戸 時 代 の 契 沖 の 研 究 以 来 の こ と で あ る 。 契 沖 は ﹃ 万 葉 集 ﹄ の 注 釈 を 通 じ て 仮 名 遣 い に つ い て 詳 細 に 観 察 を 行 い 、 ﹃ 和 字 正 濫 抄 ﹄ ︵ 1 6 9 5 年 ︶ を 著 し た 。 こ の 書 に よ り 、 古 代 は 語 ご と に 仮 名 遣 い が 決 ま っ て い た こ と が 明 ら か に さ れ 、 契 沖 自 身 も そ の 仮 名 遣 い を 実 行 し た 。 契 沖 の 掲 出 し た 見 出 し 語 は 、 後 に 楫 取 魚 彦 編 の 仮 名 遣 い 辞 書 ﹃ 古 言 梯 ﹄ ︵ 1 7 6 5 年 ︶ で 増 補 さ れ 、 後 世 に お い て 歴 史 的 仮 名 遣 い と 称 さ れ た 。
古 語 の 研 究 で は 、 松 永 貞 徳 の ﹃ 和 句 解 ﹄ ︵ 1 6 6 2 年 ︶ 、 貝 原 益 軒 の ﹃ 日 本 釈 名 ﹄ ︵ 1 7 0 0 年 ︶ が 出 た 後 、 新 井 白 石 に よ り 大 著 ﹃ 東 雅 ﹄ ︵ 1 7 1 9 年 ︶ が ま と め ら れ た 。 白 石 は 、 ﹃ 東 雅 ﹄ の 中 で 語 源 説 を 述 べ る に 当 た り 、 終 始 穏 健 な 姿 勢 を 貫 き 、 曖 昧 な も の は ﹁ 義 未 詳 ﹂ と し て 曲 解 を 排 し た 。 ま た 、 賀 茂 真 淵 は ﹃ 語 意 考 ﹄ ︵ 1 7 8 9 年 ︶ を 著 し 、 ﹁ 約 ・ 延 ・ 略 ・ 通 ﹂ の 考 え 方 を 示 し た 。 す な わ ち 、 ﹁ 語 形 の 変 化 は 、 縮 め る ︵ 約 ︶ か 、 延 ば す か 、 略 す る か 、 音 通 ︵ 母 音 ま た は 子 音 の 交 替 ︶ か に よ っ て 生 じ る ﹂ と い う も の で あ る 。 こ の 原 則 は 、 そ れ 自 体 は 正 当 で あ る が 、 後 に こ れ を 濫 用 し 、 非 合 理 な 語 源 説 を 提 唱 す る 者 も 現 れ た 。 語 源 研 究 で は 、 ほ か に 、 鈴 木 朖 が ﹃ 雅 語 音 声 考 ﹄ ︵ 1 8 1 6 年 ︶ を 著 し 、 ﹁ ほ と と ぎ す ﹂ ﹁ う ぐ い す ﹂ ﹁ か ら す ﹂ な ど の ﹁ ほ と と ぎ ﹂ ﹁ う ぐ い ﹂ ﹁ か ら ﹂ の 部 分 は 鳴 き 声 で あ る こ と を 示 す な ど 、 興 味 深 い 考 え 方 を 示 し て い る 。
本 居 宣 長 は 、 仮 名 遣 い の 研 究 お よ び 文 法 の 研 究 で 非 常 な 功 績 が あ っ た 。 ま ず 、 仮 名 遣 い の 分 野 で は 、 ﹃ 字 音 仮 字 用 格 ﹄ ︵ 1 7 7 6 年 ︶ を 著 し 、 漢 字 音 を 仮 名 で 書 き 表 す と き に ど の よ う な 仮 名 遣 い を 用 い れ ば よ い か を 論 じ た 。 そ の 中 で 宣 長 は 、 鎌 倉 時 代 以 来 、 五 十 音 図 で ﹁ お ﹂ と ﹁ を ﹂ の 位 置 が 誤 っ て 記 さ れ て い る ︵ 前 節 参 照 ︶ と い う 事 実 を 指 摘 し 、 実 に 4 0 0 年 ぶ り に 、 本 来 の 正 し い ﹁ あ い う え お ﹂ ﹁ わ ゐ う ゑ を ﹂ の 形 に 戻 し た 。 こ の 事 実 は 、 後 に 東 条 義 門 が ﹃ 於 乎 軽 重 義 ﹄ ︵ 1 8 2 7 年 ︶ で 検 証 し た 。 ま た 、 宣 長 は 文 法 の 研 究 、 と り わ け 係 り 結 び の 研 究 で 成 果 を 上 げ た 。 係 り 結 び の 一 覧 表 で あ る ﹃ ひ も 鏡 ﹄ ︵ 1 7 7 1 年 ︶ を ま と め 、 ﹃ 詞 の 玉 緒 ﹄ ︵ 1 7 7 9 年 ︶ で 詳 説 し た 。 文 中 に ﹁ ぞ ・ の ・ や ・ 何 ﹂ が 来 た 場 合 に は 文 末 が 連 体 形 、 ﹁ こ そ ﹂ が 来 た 場 合 は 已 然 形 で 結 ば れ る こ と を 示 し た の み な ら ず 、 ﹁ は ・ も ﹂ お よ び ﹁ 徒 ︵ た だ = 主 格 な ど に 助 詞 が つ か な い 場 合 ︶ ﹂ の 場 合 は 文 末 が 終 止 形 に な る こ と を 示 し た 。 主 格 な ど に ﹁ は ・ も ﹂ な ど が 付 い た 場 合 に 文 末 が 終 止 形 に な る の は 当 然 の よ う で あ る が 、 必 ず し も そ う で な い 。 主 格 を 示 す ﹁ が ・ の ﹂ が 来 た 場 合 は 、 ﹁ 君 が 思 ほ せ り け る ﹂ ︵ 万 葉 集 ︶ ﹁ に ほ ひ の 袖 に と ま れ る ﹂ ︵ 古 今 集 ︶ の よ う に 文 末 が 連 体 形 で 結 ば れ る の で あ る か ら 、 あ え て ﹁ は ・ も ・ 徒 ﹂ の 下 が 終 止 形 で 結 ば れ る こ と を 示 し た こ と は 重 要 で あ る 。
品 詞 研 究 で 成 果 を 上 げ た の は 富 士 谷 成 章 で あ っ た 。 富 士 谷 は 、 品 詞 を ﹁ 名 ﹂ ︵ 名 詞 ︶ ・ ﹁ 装 ︵ よ そ い ︶ ﹂ ︵ 動 詞 ・ 形 容 詞 な ど ︶ ・ ﹁ 挿 頭 ︵ か ざ し ︶ ﹂ ︵ 副 詞 な ど ︶ ・ ﹁ 脚 結 ︵ あ ゆ い ︶ ﹂ ︵ 助 詞 ・ 助 動 詞 な ど ︶ の 4 類 に 分 類 し た 。 ﹃ 挿 頭 抄 ﹄ ︵ 1 7 6 7 年 ︶ で は 今 日 で 言 う 副 詞 の 類 を 中 心 に 論 じ た 。 特 に 注 目 す べ き 著 作 は ﹃ 脚 結 抄 ﹄ ︵ 1 7 7 8 年 ︶ で 、 助 詞 ・ 助 動 詞 を 系 統 立 て て 分 類 し 、 そ の 活 用 の 仕 方 お よ び 意 味 ・ 用 法 を 詳 細 に 論 じ た 。 内 容 は 創 見 に 満 ち 、 今 日 の 品 詞 研 究 で も 盛 ん に 引 き 合 い に 出 さ れ る 。 ﹃ 脚 結 抄 ﹄ の 冒 頭 に 記 さ れ た ﹁ 装 図 ﹂ は 、 動 詞 ・ 形 容 詞 の 活 用 を 整 理 し た 表 で 、 後 の 研 究 に 資 す る と こ ろ が 大 き か っ た 。
活 用 の 研 究 は 、 そ の 後 、 鈴 木 朖 の ﹃ 活 語 断 続 譜 ﹄ ︵ 1 8 0 3 年 頃 ︶ 、 本 居 春 庭 の ﹃ 詞 八 衢 ﹄ ︵ 1 8 0 6 年 ︶ に 引 き 継 が れ た [ 注 釈 48 ] 。 幕 末 に は 義 門 が ﹃ 活 語 指 南 ﹄ ︵ 1 8 4 4 年 ︶ を 著 し 、 富 樫 広 蔭 が ﹃ 辞 玉 襷 ﹄ ︵ 1 8 2 9 年 ︶ を 著 す な ど 、 日 本 語 の 活 用 が 組 織 化 ・ 体 系 化 さ れ て い っ た 。
こ の ほ か 、 江 戸 時 代 で 注 目 す べ き 研 究 と し て は 、 石 塚 龍 麿 の ﹃ 仮 字 用 格 奥 山 路 ﹄ が あ る 。 万 葉 集 の 仮 名 に 2 種 の 書 き 分 け が 存 在 す る こ と を 示 し た も の で 、 長 ら く 正 当 な 扱 い を 受 け な か っ た が 、 後 に 橋 本 進 吉 が 上 代 特 殊 仮 名 遣 の 先 駆 的 研 究 と し て 再 評 価 し た 。
江 戸 時 代 後 期 か ら 明 治 時 代 に か け て 、 西 洋 の 言 語 学 が 紹 介 さ れ 、 日 本 語 研 究 は 新 た な 段 階 を 迎 え た 。 も っ と も 、 西 洋 の 言 語 に 当 て は ま る 理 論 を 無 批 判 に 日 本 語 に 応 用 す る こ と で 、 か え っ て こ れ ま で の 蓄 積 を 損 な う よ う な 研 究 も 少 な く な か っ た 。
こ う し た 中 で 、 古 来 の 日 本 語 研 究 と 西 洋 言 語 学 と を 吟 味 し て 文 法 を ま と め た の が 大 槻 文 彦 で あ っ た 。 大 槻 は ﹃ 言 海 ﹄ の 中 で 文 法 論 ﹁ 語 法 指 南 ﹂ を 記 し ︵ 1 8 8 9 年 ︶ 、 後 に こ れ を 独 立 、 増 補 し て ﹃ 広 日 本 文 典 ﹄ ︵ 1 8 9 7 年 ︶ と し た 。
そ の 後 、 高 等 教 育 の 普 及 と と も に 、 日 本 語 研 究 者 の 数 は 増 大 し た 。 1 8 9 7 年 に は 東 京 帝 国 大 学 に 国 語 研 究 室 が 置 か れ 、 ド イ ツ 帰 り の 上 田 萬 年 が 初 代 主 任 教 授 と し て 指 導 的 役 割 を 果 た し た 。
日 本 語 が 時 と 共 に 変 化 す る こ と は し ば し ば 批 判 の 対 象 と な る 。 こ の 種 の 批 判 は 、 古 典 文 学 の 中 に も 見 ら れ る 。 ﹃ 枕 草 子 ﹄ で は 文 末 の ﹁ ん と す ﹂ が ﹁ ん ず ﹂ と い わ れ る こ と を ﹁ い と わ ろ し ﹂ と 評 し て い る ︵ ﹁ ふ と 心 お と り と か す る も の は ﹂ ︶ 。 ま た 、 ﹃ 徒 然 草 ﹄ で は 古 く は ﹁ 車 も た げ よ ﹂ ﹁ 火 か か げ よ ﹂ と 言 わ れ た の が 、 今 の 人 は ﹁ も て あ げ よ ﹂ ﹁ か き あ げ よ ﹂ と 言 う よ う に な っ た と 記 し 、 今 の 言 葉 は ﹁ 無 下 に い や し く ﹂ な っ て い く よ う だ と 記 し て い る ︵ 第 22 段 ︶ 。
こ れ に と ど ま ら ず 、 言 語 変 化 に つ い て 注 意 す る 記 述 は 、 歴 史 上 、 仮 名 遣 い 書 や 、 ﹃ 俊 頼 髄 脳 ﹄ な ど の 歌 論 書 、 ﹃ 音 曲 玉 淵 集 ﹄ な ど の 音 曲 指 南 書 を は じ め 、 諸 種 の 資 料 に 見 ら れ る 。 な か で も 、 江 戸 時 代 の 俳 人 安 原 貞 室 が 、 な ま っ た 言 葉 の 批 正 を 目 的 に 編 ん だ ﹃ 片 言 ︵ か た こ と ︶ ﹄ ︵ 1 6 5 0 年 ︶ は 、 8 0 0 に わ た る 項 目 を 取 り 上 げ て お り 、 当 時 の 言 語 実 態 を 示 す 資 料 と し て 価 値 が 高 い 。
近 代 以 降 も 、 芥 川 龍 之 介 が ﹁ 澄 江 堂 雑 記 ﹂ で 、 ﹁ と て も ﹂ は 従 来 否 定 を 伴 っ て い た と し て 、 ﹁ と て も 安 い ﹂ な ど 肯 定 形 に な る こ と に 疑 問 を 呈 す る な ど 、 言 語 変 化 に つ い て の 指 摘 が 散 見 す る 。 研 究 者 の 立 場 か ら 同 時 代 の 気 に な る 言 葉 を 収 集 し た 例 と し て は 、 浅 野 信 ﹃ 巷 間 の 言 語 省 察 ﹄ ︵ 1 9 3 3 年 ︶ な ど が あ る 。
第 二 次 世 界 大 戦 後 は 、 1 9 5 1 年 に 雑 誌 ﹃ 言 語 生 活 ﹄ ︵ 当 初 は 国 立 国 語 研 究 所 が 監 修 ︶ が 創 刊 さ れ る な ど 、 日 本 語 へ の 関 心 が 高 ま っ た 。 そ の よ う な 風 潮 の 中 で 、 あ ら ゆ る 立 場 の 人 々 に よ り 、 言 語 変 化 に 対 す る 批 判 や そ の 擁 護 論 が 活 発 に 交 わ さ れ る よ う に な っ た 。 典 型 的 な 議 論 の 例 と し て は 、 金 田 一 春 彦 ﹁ 日 本 語 は 乱 れ て い な い ﹂ お よ び 宇 野 義 方 の 反 論 [ 2 2 0 ] が 挙 げ ら れ る 。
い わ ゆ る ﹁ 日 本 語 の 乱 れ ﹂ 論 議 に お い て 、 毎 度 の よ う に 話 題 に さ れ る 言 葉 も 多 い 。 1 9 5 5 年 の 国 立 国 語 研 究 所 の 有 識 者 調 査 の 項 目 に は ﹁ ニ ッ ポ ン ・ ニ ホ ン ︵ 日 本 ︶ ﹂ ﹁ ジ ッ セ ン ・ ジ ュ ッ セ ン ︵ 十 銭 ︶ ﹂ ﹁ 見 ら れ な か っ た ・ 見 れ な か っ た ﹂ ﹁ 御 研 究 さ れ ま し た ・ 御 研 究 に な り ま し た ﹂ な ど 、 今 日 で も し ば し ば 取 り 上 げ ら れ る 語 形 ・ 語 法 が 多 く 含 ま れ て い る 。 と り わ け ﹁ 見 ら れ る ﹂ を ﹁ 見 れ る ﹂ と す る 語 法 は 、 1 9 7 9 年 の N H K 放 送 文 化 研 究 所 ﹁ 現 代 人 の 言 語 環 境 調 査 ﹂ で 可 否 の 意 見 が 二 分 す る な ど 、 人 々 の 言 語 習 慣 の 違 い を 如 実 に 示 す 典 型 例 と な っ て い る 。 こ の 語 法 は 1 9 8 0 年 代 に は ﹁ ら 抜 き 言 葉 ﹂ と 称 さ れ 、 盛 ん に 取 り 上 げ ら れ る よ う に な っ た 。
﹁ 言 葉 の 乱 れ ﹂ を 指 摘 す る 声 は 、 新 聞 ・ 雑 誌 の 投 書 に も 多 い 。 文 化 庁 の ﹁ 国 語 に 関 す る 世 論 調 査 ﹂ で は 、 ﹁ 言 葉 遣 い が 乱 れ て い る ﹂ と 考 え る 人 が 1 9 7 7 年 に 7 割 近 く に な り 、 2 0 0 2 年 11 月 か ら 12 月 の 調 査 で は 8 割 と な っ て い る 。 人 々 の こ の よ う な 認 識 は 、 い わ ゆ る 日 本 語 ブ ー ム を 支 え る 要 素 の 一 つ と な っ て い る 。
若 者 特 有 の 用 法 は 批 判 の 的 に な っ て き た 。 近 代 以 降 の 若 者 言 葉 批 判 の 例 と し て 、 小 説 家 ・ 尾 崎 紅 葉 が 1 8 8 8 年 に 女 性 徒 の 間 で 流 行 し て い た ﹁ て よ だ わ 体 ﹂ [ 注 釈 50 ] を 批 判 す る な ど 、 1 9 0 0 年 前 後 に ﹁ て よ だ わ 体 ﹂ は 批 判 の 的 と な っ た 。 1 9 8 0 年 代 ご ろ か ら 単 な る 言 葉 の 乱 れ と し て で は な く 、 研 究 者 の 記 述 の 対 象 と し て も 扱 わ れ る よ う に も な っ た [ 注 釈 51 ] 。
い わ ゆ る ﹁ 若 者 言 葉 ﹂ は 種 々 の 意 味 で 用 い ら れ 、 必 ず し も 定 義 は 一 定 し て い な い 。 井 上 史 雄 の 分 類 に 即 し て 述 べ る と 、 若 者 言 葉 と 称 さ れ る も の は 以 下 の よ う に 分 類 さ れ る 。
(一) 一 時 的 流 行 語 。 あ る 時 代 の 若 い 世 代 が 使 う 言 葉 。 戦 後 の ﹁ ア ジ ャ パ ー ﹂ や 1 9 7 0 年 代 の ﹁ チ カ レ タ ビ ー ﹂ な ど 。 (二) コ ー ホ ー ト 語 ︵ 同 世 代 語 ︶ 。 流 行 語 が 生 き 残 り 、 そ の 世 代 が 年 齢 を 重 ね て か ら も 使 う 言 葉 。 次 世 代 の 若 者 は 流 行 遅 れ と 意 識 し 、 使 わ な い 。 (三) 若 者 世 代 語 。 ど の 世 代 の 人 も 、 若 い 間 だ け 使 う 言 葉 。 ﹁ ド イ 語 ﹂ ︵ ド イ ツ 語 ︶ や ﹁ 代 返 ﹂ な ど の 学 生 言 葉 ︵ キ ャ ン パ ス 用 語 ︶ を 含 む 。 (四) 言 語 変 化 。 若 い 世 代 が 年 齢 を 重 ね て か ら も 使 い 、 次 世 代 の 若 者 も 使 う も の 。 結 果 的 に 、 世 代 を 超 え て 変 化 が 定 着 す る 。 ら 抜 き 言 葉 ・ 鼻 濁 音 の 衰 退 な ど 。 上 記 は 、 い ず れ も 批 判 に さ ら さ れ う る と い う 点 で は 同 様 で あ る が 、 1 - 4 の 順 で 、 次 第 に 言 葉 の 定 着 率 は 高 く な る た め 、 そ れ だ け ﹁ 言 葉 の 乱 れ ﹂ の 例 と し て 意 識 さ れ や す く な る 。
上 記 の 分 類 の う ち ﹁ 一 時 的 流 行 語 ﹂ な い し ﹁ 若 者 世 代 語 ﹂ に 相 当 す る 言 葉 の 発 生 要 因 に 関 し 、 米 川 明 彦 は 心 理 ・ 社 会 ・ 歴 史 の 面 に 分 け て 指 摘 し て い る 。 そ の 指 摘 は 、 お よ そ 以 下 の よ う に 総 合 で き る 。 す な わ ち 、 成 長 期 に あ る 若 者 は 、 自 己 や 他 者 へ の 興 味 が 強 ま る だ け で な く 、 従 来 の 言 葉 の 規 範 か ら の 自 由 を 求 め る 。 日 本 経 済 の 成 熟 と と も に ﹁ ま じ め ﹂ と い う 価 値 観 が 崩 壊 し 、 若 者 が ﹁ ノ リ ﹂ に よ っ て 会 話 す る よ う に な っ た 。 と り わ け 、 1 9 9 0 年 代 以 降 は ﹁ ノ リ ﹂ を 楽 し む 世 代 が 低 年 齢 化 し 、 消 費 ・ 娯 楽 社 会 の 産 物 と し て 若 者 言 葉 が 生 産 さ れ て い る と い う も の で あ る 。 ま た 、 2 0 0 7 年 頃 か ら マ ス メ デ ィ ア が ﹁ 場 の 空 気 ﹂ の 文 化 を 取 り 上 げ る よ う に な っ て き て か ら 、 言 葉 で 伝 え る よ り 、 察 し 合 っ て 心 を 通 わ せ る こ と を 重 ん じ る 者 が 増 え た 。 こ れ に 対 し 、 文 化 庁 は 、 空 気 読 め な い ( KY ) と 言 わ れ る こ と を 恐 れ 、 場 の 空 気 に 合 わ せ よ う と す る 風 潮 の 現 れ で は な い か と 指 摘 し て い る [ 2 2 6 ] 。
若者の日本語は、表記の面でも独自性を持つ。年代によりさまざまな日本語の表記が行われている。
丸文字
1 9 7 0 年 代 か ら 1 9 8 0 年 代 に か け て 、 少 女 の 間 で 、 丸 み を 帯 び た 書 き 文 字 が ﹁ か わ い い ﹂ と 意 識 さ れ て 流 行 し 、 ﹁ 丸 文 字 ﹂ ﹁ ま ん が 文 字 ﹂ ﹁ 変 体 少 女 文 字 ︵ = 書 体 の 変 わ っ た 少 女 文 字 の 意 ︶ ﹂ な ど と 呼 ば れ た 。 山 根 一 眞 の 調 査 に よ れ ば 、 こ の 文 字 は 1 9 7 4 年 ま で に は 誕 生 し 、 1 9 7 8 年 に 急 激 に 普 及 を 開 始 し た と い う 。
ヘ タ ウ マ 文 字 1 9 9 0 年 頃 か ら 、 丸 文 字 に 代 わ り 、 少 女 の 間 で 、 金 釘 流 に 似 た 縦 長 の 書 き 文 字 が 流 行 し 始 め た 。 平 仮 名 の ﹁ に ﹂ を ﹁ レ こ ﹂ の よ う に 書 い た り 、 長 音 符 の ﹁ ー ﹂ を ﹁ → ﹂ と 書 い た り す る 特 徴 が あ っ た 。 一 見 下 手 に 見 え る た め 、 ﹁ 長 体 ヘ タ ウ マ 文 字 ﹂ な ど と も 呼 ば れ た 。 マ ス コ ミ で は ﹁ チ ョ ベ リ バ 世 代 が 楽 し む ヘ タ ウ マ 文 字 ﹂ [ 2 2 8 ] ﹁ 女 高 生 に 広 ま る 変 な と ん が り 文 字 ﹂ [ 2 2 9 ] な ど と 紹 介 さ れ た が 、 必 ず し も 大 人 世 代 の 話 題 に は な ら な い ま ま 、 確 実 に 広 ま っ た 。 こ の 文 字 を 練 習 す る た め の 本 [ 2 3 0 ] も 出 版 さ れ た 。
ギャル文字 携帯メールやインターネットの普及に伴い、ギャルと呼ばれる少女たちを中心に、デジタル文字の表記に独特の文字や記号を用いるようになった。「さようなら」を「±∋ぅTょら」と書く類で、「ギャル文字 」としてマスコミにも取り上げられた[231] [232]
顔文字 コンピュータの普及と、コンピュータを使用したパソコン通信などの始まりにより、日本語の約物に似た扱いとして顔文字が用いられるようになった。これは、コンピュータの文字としてコミュニケーションを行うときに、文章の後や単独で記号などを組み合わせた「(^_^)」のような顔文字を入れることにより感情などを表現する手法である。1980年代 後半に使用が開始された顔文字は、若者へのコンピュータの普及により広く使用されるようになった。
絵文字 携帯電話に絵文字 が実装されたことにより、絵文字文化と呼ばれるさまざまな絵文字を利用したコミュニケーションが行われるようになった。漢字や仮名と同じように日本語の文字として扱われ、約物のような利用方法にとどまらず、単語や文章の置き換えとしても用いられるようになった[233]
小文字
す で に 普 及 し た 顔 文 字 や 絵 文 字 に 加 え 、 2 0 0 6 年 頃 に は ﹁ 小 文 字 ﹂ と 称 さ れ る 独 特 の 表 記 法 が 登 場 し た 。 ﹁ ゎ た し ゎ 、 き ょ ぅ ゎ 部 活 が な ぃ の ﹂ の よ う に 特 定 文 字 を 小 字 で 表 記 す る も の で 、 マ ス コ ミ で も 紹 介 さ れ る よ う に な っ た [ 2 3 4 ] 。
人 々 の 日 本 語 に 寄 せ る 関 心 は 、 第 二 次 世 界 大 戦 後 に 特 に 顕 著 に な っ た と い え る 。 1 9 4 7 年 10 月 か ら N H K ラ ジ オ で ﹁ こ と ば の 研 究 室 ﹂ が 始 ま り 、 1 9 5 1 年 に は 雑 誌 ﹃ 言 語 生 活 ﹄ が 創 刊 さ れ た 。
日 本 語 関 係 書 籍 の 出 版 点 数 も 増 大 し た 。 敬 語 を テ ー マ と し た 本 の 場 合 、 1 9 6 0 年 代 以 前 は 解 説 書 5 点 、 実 用 書 2 点 で あ っ た も の が 、 1 9 7 0 年 代 か ら 1 9 9 4 年 の 25 年 間 に 解 説 書 約 10 点 、 実 用 書 約 40 点 が 出 た と い う 。
戦 後 、 最 初 の 日 本 語 ブ ー ム が 起 こ っ た の は 1 9 5 7 年 の こ と で 、 金 田 一 春 彦 ﹃ 日 本 語 ﹄ ︵ 岩 波 新 書 、 旧 版 ︶ が 77 万 部 、 大 野 晋 ﹃ 日 本 語 の 起 源 ﹄ ︵ 岩 波 新 書 、 旧 版 ︶ が 36 万 部 出 版 さ れ た 。 1 9 7 4 年 に は 丸 谷 才 一 ﹃ 日 本 語 の た め に ﹄ ︵ 新 潮 社 ︶ が 50 万 部 、 大 野 晋 ﹃ 日 本 語 を さ か の ぼ る ﹄ ︵ 岩 波 新 書 ︶ が 50 万 部 出 版 さ れ た [ 注 釈 52 ] 。
そ の 後 、 1 9 9 9 年 の 大 野 晋 ﹃ 日 本 語 練 習 帳 ﹄ ︵ 岩 波 新 書 ︶ は 1 9 0 万 部 を 超 え る ベ ス ト セ ラ ー と な っ た ︵ 2 0 0 8 年 時 点 ︶ [ 2 3 7 ] 。 さ ら に 、 2 0 0 1 年 に 齋 藤 孝 ﹃ 声 に 出 し て 読 み た い 日 本 語 ﹄ ︵ 草 思 社 ︶ が 1 4 0 万 部 出 版 さ れ た 頃 か ら 、 出 版 界 で は 空 前 の 日 本 語 ブ ー ム と い う 状 況 に な り 、 お び た だ し い 種 類 と 数 の 一 般 向 け の 日 本 語 関 係 書 籍 が 出 た [ 2 3 8 ] 。
2 0 0 4 年 に は 北 原 保 雄 編 ﹃ 問 題 な 日 本 語 ﹄ ︵ 大 修 館 書 店 ︶ が 、 当 時 よ く 問 題 に さ れ た 語 彙 ・ 語 法 を 一 般 向 け に 説 明 し た 。 翌 2 0 0 5 年 か ら 2 0 0 6 年 に か け て は 、 テ レ ビ で も 日 本 語 を テ ー マ と し た 番 組 が 多 く 放 送 さ れ 、 大 半 の 番 組 で 日 本 語 学 者 が コ メ ン テ ー タ ー や 監 修 に 迎 え ら れ た 。 ﹁ タ モ リ の ジ ャ ポ ニ カ ロ ゴ ス ﹂ ︵ フ ジ テ レ ビ 2 0 0 5 〜 2 0 0 8 ︶ 、 ﹁ ク イ ズ ! 日 本 語 王 ﹂ ︵ T B S 2 0 0 5 〜 2 0 0 6 ︶ 、 ﹁ 三 宅 式 こ く ご ド リ ル ﹂ ︵ テ レ ビ 東 京 2 0 0 5 〜 2 0 0 6 ︶ 、 ﹁ M a t t h e w ' s B e s t H i t T V + ・ な ま り 亭 ﹂ ︵ テ レ ビ 朝 日 2 0 0 5 〜 2 0 0 6 。 方 言 を 扱 う ︶ 、 ﹁ 合 格 ! 日 本 語 ボ ー ダ ー ラ イ ン ﹂ ︵ テ レ ビ 朝 日 2 0 0 5 ︶ 、 ﹁ こ と ば お じ さ ん の ナ ッ ト ク 日 本 語 塾 ﹂ ︵ N H K 2 0 0 6 〜 2 0 1 0 ︶ な ど 種 々 の 番 組 が あ っ た 。
﹁ 複 雑 な 表 記 体 系 ﹂ ﹁ S O V 構 造 ﹂ ﹁ 音 節 文 字 ﹂ ﹁ 敬 語 ﹂ ﹁ 男 言 葉 と 女 言 葉 ﹂ ﹁ 擬 態 語 が 豊 富 ﹂ ﹁ 曖 昧 表 現 が 多 い ﹂ ﹁ 母 音 の 数 が 少 な い ﹂ な ど を 根 拠 に 日 本 語 特 殊 論 が と な え ら れ る こ と が あ る 。
も っ と も 、 日 本 語 が 印 欧 語 と の 相 違 点 を 多 く 持 つ こ と は 事 実 で あ る 。 そ の た め 、 対 照 言 語 学 の 上 で は 、 印 欧 語 と の よ い 比 較 対 象 と な る 。 ま た 、 日 本 語 成 立 由 来 と い う 観 点 か ら の 研 究 も 存 在 す る ︵ ﹃ 日 本 語 の 起 源 ﹄ を 参 照 ︶ 。
日 本 語 特 殊 論 は 、 近 代 以 降 し ば し ば 提 起 さ れ て い る 。 極 端 な 例 で は あ る が 、 戦 後 、 志 賀 直 哉 が ﹁ 日 本 の 国 語 程 、 不 完 全 で 不 便 な も の は な い と 思 ふ ﹂ と し て 、 フ ラ ン ス 語 を 国 語 に 採 用 す る こ と を 主 張 し た [ 2 3 9 ] ︵ 国 語 外 国 語 化 論 ︶ 。 ま た 、 1 9 8 8 年 に は 、 国 立 国 語 研 究 所 所 長 ・ 野 元 菊 雄 が 、 外 国 人 へ の 日 本 語 教 育 の た め 、 文 法 を 単 純 化 し た ﹁ 簡 約 日 本 語 ﹂ の 必 要 性 を 説 き 、 論 議 を 呼 ん だ [ 注 釈 53 ] 。
動 詞 が 最 後 に 来 る こ と を 理 由 に 日 本 語 を 曖 昧 、 不 合 理 と 断 ず る 議 論 も あ る 。 例 え ば か つ て ジ ャ ー ナ リ ス ト 森 恭 三 は 、 日 本 語 の 語 順 で は ﹁ 思 想 を 表 現 す る の に 一 番 大 切 な 動 詞 は 、 文 章 の 最 後 に く る ﹂ た め 、 文 末 の 動 詞 の 部 分 に 行 く ま で に 疲 れ て 、 ﹁ も は や 動 詞 ︹ 部 分 で ︺ の 議 論 な ど は で き な い ﹂ と 記 し て い る 。
複 雑 な 文 字 体 系 を 理 由 に 、 日 本 語 を 特 殊 と す る 議 論 も あ る 。 計 算 機 科 学 者 の 村 島 定 行 は 、 古 く か ら 日 本 人 が 文 字 文 化 に 親 し み 、 庶 民 階 級 の 識 字 率 も 比 較 的 高 水 準 で あ っ た の は 、 日 本 語 は 表 意 文 字 ︵ 漢 字 ︶ と 表 音 文 字 ︵ 仮 名 ︶ の 2 つ の 文 字 体 系 を 使 用 し て い た か ら だ と 主 張 す る 。 た だ し 、 表 意 ・ 表 音 文 字 の 二 重 使 用 は 、 他 に 漢 字 文 化 圏 で は 韓 文 漢 字 や 女 真 文 字 な ど 、 漢 字 文 化 圏 以 外 で も マ ヤ 文 字 や ヒ エ ロ グ リ フ な ど の 例 が あ る 。 一 方 で 、 カ ナ モ ジ カ イ の よ う に 、 数 種 類 の 文 字 体 系 を 使 い 分 け る こ と の 不 便 さ を 主 張 す る 意 見 も 存 在 す る 。
日 本 語 に お け る 語 順 や 音 韻 論 、 も し く は 表 記 体 系 な ど を 取 り 上 げ て 、 そ れ ら を 日 本 人 の 文 化 や 思 想 的 背 景 と 関 連 付 け 、 日 本 語 の 特 殊 性 を 論 じ る 例 は 多 い 。 し か し 、 大 体 に お い て そ れ ら の 説 は 、 手 近 な 英 語 や 中 国 語 な ど の 言 語 と の 差 異 を 牧 歌 的 に 列 挙 す る に と ど ま り 、 言 語 学 的 根 拠 に 乏 し い も の が 多 い ︵ サ ピ ア = ウ ォ ー フ の 仮 説 も 参 照 ︶ 。 一 方 、 近 年 で は 日 本 文 化 の 特 殊 性 を 論 す る 文 脈 で あ っ て も 、 出 来 る だ け 多 く の 文 化 圏 を 俯 瞰 し 、 総 合 的 な 視 点 に 立 っ た 主 張 が 多 く 見 ら れ る と い う 。
日 本 語 を 劣 等 も し く は 難 解 、 非 合 理 的 と す る 考 え 方 の 背 景 と し て 、 近 代 化 の 過 程 で 広 ま っ た 欧 米 中 心 主 義 が あ る と 指 摘 さ れ る 。 戦 後 は 、 消 極 的 な 見 方 ば か り で な く 、 ﹁ 日 本 語 は 個 性 的 で あ る ﹂ と 積 極 的 に 評 価 す る 見 方 も 多 く な っ た 。 そ の 変 化 の 時 期 は お よ そ 1 9 8 0 年 代 で あ る と い う 。 い ず れ に し て も 、 日 本 語 は 特 殊 で あ る と の 前 提 に 立 っ て い る 点 で 両 者 の 見 方 は 共 通 す る 。
日 本 語 特 殊 論 は 日 本 国 外 で も 論 じ ら れ る 。 E . ラ イ シ ャ ワ ー に よ れ ば 、 日 本 語 の 知 識 が 乏 し い ま ま 、 日 本 語 は 明 晰 で も 論 理 的 で も な い と 不 満 を 漏 ら す 外 国 人 は 多 い と い う 。 ラ イ シ ャ ワ ー 自 身 は こ れ に 反 論 し 、 あ ら ゆ る 言 語 に は 曖 昧 ・ 不 明 晰 に な る 余 地 が あ り 、 日 本 語 も 同 様 だ が 、 簡 潔 ・ 明 晰 ・ 論 理 的 に 述 べ る こ と を 阻 む 要 素 は 日 本 語 に な い と い う [ 2 4 5 ] 。 共 通 点 の 少 な さ ゆ え に 印 欧 系 言 語 話 者 に は 習 得 が 難 し い と さ れ 、 学 習 に 関 わ る 様 々 な ジ ョ ー ク が 存 在 す る バ ス ク 語 に つ い て 、 フ ラ ン ス の バ イ ヨ ン ヌ に あ る バ ス ク 博 物 館 で は 、 ﹁ か つ て 悪 魔 サ タ ン は 日 本 に い た 。 そ れ が バ ス ク の 土 地 に や っ て き た の で あ る ﹂ と 挿 絵 入 り の 歴 史 が 描 か れ て い る も の が 飾 ら れ て い る 。 こ れ は 同 じ く 印 欧 系 言 語 話 者 か ら み て 習 得 の 難 し い バ ス ク 語 と 日 本 語 を 重 ね 合 わ せ て い る と さ れ る 。
今 日 の 言 語 学 に お い て 、 日 本 語 が 特 殊 で あ る と い う 見 方 自 体 が 否 定 的 で あ る 。 例 え ば 、 日 本 語 に 5 母 音 し か な い こ と が 特 殊 だ と 言 わ れ る こ と が あ る が 、 ク ラ ザ ー ズ の 研 究 に よ れ ば 、 2 0 9 の 言 語 の う ち 、 日 本 語 の よ う に 5 母 音 を 持 つ 言 語 は 55 あ り 、 類 型 と し て 最 も 多 い と い う 。 ま た 語 順 に 関 し て は 、 日 本 語 の よ う に S O V 構 造 を 採 る 言 語 が 約 4 5 % で あ っ て 最 も 多 い の に 対 し て 、 英 語 の よ う に S V O 構 造 を 採 る 言 語 は 3 0 % 強 で あ る ︵ ウ ル タ ン 、 ス テ ィ ー ル 、 グ リ ー ン バ ー グ ら の 調 査 結 果 よ り ︶ 。 こ の 点 か ら 、 日 本 語 は ご く 普 通 の 言 語 で あ る と い う 結 論 が 導 か れ る と さ れ る 。 ま た 言 語 学 者 の 角 田 太 作 は 語 順 を 含 め 19 の 特 徴 に つ い て 1 3 0 の 言 語 を 比 較 し 、 ﹁ 日 本 語 は 特 殊 な 言 語 で は な い 。 し か し 、 英 語 は 特 殊 な 言 語 だ ﹂ と 結 論 し て い る 。
村 山 七 郎 は 、 ﹁ 外 国 語 を 知 る こ と が 少 な い ほ ど 日 本 語 の 特 色 が 多 く な る ﹂ と い う ﹁ 反 比 例 法 則 ﹂ を 主 張 し た と い う 。 日 本 人 自 ら が 日 本 語 を 特 殊 と 考 え る 原 因 と し て は 、 身 近 な 他 言 語 ︵ 英 語 な ど ︶ が 少 な い こ と も 挙 げ ら れ る 。
日 本 で は 古 く 漢 籍 を 読 む た め の 辞 書 が 多 く 編 纂 さ れ た 。 国 内 に お け る 辞 書 編 纂 の 記 録 と し て は 、 天 武 11 年 ︵ 6 8 2 年 ︶ の ﹃ 新 字 ﹄ 44 巻 が 最 古 で あ る が ︵ ﹃ 日 本 書 紀 ﹄ ︶ 、 伝 本 は お ろ か 逸 文 す ら も 存 在 し な い た め 、 書 名 か ら 漢 字 字 書 の 類 で あ ろ う と 推 測 さ れ る 以 外 は 、 い か な る 内 容 の 辞 書 で あ っ た か も 不 明 で あ る 。
奈 良 時 代 に は 、 ﹃ 楊 氏 漢 語 抄 ﹄ や ﹃ 弁 色 立 成 ﹄ と い う 和 訓 を 有 す る 漢 和 辞 書 が 編 纂 さ れ た ら し い が 、 そ れ ぞ れ 逸 文 と し て 残 る の み で 、 詳 細 は 不 明 の ま ま で あ る 。 現 存 す る 最 古 の 辞 書 は 、 空 海 編 と 伝 え ら れ る ﹃ 篆 隷 万 象 名 義 ﹄ ︵ 9 世 紀 ︶ で あ る が 、 中 国 の ﹃ 玉 篇 ﹄ を 模 し た 部 首 配 列 の 漢 字 字 書 で あ り 、 和 訓 は 一 切 な い 。 10 世 紀 初 頭 に 編 纂 さ れ た ﹃ 新 撰 字 鏡 ﹄ は 伝 本 が 存 す る 最 古 の 漢 和 辞 書 で あ り 、 漢 字 を 部 首 配 列 し た 上 で 、 和 訓 を 万 葉 仮 名 で 記 し て い る 。 平 安 時 代 中 期 に 編 纂 さ れ た ﹃ 和 名 類 聚 抄 ﹄ は 、 意 味 で 分 類 し た 漢 語 に お お む ね 和 訳 を 万 葉 仮 名 で 付 し た も の で 、 漢 和 辞 書 で は あ る が 百 科 辞 書 的 色 彩 が 強 い 。 院 政 期 に は 過 去 の 漢 和 辞 書 の 集 大 成 と も 言 え る ﹃ 類 聚 名 義 抄 ﹄ が 編 纂 さ れ 、 同 書 の 和 訓 に 付 さ れ た 豊 富 な 声 点 に よ り 院 政 期 の ア ク セ ン ト 体 系 は ほ ぼ 解 明 さ れ て い る 。
鎌 倉 時 代 に は 百 科 辞 書 ﹃ 二 中 歴 ﹄ や 詩 作 の た め の 実 用 的 韻 書 ﹃ 平 他 字 類 抄 ﹄ ほ か 、 語 源 辞 書 と も い う べ き ﹃ 塵 袋 ﹄ や ﹃ 名 語 記 ﹄ な ど も 編 ま れ る よ う に な っ た 。 ま た 室 町 時 代 に は 、 読 み 書 き が 広 い 階 層 へ 普 及 し 始 め た こ と を 背 景 に 、 漢 詩 を 作 る た め の 韻 書 ﹃ 聚 分 韻 略 ﹄ 、 漢 和 辞 書 ﹃ 倭 玉 篇 ﹄ 、 和 訳 に 通 俗 語 も 含 め た 国 語 辞 書 ﹃ 下 学 集 ﹄ 、 日 常 語 の 単 語 を い ろ は 順 に 並 べ た 通 俗 的 百 科 辞 書 ﹃ 節 用 集 ﹄ な ど の 辞 書 が 編 ま れ た 。 さ ら に 安 土 桃 山 時 代 の 最 末 期 に は 、 イ エ ズ ス 会 の キ リ ス ト 教 宣 教 師 に よ っ て 、 日 本 語 と ポ ル ト ガ ル 語 の 辞 書 ﹃ 日 葡 辞 書 ﹄ が 作 成 さ れ た 。
江 戸 時 代 に は 、 室 町 期 の ﹃ 節 用 集 ﹄ を 元 に し て 多 数 の 辞 書 が 編 集 ・ 刊 行 さ れ た 。 易 林 本 ﹃ 節 用 集 ﹄ ﹃ 書 言 字 考 節 用 集 ﹄ な ど が 主 な も の で あ る 。 そ の ほ か 、 俳 諧 用 語 辞 書 を 含 む ﹃ 世 話 尽 ﹄ 、 語 源 辞 書 ﹃ 日 本 釈 名 ﹄ 、 俗 語 辞 書 ﹃ 志 布 可 起 ﹄ 、 枕 詞 辞 書 ﹃ 冠 辞 考 ﹄ な ど も 編 纂 さ れ た 。 と り わ け 谷 川 士 清 ﹃ 倭 訓 栞 ﹄ 、 太 田 全 斎 ﹃ 俚 言 集 覧 ﹄ 、 石 川 雅 望 ﹃ 雅 言 集 覧 ﹄ は 、 そ れ ぞ れ が き わ め て 大 部 な も の で 、 ﹁ 近 世 期 の 三 大 辞 書 ﹂ と い わ れ る 。
明 治 時 代 に 入 り 、 1 8 8 9 年 か ら 大 槻 文 彦 編 の 小 型 辞 書 ﹃ 言 海 ﹄ が 刊 行 さ れ た 。 こ れ は 、 古 典 語 ・ 日 常 語 を 網 羅 し 、 五 十 音 順 に 見 出 し を 並 べ て 、 品 詞 ・ 漢 字 表 記 ・ 語 釈 を 付 し た 初 の 近 代 的 な 日 本 語 辞 書 で あ っ た 。 ﹃ 言 海 ﹄ は 、 後 の 辞 書 の 模 範 的 存 在 と な り 、 後 に 増 補 版 の ﹃ 大 言 海 ﹄ も 刊 行 さ れ た 。
そ の 後 、 広 く 使 わ れ た 小 型 の 日 本 語 辞 書 と し て は 、 金 沢 庄 三 郎 編 ﹃ 辞 林 ﹄ の ほ か 、 新 村 出 編 ﹃ 辞 苑 ﹄ な ど が あ る 。 第 二 次 世 界 大 戦 中 か ら 戦 後 に か け て は 金 田 一 京 助 編 ﹃ 明 解 国 語 辞 典 ﹄ が よ く 用 い ら れ [ 注 釈 54 ] 、 今 日 の ﹃ 三 省 堂 国 語 辞 典 ﹄ ﹃ 新 明 解 国 語 辞 典 ﹄ に 引 き 継 が れ て い る 。
中 型 辞 書 と し て は 、 第 二 次 世 界 大 戦 前 は ﹃ 大 言 海 ﹄ の ほ か 、 松 井 簡 治 ・ 上 田 万 年 編 ﹃ 大 日 本 国 語 辞 典 ﹄ な ど が 刊 行 さ れ た 。 戦 後 は 新 村 出 編 ﹃ 広 辞 苑 ﹄ な ど が 広 く 受 け 入 れ ら れ て い る 。 現 在 で は 松 村 明 編 ﹃ 大 辞 林 ﹄ を は じ め 、 数 種 の 中 型 辞 書 が 加 わ っ て い る ほ か 、 唯 一 に し て 最 大 の 大 型 辞 書 ﹃ 日 本 国 語 大 辞 典 ﹄ ︵ 約 50 万 語 ︶ が あ る 。
(一) ^ 琉 球 諸 語 を 方 言 と み な し 、 数 に 含 ん だ 場 合 で 、 国 勢 調 査 を 基 に し た 場 合 の 概 数 。 (二) ^ a b 1 9 8 2 年 の ア ン ガ ウ ル 州 憲 法 に よ れ ば 、 ア ン ガ ウ ル 州 の 公 用 語 は 、 パ ラ オ 語 ・ 英 語 ・ 日 本 語 で あ る [ 5 ] 。 日 本 は 法 令 に よ っ て 公 用 語 を 規 定 し て い な い た め 、 ア ン ガ ウ ル 州 は 日 本 語 を 正 式 に 公 用 語 と し て い る 世 界 で 唯 一 の 地 域 で あ る 。 (三) ^ ﹁ に っ ぽ ん ご ﹂ を 見 出 し 語 に 立 て て い る 国 語 辞 典 は 日 本 国 語 大 辞 典 等 少 数 に 留 ま る 。 (四) ^ 裁 判 所 法 第 74 条 、 公 証 人 法 第 27 条 、 会 社 計 算 規 則 第 57 条 第 2 項 、 特 許 法 施 行 規 則 第 2 条 等 。 (五) ^ 韓 国 ・ 朝 鮮 語 も 漢 字 ・ ハ ン グ ル ・ ラ テ ン 文 字 を 併 用 す る が 、 国 家 政 策 に よ っ て 漢 字 の 使 用 は 激 減 し て お り 、 朝 鮮 民 主 主 義 人 民 共 和 国 で は 公 式 に 漢 字 を 廃 止 し て い る ︵ ﹁ 朝 鮮 漢 字 ﹂ や ﹁ ハ ン グ ル 専 用 ﹂ を 参 照 ︶ 。 (六) ^ E t h n o l o g u e ウ ェ ブ 版 で は 、 日 本 で の 話 者 人 口 を 1 9 8 5 年 に 1 億 2 1 0 0 万 人 、 全 世 界 で 1 億 2 2 0 8 万 0 1 0 0 人 と 推 計 し て い る [ 11 ] 。 な お 、 田 野 村 忠 温 が 1 9 7 7 年 か ら 1 9 9 7 年 ま で に 刊 行 さ れ た 10 点 ( 版 の 相 違 を 含 め る と 16 点 ) の 資 料 を 調 査 し た 結 果 、 そ れ ぞ れ に 記 載 さ れ た 日 本 語 の 話 者 人 口 は 最 少 で 1 . 0 2 億 人 、 最 多 で 1 . 2 5 億 人 以 上 だ っ た 。 (七) ^ 表 ( 増 補 2 版 、 2 0 1 0 - 0 1 - 0 3 閲 覧 ) [ リ ン ク 切 れ ] 。 (八) ^ 見 坊 豪 紀 ( 1 9 6 4 ) ︵ 1 9 8 3 年 の ﹃ こ と ば さ ま ざ ま な 出 会 い ﹄ ︵ 三 省 堂 ︶ に 収 録 ︶ で は 、 1 9 6 0 年 代 の ロ サ ン ゼ ル ス お よ び ハ ワ イ の 邦 字 新 聞 の 言 葉 遣 い に 触 れ る 。 井 上 史 雄 ( 1 9 7 1 ) は 、 ハ ワ イ 日 系 人 の 談 話 引 用 を 含 む 報 告 で あ る 。 本 堂 寛 ( 1 9 9 6 ) に よ れ ば 、 1 9 7 9 〜 1 9 8 0 年 の 調 査 に お い て 、 ブ ラ ジ ル 日 系 人 で ﹁ 日 本 語 を う ま く 使 え る ﹂ と 回 答 し た 人 は 、 1 9 5 0 年 以 前 生 ま れ で 2 0 . 6 % 、 以 後 生 ま れ で 8 . 3 % だ と い う 。 (九) ^ ミ ク ロ ネ シ ア で は 日 本 語 教 育 を 受 け た 世 代 が 今 で も 同 世 代 と の 会 話 に 日 本 語 を 利 用 し 、 一 般 に も 日 本 語 由 来 の 語 句 が 多 く 入 っ て い る と い う 。 (十) ^ 第 一 次 世 界 大 戦 後 ︵ 日 独 戦 争 ︶ 、 当 時 ド イ ツ 帝 国 の 植 民 地 で あ っ た 現 在 の パ ラ オ 共 和 国 は 戦 勝 国 の 日 本 に 委 任 統 治 ︵ 南 洋 諸 島 を 参 照 ︶ さ れ る こ と と な っ た 。 (11) ^ 2 0 0 5 年 の パ ラ オ 共 和 国 の 国 勢 調 査 の 結 果 、 2 0 0 5 年 4 月 現 在 ﹁ 自 宅 で 日 本 語 を 話 す 、 5 歳 以 上 の ア ン ガ ウ ル 州 の 居 住 者 、 お よ び 法 定 居 住 者 ﹂ は い な か っ た と 報 告 さ れ て い る [ 20 ] 。 ま た 、 自 身 が 日 本 な い し は 日 本 の 民 族 的 出 身 で あ る と 報 告 し た 人 も い な か っ た [ 21 ] 。 2 0 1 2 年 の パ ラ オ 共 和 国 の 簡 単 な 国 勢 調 査 で は 、 ア ン ガ ウ ル 州 の 総 人 口 1 3 0 人 の う ち ﹁ パ ラ オ 語 と 英 語 以 外 の 言 語 ﹂ で 読 み 書 き が で き る 、 10 歳 以 上 の 居 住 者 は 、 7 人 い る こ と が 報 告 さ れ た [ 22 ] 。 (12) ^ ﹁ 解 明 さ れ る 目 途 も 立 っ て い な い 。 [ 要 出 典 ] ﹂ [ い つ ? ] ﹁ ﹁ 孤 立 し た 言 語 ﹂ が 総 合 的 な 結 論 だ [ 要 出 典 ] ﹂ と 主 張 す る 者 も い る 。 (13) ^ ウ ィ リ ア ム ・ バ ク ス タ ー に よ る 。 平 声 ・ 入 声 は 無 標 、 上 声 は X 、 去 声 は H で 表 す 。 w : B a x t e r ' s t r a n s c r i p t i o n f o r M i d d l e C h i n e s e 参 照 。 (14) ^ イ ェ ー ル 式 表 記 。 (15) ^ ア レ キ サ ン ダ ー ・ ボ ビ ン は 、 朝 鮮 半 島 に い た 日 琉 語 族 の 話 者 が 、 紀 元 前 7 0 0 年 ~ 紀 元 3 0 0 年 頃 に 朝 鮮 半 島 か ら 日 本 列 島 に 移 住 し 、 最 終 的 に 列 島 先 住 言 語 に 取 っ て 代 わ っ た と 主 張 し た [ 41 ] 。 ま た 、 朝 鮮 半 島 に お け る 無 文 土 器 文 化 の 担 い 手 が 現 代 日 本 語 の 祖 先 と な る 日 琉 語 族 に 属 す る 言 語 を 話 し て い た と い う 説 が 複 数 の 学 者 か ら 提 唱 さ れ て い る が 、 こ れ ら の 説 に よ れ ば 、 古 代 満 州 南 部 か ら 朝 鮮 半 島 北 部 に か け て の 地 域 で 確 立 さ れ た 朝 鮮 語 族 に 属 す る 言 語 集 団 が 北 方 か ら 南 方 へ 拡 大 し 当 時 朝 鮮 半 島 中 部 か ら 南 部 に 存 在 し て い た 日 琉 語 族 の 集 団 に 置 き 換 わ っ て い き 、 こ の 過 程 で 南 方 へ 追 い や ら れ る 形 と な っ た 日 琉 語 族 話 者 の 集 団 が 弥 生 人 の 祖 で あ る と さ れ る [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] 。 (16) ^ ﹁ だ が 、 語 例 は 十 分 で は な く 、 推 定 ・ 不 確 定 の 例 を 多 く 含 む 。 [ 要 出 典 ] ﹂ (17) ^ 大 野 晋 ( 1 9 8 7 ) な ど を 参 照 。 研 究 の 集 大 成 と し て 、 大 野 晋 ( 2 0 0 0 ) を 参 照 。 (18) ^ 主 な 批 判 ・ 反 批 判 と し て 、 家 本 太 郎 ・ 児 玉 望 ・ 山 下 博 司 ・ 長 田 俊 樹 ( 1 9 9 6 ) 、 大 野 晋 ( 1 9 9 6 ) 、 山 下 博 司 ( 1 9 9 8 ) な ど が あ る 。 (19) ^ 松 崎 寛 ( 1 9 9 3 ) で は 、 外 来 音 を 多 く 認 め た 1 2 9 モ ー ラ か ら な る 音 韻 体 系 を 示 す 。 (20) ^ 厳 密 に は ア ク セ ン ト 核 と は 、 弁 別 的 な ピ ッ チ の 変 動 を も た ら す モ ー ラ ま た は 音 節 の こ と で 、 下 げ 核 、 上 げ 核 、 昇 り 核 、 降 り 核 の 総 称 で あ る 。 下 げ 核 は 直 後 の モ ー ラ の 音 を 下 げ る 働 き を 持 つ 。 (21) ^ 鈴 木 重 幸 ( 1 9 7 2 ) は 、 5 , 6 の ﹁ 象 は ﹂ は 、 題 目 を 差 し 出 す 機 能 を 持 つ ﹁ 題 目 語 ﹂ と と ら え る 。 た だ し 、 7 の 文 に つ い て ﹁ 象 は ﹂ が 主 語 、 ﹁ 鼻 が 長 い ﹂ を 連 語 述 語 と と ら え る 。 (22) ^ た と え ば 、 東 京 書 籍 ﹃ 新 編 新 し い 国 語 1 ﹄ ︵ 中 学 校 国 語 教 科 書 ︶ で は 、 1 9 7 7 年 の 検 定 本 で は ﹁ 主 語 ・ 述 語 ﹂ を 一 括 し て 扱 っ て い る が 、 1 9 9 6 年 の 検 定 本 で は ま ず 述 語 に つ い て ﹁ 文 を ま と め る 重 要 な 役 割 を す る ﹂ と 述 べ た あ と 、 主 語 に つ い て は 修 飾 語 と 一 括 し て 説 明 し て い る 。 (23) ^ 鈴 木 重 幸 ( 1 9 7 2 ) 、 高 橋 太 郎 他 ( 2 0 0 5 ) な ど 。 (24) ^ ︵ 馬 が 走 り 抜 け る よ り 前 に ︶ 崩 れ た 納 屋 、 で は な い 。 英 語 は ︵ 日 本 語 と 違 い ︶ い わ ゆ る 時 制 の 一 致 が 働 く 言 語 で あ る た め 、 ︵ 本 文 中 候 補 ( 1 ) に 沿 っ た 構 造 解 釈 に お い て は ︶ 馬 が 走 り 抜 け る の と 、 納 屋 が 崩 れ る の が ︵ 時 制 上 ︶ 同 じ 時 点 で あ る こ と に な る 。 (25) ^ ロ シ ア 語 ラ テ ン 翻 字 : m y a u (26) ^ 中 国 語 ラ テ ン 翻 字 : m i a o m i a o (27) ^ 朝 鮮 語 ラ テ ン 翻 字 : y a o n g y a o n g (28) ^ 鈴 木 孝 夫 ( 1 9 7 3 ) , p . 1 5 8 以 下 に も 言 及 が あ る 。 (29) ^ 現 代 語 の 例 は 陳 力 衛 ( 2 0 0 1 ) の 例 示 に よ る 。 (30) ^ 文 化 庁 ( 2 0 0 1 ) ﹃ 公 用 文 の 書 き 表 し 方 の 基 準 ︵ 資 料 集 ︶ 増 補 二 版 ﹄ ︵ 第 一 法 規 ︶ に は 、 1 9 8 1 年 の ﹃ 公 用 文 に お け る 漢 字 使 用 等 に つ い て ﹄ ﹃ 法 令 に お け る 漢 字 使 用 等 に つ い て ﹄ な ど 、 諸 種 の 資 料 が 収 め ら れ て い る 。 (31) ^ 国 立 国 語 研 究 所 ( 1 9 6 3 ) に 記 載 さ れ て い る 表 音 ロ ー マ 字 を 国 際 音 声 記 号 に 直 し た も の 。 (32) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 5 4 ) や 奥 村 三 雄 ( 1 9 5 5 ) な ど 。 (33) ^ 両 者 の 違 い に つ い て は 小 松 英 雄 ( 1 9 9 9 , p p . 1 2 – 1 5 ) や 小 松 英 雄 ( 2 0 0 1 , p p . 1 8 – 1 9 ) に 詳 し い 。 (34) ^ 異 説 と し て 、 服 部 四 郎 の 6 母 音 説 [ 47 ] な ど が あ る 。 (35) ^ 坂 梨 隆 三 ( 1 9 6 9 ) 。 な お 、 坂 梨 に よ れ ば 、 ﹁ 読 む る ﹂ な ど の 形 が 歴 史 的 に 確 認 さ れ る た め 、 ﹁ 読 み 得 ︵ え ︶ る ﹂ か ら ﹁ 読 め る ﹂ が で き た と す る 説 は 誤 り と い う こ と に な る 。 (36) ^ 松 井 栄 一 ( 1 9 8 3 ) , p . 1 3 0 以 下 で 、 明 治 時 代 の 永 井 荷 風 ﹃ を さ め 髪 ﹄ ︵ 1 8 9 9 年 ︶ に ﹁ 左 団 扇 と 来 ︵ こ ︶ れ る 様 な 訳 な ん だ ね 。 ﹂ と い う 例 が あ る こ と な ど を 紹 介 し て い る 。 (37) ^ 林 巨 樹 ・ 斎 藤 正 人 ・ 飯 田 晴 巳 ( 1 9 7 3 ) に は 1 3 4 3 語 の 形 容 詞 が 載 り 、 う ち 文 語 形 が 示 さ れ て い る も の は 1 1 9 2 語 で あ る 。 残 り の 1 5 1 語 の う ち 、 ﹃ 日 本 国 語 大 辞 典 ﹄ 第 2 版 ︵ 小 学 館 ︶ に お い て 明 治 以 降 の 用 例 の み 確 認 で き る も の は ﹁ 甘 酸 っ ぱ い ﹂ ﹁ 黄 色 い ﹂ ﹁ 四 角 い ﹂ ﹁ 粘 っ こ い ﹂ な ど 30 語 程 度 で あ る 。 (38) ^ 2 0 0 6 年 10 月 、 大 阪 ・ 難 波 宮 跡 で ﹁ 皮 留 久 佐 乃 皮 斯 米 之 刀 斯 ﹂ ︵ 春 草 の は じ め の と し ︶ と 記 さ れ た 木 簡 が 発 見 さ れ た 。 7 世 紀 中 頃 の も の と み ら れ る 。 (39) ^ 村 井 実 [ 訳 ・ 解 説 ] ( 1 9 7 9 ) ﹃ ア メ リ カ 教 育 使 節 団 報 告 書 ﹄ ︵ 講 談 社 学 術 文 庫 ︶ に は 、 第 1 次 報 告 書 が 収 め ら れ て い る 。 (40) ^ 万 葉 集 に 記 録 さ れ た 東 国 方 言 は 8 母 音 で は な い こ と が 知 ら れ る [ 1 6 5 ] 。 (41) ^ 文 部 省 ( 1 9 0 4 ) ﹃ 国 定 教 科 書 編 纂 趣 意 書 ﹄ に 収 録 さ れ て い る ﹁ 尋 常 小 学 読 本 編 纂 趣 意 書 ﹂ の ﹁ 第 二 章 形 式 ﹂ に は 、 ﹁ 文 章 ハ 口 語 ヲ 多 ク シ 用 語 ハ 主 ト シ テ 東 京 ノ 中 流 社 会 ニ 行 ハ ル ル モ ノ ヲ 取 リ カ ク テ 国 語 ノ 標 準 ヲ 知 ラ シ メ 其 統 一 ヲ 図 ル ヲ 務 ム ル ト 共 ニ … … ﹂ ︵ p . 5 1 ︶ と あ る 。 (42) ^ 1 9 3 4 年 に 発 足 し た 放 送 用 語 並 発 音 改 善 調 査 委 員 会 の ﹁ 放 送 用 語 の 調 査 に 関 す る 一 般 方 針 ﹂ で は 、 ﹁ 共 通 用 語 は 、 現 代 の 国 語 の 大 勢 に 順 応 し て 大 体 、 帝 都 の 教 養 あ る 社 会 層 に お い て 普 通 に 用 い ら れ る 語 彙 ・ 語 法 ・ 発 音 ・ ア ク セ ン ト ︵ イ ン ト ネ ー シ ョ ン を 含 む ︶ を 基 本 と す る ﹂ と さ れ た 。 (43) ^ 仲 宗 根 政 善 ( 1 9 9 5 ) の 序 で は 、 1 9 0 7 年 生 ま れ の 著 者 が 、 沖 縄 の 小 学 校 時 代 に 経 験 し た 方 言 札 に つ い て ﹁ あ の 不 快 を 、 私 は 忘 れ る こ と が で き な い ﹂ と 記 し て い る 。 (44) ^ 戦 意 高 揚 映 画 ﹃ 決 戦 の 大 空 へ ﹄ ︵ 1 9 4 3 年 ︶ で は 全 国 か ら 集 め ら れ た 海 軍 飛 行 予 科 練 習 生 の 新 入 隊 員 ら が 、 指 導 教 官 か ら 訛 り が あ る と 指 摘 さ れ 、 軍 隊 の 言 葉 を 使 え と 指 導 さ れ る シ ー ン が あ る 。 (45) ^ 石 黒 修 ( 1 9 6 0 ) に は 茨 城 な ま り を 笑 わ れ て 人 を 刺 し た 少 年 の 記 事 が 紹 介 さ れ て い る 。 ま た 、 ﹃ 毎 日 新 聞 ﹄ 宮 城 版 ︵ 1 9 9 6 年 8 月 24 日 付 ︶ に は 1 9 6 4 年 に 秋 田 出 身 の 少 年 工 員 が 言 葉 を 笑 わ れ 同 僚 を 刺 し た 事 件 そ の 他 が 紹 介 さ れ て い る [ 1 7 2 ] 。 (46) ^ た と え ば 、 脇 田 順 一 ( 1 9 3 8 ) ︵ 1 9 7 5 年 に 国 書 刊 行 会 か ら 復 刻 版 ︶ の 緒 言 に は 、 ﹁ 児 童 を し て 純 正 な る 国 語 生 活 を 営 ま し む る に は 先 づ 其 の 方 言 を 検 討 し 之 が 醇 化 矯 正 に 力 を 致 さ な け れ ば な ら ぬ ﹂ と あ る 。 ま た 、 方 言 学 者 の グ ロ ー タ ー ス は ﹁ 日 本 の 方 言 研 究 家 た ち は 、 方 言 に よ っ て 標 準 語 を 豊 か に し よ う と い う 考 え だ か ら 、 結 局 は 、 標 準 語 に よ る 日 本 語 の 統 一 が 重 要 な 目 標 に な る 。 ﹂ と 指 摘 さ れ て い る 。 (47) ^ 柳 田 國 男 ( 1 9 3 0 ) ︵ 1 9 8 0 年 に 岩 波 文 庫 ︶ で は 、 方 言 が 中 央 を 中 心 に 同 心 円 状 の 分 布 を な す こ と ︵ 周 圏 分 布 ︶ が 示 さ れ る 。 (48) ^ 盲 目 で あ っ た 春 庭 の 苦 心 は 足 立 巻 一 ( 1 9 7 4 ) ︵ 1 9 9 0 年 に 新 装 版 、 1 9 9 5 年 に 朝 日 学 芸 文 庫 、 2 0 1 5 年 に 中 公 文 庫 ︶ で 知 ら れ る 。 (49) ^ 浜 野 保 樹 ( 2 0 0 5 ) , p . 1 2 に よ る と ﹁ ﹃ キ ル ・ ビ ル ﹄ な ど の 映 画 で 非 日 本 人 俳 優 同 士 が 日 本 語 で 会 話 し て い る の は 、 日 本 の ﹁ カ ッ コ よ さ ﹂ の 高 さ を 表 す 証 左 ﹂ と い う 。 (50) ^ ﹁ 梅 は ま だ 咲 か な く っ て よ ﹂ ﹁ 桜 の 花 は ま だ 咲 か な い ん だ わ ﹂ の よ う な 言 葉 遣 い の 文 末 の こ と 。 (51) ^ 体 系 化 を 試 み る 本 格 的 な 著 作 と し て は 米 川 明 彦 ( 1 9 9 8 ) な ど が あ る 。 (52) ^ 見 坊 豪 紀 ( 1 9 7 7 ) は 、 1 9 7 5 年 頃 の 日 本 語 ブ ー ム を 検 証 し た 文 章 で あ る 。 (53) ^ 野 元 菊 雄 ( 1 9 7 9 ) な ど で す で に 主 張 さ れ て い た が 、 論 議 が 起 こ っ た の は 1 9 8 8 年 の こ と で あ る 。 ち な み に 、 自 然 言 語 を 単 純 化 し て 新 し い 国 際 補 助 語 を 作 る 試 み は 他 に も 、 ﹁ ベ ー シ ッ ク 英 語 ﹂ 、 ﹁ ス ペ シ ャ ル ・ イ ン グ リ ッ シ ュ ﹂ 、 ﹁ 無 活 用 ラ テ ン 語 ﹂ な ど が あ る 。 (54) ^ 実 質 的 に は 見 坊 豪 紀 が 独 力 で 編 纂 し た も の で 、 山 田 忠 雄 や 金 田 一 春 彦 が 補 佐 し た
(一) ^ 日 本 国 語 大 辞 典 ︵ 小 学 館 ︶ の 日 本 語 の 項 に よ る と ﹁ ニ ホ ン ゴ ﹂ 。 (二) ^ a b “ ﹁ 鼻 濁 音 ﹂ 来 世 紀 ほ ぼ 消 滅 ? も と も と 使 わ な い 地 域 も … ” . 朝 日 新 聞 デ ジ タ ル ( 朝 日 新 聞 社 ) . ( 2 0 1 5 年 3 月 5 日 ) . オ リ ジ ナ ル の 2 0 1 5 年 3 月 5 日 時 点 に お け る ア ー カ イ ブ 。 . https://web.archive.org/web/20150305002557/https://www.asahi.com/articles/ASH2W5751H2WUCVL00X.html (三) ^ 日 本 国 語 大 辞 典 ︵ 小 学 館 ︶ の 日 本 語 の 項 に よ る と ﹁ ニ ッ ポ ン ゴ ﹂ 。 (四) ^ " V ä r l d e n s 1 0 0 s t ö r s t a s p r å k 2 0 1 0 " ( T h e W o r l d ' s 1 0 0 L a r g e s t L a n g u a g e s i n 2 0 1 0 ) , i n N a t i o n a l e n c y k l o p e d i n (五) ^ “ C o n s t i t u t i o n o f t h e S t a t e o f A n g a u r ” . P a c i f i c D i g i t a l L i b r a r y . 2 0 2 1 年 3 月 15 日 閲 覧 。 “ T h e t r a d i t i o n a l P a l a u a n l a n g u a g e , p a r t i c u l a r l y t h e d i a l e c t s p o k e n b y t h e p e o p l e o f A n g a u r S t a t e , s h a l l b e t h e l a n g u a g e o f t h e S t a t e o f A n g a u r . P a l a u a n , E n g l i s h a n d J a p a n e s e s h a l l b e t h e o f f i c i a l l a n g u a g e s . ” (六) ^ H a m m a r s t r ö m , H a r a l d ; F o r k e l , R o b e r t ; H a s p e l m a t h , M a r t i n e t a l . , e d s ( 2 0 1 6 ) . “ J a p a n e s e ” . G l o t t o l o g 2 . 7 . J e n a : M a x P l a n c k I n s t i t u t e f o r t h e S c i e n c e o f H u m a n H i s t o r y . http://glottolog.org/resource/languoid/id/nucl1643 (七) ^ “ J a p a n e s e L a n g u a g e ” . M I T . 2 0 0 9 年 5 月 13 日 閲 覧 。 (八) ^ “ ︵ 1 ︶ 世 界 の 母 語 人 口 ︵ 上 位 20 言 語 ︶ ‥ 文 部 科 学 省 ” . w w w . m e x t . g o . j p . 2 0 2 1 年 10 月 24 日 閲 覧 。 (九) ^ 呉 善 花 ( 2 0 0 8 ) . (十) ^ 南 不 二 男 ﹁ 日 本 語 ・ 総 説 ﹂ ( 亀 井 孝 , 河 野 六 郎 & 千 野 栄 一 1 9 9 7 ) を 参 照 (11) ^ h t t p s : / / w w w . e t h n o l o g u e . c o m / s h o w _ l a n g u a g e . a s p ? c o d e = j p n ( 2 0 1 0 - 0 1 - 0 3 閲 覧 ) (12) ^ 田 野 村 忠 温 ( 1 9 9 7 ) . (13) ^ a b “ A p r e n d e r j a p o n é s ” . ウ ル グ ア イ O R T 大 学 ︵ ス ペ イ ン 語 版 ︶ . オ リ ジ ナ ル の 2 0 2 1 年 3 月 12 日 時 点 に お け る ア ー カ イ ブ 。 . https://web.archive.org/web/20210312112022/https://www.ort.edu.uy/centro-de-idiomas/aprender-japones (14) ^ 南 不 二 男 ﹁ 日 本 語 ・ 総 説 ﹂ ( 亀 井 孝 , 河 野 六 郎 & 千 野 栄 一 1 9 9 7 ) な ど を 参 照 。 (15) ^ 真 田 信 治 ( 2 0 0 2 ) . (16) ^ 青 柳 森 ( 1 9 8 6 ) ﹁ 台 湾 山 地 紀 行 ﹂ ﹃ 東 京 消 防 ﹄ 1 9 8 6 年 10 月 ︵ ウ ェ ブ 版 は 、 “ 日 本 ペ ン ク ラ ブ ‥ 電 子 文 藝 館 ・ 地 球 ウ ォ ー カ ー ” . 2 0 1 2 年 7 月 15 日 時 点 の オ リ ジ ナ ル よ り ア ー カ イ ブ 。 2 0 1 2 年 2 月 15 日 閲 覧 。 ︶ 。 (17) ^ 真 田 信 治 & 簡 月 真 ( 2 0 0 8 ) . (18) ^ 矢 崎 幸 生 ( 2 0 0 1 ) , p p . 1 0 – 1 1 . (19) ^ ﹁ “ 2 0 0 5 年 度 パ ラ オ 共 和 国 国 勢 調 査 ” . 2 0 0 8 年 2 月 16 日 時 点 の オ リ ジ ナ ル よ り ア ー カ イ ブ 。 2 0 1 2 年 6 月 26 日 閲 覧 。 ︵ 英 語 、 P D F ︶ ﹂ パ ラ オ 共 和 国 統 計 局 、 2 0 0 5 年 12 月 、 26 頁 。 (20) ^ “ 2 0 0 5 C e n s u s o f P o p u l a t i o n & H o u s i n g ” . B u r e a u o f B u d g e t & P l a n n i n g . 2 0 2 1 年 3 月 15 日 閲 覧 。 (21) ^ “ 2 0 0 5 C e n s u s M o n o g r a p h F i n a l R e p o r t ” . B u r e a u o f B u d g e t & P l a n n i n g . 2 0 2 1 年 3 月 15 日 閲 覧 。 (22) ^ “ 2 0 1 3 R O P S t a t i s t i c a l Y e a r b o o k ” . B u r e a u o f B u d g e t & P l a n n i n g . 2 0 2 1 年 3 月 15 日 閲 覧 。 (23) ^ 2 0 1 5 年 度 海 外 日 本 語 教 育 機 関 調 査 結 果 ︵ 速 報 値 ︶ ( P D F ) (24) ^ 文 化 庁 調 査 ﹁ 平 成 27 年 度 国 内 の 日 本 語 教 育 の 概 要 ﹂ ( 2 0 1 5 ) 。 (25) ^ 長 田 俊 樹 ( 2 0 2 0 ) , p . 3 2 9 . (26) ^ 斎 藤 純 男 ( 2 0 1 0 ) , p . 1 8 9 . (27) ^ 佐 佐 木 隆 ( 1 9 7 8 ) . (28) ^ a b 亀 井 孝 , 大 藤 時 彦 & 山 田 俊 雄 ( 1 9 6 3 ) . (29) ^ 藤 岡 勝 二 ( 1 9 0 8 a ) 、 藤 岡 勝 二 ( 1 9 0 8 b ) 、 藤 岡 勝 二 ( 1 9 0 8 c ) な ど 。 (30) ^ a b 有 坂 秀 世 ( 1 9 3 1 ) ︵ 1 9 5 7 年 の ﹃ 国 語 音 韻 史 の 研 究 増 補 新 版 ﹄ ︵ 三 省 堂 ︶ に 収 録 ︶ (31) ^ ﹁ ア ル タ イ 型 ﹂ ( 亀 井 孝 , 河 野 六 郎 & 千 野 栄 一 1 9 9 6 ) (32) ^ 大 江 孝 男 ( 1 9 8 1 ) , p . 1 2 1 . (33) ^ a b 伊 藤 英 人 ( 2 0 1 9 ) . (34) ^ W h i t m a n , J o h n ( 2 0 1 1 ) , “ N o r t h e a s t A s i a n L i n g u i s t i c E c o l o g y a n d t h e A d v e n t o f R i c e A g r i c u l t u r e i n K o r e a a n d J a p a n ” , R i c e 4 ( 3 - 4 ) : 1 4 9 – 1 5 8 , d o i : 1 0 . 1 0 0 7 / s 1 2 2 8 4 - 0 1 1 - 9 0 8 0 - 0 (35) ^ a b c 伊 藤 英 人 ( 2 0 2 1 b ) . (36) ^ a b c d e f g h 板 橋 義 三 ( 2 0 0 3 ) . (37) ^ a b c d e f g h K i - M o o n L e e & S . R o b e r t R a m s e y ( 2 0 1 1 ) . (38) ^ ( 2 0 1 7 ) , “ O r i g i n s o f t h e J a p a n e s e L a n g u a g e ” , O x f o r d R e s e a r c h E n c y c l o p e d i a o f L i n g u i s t i c s , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , d o i : 1 0 . 1 0 9 3 / a c r e f o r e / 9 7 8 0 1 9 9 3 8 4 6 5 5 . 0 1 3 . 2 7 7 . (39) ^ 伊 藤 英 人 ( 2 0 2 1 a ) . (40) ^ U n g e r , J a m e s M . ( 2 0 1 3 ) . C o m p a r i n g t h e J a p a n e s e a n d K o r e a n L a n g u a g e s : C u l l i n g B o r r o w e d W o r d s . D e p a r t m e n t o f E a s t A s i a n L a n g u a g e s & L i t e r a t u r e s T h e O h i o S t a t e U n i v e r s i t y . (41) ^ V o v i n , A l e x a n d e r ( 2 0 1 7 ) , “ O r i g i n s o f t h e J a p a n e s e L a n g u a g e ” , O x f o r d R e s e a r c h E n c y c l o p e d i a o f L i n g u i s t i c s , O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s , d o i : 1 0 . 1 0 9 3 / a c r e f o r e / 9 7 8 0 1 9 9 3 8 4 6 5 5 . 0 1 3 . 2 7 7 . (42) ^ B e l l w o o d , P e t e r ( 2 0 1 3 ) . T h e G l o b a l P r e h i s t o r y o f H u m a n M i g r a t i o n . M a l d e n : B l a c k w e l l P u b l i s h i n g . I S B N 9 7 8 1 1 1 8 9 7 0 5 9 1 (43) ^ V o v i n , A l e x a n d e r ( 2 0 1 3 ) . “ F r o m K o g u r y o t o T a m n a : S l o w l y r i d i n g t o t h e S o u t h w i t h s p e a k e r s o f P r o t o - K o r e a n ” . K o r e a n L i n g u i s t i c s 15 ( 2 ) : 2 2 2 – 2 4 0 . (44) ^ L e e , K i - M o o n ; R a m s e y , S . R o b e r t ( 2 0 1 1 ) . A H i s t o r y o f t h e K o r e a n l a n g u a g e . C a m b r i d g e : C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . I S B N 9 7 8 - 0 - 5 2 1 - 6 6 1 8 9 - 8 (45) ^ W h i t m a n , J o h n ( 2 0 1 1 ) . “ N o r t h e a s t A s i a n L i n g u i s t i c E c o l o g y a n d t h e A d v e n t o f R i c e A g r i c u l t u r e i n K o r e a a n d J a p a n ” . R i c e 4 ( 3 - 4 ) : 1 4 9 – 1 5 8 . d o i : 1 0 . 1 0 0 7 / s 1 2 2 8 4 - 0 1 1 - 9 0 8 0 - 0 . (46) ^ U n g e r , J . M a r s h a l l ( 2 0 0 9 ) . T h e r o l e o f c o n t a c t i n t h e o r i g i n s o f t h e J a p a n e s e a n d K o r e a n l a n g u a g e s . H o n o l u l u : U n i v e r s i t y o f H a w a i ? i P r e s s . I S B N 9 7 8 - 0 - 8 2 4 8 - 3 2 7 9 - 7 (47) ^ a b c d 服 部 四 郎 ( 1 9 5 9 ) ︵ 1 9 9 9 年 に 岩 波 文 庫 ︶ 。 (48) ^ 中 川 裕 ( 2 0 0 5 ) . (49) ^ 泉 井 久 之 助 ( 1 9 5 3 ) ︵ 1 9 7 5 年 の ﹃ マ ラ イ = ポ リ ネ シ ア 諸 語 比 較 と 系 統 ﹄ ︵ 弘 文 堂 ︶ に 収 録 ︶ (50) ^ 服 部 四 郎 ( 1 9 5 0 ) ︵ 1 9 6 0 年 の ﹃ 言 語 学 の 方 法 ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ (51) ^ 亀 井 孝 ( 1 9 5 6 ) . (52) ^ 窪 薗 晴 夫 ( 1 9 9 9 ) , p p . 3 5 – 3 7 . (53) ^ 窪 薗 晴 夫 ( 1 9 9 9 ) , p p . 3 4 – 3 5 . (54) ^ 窪 薗 晴 夫 ( 1 9 9 9 ) , p . 1 0 0 . (55) ^ 窪 薗 晴 夫 ( 1 9 9 9 ) , p . 3 5 . (56) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 5 0 ) ︵ 1 9 6 7 年 に ﹁ ﹁ 里 親 ﹂ と ﹁ 砂 糖 屋 ﹂ ― 引 き 音 節 の 提 唱 ﹂ と し て ﹃ 国 語 音 韻 の 研 究 ﹄ ︵ 東 京 堂 出 版 ︶ に 収 録 ︶ な ど を 参 照 。 (57) ^ a b c d e ﹁ 音 韻 総 覧 ﹂ ( 徳 川 宗 賢 1 9 8 9 ) (58) ^ 窪 薗 晴 夫 ( 1 9 9 9 ) , p . 5 9 . (59) ^ a b 上 田 萬 年 ( 1 9 0 3 ) , p p . 3 2 – 3 9 . (60) ^ ﹁ ハ 行 子 音 の 分 布 と 変 化 ﹂ 、 田 中 伸 一 、 2 0 0 8 、 東 京 大 学 教 養 学 部 の 講 義 ﹁ 言 語 科 学 2 ﹂ に て (61) ^ 上 野 善 道 ( 1 9 8 9 ) . (62) ^ 酒 井 邦 嘉 ( 2 0 0 2 ) , p . 1 0 5 . (63) ^ a b 三 上 章 ( 1 9 7 2 ) . (64) ^ 三 上 章 ( 1 9 6 0 ) . (65) ^ 森 重 敏 ( 1 9 6 5 ) . (66) ^ 北 原 保 雄 ( 1 9 8 1 ) . (67) ^ a b 橋 本 進 吉 ( 1 9 3 4 ) ︵ 1 9 4 8 年 の ﹃ 国 語 法 研 究 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 2 冊 ︶ ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ (68) ^ 石 神 照 雄 ( 1 9 8 3 ) な ど 。 (69) ^ 鈴 木 一 彦 ( 1 9 5 9 ) . (70) ^ a b 時 枝 誠 記 ( 1 9 5 0 ) . (71) ^ 山 田 孝 雄 ( 1 9 0 8 ) . (72) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 8 8 ) . (73) ^ 国 立 国 語 研 究 所 ( 1 9 6 4 a ) . (74) ^ 中 野 洋 ( 1 9 8 1 ) . (75) ^ 柴 田 武 & 山 田 進 ( 2 0 0 2 ) . (76) ^ ﹁ 人 称 代 名 詞 ﹂ ( 亀 井 孝 , 河 野 六 郎 & 千 野 栄 一 1 9 9 6 ) (77) ^ 改 田 昌 直 ・ ク ロ イ ワ カ ズ ・ ﹃ リ ー ダ ー ズ 英 和 辞 典 ﹄ 編 集 部 [ 編 ] ( 1 9 8 5 ) ﹃ 漫 画 で 楽 し む 英 語 擬 音 語 辞 典 ﹄ ︵ 研 究 社 ︶ に よ る 。 (78) ^ 山 口 仲 美 ( 2 0 0 3 ) , p . 1 . (79) ^ 浅 野 鶴 子 ( 1 9 7 8 ) , p . 1 . (80) ^ 手 塚 治 虫 ( 1 9 7 7 ) , p . 1 1 2 . (81) ^ 堀 淵 清 治 ( 2 0 0 6 ) . (82) ^ 金 田 一 京 助 他 [ 編 ] ( 2 0 0 2 ) ﹃ 新 選 国 語 辞 典 ﹄ 第 8 版 ︵ 小 学 館 ︶ 裏 見 返 し 。 (83) ^ 柳 田 国 男 ( 1 9 3 8 ) ﹁ 方 言 の 成 立 ﹂ ﹃ 方 言 ﹄ 8 - 2 ︵ 1 9 9 0 年 の ﹃ 柳 田 國 男 全 集 22 ﹄ ︵ ち く ま 文 庫 ︶ に 収 録 p . 1 8 1 ︶ (84) ^ H o w m a n y w o r d s a r e t h e r e i n t h e E n g l i s h l a n g u a g e ? [ リ ン ク 切 れ ] (85) ^ 野 村 雅 昭 ( 1 9 9 8 ) . (86) ^ 柴 田 武 ( 1 9 8 8 ) な ど を 参 照 。 (87) ^ 大 槻 文 彦 ( 1 8 8 9 ) ﹁ 語 法 指 南 ﹂ ︵ 国 語 辞 書 ﹃ 言 海 ﹄ に 収 録 ︶ 。 (88) ^ 佐 久 間 鼎 ( 1 9 3 6 ) ︵ 1 9 8 3 年 く ろ し お 出 版 か ら 増 補 版 ︶ 。 (89) ^ 佐 竹 昭 広 ( 1 9 5 5 ) ︵ 2 0 0 0 年 に ﹃ 萬 葉 集 抜 書 ﹄ ︵ 岩 波 現 代 文 庫 ︶ に 収 録 ︶ (90) ^ 小 松 英 雄 ( 2 0 0 1 ) , 5 ﹁ 日 本 語 の 色 名 ﹂ . (91) ^ B r e n t B e r l i n & P a u l K a y ( 1 9 6 9 ) , B a s i c c o l o r t e r m s : t h e i r u n i v e r s a l i t y a n d e v o l u t i o n , B e r k e l e y : U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a P r e s s . (92) ^ 大 矢 透 ( 1 8 9 9 ) , p . 2 6 な ど 。 (93) ^ a b 柴 田 武 ( 1 9 6 8 ) ︵ 1 9 7 9 年 の ﹃ 日 本 の 言 語 学 第 5 巻 意 味 ・ 語 彙 ﹄ ︵ 大 修 館 書 店 ︶ に 収 録 ︶ (94) ^ 田 中 章 夫 ( 1 9 7 8 ) 第 2 章 の 図 。 (95) ^ 樺 島 忠 夫 ( 1 9 8 1 ) p . 1 8 、 お よ び p . 1 7 6 以 下 。 (96) ^ 岩 田 麻 里 ( 1 9 8 3 ) , p . 1 8 3 . (97) ^ 以 上 は 石 綿 敏 雄 ( 2 0 0 1 ) の 例 示 に よ る 。 (98) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 9 1 ) , p . 5 4 . (99) ^ ﹃ ラ ン ダ ム ハ ウ ス 英 和 大 辞 典 ﹄ ︵ 小 学 館 ︶ の 当 該 項 目 に よ る 。 (100) ^ 鈴 木 孝 夫 ( 1 9 9 0 ) , p p . 1 3 2 – 1 3 3 . (101) ^ 梅 棹 忠 夫 ( 1 9 7 2 ) な ど 。 (102) ^ 鈴 木 孝 夫 ( 1 9 7 5 ) な ど 。 (103) ^ a b 村 島 定 行 ( 2 0 0 9 ) . (104) ^ 高 島 俊 男 ( 2 0 0 1 ) . (105) ^ a b 西 尾 実 ・ 久 松 潜 一 [ 監 修 ] ( 1 9 6 9 ) ﹃ 国 語 国 字 教 育 史 料 総 覧 ﹄ ︵ 国 語 教 育 研 究 会 ︶ 。 (106) ^ 北 条 忠 雄 ( 1 9 8 2 ) , p p . 1 6 1 – 1 6 2 . (107) ^ a b 山 浦 玄 嗣 ( 1 9 8 6 ) ︵ 1 9 8 9 年 に 改 訂 補 足 版 ︶ (108) ^ 西 岡 敏 & 仲 原 穣 ( 2 0 0 0 ) , p . 1 5 4 . (109) ^ 笹 原 宏 之 ( 2 0 0 6 ) , p . 1 4 2 - 1 4 5 . (110) ^ 半 澤 幹 一 ﹁ 談 話 体 ﹂ ( 飛 田 良 文 2 0 0 7 , p . 2 6 6 ) (111) ^ 庵 功 雄 ・ 高 梨 信 乃 ・ 中 西 久 実 子 ・ 山 田 敏 弘 ( 2 0 0 0 ) , p . 3 2 4 . (112) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 2 8 ) ﹁ 国 語 学 史 概 説 ﹂ ︵ 1 9 8 3 年 ﹃ 国 語 学 史 ・ 国 語 特 質 論 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 9 ・ 10 冊 ︶ ﹄ 岩 波 書 店 ︶ p . 4 の 図 に ﹁ 独 語 体 ・ 対 話 体 ﹂ の 語 が 出 て い る 。 (113) ^ 金 水 敏 ( 2 0 0 3 ) . (114) ^ J ・ V ・ ネ ウ ス ト プ ニ ー ( 1 9 7 4 ) . (115) ^ 菊 地 康 人 ( 1 9 9 4 ) . (116) ^ 文 化 審 議 会 ﹃ 敬 語 の 指 針 ︵ 文 化 審 議 会 答 申 ︶ ﹄ ︵ P D F ︶ 文 化 庁 、 2 0 0 7 年 2 月 2 日 。https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/sokai/sokai_6/pdf/keigo_tousin.pdf 。 (117) ^ a b 宮 地 裕 ( 1 9 7 1 ) . (118) ^ a b 宮 地 裕 ( 1 9 7 6 ) . (119) ^ 蒲 谷 宏 , 川 口 義 一 & 坂 本 惠 ( 1 9 9 8 ) . (120) ^ 入 江 敦 彦 ( 2 0 0 5 ) . (121) ^ a b c Y a m a g i w a , J o s e p h K . ( 1 9 6 7 ) . “ O n D i a l e c t I n t e l l i g i b i l i t y i n J a p a n ” . A n t h r o p o l o g i c a l L i n g u i s t i c s 9 ( 1 ) : 4 , 5 , 1 8 . (122) ^ 東 条 操 ( 1 9 5 4 ) . (123) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 6 4 a ) . (124) ^ 山 口 幸 洋 ( 2 0 0 3 ) , p p . 2 3 8 – 2 4 7 . (125) ^ 和 田 実 ( 1 9 6 6 ) . (126) ^ 山 口 幸 洋 ( 2 0 0 2 ) . (127) ^ 吉 田 則 夫 ( 1 9 8 4 ) . (128) ^ 都 竹 通 年 雄 ( 1 9 8 6 ) . (129) ^ 松 森 晶 子 ( 2 0 0 3 ) , p . 2 6 2 . (130) ^ 服 部 四 郎 ( 1 9 5 1 ) . (131) ^ 山 口 幸 洋 ( 2 0 0 3 ) , p p . 9 – 6 1 . (132) ^ 金 田 一 春 彦 ﹁ 音 韻 ﹂ (133) ^ 平 山 輝 男 ( 1 9 9 8 ) ﹁ 全 日 本 の 発 音 と ア ク セ ン ト ﹂ N H K 放 送 文 化 研 究 所 編 ﹃ N H K 日 本 語 発 音 ア ク セ ン ト 辞 典 ﹄ ︵ 日 本 放 送 出 版 協 会 ︶ 。 (134) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 1 7 ) ﹁ 国 語 仮 名 遣 研 究 史 上 の 一 発 見 ‥ 石 塚 龍 麿 の 仮 名 遣 奥 山 路 に つ い て ﹂ ﹃ 帝 国 文 学 ﹄ 2 6 - 1 1 ︵ 1 9 4 9 年 の ﹃ 文 字 及 び 仮 名 遣 の 研 究 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 3 冊 ︶ ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ 。 (135) ^ 大 野 晋 ( 1 9 5 3 ) , p . 1 2 6 以 下 に 研 究 史 の 紹 介 が あ る 。 (136) ^ 大 野 晋 ( 1 9 8 2 ) , p . 6 5 . (137) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 2 8 ) ﹁ 波 行 子 音 の 変 遷 に つ い て ﹂ ﹃ 岡 倉 先 生 記 念 論 文 集 ﹄ ︵ 1 9 5 0 年 の ﹃ 国 語 音 韻 の 研 究 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 4 冊 ︶ ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ 。 (138) ^ 土 井 忠 生 ( 1 9 5 7 ) , p p . 1 5 8 – 1 5 9 . (139) ^ a b c 佐 藤 武 義 ( 1 9 9 5 ) , p p . 8 4 – 9 7 . (140) ^ a b c d e 佐 藤 武 義 ( 1 9 9 5 ) , p p . 9 8 – 1 1 4 . (141) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 4 2 ) ﹁ 国 語 音 韻 史 の 研 究 ﹂ ︵ 1 9 6 6 年 の ﹃ 国 語 音 韻 史 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 6 冊 ︶ ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ p . 3 5 2 。 (142) ^ 外 山 映 次 ( 1 9 7 2 ) , p p . 2 3 8 – 2 3 9 . (143) ^ 桜 井 茂 治 ( 1 9 6 6 ) . (144) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 3 8 ) ︵ 1 9 8 0 年 の ﹃ 古 代 国 語 の 音 韻 に 就 い て 他 2 篇 ﹄ ︵ 岩 波 文 庫 ︶ に 収 録 ︶ 。 (145) ^ ﹁ 外 来 語 の 表 記 ﹂ ︵ 1 9 9 1 年 6 月 内 閣 告 示 ︶ に よ る 。 (146) ^ 奥 村 三 雄 ( 1 9 6 8 ) . (147) ^ 阿 部 秋 生 ・ 秋 山 虔 ・ 今 井 源 衛 [ 校 注 ] ( 1 9 7 0 ) ﹃ 日 本 古 典 文 学 全 集 源 氏 物 語 一 ﹄ ︵ 小 学 館 ︶ p . 2 7 4 。 (148) ^ 湯 沢 幸 吉 郎 ( 1 9 5 4 ) . (149) ^ 小 松 英 雄 ( 1 9 9 9 ) , p p . 9 0 – 9 1 . (150) ^ 池 田 亀 鑑 ・ 岸 上 慎 二 ・ 秋 山 虔 [ 校 注 ] ( 1 9 5 8 ) ﹃ 日 本 古 典 文 学 大 系 19 枕 草 子 紫 式 部 日 記 ﹄ p . 6 8 。 (151) ^ a b 楳 垣 実 ( 1 9 4 3 ) . (152) ^ a b 宮 島 達 夫 ( 1 9 7 1 ) (153) ^ 宮 島 達 夫 ( 1 9 6 7 ) . (154) ^ ﹃ 都 鄙 新 聞 ﹄ 第 一 1 8 6 8 ︵ 慶 応 4 ︶ 年 5 月 ︵ 1 9 2 8 年 の ﹃ 明 治 文 化 全 集 ﹄ 17 ︵ 日 本 評 論 社 ︶ に 収 録 ︶ 。 (155) ^ 国 立 国 語 研 究 所 ( 1 9 6 4 b ) . (156) ^ a b c 国 立 国 語 研 究 所 ( 2 0 0 6 ) . (157) ^ 以 上 、 伝 来 の 時 代 認 定 は 、 ﹃ コ ン サ イ ス カ タ カ ナ 語 辞 典 ﹄ 第 3 版 ︵ 三 省 堂 ︶ に よ る 。 (158) ^ 山 田 孝 雄 ( 1 9 4 0 ) ︵ 1 9 5 8 年 に 訂 正 版 ︶ の ﹁ 第 一 章 序 説 ﹂ 。 (159) ^ 遠 藤 好 英 ﹁ 和 語 ﹂ ( 飛 田 良 文 2 0 0 7 , p . 1 5 2 ) (160) ^ 岩 田 麻 里 ( 1 9 8 3 ) . (161) ^ 山 田 孝 雄 ( 1 9 3 7 ) , p . 4 1 以 下 な ど を 参 照 。 (162) ^ 斎 藤 達 哉 ( 2 0 1 9 年 3 月 8 日 ) . “ 漢 字 は い つ か ら 日 本 に あ る の で す か 。 そ れ ま で 文 字 は な か っ た の で し ょ う か ” . こ と ば 研 究 館 . 国 立 国 語 研 究 所 . 2 0 2 2 年 11 月 30 日 閲 覧 。 (163) ^ 読 み 書 き 能 力 調 査 委 員 会 ( 1 9 5 1 ) . (164) ^ 高 木 市 之 助 ・ 小 澤 正 夫 ・ 渥 美 か を る ・ 金 田 一 春 彦 [ 校 注 ] ( 1 9 5 8 ) ﹃ 日 本 古 典 文 学 大 系 33 平 家 物 語 下 ﹄ p . 1 0 1 。 用 字 は 一 部 改 め た 。 (165) ^ 前 田 富 棋 ﹁ 奈 良 時 代 ﹂ ( 佐 藤 喜 代 治 1 9 7 3 , p p . 6 0 – 6 4 ) (166) ^ 真 田 信 治 ( 1 9 9 1 ) . (167) ^ 日 本 放 送 協 会 ( 1 9 6 5 ) , p . 4 2 7 . (168) ^ 伊 沢 修 二 ( 1 9 0 9 ) . (169) ^ ﹁ 全 国 の 方 言 を 録 音 ﹂ ﹃ 日 本 経 済 新 聞 ﹄ 昭 和 28 年 6 月 19 日 9 面 (170) ^ 白 勢 彩 子 ( 2 0 1 9 ) . (171) ^ “ こ と ば Q & A - 国 語 研 の 窓 ” . こ と ば 研 究 館 . 国 立 国 語 研 究 所 . 2 0 2 2 年 12 月 5 日 閲 覧 。 (172) ^ 毎 日 新 聞 地 方 部 特 報 班 ( 1 9 9 8 ) に 収 録 。 (173) ^ 橋 本 典 尚 ( 2 0 0 4 ) . (174) ^ 加 藤 正 信 ( 1 9 8 3 ) 。 調 査 は 1 9 7 9 〜 1 9 8 1 年 で 、 回 答 者 は 首 都 圏 ・ 茨 城 県 ・ 東 北 地 方 を 中 心 に 全 国 に 及 ぶ 。 (175) ^ ﹃ 朝 日 新 聞 ﹄ 夕 刊 1 9 9 5 年 6 月 22 日 付 な ど 。 (176) ^ 陣 内 正 敬 ( 2 0 0 3 ) ﹁ 関 西 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 広 が り ― 首 都 圏 で は ﹂ ﹃ 文 部 省 平 成 14 年 度 科 研 費 成 果 報 告 書 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 地 域 性 と 関 西 方 言 の 影 響 力 に つ い て の 広 域 的 研 究 ﹄ 。 (177) ^ ﹃ 産 経 新 聞 ﹄ 2 0 0 5 年 9 月 18 日 付 。 (178) ^ コ ト バ 探 偵 団 ( 2 0 0 5 ) な ど 。 (179) ^ 井 上 史 雄 & 鑓 水 兼 貴 ( 2 0 0 2 ) . (180) ^ W . A . グ ロ ー タ ー ス ( 1 9 8 4 ) , p . 1 5 3 . (181) ^ a b 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 3 0 5 . (182) ^ 山 本 真 吾 ( 2 0 1 3 ) , p . 2 6 1 . (183) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 4 . (184) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 5 . (185) ^ 小 松 英 雄 ( 1 9 7 9 ) . (186) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 7 . (187) ^ 橋 本 進 吉 ( 1 9 2 8 ) ﹁ 国 語 学 史 概 説 ﹂ ︵ 1 9 8 3 年 の ﹃ 国 語 学 史 ・ 国 語 特 質 論 ︵ 橋 本 進 吉 博 士 著 作 集 第 9 ・ 10 冊 ︶ ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ に 収 録 ︶ p . 6 1 。 (188) ^ a b c 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 8 . (189) ^ a b 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 9 . (190) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 3 ) , p p . 2 4 – 4 7 . (191) ^ a b 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 3 0 6 . (192) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p p . 3 0 8 – 3 0 9 . (193) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 1 . (194) ^ a b c d 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 2 . (195) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 6 . (196) ^ a b 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 4 . (197) ^ 大 久 保 正 ( 1 9 7 5 ) . (198) ^ 田 辺 正 男 ( 1 9 7 5 ) . (199) ^ 野 口 武 彦 ( 1 9 7 5 ) . (200) ^ 福 島 邦 道 ( 1 9 7 6 ) . (201) ^ 杉 田 昌 彦 ( 2 0 1 5 ) . (202) ^ a b 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 7 . (203) ^ 仁 田 義 雄 ( 2 0 2 1 ) , p p . 1 3 4 – 1 3 5 . (204) ^ 安 田 尚 道 ( 2 0 0 3 ) ︵ 後 に 安 田 尚 道 ( 2 0 2 3 ) 収 録 ︶ (205) ^ 安 田 尚 道 ( 2 0 0 4 ) ︵ 後 に 安 田 尚 道 ( 2 0 2 3 ) 収 録 ︶ (206) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 5 . (207) ^ 猿 田 知 之 ( 1 9 9 3 ) , p p . 1 4 – 4 0 . (208) ^ 山 東 功 ( 2 0 0 2 ) , p p . 1 1 – 1 2 . (209) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p p . 3 0 0 – 3 0 1 . (210) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p p . 2 9 9 – 3 0 0 . (211) ^ 本 名 信 行 & 岡 本 佐 智 子 ( 2 0 0 0 ) . (212) ^ “ 世 界 の 日 本 語 教 育 ” . 2 0 1 5 年 1 月 17 日 時 点 の オ リ ジ ナ ル よ り ア ー カ イ ブ 。 2 0 0 5 年 3 月 4 日 閲 覧 。 も 参 照 。 (213) ^ D o u g l a s M c G r a y ︵ 神 山 京 子 訳 ︶ ( 2 0 0 3 ) ﹁ 世 界 を 闊 歩 す る 日 本 の カ ッ コ よ さ ﹂ ﹃ 中 央 公 論 ﹄ ︵ 2 0 0 3 年 5 月 号 ︶ (214) ^ 2 0 2 3 D u o l i n g o L a n g u a g e R e p o r t (215) ^ “ M I S C T h i s i s t h e L a n g u a g e E a c h C o u n t r y W a n t s t o L e a r n t h e M o s t ” ( 英 語 ) . V i s u a l C a p i t a l i s t ( 2 0 2 1 年 8 月 27 日 ) . 2 0 2 1 年 10 月 1 日 閲 覧 。 (216) ^ 井 上 史 雄 ( 2 0 0 1 ) , p . 6 9 . (217) ^ 月 刊 宝 島 編 集 部 ( 1 9 8 7 ) 、 田 野 村 忠 温 ( 2 0 0 3 ) な ど 。 (218) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 6 4 b ) . (219) ^ 金 田 一 春 彦 ( 1 9 6 5 ) . (220) ^ 宇 野 義 方 ( 1 9 6 4 ) ﹁ 日 本 語 は 乱 れ て い な い か ― 金 田 一 春 彦 氏 に 反 論 ﹂ ﹃ 朝 日 新 聞 ﹄ 夕 刊 1 9 6 4 年 12 月 5 日 付 。 (221) ^ 国 立 国 語 研 究 所 ( 1 9 5 5 ) . (222) ^ a b 山 口 仲 美 ( 2 0 0 7 ) , p p . 1 5 – 1 7 . (223) ^ 井 上 史 雄 ( 1 9 9 4 ) . (224) ^ 米 川 明 彦 ( 1 9 9 6 ) . (225) ^ 北 原 保 雄 ( 2 0 0 8 ) . (226) ^ “ K Y イ ヤ … 言 葉 で 伝 え ず ﹁ 察 し 合 う ﹂ が 人 気 ” . Y O M I U R I O N L I N E ( 読 売 新 聞 社 ) . ( 2 0 0 9 年 9 月 4 日 ) . オ リ ジ ナ ル の 2 0 0 9 年 9 月 6 日 時 点 に お け る ア ー カ イ ブ 。 . https://archive.is/20090906012139/https://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090904-OYT1T00983.htm (227) ^ 山 根 一 眞 ( 1 9 8 6 ) . (228) ^ ﹃ 週 刊 読 売 ﹄ 1 9 9 6 年 9 月 15 日 号 。 (229) ^ ﹃ A E R A ﹄ 1 9 9 7 年 6 月 30 日 号 。 (230) ^ ﹃ HA ・ YA ・ RI 系 文 字 マ ス タ ー ノ ー ト ﹄ ︵ ア ス キ ー 1 9 9 7 ︶ な ど 。 (231) ^ N H K 総 合 テ レ ビ ﹁ お 元 気 で す か 日 本 列 島 ・ 気 に な る こ と ば ﹂ 2 0 0 4 年 2 月 18 日 な ど 。 (232) ^ ﹃ ギ ャ ル 文 字 へ た 文 字 公 式 B O O K ﹄ ︵ 実 業 之 日 本 社 2 0 0 4 ︶ な ど 。 (233) ^ “ 渦 巻 き 絵 文 字 は ﹁ 台 風 ﹂ で は な く ﹁ ま い っ た ﹂ 、 バ イ ド ゥ が 調 査 ” . I N T E R N E T W a t c h ( 2 0 0 9 年 11 月 20 日 ) . 2 0 2 2 年 11 月 30 日 閲 覧 。 (234) ^ ﹃ 毎 日 新 聞 ﹄ 2 0 0 6 年 10 月 5 日 付 な ど 。 (235) ^ 飯 間 浩 明 ( 2 0 1 0 ) , p p . 5 – 1 4 . (236) ^ 菊 地 康 人 ( 1 9 9 6 ) . (237) ^ “ 岩 波 新 書 ﹁ 現 代 ﹂ つ か み 続 け て 70 年 ” . Y O M I U R I O N L I N E ( 読 売 新 聞 社 ) . ( 2 0 0 8 年 6 月 3 日 ) . https://www.yomiuri.co.jp/book/news/20080603bk07.htm [ リ ン ク 切 れ ] (238) ^ 以 上 、 部 数 の 数 字 は ﹃ 朝 日 新 聞 ﹄ 夕 刊 2 0 0 2 年 11 月 18 日 付 に よ る 。 (239) ^ 志 賀 直 哉 ( 1 9 6 4 ) ﹁ 国 語 問 題 ﹂ ﹃ 改 造 ﹄ 1 9 4 6 年 4 月 号 ︵ 1 9 7 4 年 の ﹃ 志 賀 直 哉 全 集 第 7 巻 ﹄ ︵ 岩 波 書 店 ︶ p . 3 3 9 - 3 4 3 に 収 録 ︶ 。 (240) ^ 森 恭 三 ( 1 9 5 9 ) . (241) ^ 金 文 京 ( 2 0 1 0 ) . (242) ^ 内 田 樹 ( 2 0 0 9 ) . (243) ^ a b 柴 谷 方 良 ( 1 9 8 1 ) . (244) ^ a b 松 村 一 登 ( 1 9 9 5 ) . (245) ^ E d w i n O . R e i s c h a u e r ( 1 9 7 7 ) T h e J a p a n e s e , T o k y o : C h a r l e s E . T u t t l e , p . 3 8 5 - 3 8 6 . (246) ^ 城 生 佰 太 郎 & 松 崎 寛 ( 1 9 9 5 ) , p p . 2 8 – 2 9 . (247) ^ 角 田 太 作 ( 1 9 9 1 ) . (248) ^ W . A . グ ロ ー タ ー ス ( 1 9 8 4 ) , p p . 1 8 1 – 1 8 2 . (249) ^ a b 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p . 1 2 . (250) ^ a b c d 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 8 6 . (251) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p . 1 3 . (252) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 1 8 – 1 9 . (253) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 2 – 2 3 . (254) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 5 – 2 7 . (255) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 4 0 – 4 1 . (256) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 4 2 – 4 3 . (257) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 4 4 – 4 5 . (258) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 5 4 – 5 5 . (259) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 7 6 – 7 7 . (260) ^ 山 東 功 ( 2 0 1 9 ) , p . 2 9 8 . (261) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 1 4 – 2 1 5 . (262) ^ a b 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 2 8 – 2 2 9 . (263) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 2 4 – 2 2 5 . (264) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 3 0 – 2 3 1 . (265) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 3 2 – 2 3 3 . (266) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 3 8 – 2 3 9 . (267) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 1 8 – 2 1 9 . (268) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 3 4 – 2 3 5 . (269) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 4 0 – 2 4 1 . (270) ^ 沖 森 卓 也 ( 2 0 2 3 ) , p p . 2 3 6 – 2 3 7 .
● 城 生 佰 太 郎 、 松 崎 寛 ﹃ 日 本 語 ﹁ ら し さ ﹂ の 言 語 学 ﹄ 講 談 社 、 1 9 9 5 年 1 月 。 I S B N 4 0 6 2 0 6 5 6 9 X 。 ● 蒲 谷 宏 、 川 口 義 一 、 坂 本 惠 ﹃ 敬 語 表 現 ﹄ 大 修 館 書 店 、 1 9 9 8 年 10 月 。 ● 西 岡 敏 、 仲 原 穣 ﹃ 沖 縄 語 の 入 門 ‥ た の し い ウ チ ナ ー グ チ ﹄ 白 水 社 、 2 0 0 0 年 4 月 。 ● 庵 功 雄 ・ 高 梨 信 乃 ・ 中 西 久 実 子 ・ 山 田 敏 弘 ﹃ 初 級 を 教 え る 人 の た め の 日 本 語 文 法 ハ ン ド ブ ッ ク ﹄ ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク 、 2 0 0 0 年 5 月 。 ● 高 橋 太 郎 他 ﹃ 日 本 語 の 文 法 ﹄ ひ つ じ 書 房 、 2 0 0 5 年 4 月 。 I S B N 9 7 8 4 8 9 4 7 6 2 4 4 2 。 ● K i - M o o n L e e ; S . R o b e r t R a m s e y ( 2 0 1 1 ) . A h i s t o r y o f t h e K o r e a n l a n g u a g e . C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . I S B N 9 7 8 0 5 2 1 6 6 1 8 9 8
● 読 み 書 き 能 力 調 査 委 員 会 編 ﹃ 日 本 人 の 読 み 書 き 能 力 ﹄ 東 京 大 学 出 版 部 、 1 9 5 1 年 4 月 。 ● 東 條 操 編 ﹃ 日 本 方 言 学 ﹄ 吉 川 弘 文 館 、 1 9 5 4 年 1 月 。 ● 亀 井 孝 、 大 藤 時 彦 、 山 田 俊 雄 編 ﹃ 日 本 語 の 歴 史 1 ‥ 民 族 の こ と ば の 誕 生 ﹄ 平 凡 社 、 1 9 6 3 年 9 月 。 ● 日 本 放 送 協 会 編 ﹃ 日 本 放 送 史 ・ 上 ﹄ 日 本 放 送 出 版 協 会 、 1 9 6 5 年 。 ● 宮 島 達 夫 編 ﹃ 古 典 対 照 語 い 表 ﹄ 笠 間 書 院 ︿ 笠 間 索 引 叢 刊 4 ﹀ 、 1 9 7 1 年 9 月 。 ● 佐 藤 喜 代 治 編 ﹃ 国 語 史 ﹄ 桜 楓 社 、 1 9 7 3 年 。 ● 月 刊 宝 島 編 集 部 編 ﹃ V O W ‥ 現 代 下 世 話 大 全 ‥ ま ち の ヘ ン な も の 大 カ タ ロ グ ﹄ J I C C 出 版 局 、 1 9 8 7 年 10 月 。 ● 亀 井 孝 、 河 野 六 郎 、 千 野 栄 一 編 ﹃ 日 本 列 島 の 言 語 ‥ 言 語 学 大 辞 典 セ レ ク シ ョ ン ﹄ 三 省 堂 、 1 9 9 7 年 1 月 。 I S B N 4 3 8 5 1 5 2 0 7 1 。 ● 毎 日 新 聞 東 京 本 社 地 方 部 特 報 班 編 ﹃ 東 北 ﹁ 方 言 ﹂ も の が た り ﹄ 無 明 舎 出 版 、 1 9 9 8 年 3 月 。 I S B N 4 8 9 5 4 4 1 8 0 6 。 ● 本 名 信 行 、 岡 本 佐 智 子 編 ﹃ ア ジ ア に お け る 日 本 語 教 育 ﹄ 三 修 社 、 2 0 0 0 年 5 月 。 I S B N 4 3 8 4 0 1 5 9 6 8 。 ● コ ト バ 探 偵 団 編 ﹃ ザ ・ 方 言 ブ ッ ク ﹄ 日 本 文 芸 社 、 2 0 0 5 年 7 月 。 I S B N 4 5 3 7 2 5 2 9 8 7 。 ● 国 立 国 語 研 究 所 編 ﹃ 現 代 雑 誌 2 0 0 万 字 調 査 語 彙 表 ﹄ 2 0 0 6 年 3 月 。
W.A.グロータース 著、柴田武 訳『私は日本人になりたい:知りつくして愛した日本文化のオモテとウラ』大和出版、1984年10月。ISBN 4804720561 。 藤岡勝二「日本語の位置」『國學院雜誌』第14巻第8号、1908年8月、1-9頁。 藤岡勝二「日本語の位置(二)」『國學院雜誌』第14巻第10号、1908年10月、14-23頁。 藤岡勝二「日本語の位置(三)」『國學院雜誌』第14巻第11号、1908年11月、12-20頁。 有坂秀世「国語にあらはれる一種の母音交替について」『音声の研究』第4号、1931年。 橋本進吉「国語音韻の変遷」『国語と国文学』第15巻第10号、1938年10月。 金田一春彦「「五億」と「業苦」:引き音節の提唱」『国語と国文学』第27巻第1号、1950年1月。 金田一春彦「東西両アクセントのちがいが出来るまで」『文学』第22巻第8号、岩波書店、1954年8月。 金田一春彦「日本語は乱れていない:紫式部、近松 、芭蕉 などは典型的な悪文家だった」『文芸春秋』第42巻第12号、文芸春秋、1964年12月。 金田一春彦「泣いて明治の文豪を斬る:続日本語は乱れていない」『文芸春秋』第43巻第4号、文芸春秋、1965年4月。 服部四郎「Phoneme, Phone, and Compound Phone 」『言語研究』第16号、日本言語学会、1950年8月。 泉井久之助「日本語と南島諸語:系譜関係か寄与の関係か」『民族学研究』第17巻第2号、1953年3月。 佐竹昭広「古代日本語における色名の性格」『国語国文』第24巻第6号、1955年6月。 奥村三雄「東西アクセント分離の時期:外来語のアクセント」『国語国文』第24巻第12号、1955年12月。 亀井孝「「音韻」の概念は日本語に有用なりや」『国文学攷』第15号、1956年3月。 鈴木一彦「副詞の整理」『国語と国文学』第36巻第12号、1959年12月。 石黒修「方言の悲劇」『言語生活』第108号、筑摩書房、1960年9月。 見坊豪紀「アメリカの邦字新聞を読む」『言語生活』第157号、筑摩書房、1964年10月。 和田実「第一次アクセントの発見:伊吹島」『国語研究』第22号、國學院大學、1966年5月。 桜井茂治「形容詞音便の一考察:源氏物語を中心として」『立教大学日本文学』第16号、1966年6月。 柴田武「語彙体系としての親族名称:トルコ語・朝鮮語・日本語」『アジア・アフリカ言語文化研究』第1号、東京外国語大学、1968年2月。 坂梨隆三「いわゆる可能動詞の成立について」『国語と国文学』第46巻第11号、1969年11月。 井上史雄「ハワイ日系人の日本語と英語」『言語生活』第236号、筑摩書房、1971年5月。 大久保正 「〈書評〉足立巻一著「やちまた」上・下」『國文學 』第20巻第3号、学燈社 、1975年3月、29頁。 田辺正男「〈わたしの読んだ本〉足立巻一著「やちまた」上・下」『言語生活』第284号、筑摩書房 、1975年5月、91-92頁。 野口武彦 「言霊のありか:足立巻一「やちまた」をめぐって」『すばる 』第20号、集英社 、1975年6月、196-203頁。 福島邦道「〈紹介〉足立巻一著「やちまた」」『国語学』第104号、国語学会、1976年3月、121-123頁。 野元菊雄「「簡約日本語」のすすめ:日本語が世界語になるために」『言語』第8巻第3号、大修館書店、1979年3月。 中野洋「『分類語彙表』の語数」『計量国語学』第12巻第8号、計量国語学会、1981年3月。 柴谷方良「日本語は特異な言語か?:類型論から見た日本語」『言語』第10巻第12号、大修館書店、1981年12月。 加藤正信「方言コンプレックスの現状」『言語生活』第377号、筑摩書房、1983年5月。 松崎寛「外来語音と現代日本語音韻体系 」『日本語と日本文学』第18号、筑波大学、1993年8月、22-30頁。 松村一登「世界の中の日本語:日本語は特異な言語か」『アジア・アフリカ言語文化研究所通信』第84号、アジア・アフリカ言語文化研究所、1995年7月。 家本太郎・児玉望・山下博司・長田俊樹「「日本語=タミル語同系説」を検証する:大野晋『日本語の起源 新版』をめぐって」『日本研究(国際文化研究センター紀要)』第13号、1996年3月、248-169頁。 大野晋「「タミル語=日本語同系説に対する批判」を検証する 」『日本研究(国際文化研究センター紀要)』第15号、1996年12月、247-186頁。 山下博司「大野晋氏のご批判に答えて:「日本語=タミル語同系説」の手法を考える 」『日本研究(国際文化研究センター紀要)』第17号、1998年2月、372-342頁。 田野村忠温「日本語の話者数順位について:日本語は世界第六位の言語か? 」『国語学』189集、1997年6月、37-41頁。 田野村忠温「中国の日本語」『日本語学』第22巻第12号、明治書院、2003年11月、6-15頁。 陳力衛「和製漢語と語構成」『日本語学』第20巻第9号、明治書院、2001年8月、40-49頁。 安田尚道「石塚龍麿と橋本進吉:上代特殊仮名遣の研究史を再検討する」『國語學』第54巻第2号、2003年4月、1-14頁。 安田尚道「橋本進吉は何を発見しどう呼んだのか:上代特殊仮名遣の研究史を再検討する」『國語と國文學 』第81巻第3号、2004年3月、1-15頁。 橋本典尚「「ネサヨ運動」と「ネハイ運動」」『東洋大学大学院紀要』第40号、2004年3月、250-237頁。 中川裕「アイヌ語にくわわった日本語」『国文学・解釈と鑑賞』第70巻第1号、至文堂、2005年1月、96-104頁。 真田信治、簡月真「台湾における日本語クレオールについて 」『日本語の研究』第4巻第2号、日本語学会、2008年4月。 飯間浩明 「「日本語ブーム」はあったのか、そしてあるのか」『日本語学 』第29巻第5号、明治書院、2010年5月、4-15頁。 杉田昌彦「〈書評〉足立巻一『やちまた』(中公文庫版)の読後に」『鈴屋学会報』第32号、鈴屋学会、2015年12月、70-77頁。 白勢彩子「学習指導要領における「方言」を辿る 」『東京学芸大学紀要. 人文社会科学系. I』第70巻、2019年1月、15–22頁。 伊藤英人「「高句麗地名」中の倭語と韓語 」『専修人文論集』第105巻、2019年11月、365-421頁。 伊藤英人「濊倭同系論 」『KOTONOHA』第224号、古代文字資料館、2021年7月、1-70頁。