土砂災害
表示
(山崩れから転送)



土砂災害︵どしゃさいがい︶とは、大雨や地震に伴う斜面崩壊︵がけ崩れ・土砂崩れ︶、地すべり、土石流などにより人の生命や財産が脅かされる災害[注 1][1]。
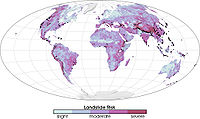
衛星観測を基に作成された世界の土砂災害リスク分布図。紫色は危険性 が高い。
後述︵#原因︶の通り、土砂災害は起伏に富んだ土地で起きやすい。日本は、国土の7割を山地・丘陵地が占め、地殻変動が活発な変動帯︵環太平洋変動帯︶にあり、火山も多いことから土砂災害が起きやすい。そのうえ、平野が少なく土地利用に制約があるため、特に第二次世界大戦後の経済成長や人口増加に伴って郊外の台地や丘陵地までもが都市化し、土砂災害が居住地域に及びやすくなった経緯がある[8]。
一方、国土の広い国、例えばアメリカやカナダ、ロシアなどでは、こちらも広大な山地を有するものの、地すべりなどが発生して道路や住宅が被害を受けても、場所を移して復旧するほうが安上がりなため、同じ場所で再建し更に崩壊を防止する工事などを行うことは少ない[9]。例えばアメリカの場合、工事を行う場合も、政府・行政が行う公共工事は、道路への土砂流入を防ぐ、農地などの土砂流出︵侵食︶・土砂流入︵堆積︶を防ぐといった目的が主であり、住宅を守る目的では行われない。これは、斜面崩壊などの災害について、リスクを織り込んで居住を選択するという、受益者負担の原則を重く見る考え方が根底にあるとみられる[10]。
また学問においても、欧米では粘土質地盤の性質を扱う土質力学が広く受け入れられ、土砂の粒径や土質・移動形態・移動速度などを基準とする細かい﹁地すべり分類﹂[注 2] が発達し、防災を意識することが少ない。対する日本では、土木工学が岩や礫質地盤、斜面安定などの理論に長け、分類も地﹁すべり﹂と斜面﹁崩壊﹂の区分を行う独自のものになっている[9][11]。
定義[編集]
地表の斜面を構成する岩石や土砂は重力を受けており、何らかの要因により不安定になると下方へ移動する。その様式には、落石、地すべり、崩壊、流砂、土石流などいくつかの種類がある。これらの現象は全て一括りにして、﹁マスムーブメント︵英: mass movement︶﹂[2]、または﹁斜面移動︵英: slope movement︶﹂、あるいは﹁︵広義の︶地すべり︵英: landslide︶﹂[注 2][3] という用語で、専門的には定義される。 ﹁土砂災害﹂は、上記のマスムーブメント︵あるいは斜面移動、広義の地すべり︶により発生する災害全般を指す[4]。ただ、斜面崩壊・地すべり・土石流の3分類が定着しており、この3つが土砂災害であると説明する場合がある。特に砂防、防災の場面でこのような分類・説明をすることが多い[5]。なお、この概念は世界共通ではない︵cf.#日本の特質性︶[注 3]。 類義語に、斜面で起こるという点に着目した﹁斜面災害﹂[3][6]、山地で起こるという点に着目した﹁山地災害﹂があり[7]、場合により同義としたり使い分けたりする。このほか、地盤を人為的に削ったり盛ったりした造成地で起こる法面崩壊などの災害も、土砂災害に含めることがある[8]。日本の特質性[編集]
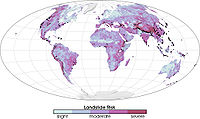
原因[編集]
発生機構[編集]

詳細は「斜面安定解析」を参照
斜面を構成する土塊や岩盤はふつう、重力や摩擦力などの作用の結果、﹁斜面を移動させようとする力﹂よりも、それに﹁抵抗する力﹂が大きい状態で安定している。ここで、前者が大きくなったり後者が小さくなったりすると、バランスが崩れて変形を生じる[12]。土質力学上、これは土塊の剛性を超える外力によるピーク破壊と呼ばれ、破壊時の外力をピーク強度という[12]。また、斜面安定を考える上では、仮定したすべり面において土塊を滑動させるせん断破壊である[13][14]。
斜面を移動させようとする﹁せん断応力﹂が、それに抵抗する﹁せん断抵抗力﹂を上回ると滑動が始まる。後者に対する前者の比を安全率Fsといい、斜面安定の指標とする。実際には、クーロンの破壊規準により求められる土の強度定数などを組み入れた解析法を用い、計算を行う[15]。
ピーク破壊の直前に生じる微小変形に対応して、斜面崩壊の実験等では崩壊直前に極めて低速のクリープと呼ばれる変形が生じることが確かめられている[12]。このクリープは土砂災害のいわゆる前兆現象を生じさせる原因の1つでもある。
斜面崩壊や地すべりの発生は、土塊に含まれる水の作用が関わる場合が多い。これは、浸透した水が間隙水圧を増加させ、土粒子の有効応力が減少して、せん断抵抗力が低下しせん断破壊に至るメカニズムである。土中の水を抜く、あるいは水を浸み込ませないような工事により、間隙水圧を減少させることが対策として有効である[16]。
素因[編集]
地球上において、土砂災害の主な素因は、地殻変動、火山活動、寒冷な気候である。地殻変動は、断層運動による地盤の破砕、造山運動による地盤の隆起などを起こす。火山は、崩れやすい火山灰や火砕流などの堆積物︵火山砕屑物︶を一度に大量に降らせ、起伏のある溶岩地形を造る。高緯度や高山などの寒冷地域では、凍結融解を繰り返す周氷河作用が崩れやすい地質を造る[17]。 世界における巨大な崩壊・地すべり︵崩壊体積107 - 109m3︶の発生地域は、インドネシア、ネパール、中国、日本、台湾、フィリピン、ニュージーランド、アメリカ、カナダ、ペルーなどが挙げられ、ほとんどが変動帯︵環太平洋変動帯あるいはアルプス・ヒマラヤ変動帯︶に位置する[17]。なお、例外的にノルウェーやスウェーデンなどでは、氷河の後退による岩盤地すべりやクイッククレイ地すべりが起こる[17]。 その他の素因として、強風化花崗岩︵真砂土︶や火山性土壌︵シラスなど︶、厚い堆積土︵レス︶といった局地的な地質、また、過放牧や大気汚染による植生の破壊、過度な採鉱、山沿いや台地の市街地化といった人為的・社会的要因も挙げられる[17]。誘因[編集]
土砂災害の誘因︵引き金︶には、集中豪雨や台風などによる大雨[18]、地震、火山活動、天然ダムの決壊、人工的な掘削などがある[17]。日本の土砂災害の状況[編集]
近世以降[編集]
歴史的に見ると、日本では江戸時代を通して山林の荒廃が進行し続け、江戸末期から明治初期にかけては最も荒廃した状態にあったと考えられる。これは、この時代、日本人が生活する上で、生活に必要な物、建材、船や荷車、燃料、肥料などの大部分に木材や草を利用し、森林に大きく依存していたためである。庶民は、生活苦から株や根まで掘り起こして燃料等に用いていた時期もあるほどだった。各地で焼き畑の禁止や植林、伐採禁止・入山禁止などの御触れが出されたが、効果は乏しかったと考えられる。集落に近い里山を中心に伐採された木の無い山林が広がり、本州の広い範囲、特に西日本にはハゲ山が多く分布していたと推定される。これにより、山林では激しい土壌浸食や表層崩壊が多発した[19]。 明治に入ると、産業革命により木材の代替品が開発・普及し始めるが、工業化や戦争などで木材の需要は高く、山奥まで森林鉄道を敷いて伐採が進められた地域もあった。一方、防災のため明治政府は治水三法[注 4] を制定し、国家として﹁治山﹂や﹁砂防﹂の事業を開始した。ヨーロッパからの技術導入により、ハゲ山の土砂を安定させる山腹工や砂防ダムの技術も発達した[20]。 第二次世界大戦後には、復興のための木材需要により、伐採が急速に奥地まで拡大してしまう。一方で、植林政策により伐採地は急速に人工林化され、ハゲ山はほとんどなくなる。また高度経済成長期には、安価な輸入木材が国産に取って代わり、伐採は急速に減少する。しかし、崩壊防止機能が弱い若齢林︵若い人工林︶などで、表層崩壊や土石流が多発した。さらに、都市化により市街地のがけ崩れが顕在化した。1960年代後半から1970年代前半には、毎年100名以上が土砂災害の犠牲となり、自然災害犠牲者の半数以上を占める状況となった。これに対し、がけ崩れ防止や砂防ダムなどのハード対策が進められる。その後、戦後大量に植林された森林が成長して崩壊防止機能が高まり、ハード対策の進展も相まって犠牲者は次第に減少してきた[21][22]。現代[編集]
1979年 - 2008年までの30年間には、平均すると、およそ年間1,000件程度の土砂災害が発生している[23]。また、2009年 - 2013年までの5年間も同じく年間1,000件程度である[24]。ただし、気象条件などにより200件位から2,000件超と大きく変動がある[23]。例えば、2004年は新潟・福島豪雨や福井豪雨、多数の台風上陸などにより土砂災害が多発し、2,537件に上った[24]。 死者数も年により変動があり、例えば2003年 - 2013年の11年間では、2007年は0人、2010年は11人だった一方、上記のように各地で土砂災害が多発した2004年は62人、台風12号による紀伊半島大水害で犠牲者が多く出た2011年は85人に上った[24]。 自然災害全体で見ても、土砂災害被害の比率は低くない。1980年代から2000年代まで、年変動は大きいものの、1割から4割あり、年によっては6割に達している[22]。斜面崩壊・地すべり・土石流の形態と被害[編集]
| 種類 /(主な別名) |
特徴 | 被害の様相 |
|---|---|---|
| 斜面崩壊[13] /(山崩れ[13][25]、崖崩れ[13][25]、土砂崩れ[13]、岩崩れ[26]、急傾斜地崩壊) |
||
| 地すべり[6] |
|
|
| 土石流 /(鉄砲水[32]、山津波[32]、泥流[32]) |
|
その他の土砂災害[編集]

「落石 (自然災害)」も参照
地震による崩壊・地すべり
地震動による力は斜面に対し、角度が急になったり重量を増したりしたような効果を及ぼす。これにより、雨による崩壊はあまり起こらない傾斜10 - 20度の緩い斜面でも崩壊を起こし、大雨の時よりも広い範囲で崩壊が起こる。表土がない急な崖でも崩壊を起こす。周囲より盛り上がった部分は地震動が増幅されやすく、大雨で通常崩れないような、山の尾根や稜線部分なども崩壊する。また、崩壊の規模が大きくなりやすく、土砂の移動距離も長くなりやすい。なお、突発的なため避難することが難しい[38]。
流木による被害
土石流や洪水では、河川上流の崩壊に伴い発生した流木が一緒に流下し、被害を拡大させることがある。特に、流木が直撃して家屋や橋などを破壊する被害や、土石流が流れ下る途中、橋や水路などに流木が詰まり、土砂や泥水が溢れて周辺の家屋に及ぶ被害は、危険性が高い。なお、樹種では広葉樹林よりも針葉樹林の方が、面積当たりの流木体積が大きい傾向にある[39]。
造成地の災害
法面崩壊などの災害。切土や盛土、谷埋めや腹付けなど人工的に盛られた地盤は地質的に若く緩い状態にあるため、自然に形成された地盤に比べると崩壊や流動化を起こしやすい。更に、住宅地などに利用されることが多く、災害が発生すれば人命や財産に大きな影響を及ぼし得るため、造成後に起こりうる現象を想定して工事を行わなければならない。日本では、宅地造成及び特定盛土等規制法︵1961年制定︶が宅地などにおける地盤の安全性に基準を設け、崖への擁壁の設置や排水施設の設置などを定めている[40]。
山体崩壊・岩屑なだれ
地震や噴火により山地の一部が大規模に崩壊するもの。落差が大きいため、崩れた土砂は高速で長距離を流れ下る︵岩屑なだれ︶。大きなものでは厚さ100m以上の土砂が時速100km以上で谷を流れ下り、水平の移動距離は高低差の10倍程度に達する。火山地帯、特に成層火山で起こりやすい。海に流れ下ると津波を発生させる[41]。

傾きのある斜面の崩壊を防ぐ構造物を擁壁という。写真は古典的な石垣 方式の擁壁の工事の様子。
対策[編集]

被害を防ぐため、初歩的には危険な土地の利用を避けること、やむを得ず利用する場合には、崩壊などを防ぐ土木設備を設けたり、前兆現象や雨の降り方などを参考に適切なタイミングで避難を行うことが有効である。
危険地帯は、特に法律に基づく土砂災害警戒区域に指定されているところやその基礎調査が行われているところ、また都道府県が調査した土砂災害危険箇所に含まれているところなどである︵cf.#行政が公表している危険地帯︶。ただし、これらに該当しなくても、山間部や、周りに斜面や崖のある土地では注意が必要である[42][43]。
危険地帯において土砂災害を避けるためには、雨の降り方と各種の前兆現象に注意し、前兆に気付いたときは、速やかに市町村や近隣住民などに知らせるとともに、自らも率先して避難することが有効である[42][44]。
注意すべき時期は、雨の量が多いとき、雨が長期間続いているとき、さらに雨が止んだ後しばらくの間である[42]。また、大きな地震の後もしばらくの間注意が必要である[42]。日本では、気象庁がこれまでの雨量と数時間先までの予想雨量を基に大雨警報や土砂災害警戒情報などを発表しており、これが目安になる︵cf.#土砂災害が起きやすくなっていることを知らせる情報︶[45]。

斜面崩落の後、コンクリートまたはモルタルを格子状に成形して斜面を 支える﹁法枠工﹂が行われている様子︵2012年、大阪府︶
その土地の地質や土地利用の目的などに応じた、さまざまな工法がある。
斜面崩壊や岩盤崩落の危険地帯では、斜面へのコンクリート吹き付けやプレキャストコンクリート枠の設置︵法枠工︶、法面アンカーの埋め込みなどの法面工︵法面保護工︶をはじめ、斜面への植樹︵播種︶や芝生張りといった植生工などが有効である[59]。
水の作用が原因となりうる斜面崩壊や地すべりの危険地帯では、水を排除するため、水路の暗渠化、横方向のボーリング、集水井の設置などの地下水排除工、地表の排水路設置、雨水浸透防止などの地表水排除工が有効である[16]。
地すべり地では、地すべり面上部の土を取り除く上部排土工と末端に盛土し擁壁で抑える抑え盛土工の併用という方法もある。盛土部は公園として利用されることが多い[59]。
土石流の危険性が高い渓流では、構造物を設けて土砂を堆積させる砂防堰堤・治山ダムの設置も有効である。ただし、その容積が限られ、時間経過により埋まってしまうため、効果は限られる[60]。
小規模で突発的な崩壊・崩落に対しては、危険地帯の道路沿い・鉄道沿いに落石シェッドや落石防止網、落石防止壁を取り付ける方法もあるが1989年に福井県の越前海岸で発生した崩落事故のように、稀に予想を超える規模の崩壊が発生して被害が生じる場合もある[61]。これを補うものとして、衝撃や移動を検知する落石検知器や地すべり計、土石流センサーなどを設置して道路の管理事務所の警報装置と連動させるようなシステムもある[61]。
日本以外でも、急峻な国土を持ち土砂災害の被害が多いインドネシア、ネパールなどで、日本の砂防技術を導入した対策が行われているところがあり、主にJICAを通じた技術支援により進められている[62]。
ただし、砂防ダムが設けられていてもふもとで土石流の被害が発生してしまった例は少なくないことなどから、対策工事が行われたから安全だ、と思い込むことは危険である[63]。
対策の要点[編集]
日本は、前述した国土の特性から住宅や公共施設などが被災する可能性のある地域を多く抱え[27]、2020年の時点でその数は約60万を超えている[46]。日本の政府広報のページでは、土砂災害から身を守る基本的な方法として以下の3つを挙げている[27]。 (一)普段から自分が住んでいる場所が土砂災害警戒区域か確認しておくこと[27]。 ●参考外部リンク:国土交通省 土砂災害警戒区域・土砂災害危険箇所 (二)雨が降りだしたら土砂災害警戒情報に注意すること[27]。 ●参考外部リンク:気象庁 土砂災害警戒情報 (三)土砂災害警戒情報が発表されたら早めに避難すること[27]。 また東京都が2015年に発行した防災ハンドブック﹁東京防災﹂では、土砂災害から身を守るための﹁普段からの備え﹂として3つのポイントを挙げている[47]。 (一)危険箇所を確認しておくこと︵上記1.︶[47]。 (二)避難場所を確認しておくこと[47]。 ●市区町村は避難場所を指定している。これを参考に、避難する場所、そこへ移動する経路、また家族間の連絡方法について、家族で話し合っておく[47]。 ●参考外部リンク:防災ポータルサイト 全国ハザードマップ (三)非常用持ち出し袋の用意をしておくこと[47]。 このほか、同書では以下も挙げている[47]。 ●がけ地周辺や山間部では、警報が発表されなくとも、土砂災害の前兆が見られたら、安全を確保した上で避難すること[43]。 ●土砂災害の危険を感じたら、早めのうちに、活動しやすい服装に着替えていつでも避難できるようにしておくこと[47]。 ●避難する時は、持ち物を最小限にして、両手が使えるようにしておくこと[47]。森林との関係[編集]
森林は土壌侵食や表層崩壊を抑止する 深さ数mの表層崩壊に対しては、樹木が存在することで斜面を安定させる効果がある。特に、急斜面において高い効果がある[48]。土壌中に広がった樹木の根が、土層のずれを受け止めて変形したり、摩擦力により引き抜きに抵抗したりして、斜面を滑らせようとするせん断力に抵抗する[49]、あるいは根が土層の変形を防ぐ配筋として働き、土壌の滑りに抵抗するアーチ構造を保つ[50] などと考えられている。 更に、土壌表面の浸食を防ぐ高い効果も持つ[51][52]。 ただし、抑止効果には限界があり、異常な豪雨に見舞われると、森林があっても表層崩壊が起こりうる。このようにして森林が失われた場合、できるだけ早期に森林を復元することが、更なる崩壊の抑止となる[53]。 深層崩壊の抑止効果は乏しい 一方深層崩壊に対しては、すべり面が深いため地表の植生の影響を受けにくく、管理が行き届いた森林でも発生する。崩壊抑止の効果は乏しいと考えられている[52][54]。 伐採は崩壊を促進させる 森林の樹木を伐採した斜面は、土層を支える根が弱くなるため、表層崩壊が起きやすい。ただし、伐採直後よりも数年 - 十数年後のほうが崩壊に弱い。これは、伐採後に根の腐朽が次第に進行していくことによる。ただし、樹種や環境により程度は異なる[55]。 また林業においては、樹木の根系を強く保つために、伐採間隔をより長くして十分生育させることや、根が発達していない伐採時や若齢・壮齢林の時期でも林床を土むき出しにさせない︵落葉や下草に覆われた状態に保つ︶ことが望ましいとされる[56]。 樹齢が長いほど抑止効果が高い 樹齢の長い森林ほど、表層崩壊は起きにくい。樹齢40-50年を超える森林に比べると、若い森林︵幼齢林︶は崩壊を起こしやすい[57]。 間伐の影響 人工林において、間伐は病虫害や強風害などを防ぎ、良好な生育を助ける効果がある。日本では、林業の経営環境の悪化などから間伐の遅れる森林が増加する傾向にあり、森林の持つ崩壊防止機能の低下が懸念されている。ただしいくつかの研究では、間伐林では根の量が増えるため崩壊への抵抗力が増すという報告もあれば、逆に低下したという報告もあるなど、効果は明確ではない[58]。工事などの発生防止策[編集]

主な前兆現象[編集]
●土石流 ●川の中でゴロゴロという音︵石がぶつかり合う音︶がしたり、火花が見えたりする[42][47]。 ●山全体が唸っているような音︵山鳴り︶がしたり、地震のように震えたりする。異常なにおい︵腐った土のにおい︶がする[42][47]。 ●川の水が濁り、水と一緒に倒れた木︵生の木︶が流れてくる[42]。 ●雨は降り続いているのに、川の水が減る[42]。 ●地すべり ●崖や斜面から水が噴き出す。湧き水が増える[42]。 ●風もないのに山の木がザワザワする。木が裂ける音や木の根が切れる音がする。地鳴りや山鳴りがする[42]。 ●沢や池、井戸の水が濁ったり、急に増えたり減ったりする[42][47]。 ●地面にひび割れや段差、陥没ができる[42][47]。 ●斜面崩壊︵崖崩れ︶ ●崖から新しく水が湧き出る。また、湧き水が濁ったり、量が増えたり、急に止まったりする[42][47]。 ●崖にひび割れができる。あるいは、崖が膨らむ[42]。 ●崖の上の木が揺れたり傾いたりする。地鳴りがする[42]。 ●崖から小石がパラパラと落ちてくる[42]。※崖崩れは、前兆もなくいきなり起こることもある[42]。 なお、これらの前兆現象は、発生の前に必ず現れるわけではない。また、周囲が暗く寝ている人が多い夜間や、雨が激しい時間帯などは、前兆現象があっても発見するのが難しい。少しでもおかしいと感じたら対処することや、早めの避難をすることが、土砂災害の回避に有効である[64]行政が公表している危険地帯[編集]
●土砂災害警戒区域・特別警戒区域 - 土砂災害防止法に基づいて都道府県が調査・指定・公表している。土砂災害のおそれがある区域の住民の避難を促し、特に危険な区域は開発制限を行うもの[65]。2020年末時点で、指定済みが約64万箇所でうち約52万箇所︵約81%︶が特別警戒区域、今後指定される見込みの区域が約3万箇所[46]。 ●土砂災害警戒区域 - 市町村の地域防災計画において、区域ごとに警報の伝達や避難の体制を定める[65]。 ●土砂災害特別警戒区域 - 警戒区域の措置に加えて、建築規制や開発行為の制限を定める[65]。 ●基礎調査後公表される、土砂災害警戒区域に相当する区域 - 警戒区域の指定には調査などで期間がかかる。その間の被害を防ぐため、基礎調査の後に都道府県は速やかにその区域を公表することが定められている[65]。 ●土砂災害危険箇所 - 旧建設省・国土交通省が定める調査要領に基づいて都道府県が調査し、公表している。土砂災害により人家や公共施設等に被害のおそれがある区域[65]。1966年から2000年代にかけて行われ、調査の進展と開発の進行により年々増加し、2003年3月時点で約53万箇所を数える[注 5][66][67][68]。 ●急傾斜地崩壊危険箇所 - 傾斜30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で、人家や公共施設に被害を及ぼすおそれのある急傾斜地およびその近接地[65]。 ●土石流危険区域 - 渓流の勾配が3度以上︵火山砂防地域では2度以上︶あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある区域[65]。 ●地すべり危険区域 - 空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生するおそれがあると判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与えるおそれのある範囲[65]。 ●山地災害危険地区 - 林野庁︵農林水産省の外局︶が定める調査要領に基づき都道府県の森林担当部局が調査し、市町村に伝達している。山地災害︵山腹崩壊、崩壊土砂流出、地すべり︶により人家や公共施設等に被害のおそれがある地区[69]。森林︵国有林または民有林︶を対象としたもの。2012年時点で計約18万箇所[68][70]。 ●斜面崩壊や落石のおそれがある山腹崩壊危険地区、土石流のおそれがある崩壊土砂流出危険地区、地すべりのおそれがある地すべり危険地区の3種類[69]。 ●砂防三法による指定区域 - 排水工や擁壁工、砂防ダム設置などの対策工事︵砂防事業︶を行うことを前提に、土砂災害のおそれがあり工事の必要性が高い地域を指定するもの。土砂災害危険箇所に比べると件数が少ない。 ●砂防指定地 - 砂防法に基づいて国土交通大臣が指定している。掘削や盛土、竹木の伐採や土石の採取などの開発が制限される。 ●地すべり防止区域 - 地すべり等防止法に基づいて国土交通大臣が指定している。掘削や盛土、土石の採取などの開発が制限される。 ●急傾斜地崩壊危険区域 - 急傾斜地法に基づいて都道府県が指定している。掘削や盛土、土石の採取などの開発が制限される。土砂災害が起きやすくなっていることを知らせる情報[編集]
大雨警報や土砂災害警戒情報などは気象庁が災害の危険度が高まっていることを知らせ、避難指示などは市町村が危険な地域の住民に避難を強く促すものである。土砂災害は、発生してから逃げるのは困難で、木造住宅を流失・全壊させるほどの破壊力を有し、人的被害が出やすい。その反面、危険な区域は事前に調べれば絞り込むことができ、危険な区域から少しでも離れれば人的被害を軽減できるため、各種情報を手がかりにして早めの避難を行うことは有効である。 しかし、こうした情報は市町村などの広い範囲に画一的に出されるため、住民が個々の場所の危険度の大小を認識しないまま、﹁警報や避難指示が出されていないこと﹂を﹁安全﹂と捉える場合がある。例えば、山間の1つの集落内においても、段丘面の上にある建物は下にある建物より土石流の危険度が低い、他方では段丘面上にあっても近くに山の斜面が迫っていれば斜面崩壊の危険度が高い。そのため、﹁警報や避難指示が出されていないこと﹂を安全と捉えることは好ましくなく、個々の場所の危険度の大小に応じて避難の是非を判断するべきとされる。 なお、土砂災害の前兆があった場合は警報などが出されていなくても避難し市町村などに連絡するべきとされる[71]。 ただし、地震による崩壊は、突発的である上、場所を特定できず大規模になりやすい。そのため、避難の余地がほとんどなく、有効な対処としては危険な土地の利用をあらかじめ避けるしかない[38]。 大雨警報などは、土砂災害の危険度を段階的に示すものである。市町村単位。累積雨量や予想雨量などにより求められ、気象庁が発表する[45][72]。 ●大雨注意報︵土砂災害︶ - レベル2 - 大雨によって災害が起こるおそれがある[72][73]。 ●大雨警報︵土砂災害︶ - レベル3相当 - 大雨によって重大な災害が起こるおそれがある。市町村が避難準備情報の発令を判断する要素の1つ[72][73]。 ●土砂災害警戒情報 - レベル4相当 - 大雨警報発表後、土砂災害の危険度がさらに高くなっている。市町村が避難勧告の発令を判断する要素の1つ[72][74]。 ●記録的短時間大雨情報 - 数年に一度しかないような大雨が降った。急激に雨量が増し、災害の危険度が高まっている[72][75]。 ●大雨特別警報︵土砂災害︶ - レベル5相当 - 大雨によって重大な災害が起こるおそれが著しく大きい[72][73]。 ●土砂災害の危険度分布﹁土砂キキクル﹂[注 6] - 注意、 警戒、 非常に危険、 極めて危険 - 地図上に1km四方単位、10分ごと更新で土砂災害の危険度を示す。気象庁が公開し、防災機関向け情報システムに提供されるほか、気象庁のホームページ上で閲覧できる。地域差を反映した細かい危険度を示す。また2時間後までの予想雨量を根拠にするため予報的要素も含むが、急激に発達する局地的大雨は予想できない場合がある[72][74][77]。 ●土砂災害緊急情報 - 速度が比較的遅い地すべり、火山噴火後の降灰が引き起こす火山泥流、天然ダム決壊などによる災害の危険度が高まったことを知らせる情報。都道府県が発表する[78]。 市町村が発令する避難指示などは、対象区域の住民に対して避難を強く促すもので、警報や雨量などを参考に市町村長が発令する。この意味するところは、﹁立ち退き避難﹂ = 避難場所への避難︵指定緊急避難場所への移動︶あるいは安全な親戚・友人の家などへの避難を基本とし、それがかえって危険な場合や緊急の場合は、﹁緊急的な待避﹂ = 近隣の高い建物、強度の強い建物、公園などへの移動や、﹁屋内での安全確保措置﹂ = 建物内のより安全な場所に留まることである。内閣府の﹃避難情報に関するガイドライン﹄︵2021年︶によると、水害等において、要配慮者を除く住民は、高齢者等避難の段階でまず避難の準備をして情報に注意を向け、避難指示を受けて避難を始めるよう推奨されている一方、土砂災害においては、対象区域のすべての住民が﹁高齢者等避難の段階で避難を始める﹂ことが推奨されている。これは、突発的で予測困難な土砂災害の性質を考慮したもので、2019年の令和元年東日本台風の教訓から改められたものである[79]。 ●高齢者等避難 - 対象地域の災害時要配慮者︵高齢者、障害者、乳幼児など[注 7][80]︶は避難を始める。その他の住民は、準備が整い次第、避難を始める[81]。 ●避難指示 - 対象地域のすべての住民は避難を始める。避難に急を要する。 ●緊急安全確保 - 既に災害が発生し、安全な避難が困難となり、人命に危険が及ぶ可能性のある状態。 土砂災害の避難において留意すべき点は以下の通り。 ●避難指示などが出ていなくても、身の危険を感じたら、避難指示を待たず、自発的に避難すべきこと[82]。 ●土砂災害の前兆現象を発見したら、率先して自発的に避難し、すぐ市町村にも連絡すべきこと︵前兆の報告は避難勧告などの発令基準の1つであり、他の住民の安全にも資する︶[82]。 ●特に木造家屋は土砂災害により倒壊したり埋没したりする危険性が高く、その住民は高齢者等避難開始の段階で早めに避難場所へ移動しておくことが勧められる[83]。 ●屋外行動の危険性が高い、夜間や、暴風・豪雨の最中であっても避難指示等は出される。この場合、離れた避難場所への移動の危険性や周囲の状況を見極める必要があり、近隣の待避場所への移動や屋内での安全確保などを考慮すべきこと。さらに、このような事態が予想される場合、明るいうちに・風雨が弱いうちに、避難場所へ避難しておくことが望ましい[84]。 ●避難しようとした時点で既に水害や土砂災害がまわりで発生しているなど、避難場所までの移動がかえって危険な場合、土石流の予想到達区域や急傾斜地からできるだけ離れたところ、できるだけ高いところ、あるいは頑丈な建物の上層階といった緊急的な待避場所への移動も考慮すべきこと。例として、近隣にあるコンクリート造のビル上層階、山から離れた小高い場所など[84]。 ●小規模ながけ崩れが予想される地区では、避難場所までの移動がかえって危険な場合、自宅の2階以上に移動するといった、緊急的な屋内での安全確保も考慮すべきこと。ただし、通常の木造家屋は土石流によって全壊する恐れがあり、土石流が予想される地区では自宅外の緊急的な待避場所への移動が望ましい。自宅の2階などへの避難はやむを得ない場合の選択肢であり、そうならないように早い段階から避難場所へと避難しておくことが望ましい[84]。 警報や避難情報は、災害の﹁見逃し﹂がないように出される。そのため、発表されたにもかかわらず災害が発生しない、いわゆる﹁空振り﹂はつきものとなる。住民側の意識として、空振りだったけれど﹁被害がなくて良かった﹂・避難したけれど﹁何もなくて幸運だった﹂と考え、警報や避難情報を軽視しないよう心掛けることが、自らの被害回避や、行政側が避難指示発令に躊躇してしまう事態の抑止につながると考えられる[85][86]。事例[編集]


脚注[編集]
注釈[編集]
(一)^ 火山の噴火に伴う溶岩流・火砕流・火山泥流を含める場合もある。
(二)^ ab3つの国際学会とユネスコが設けた世界地すべり目録委員会は、滑り、落下、前方回転、伸張、流動を含んだ運動を総称して"landslide"︵日本語訳:地すべり︶と定義している。運動のタイプ、せん断タイプ、材料の3要素により細かい地すべり分類 (landslide classification) を行っている。せん断タイプとしてすべり、液状化、クリープの3種、材料として岩、砂質土、粘性土の3種がある。
(三)^ 例えば、日本の法律でも、災害防止を目的としていることから、﹁土砂災害﹂を
●急傾斜地の崩壊︵傾斜度が三十度以上である土地が崩壊する自然現象をいう。︶
●土石流︵山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象をいう。︶
●地滑り︵土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象をいう。︶
3つのいずれかを発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害と定めている︵土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律2条︶。
(四)^ 治水三法: 河川法︵1896年制定︶、砂防法︵1897年制定︶、森林法︵1897年制定︶。
(五)^ 1972年約4.7万箇所、1993年頃約17万箇所︵※急傾斜地は1992年の数字︶、2002年頃約53万箇所︵※地すべりは1998年︶。2002年の急増は調査対象を人家5戸未満まで含めるよう拡大したためであり、従前基準では約21万箇所だった。なお、この頃土砂災害防止法に基づく基礎調査が開始されたため、これ以降は新たに行われていない。
(六)^ 2018年までの呼称は﹁土砂災害警戒判定メッシュ情報﹂[76]。2021年に愛称付与。
(七)^ 避難に必要な情報を把握したり、避難行動をとったりする、また自身の身を守るにあたって、手助けが必要な者。高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦など。災害時要援護者。
(八)^ 氷河の作用で堆積した土砂や岩。
(九)^ 素掘りの用水路とは、土を掘っただけで石などを敷いていない単純な形式の用水路をいう。水が浸透しやすい。
出典[編集]
(一)^ goo国語辞書﹁︻土砂災害︼﹂、2016年10月22日閲覧。︵原典:松村明︵監修︶﹃デジタル大辞泉﹄、小学館︶
(二)^ 地盤工学会︵2006年︶、p.196
(三)^ ab土岐・河田︵2002年︶、p.171 土井次郎﹁地すべり﹂
(四)^ 地盤工学会︵2006年︶、p.459
(五)^ 渕田 他︵2014年︶、p.67
(六)^ ab渕田 他︵2014年︶、p.149
(七)^ 高谷︵2008年︶、p.1
(八)^ ab地盤工学会・編︵2012年︶、pp.11-12
(九)^ ab水谷︵2012年︶、pp.13-15
(十)^ 大久保駿﹁アメリカの砂防﹂、砂防学会﹃砂防学会誌﹄Vol.27、No.1、pp.21-26、1974年6月。doi:10.11475/sabo1973.27.21
(11)^ 三森︵2006年︶、p.15
(12)^ abc萩原幸男︵1992年︶、pp.222-225
(13)^ abcdef地盤工学会・編︵2012年︶、pp.12-13
(14)^ 渕田 他︵2014年︶、pp.136-137, p.150
(15)^ 東建ジオテック﹁斜面の安定解析﹂、一般社団法人斜面防災対策技術協会、2017年1月9日閲覧。
(16)^ ab渕田 他︵2014年︶、pp.136-137, p.150, p.153
(17)^ abcdef大石︵2014年︶、pp.41-43,pp.50-59,p.61
(18)^ 矢野︵1973年︶、p.2
(19)^ 塚本︵2006年︶、pp.4-7
(20)^ 塚本︵2006年︶、pp.7-8
(21)^ 塚本︵2006年︶、p.8
(22)^ ab三森利昭﹁現在の森林の状況と土砂災害防止機能評価の試み﹂、第122回日本森林学会大会﹃森林の取り扱いと土砂災害-災害防止から見た森林施業のあり方-﹄、セッションID:G03、2011年3月22日。doi:10.11519/jfsc.122.0.205.0
(23)^ ab国土交通省﹃平成20年版 国土交通白書﹄2008年、図表I-1-1-25
(24)^ abc﹁土砂災害の基礎知識―理解し、備える土砂災害(1)﹂、webside.jp︵東京法規出版︶、2014年9月20日、2017年1月9日閲覧。
(25)^ ab高谷︵2008年︶、p.5
(26)^ abcde渕田 他︵2014年︶、p.151
(27)^ abcdefgh﹁土砂災害の危険箇所は全国に53万箇所!土砂災害から身を守る3つのポイント﹂、政府広報オンライン︵内閣府大臣官房政府広報室︶、2015年5月12日最終更新、2016年12月7日閲覧。
(28)^ abcd渕田 他︵2014年︶、p.150
(29)^ abcd地盤工学会・編︵2012年︶、pp.13-14
(30)^ 渕田 他︵2014年︶、pp.150-151
(31)^ ab﹁風水害の基礎知識 3.土砂災害 地すべり﹂一般財団法人消防防災科学センター 消防防災博物館、2016年11月12日閲覧。
(32)^ abcde渕田 他︵2014年︶、p.65
(33)^ abc地盤工学会・編︵2012年︶、p.14
(34)^ ab渕田 他︵2014年︶、pp.64-65
(35)^ abc﹁風水害の基礎知識 3.土砂災害 土石流﹂一般財団法人消防防災科学センター 消防防災博物館、2016年11月12日閲覧。
(36)^ 渕田 他︵2014年︶、p.66
(37)^ 渕田 他︵2014年︶、p.152
(38)^ ab防災科学技術研究所︵2013年︶、p.27
(39)^ 石川︵2006年︶、p.28, pp.30-31
(40)^ 地盤工学会・編︵2012年︶、p.15
(41)^ 防災科学技術研究所︵2013年︶、p.29, p.32
(42)^ abcdefghijklmnopq﹁土砂災害の前触れを知る﹂特定非営利活動法人土砂災害防止広報センター、2016年11月12日閲覧。
(43)^ ab﹃東京防災﹄︵2015年︶、p.147
(44)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.6
(45)^ ab﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.21-23, p.41
(46)^ ab﹁土砂災害防止法 全国における土砂災害警戒区域等の指定状況︵R2.12.31時点︶ (PDF) ﹂、国土交通省、2021年4月18日閲覧。
(47)^ abcdefghijklm﹃東京防災﹄︵2015年︶、p.153
(48)^ 三森︵2006年︶、pp.17-18
(49)^ 佐藤︵2006年︶、pp.22-23
(50)^ 佐藤︵2006年︶、pp.23-24
(51)^ 五味︵2006年︶、pp.11-13
(52)^ ab太田︵2006年︶、p.34
(53)^ 太田︵2006年︶、p.35
(54)^ 三森︵2006年︶、p.18
(55)^ 佐藤︵2006年︶、pp.22-24
(56)^ 太田︵2006年︶、p.36
(57)^ 佐藤︵2006年︶、pp.25-26
(58)^ 佐藤︵2006年︶、pp.24-25
(59)^ ab渕田 他︵2014年︶、p.153
(60)^ ab防災科学技術研究所︵2013年︶、p.29
(61)^ ab渕田 他︵2014年︶、p.154
(62)^ DMSP.JICAだよりNo.10.2000.8.28
(63)^ 防災科学技術研究所︵2013年︶、p.27, p.29
(64)^ ﹁命を守るために必要なこと識―理解し、備える土砂災害(4)﹂、webside.jp︵東京法規出版︶、2014年10月31日、2017年1月9日閲覧。
(65)^ abcdefgh﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.14, p.39, p.104
(66)^ ﹁都道府県別土砂災害危険箇所の調査結果﹂国土交通省河川局砂防部、2003年3月28日
(67)^ 八木寿明﹁土砂災害の防止と土地利用規制﹂、国立国会図書館﹃レファレンス﹄、678号︵平成19年7月号︶、p.30、2007年7月 doi:10.11501/999735
(68)^ ab﹁土砂災害対策に関する行政評価・監視結果報告書﹂、総務省行政評価局、pp.19-25、2017年5月26日、2021年4月18日閲覧
(69)^ ab﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.39-40, p.100
(70)^ ﹁日本に山地災害が多いわけ﹂、林野庁、2016年12月8日閲覧。
(71)^ 防災科学技術研究所︵2013年︶、pp.42-43
(72)^ abcdefg知識・解説 > 台風や集中豪雨から身を守るために > ﹁土砂災害に関する防災気象情報の活用﹂、気象庁、2021年4月14日閲覧
(73)^ abc﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.41, p.97
(74)^ ab﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.21-23, p.41, p.104
(75)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.21-23, p.41, p.98
(76)^ ﹁配信資料に関する技術情報第508号~高解像度化した大雨警報︵土砂災害︶の危険度分布︵土砂災害警戒判定メッシュ情報︶の提供開始について~﹂、気象庁予報部、2018年3月6日︵2018年6月24日訂正︶、2021年4月14日閲覧
(77)^ ﹁土砂災害警戒情報・大雨警報︵土砂災害︶の危険度分布﹂、気象庁、2021年4月14日閲覧
(78)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.38
(79)^ 避難情報に関するガイドラインの改定︵令和3年5月︶
(80)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.100
(81)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.18-19, p.106
(82)^ ab﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、pp.5-6
(83)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.13
(84)^ abc﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p.6, pp.18-19, p.38
(85)^ 防災科学技術研究所︵2013年︶、pp.40-41
(86)^ ﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄︵2015年︶、p,6, p.18
(87)^ 萩原幸男︵1992年︶、pp.187-188
(88)^ ab防災科学技術研究所︵2013年︶、p.32
(89)^ 萩原幸男︵1992年︶、pp.182-183
(90)^ 萩原︵1992年︶、pp.185-187
(91)^ 萩原︵1992年︶、p.183
(92)^ ﹁昭和47年の繁藤豪雨﹂﹁昭和47年の繁藤災害﹂、四国災害アーカイブス︵一般社団法人四国クリエイト協会︶、2016年12月11日閲覧。
(93)^ abc水谷武司﹁21. 大規模な山崩れや地すべりでは事前に種々の明瞭な地変現象が認められる-1963年イタリア・バイヨントダム地すべりなど﹂、﹃防災基礎講座‥災害事例編﹄、防災科学技術研究所、2011年7月5日最終更新、2017年1月9日閲覧。
(94)^ 出水市総務課﹁平成9年土石流災害とその後の対策について﹂、消防防災博物館︵一般財団法人消防科学センター︶、1999年、2016年12月11日閲覧。﹁災害復興対策事例集 1997年︵平成9年︶ 針原地区土石流災害﹂、内閣府防災担当、2016年12月11日閲覧。
(95)^ ﹁1997年7月鹿児島県出水市針原川土石流災害調査報告﹂、防災科学技術研究所﹃主要災害調査﹄No.35, 1998年5月, p11, pp.65-66
(96)^ 萩原︵1992年︶、pp.189-190
(97)^ 萩原︵1992年︶、p.190
(98)^ 萩原︵1992年︶、pp.191-192
(99)^ ﹁過去の発生事例―理解し、備える土砂災害(2)﹂、webside.jp︵東京法規出版︶、2014年9月30日、2017年1月9日閲覧。
(100)^ 萩原︵1992年︶、pp.
(101)^ 萩原︵1992年︶、p.93
(102)^ 萩原︵1992年︶、pp.198-199
(103)^ 萩原︵1992年︶、pp.196-197
参考文献[編集]
●水谷武司﹃自然災害の予測と対策 -地形・地盤条件を基軸として-﹄朝倉書店、2012年。ISBN 978-4-254-16061-1 ●高谷精二﹃技術者に必要な地すべり山くずれの知識﹄鹿島出版会、2008年。ISBN 978-4-306-02401-4 ●渕田邦彦 他﹃防災工学﹄コロナ社 <環境都市システム工学系教科書シリーズ 20>、2014年。ISBN 978-4-339-05520-7 ●公益社団法人地盤工学会︵編︶﹃全国77都市の地盤と災害ハンドブック﹄丸善出版、2012年。ISBN 978-4-621-08477-9 ●公益社団法人地盤工学会﹃地盤工学用語辞典﹄丸善出版、2006年。ISBN 978-4-88644-073-0 ●大石道夫﹃微地形砂防の実際 微地形判読から砂防計画まで﹄鹿島出版会、2014年。ISBN 978-4-306-02457-1 ●防災科学技術研究所 自然災害情報室︵編︶﹃防災科学テキスト -自然災害の発生機構・危険予測・防災対応︵改訂版︶﹄、防災科学技術研究所、2013年2月。 ●矢野義男﹃山地防災工学﹄山海堂、1973年。全国書誌番号:69014061 ●土岐憲三、河田恵昭﹃防災事典﹄築地書館、2002年。ISBN 978-4-8067-1233-6 ●萩原幸男︵編︶﹃災害の事典﹄<初版>、朝倉書店、1992年。ISBN 978-4-254-16024-6 ●東京都総務局総合防災部防災管理課︵編集・発行︶﹃東京防災﹄、2015年9月。 ●内閣府防災担当︵編集・発行︶﹃避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン﹄、2015年8月。 ●塚本良則﹁I章 日本の土砂災害と対策の歴史 (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 4–9、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758631 ●五味高志﹁II章 土壌侵食と森林 : 森林斜面から流域の視点へ (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 10–14、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758632 ●三森利昭﹁III章 山地における斜面崩壊 (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 15–21、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758633 ●佐藤創﹁IV章 表層崩壊と森林 (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 22–27、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758634 ●石川芳治﹁V章 流木災害と森林 (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 28–32、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758635 ●太田猛彦﹁VI章 土砂災害と今後の森林管理のあり方 (<特集>土砂災害と森林)﹂、﹃森林科学﹄47巻、pp. 33–38、日本森林学会、2006年6月。NAID 110004758636関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 土砂災害から身を守るための情報(日本)
- 土砂災害から身を守る3つのポイント - 政府広報
- 各都道府県が公開している土砂災害危険箇所と土砂災害警戒区域 - 国土交通省 砂防部
- 土砂災害警戒情報 土砂災害警戒判定メッシュ情報 - 気象庁
- 土砂災害に関する防災気象情報の活用 - 情報活用の手引き
- 国土交通省ハザードマップポータルサイト - 国土交通省がリンク集として取りまとめている各市町村の土砂災害ハザードマップ
- 基礎知識・防災広報
- 土砂災害防止広報センター
- 風水害の基礎知識 - 消防防災科学センター 消防防災博物館
- 土砂災害の事例
- 土砂災害年表(日本) - 土砂災害防止広報センター
- 災害事例データベース・災害年表マップ(日本・市町村ごと) - 防災科学技術研究所
- Disasters - Type:Land Slide, Mud Slide(世界) - リリーフウェブ(ReliefWeb)による直近・過去の人道支援を必要とする(した)土砂災害事例
- 土砂災害・砂防関連組織
