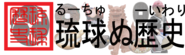先島諸島
 NASAによる撮影(2015年7月30日) | |
| 地理 | |
|---|---|
| 場所 | 東シナ海・フィリピン海(太平洋) |
| 座標 |
北緯24度00分 - 26度00分 東経122度45分 - 125度45分 |
| 諸島 | 南西諸島 |
| 島数 | 44島(うち20島は有人島)[1] |
| 主要な島 |
西表島(289.27km2)[2] 石垣島(222.63km2)[2] 宮古島(159.25km2)[2] |
| 面積 |
818.45 km2 (316.01 sq mi) (国土地理院、2010年10月1日現在)[2] |
| 最高標高 | 526 m (1726 ft)[3] |
| 最高峰 | 於茂登岳[3] |
| 所属国 | |
| 都道府県 | 沖縄県 |
| 市町村 |
宮古島市、石垣市 宮古郡:多良間村 八重山郡:竹富町、与那国町 |
| 最大都市 | 宮古島市(人口52,039人[4]) |
| 人口統計 | |
| 人口 |
105,708人 (国勢調査、2010年10月1日現在)[4] |
| 人口密度 | 129.2 /km2 (334.6 /sq mi) |
先島諸島に含まれうる諸島[編集]
●宮古列島 ●宮古島 ●池間島 ●大神島 ●来間島 ●伊良部島 ●下地島 ●多良間島 ●水納島 ●八重山列島 ●石垣島 ●竹富島 ●小浜島 ●黒島 ●新城島 ●西表島 ●鳩間島 ●由布島 ●波照間島 ●与那国島 ●尖閣諸島 ●魚釣島 ●久場島 ●大正島 この他いくつかの無人島がある。 尖閣諸島については、先島諸島に含めない場合[5][6][7]と、含める場合[8]とが有る。中国と台湾がそれぞれ領有権を主張している。名称[編集]
日本本土から見た場合に沖縄本島よりも先にある島々であるために、明治時代に先島諸島と命名されたとされる[9]。かつては大平山と呼ばれていた。行政区分[編集]
- 宮古列島
- 八重山列島
歴史[編集]
時代区分[編集]
先島諸島の歴史は日本本土や沖縄本島に比べて独自性が強いため、独自の編年が提案されているが確立されたものはない。 他の地域とは違い、19世紀まで土器文化が続いたため土器を中心とした編年がよく使われている。 沖縄県の公式ホームページに掲載されているものに基づくものは以下の通り[10]。
旧石器時代と下田原期との間と、下田原期と無土器期との間には遺物がほとんど出土しない空白期間がある。
地質時代[編集]
40万年前まで琉球孤の島々は隆起と沈降を繰り返していたようである。沖縄本島と宮古島の間には沖縄-宮古海台(OMSP)があり、27万年前までここは陸地だったようである[11]。
先史[編集]
旧石器時代[編集]
宮古島ではピンザアブ遺跡が、石垣島では白保竿根田原洞穴遺跡が発見されている。
先島先史時代[編集]
旧石器時代や後述する新里村期も広義の先史時代に当てはまるが、下田原期及び無土器期との連続性が確認されていないため、あえて区別されている。
先史時代の先島諸島では縄文文化の影響はほとんど見られず、台湾との共通点が指摘される土器が多く見つかっている。 約2500年前から無土器文化(料理には同様に無土器文化を持つポリネシアと同じく石焼を多く用いたと考えられている)に入るが、この時代もシャコガイ貝斧などがみられ、これもフィリピン方面との文化的関係が考えられている。 約800年前ごろからカムィ焼や鍋形土器など、本島さらには北方との関係がみられるようになる。 記録としては、『続日本紀』に、714年(和銅7年)に「信覚」などの人々が来朝したと記されており、「信覚」は石垣島を指すといわれる。 13世紀頃までは、自前の船で沖縄諸島と先島諸島の往来をすることは容易ではなく、両地域の結び付きは薄く、先島諸島は南琉球先史文化圏に属し、それは中国、台湾、フィリピン文化圏の影響が色濃いものであった。
この節の加筆が望まれています。 |
原史~中世[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
新里村期[編集]
新里村期は12世紀から13世紀までの時期で、この時代の遺跡から新里村式土器が出土することに由来する。
この時代にそれまでの狩猟採集文化に代わって農耕文化や南琉球諸語の祖語を話す集団が北方より沖縄以南に進出し、現在に続く先島諸島の文化が成立したようである。
この節の加筆が望まれています。 |
中森期[編集]
近世[編集]
1609年、時の大和政権江戸幕府徳川家康、秀忠より琉球征伐御朱印状を得た薩摩藩島津氏が琉球王国に侵攻、琉球王尚寧王は降伏し琉球王国は薩摩藩に服属することとなった。薩摩藩の命を受け、王府は先島諸島火番盛を設けた。 王府は薩摩服属後も徴税代理人となり先島諸島からの年貢を徴収。1637年、王府は先島諸島に対して人頭税を導入。この制度は1903年まで続いた。 薩摩による琉球侵攻の頃から琉球処分までの間、日本本土における江戸時代とほぼ重なる時代に新城島ではパナリ焼きと呼ばれる土器が生産され、先島諸島の広い範囲で流通したため、この時代をパナリ期と呼ぶ。先島諸島の人頭税[編集]
『沖縄県宮古島島費軽減及島政改革請願書』 (明治28年(1895年)第八帝國議会可決)の一葉より: 第二 生活の状態 (食物)島民は皆薩摩芋を常食とし富裕者と雖も僅に祝事祭典の時 粟を食するのみ大半の島民は粟の味を知らず味噌を有するものは 全島民四分の一にして他は皆海水に淡水を和し薩摩芋の葉蔓或は 海藻等を煮て食せり其海岸に瀕せざる所のものは塩を以て味噌に 代用す醤油の如きは素より以て口に入るなし且つ内地の如く香の物 とてはなく豚の常食たる焼酎粕を購ひ来て薩摩芋に和し之を食せり (衣服) 其衣服に至ても亦甚た粗悪にして夏は芭蕉布一枚冬は破れたる木綿の 袷一枚を着するのみ是等は全島民の半數にして其他のものに至ては 周年僅に一領の夏衣に過きさるものあり甚だしきは一枚若くは二枚の 夏衣を以て家族數人交る々々用ゆるものあるに至る (家屋) 前略 其の家屋矮小なる間口三間奥行三間半位のもの十分の一、 同上二間に二間半位のもの十分の六、九尺二間のもの十分の三にして 要するにその衣食住の粗悪なるヿ内地の乞食に彷彿たりともかく20世紀における先島諸島民の訴えによれば、薩摩支配下の琉球王国により宮古島・八重山諸島において﹁正頭︵しょうず︶﹂と呼ばれる15歳から50歳まで︵数え年︶の男女を対象に1637年から制度化され、年齢と性別・身分、居住地域の耕地状況︵村位︶を組み合わせて算定された額によって賦課が行われた︵古琉球時代説もある︶。この正頭は廃藩置県後も旧琉球王国の既得権益層への懐柔のために執られた旧慣温存策により存続したが、本土の中央社会に南西諸島を含む辺境の地の実情を啓蒙し﹃南嶋探験﹄を著して人頭税の反対を訴えた笹森儀助の尽力もあり、1893年︵明治26年︶の中村十作、城間正安、平良真牛、西里蒲ら4人により、沖縄本島の官憲や士族らの妨害を乗り越えて、国会請願書が当時内務大臣であった井上馨に届けられた。中村の同郷︵新潟県︶の読売新聞記者である増田義一の記事で国民に周知されるところとなり、世論の後押しも受け第8回帝国議会において1903年︵明治36年︶廃止され、日本本土と同様の地租に切り替えられた[15]。 中川正晴によれば、尚真王が中央集権を進める過程と平行して宮古・八重山を含む﹁三十六島﹂にも﹁税を定め貢を納めし﹂めたものであり、その方法は宮古島・八重山の地方官人への辞令[16]に見られるとおり、琉球本島と同様のものであった。 そして、琉球の貢租制度は元来人頭税の性格をもつものであるから、宮古・八重山固有とは言えず、また、人頭税は負担者人口の増加局面では軽く作用し、逆に減少局面では過酷に作用する税制であることから、1647 年の人口が5千人強であったのに対し、1771 年の大津波直前のそれが3万人弱まで増加していることからも、大津波までは明治期の悲惨さほどではなかったものと推測することができ、大津波の被害で人口の1/3が失われ、その後の世界的異常気象によってもたらされた飢饉・疫病等で頭数が大幅に失われたために、人頭税は農民にとって負担となったとし、人頭税=過酷という図式で﹁宮古・八重山は 260 年余にわたって人頭税のために苦しめられた﹂と一言でいい切るのは単純化し過ぎであるとしている。[17] また、大﨑正治によれば、公定の貢租率は日本本土の四公六民に比べ、琉球で三公七民、先島諸島では島により異なり四公 - 五公ほどと格別に重い訳では無かったとしている[18]。 王府は二重搾取等を放置していた訳ではなく、割重穀事件において王府は現地支配層を厳しく指弾し処罰する内容となっていたが、現実には罰の猶予や緩徐が行われるなどの竜頭蛇尾に終始したと指摘しており[12]、これが多良間騒動や落書事件などの紛糾へと続くこととなる。 平民が人頭税を納めるための方法として、各村に五人組の制度があった。五人組のものは木札に名前を記し、毎朝畑に出るときは、番所で耕作筆者(役人の職名)のしらべを受けた。時刻に遅れれば鞭で叩かれ、病気で畑に出られないものは五人組の他の者が加勢した[19]。 平民が人頭税をなく滞納したり、士族に反抗したりしたら刑があり、﹁不納の者は番所向足車に入れ、または在番頭に申出入牢申付べし﹂と人頭税の貢納規則にあるように﹁カシギ﹂といって両脚を丸太ではさんで締めつける方法がとられた[19]。 八重山諸島の竹富島では、口減らし、あるいは子供に人頭税の苦しみを味わわせたくないと、生まれたばかりの子供を生き埋めにすることも行われた[20]。また与那国島にはトゥングダ(人枡田) という習慣が過去にあった。ある日、予告も無しに法螺貝や銅鑼が激しく鳴らされる。その音を合図に村人は島内の人枡田に集合するが、時間までに間に合わなければ、働き手とならないという理由で打ち首にされた[21]。 人頭税から逃れるために男は匹人や名子となるほかなく、女は役人の妾となるものがいた[22]。これら匹人とならないものは役人の家に身を寄せて名子となった[22]。 1893年、真珠貝養殖のため宮古島にきていた新潟県出身の中村十作、城間正安 (那覇出身)、西里蒲(宮古福里村) 平良真牛(保良村)の四人を嘆願代表として東京に送った[23]。 四人は人頭税廃止運動を指導し、政界有力者や日本政府に、沖縄で特に宮古・八重山の農民の、人頭税に原因する生活の窮状を訴えた。 ﹁琉球の佐倉宗五郎現わる﹂と当時の読売新聞が報道した。1894年、内務省、大蔵省から調査のため係官が来県し、また日本政府内には沖縄諸制度改正法案取調委員会が設置された[23]。 1903年、 266年間続いた人頭税は廃止された[23]。
明和の大津波[編集]
近代[編集]
明治政府は、1872年︵明治5年︶、琉球王国を廃止して琉球藩を設置した。しかし、清はこの日本の政策に反発、琉球は古来中華帝国に服属していたものとして、琉球の領有権を主張した。 1871年︵明治4年︶、首里王府に年貢を納めて帰途についた宮古、八重山の船4隻のうち宮古船の1隻が台湾近海で遭難し、漂着した69人のうち3人が溺死、山中をさまよった生存者のうち54名が台湾先住民によって殺害された宮古島島民遭難事件事件に対し、日本政府は清朝に厳重に抗議したが、原住民は﹁化外の民﹂︵国家統治の及ばない者︶であるという清朝からの返事があり、これにより、日本政府は1874年︵明治7年︶、台湾出兵を行った。 1879年︵明治12年︶、明治政府は琉球藩を廃止し、沖縄県を設置︵琉球処分︶するが、清との間に琉球の領有権問題が発生し、日本政府は日清修好条規への最恵国待遇条項の追加とひき替えに、沖縄本島を日本領とし八重山諸島と宮古島を清領とする先島諸島割譲案︵分島問題︶を提案した。清も一度は応じ仮調印したが、﹁清は八重山諸島と宮古島を望まず、琉球領としたうえで、清と冊封関係を維持したままの琉球王国を再興させる﹂という李鴻章の意向によって妥結にはいたらず、琉球帰属問題も棚上げ状態になった。 琉球再興に動かない清の態度に抗議した脱清人・名城春傍︵林世功︶の自害もこの時のことである。日清戦争の結果、旧琉球王国領の全域が日本領であることを清は事実上認めざるを得なくなった。 政府による近代化は本土や沖縄本島よりもかなり遅れ、前述のとおり、人頭税を中心とした王国の制度は20世紀初頭まで温存された。また1937年まで日本標準時より1時間遅い西部標準時が適用されていた。 人頭税廃止後は砂糖黍栽培や炭鉱開発などにより経済は発展したが海外からウリミバエがもたらされ農業に大きな被害をもたらした。また近代化により元々あった文化の多くが失われていったが、同地を訪れた岩崎卓爾やニコライ・ネフスキーにより多数が記録・研究されていった。太平洋戦争と米国統治[編集]
沖縄本島とは違って太平洋戦争の戦場にはならなかったものの、1945年に入ると激しい空襲と艦砲射撃を受け、6月以降には八重山諸島で山岳地帯や西表島などマラリア危険地域への移住命令が出され、マラリアによる死者が多数出た︵戦争マラリア︶。 宮古島は平坦で、連合軍の飛行場設置を恐れ3万人の陸軍兵が駐留した。約1割の兵士が戦病死したが、宮古の女性と仲良くなる兵士が多く、引き上げ時は港は悲しみの女性で一杯であった。残った兵士もいた。 さらに沖縄本島の陸軍が壊滅すると、軍、行政ともに機能が停止し、指揮系統が切断された守備隊の一部が畑から作物を盗んだり、島民に暴力を振るうなどしたため、石垣島の住民は自警団を結成してこれに対抗し、さらにこれを発展させて12月15日に﹁八重山自治会﹂を発足させた[25]。一方アメリカ軍は11月26日告示された﹁米国海軍軍政府布告第1-A号﹂を12月8日に宮古島で、12月23日に石垣島で公布、軍政樹立を宣言し、宮古支庁︵現・宮古事務所︶と八重山支庁︵現・八重山事務所︶を復活させた[26]。1952年の日本国との平和条約によって国際法上も米国統治下に置かれることが確認された。沖縄返還後[編集]
1972年の沖縄返還に伴って日本国の施政権が回復した。しかし米国統治下で東経123度の与那国島の上空に防空識別圏の境界線が引かれていたため、返還後も島の領空の西3分の2は台湾の防空識別圏内のままであった。ただし台湾は、自主的に与那国島を避けるように台湾寄りの海上に防空識別圏の境界線を設定して運用しており、外務省も﹁防空上の問題は事実上生じない﹂という立場をとっていた。そして2010年6月25日に正式に防衛省の訓令の見直しが施行され、日本の防空識別圏が与那国島の西端から西側に14海里︵領空12海里+緩衝地帯2海里︶広げられて日本の領空と台湾の防空識別圏の重複問題が解決した。台湾の馬英九政権は﹁一方的な識別圏の変更は認められない﹂との声明を出したが、台湾は前述の通り、元より識別圏の境界線を与那国島上空から西側の海上に設定して運用していたため、問題にはならないと見られている。 テレビやラジオの放送は、テレビがNHK沖縄放送局︵前身は沖縄放送協会 (OHK)︶、ラジオは民放の琉球放送 (RBC) が開局してサービスを開始した。民放のテレビ放送は1993年に中継局が開局するまで、全てケーブルテレビの自主放送で時差配信されていた。詳細は宮古島中継局を参照。文化[編集]
方言[編集]
方言として南琉球諸語の三言語である宮古語、八重山語、与那国語が話されている。神話・伝承[編集]
この節の加筆が望まれています。 |
宮古列島[編集]
日本本土とも沖縄本島とも異なる神話が伝わっており、口承を纏めて書き写したものの写本である宮古島旧記が伝わっている。
この節の加筆が望まれています。 |
八重山諸島[編集]
洪水型兄妹始祖神話が多く伝わる。 波照間島では島民の始祖をアラマリヌパー(新しく生まれた女)と呼んで御嶽で祀っている。
この節の加筆が望まれています。 |
自然[編集]
沖縄本島との間に日本最大級の海峡である宮古海峡があり、そのため鳥類や無脊椎動物などで台湾との共通種が多い(蜂須賀線)。 一方で沖縄本島以北との共通種も多い。分子生物学の遺伝子分析による沖縄本島のものと宮古列島のものとの種の分岐の時期と、地質学的分析による地層の調査による宮古列島周辺が陸地だった時期が合わないことからかつて宮古海峡に陸地があり、そこが沖縄本島と切り離されてからしばらく後に海底から隆起した宮古列島に繋がるととそこから宮古列島へ移り住んだようである[27]。