「日本の歴史」の版間の差分
| 315行目: | 315行目: | ||
一方、日本の占領は分断国家にはされず、日本国政府と皇室を存続したまま[[アメリカ合衆国]]が間接的に占領するという間接統治を実行した(占領期間も内閣総理大臣なども存在していた)。 |
一方、日本の占領は分断国家にはされず、日本国政府と皇室を存続したまま[[アメリカ合衆国]]が間接的に占領するという間接統治を実行した(占領期間も内閣総理大臣なども存在していた)。 |
||
GHQは直ちに日本軍や |
GHQは直ちに日本軍や[[皇国史観]]、国家神道などを解体し、占領政策に基づいた[[象徴天皇制]]、[[国民主権]]、[[平和主義]]、[[政教分離]]を定めた[[日本国憲法]]を新たに制定、[[大日本帝国憲法]]は第73条により全部改正という名目で廃止された。日本が保有していた海外の軍事基地をはじめとする植民地、占領地は全て失う事になった。例えば、台湾は[[国共内戦]]によって、[[中国共産党]]に敗北した[[中国国民党]]が統治する。[[朝鮮半島]]に関しては、[[在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁|南部分はアメリカ合衆国]]と[[ソビエト民政庁|北部分はソビエト連邦]]の2カ国による直接統治となった。その影響でドイツと同じく[[大韓民国]](資本主義)と[[朝鮮民主主義人民共和国]](共産主義)の分断国家が誕生し、後の[[朝鮮戦争]]に繋がる。また、第一次世界大戦の勝利でドイツ帝国から得た南洋諸島も[[太平洋諸島信託統治領|アメリカ合衆国側が統治する方針になった]]。 |
||
「侵略戦争の経済的基盤」を無力化するために[[農地改革]]と[[財閥解体]]が断行された。解体された財閥は[[コンツェルン]]としての形から企業グループと再び復活した。企業グループとは、[[アメリカ対日協議会]]の圧力により[[過度経済力集中排除法]]が適用されないことになった「トップのいない企業結合体」である。無力化の対象となった[[寄生地主制]]と財閥は、戦中より産業合理化の障害としても論じられていた<ref>Freda Utley ''[[:en:Freda Utley#Books|Japan's Feet of Clay]]'', Faber & Faber, London (1937)</ref>。そこで[[傾斜生産方式]]という合理化が推進された。1952年、日本は[[世界銀行]]と[[国際通貨基金]]に加盟した。この頃は[[新円切替]]などが国民生活を脅かした。 |
「侵略戦争の経済的基盤」を無力化するために[[農地改革]]と[[財閥解体]]が断行された。解体された財閥は[[コンツェルン]]としての形から企業グループと再び復活した。企業グループとは、[[アメリカ対日協議会]]の圧力により[[過度経済力集中排除法]]が適用されないことになった「トップのいない企業結合体」である。無力化の対象となった[[寄生地主制]]と財閥は、戦中より産業合理化の障害としても論じられていた<ref>Freda Utley ''[[:en:Freda Utley#Books|Japan's Feet of Clay]]'', Faber & Faber, London (1937)</ref>。そこで[[傾斜生産方式]]という合理化が推進された。1952年、日本は[[世界銀行]]と[[国際通貨基金]]に加盟した。この頃は[[新円切替]]などが国民生活を脅かした。 |
||
| 321行目: | 321行目: | ||
[[File:Yoshida signs San Francisco Peace Treaty.jpg|thumb|right|[[サンフランシスコ平和条約]]に署名する[[吉田茂]]と日本全権委員団。]] |
[[File:Yoshida signs San Francisco Peace Treaty.jpg|thumb|right|[[サンフランシスコ平和条約]]に署名する[[吉田茂]]と日本全権委員団。]] |
||
[[1950年代]]にさしかかる頃から[[逆コース]]が進展した。[[朝鮮戦争]]では占領軍の指令に基づき掃海部隊や港湾労働者を朝鮮半島に送り込むなど韓国支援活動を行った<ref name=ishimaru>{{Cite web|和書|url =http://www.nids.go.jp/publication/senshi/pdf/200803/03.pdf|title =朝鮮戦争と日本の関わり―忘れ去られた海上輸送―|publisher =[[防衛研究所]]|author =防衛研究所戦史部[[石丸安蔵]]|accessdate =2011-08-02|archiveurl =https://web.archive.org/web/20110323030422/http://www.nids.go.jp///publication/senshi/pdf/200803/03.pdf|archivedate =2011年3月23日|deadlinkdate =2017年10月}}</ref>。[[1952年]]︵昭和27年︶に[[日本国との平和条約|サンフランシスコ平和条約]]により主権を回復した後、外債の導入により |
[[1950年代]]にさしかかる頃から[[逆コース]]が進展した。[[朝鮮戦争]]では占領軍の指令に基づき掃海部隊や港湾労働者を朝鮮半島に送り込むなど韓国側の支援活動を行った<ref name=ishimaru>{{Cite web|和書|url =http://www.nids.go.jp/publication/senshi/pdf/200803/03.pdf|title =朝鮮戦争と日本の関わり―忘れ去られた海上輸送―|publisher =[[防衛研究所]]|author =防衛研究所戦史部[[石丸安蔵]]|accessdate =2011-08-02|archiveurl =https://web.archive.org/web/20110323030422/http://www.nids.go.jp///publication/senshi/pdf/200803/03.pdf|archivedate =2011年3月23日|deadlinkdate =2017年10月}}</ref>。財閥は企業グループとして形を変えて再び復活した。
|
||
[[1952年]](昭和27年)に[[日本国との平和条約|サンフランシスコ平和条約]]により主権を回復した後、[[朝鮮特需]]や外債の導入により急速に戦後復興を進めた。 |
|||
戦後のドイツは[[ナチス・ドイツの国旗|ナチスの国旗]]の廃止や国歌の制限、国章の変更、戦後のイタリアも国旗と国章の変更を行ったが、日本に関しては戦前戦後と[[日の丸|国旗]]・国歌・[[日本の国章|国章]]の変更や制限は一切されず存続することになった。
|
戦後のドイツは[[ナチス・ドイツの国旗|ナチスの国旗]]の廃止や国歌の制限、国章の変更、戦後のイタリアも国旗と国章の変更を行ったが、日本に関しては戦前戦後と[[日の丸|国旗]]・国歌・[[日本の国章|国章]]の変更や制限は一切されず存続することになった。
|
||
| 329行目: | 331行目: | ||
[[冷戦]]下では西側陣営として[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約|日米安全保障条約]]を締結した。主権回復後の日本は[[西側諸国]]の中でも特に米国寄りの立場をとったが、[[日本国憲法第9条]]を根拠に軍事力の海外派遣を行わなかった。サンフランシスコ平和条約発効直前に発生した韓国による[[竹島問題|竹島軍事占領]]を除き、戦後の日本は諸外国からの軍事的実力行使にさらされることが一切なかった。また国内においても[[共産主義]]等の非合法化といった強権措置は行わなかった。
|
[[冷戦]]下では西側陣営として[[日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約|日米安全保障条約]]を締結した。主権回復後の日本は[[西側諸国]]の中でも特に米国寄りの立場をとったが、[[日本国憲法第9条]]を根拠に軍事力の海外派遣を行わなかった。サンフランシスコ平和条約発効直前に発生した韓国による[[竹島問題|竹島軍事占領]]を除き、戦後の日本は諸外国からの軍事的実力行使にさらされることが一切なかった。また国内においても[[共産主義]]等の非合法化といった強権措置は行わなかった。
|
||
[[1960年代]]、日本の[[国民総生産]]は[[高度経済成長]]を。[[1964年]]︵昭和39年︶にはアジア初であり、有色人種の国家としては初となる[[東京オリンピック (1964年)|東京オリンピック]]・[[1964年東京パラリンピック|パラリンピック]]が[[昭和天皇]]の開会宣言によって開催された。高速道路や国際空港などインフラの整備や[[オリンピック景気]]、1965年以降は[[いざなぎ景気]]と呼ばれる好景気が発生するなど繁栄する年が長年続くこととなった。また、[[国内総生産]]︵GDP︶に関しては[[1966年]]︵昭和41年︶に[[フランス]]を、[[1967年]]︵昭和42年︶に[[英国]]を、[[1968年]]︵昭和43年︶には[[西ドイツ]]をそれぞれ追い抜 |
[[1960年代]]、日本の[[国民総生産]]は[[高度経済成長]]を。[[1964年]]︵昭和39年︶にはアジア初であり、有色人種の国家としては初となる[[東京オリンピック (1964年)|東京オリンピック]]・[[1964年東京パラリンピック|パラリンピック]]が[[昭和天皇]]の開会宣言によって開催された。高速道路や国際空港などインフラの整備や[[オリンピック景気]]、1965年以降は[[いざなぎ景気]]と呼ばれる好景気が発生するなど繁栄する年が長年続くこととなった。また、[[国内総生産]]︵GDP︶に関しては[[1966年]]︵昭和41年︶に[[フランス]]を、[[1967年]]︵昭和42年︶に[[英国]]を、[[1968年]]︵昭和43年︶には[[西ドイツ]]をそれぞれ追い抜き、日本は[[先進国]]となった。壊滅的な敗戦から奇跡的な復興を遂げた日本は途上国のモデル国家とされた。
|
||
[[1970年代]]は[[ニクソン・ショック]]と[[オイルショック]]の二重苦にもかかわらず軟着陸できたので[[安定成長期]]と呼ば |
[[1970年代]]は[[ニクソン・ショック]]と[[オイルショック]]の二重苦にもかかわらず軟着陸できたので[[安定成長期]]と呼ばれた。重化学工業から[[自動車]]・[[電機]]へと産業の主役が移る[[産業構造の転換]]が進んだ。同時に[[公害病]]問題が注目される。
|
||
[[1970年]]︵昭和45年︶、大阪にて[[日本万国博覧会|大阪万博]]が開催された。博覧会の[[名誉総裁]]は当時の[[皇太子]][[上皇明仁|明仁親王]]、名誉会長は当時の首相の[[佐藤栄作]]となった。当時では普及していなかった[[電気自動車]]や[[動く歩道]]、[[電動自転車]]などを展開するなど未来世界を作り上げたことが世界から注目され、6,422万人以上が来場し大成功を収めた。
|
[[1970年]]︵昭和45年︶、大阪にて[[日本万国博覧会|大阪万博]]が開催された。博覧会の[[名誉総裁]]は当時の[[皇太子]][[上皇明仁|明仁親王]]、名誉会長は当時の首相の[[佐藤栄作]]となった。当時では普及していなかった[[電気自動車]]や[[動く歩道]]、[[電動自転車]]などを展開するなど未来世界を作り上げたことが世界から注目され、6,422万人以上が来場し大成功を収めた。
|
||
| 341行目: | 343行目: | ||
[[バブル景気]]中の日本企業による国外不動産(主にアメリカ企業の)買い漁りの象徴となった。]] |
[[バブル景気]]中の日本企業による国外不動産(主にアメリカ企業の)買い漁りの象徴となった。]] |
||
経済学者のラビ・バトラは高い成長率と一億総中流を実現した1960年代から70年代の日本経済を指して「[[資本主義]]の究極の理想に近い」と評価した。ロナルド・レーガンはGDPと軍事力で日本がアメリカを追い抜くことを覚悟した。また、日本企業の輸出攻勢は[[貿易摩擦]]をもたらした。 |
経済学者の[[ラビ・バトラ]]は高い成長率と一億総中流を実現した1960年代から70年代の日本経済を指して「[[資本主義]]の究極の理想に近い」と評価した。[[ロナルド・レーガン]]はGDPと軍事力で日本がアメリカを追い抜くことを覚悟した。また、日本企業の輸出攻勢は[[貿易摩擦]]をもたらした。 |
||
[[日本の民営化の一覧#中曽根内閣(1982-1987)|中曽根内閣の民営化政策]]が推進され始めて程なく[[プラザ合意]]がなされた。これにより[[円高不況]]が起こり、そこで行き過ぎた[[政策金利|金融緩和]]がなされて[[リクルート事件]]の頃に[[バブル景気]]が到来した。1人あたりの[[国民所得]]はアメリカに次ぐ世界第2位となった。引き続き年5%-7%の高い経済成長が見込まれ、21世紀は日本の時代になるとまでいわれた([[ジャパン・アズ・ナンバーワン]])。日本は大規模な好景気を経験する一方、アメリカなどは経済低迷を経験していたため日米間で[[日米貿易摩擦|貿易摩擦]]が起きた。 |
[[日本の民営化の一覧#中曽根内閣(1982-1987)|中曽根内閣の民営化政策]]が推進され始めて程なく[[プラザ合意]]がなされた。これにより[[円高不況]]が起こり、そこで行き過ぎた[[政策金利|金融緩和]]がなされて[[リクルート事件]]の頃に[[バブル景気]]が到来した。1人あたりの[[国民所得]]はアメリカに次ぐ世界第2位となった。引き続き年5%-7%の高い経済成長が見込まれ、21世紀は日本の時代になるとまでいわれた([[ジャパン・アズ・ナンバーワン]])。日本は大規模な好景気を経験する一方、アメリカなどは経済低迷を経験していたため日米間で[[日米貿易摩擦|貿易摩擦]]が起きた。 |
||
2024年1月11日 (木) 17:58時点における版
| 日本の歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京奠都以降を東京時代(1868年 – )とする説もある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各時代の始期・終期は諸説ある。各記事を参照のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category:日本のテーマ史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時代区分
日本の歴史における時代区分には様々なものがあり、定説と呼べるものはない。︵原始・︶古代・中世・近世・近代︵・現代︶とする時代区分法が歴史研究では広く受け入れられている。この場合でも、各時代の画期をいつに置くかは論者によって大きく異なる。 古代の始期については古代国家の形成時期をめぐって見解が分かれており、3世紀説、5世紀説、7世紀説があり、研究者の間で七五三論争と呼ばれている[1]。中世については、中世を通じての社会経済体制であった荘園公領制が時代の指標とされ、始期は11世紀後半〜12世紀の荘園公領制形成期に、終期は荘園公領制が消滅した16世紀後半の太閤検地にそれぞれ求められる。近世は、太閤検地前後に始まり、明治維新前後に終わるとされる。近代の始期は一般に幕末期〜明治維新期とされるが、18世紀前半の家内制手工業の勃興を近代の始まりとする考えもある。さらに、第二次世界大戦での敗戦をもって近代と現代を区分することもあるが、最近は日本史においても、近代と現代の境目は冷戦構造が崩壊して、バブル崩壊で右肩上がりの経済成長が終わった1990年前後に変更すべきという意見もある。[誰?]︵以上の詳細→古代、中世、近世、近代、現代︶ 上記のような時代区分論は、発展段階史観の影響を少なからず受けており、歴史の重層性・連続性にあまり目を向けていないという限界が指摘されている。そのため、時代を区分する対象ではなく移行するものとして捉える﹁時代移行論﹂を提唱する研究者も現れ始めている。 一般によく知られている時代区分は、主として政治センターの所在地に着目した時代区分である。この時代区分は明確な区分基準を持っている訳ではなく、歴史研究上の時代区分としては適当でない。単に便宜的に用いられているに過ぎない時代区分である。文献史料がなく考古資料が残る時代は、考古学上の時代区分に従い、旧石器時代・縄文時代と区分する。文献史料がある程度残る時代以降は政治の中心地の所在地に従って、弥生時代後期〜古墳時代 (大阪市)・飛鳥時代︵明日香村︶・奈良時代︵奈良市︶・平安時代︵京都市︶・鎌倉時代︵鎌倉市︶・室町時代︵京都市︶・安土桃山時代︵近江八幡市・京都市伏見区︶・江戸時代︵東京23区・旧東京市︶と区分する。ただこれだけでは必ずしも十分でないため弥生時代後期から飛鳥時代前期に大和時代、鎌倉時代の後に建武の新政、室町時代前期に南北朝時代、室町時代後期に戦国時代、江戸時代後期に幕末という区分を設けており、このうち南北朝時代と戦国時代は中国の歴史の時代区分からの借用である。江戸時代の次は、天皇の在位期間︵一世一元の制︶に従って明治時代︵明治天皇︶・大正時代︵大正天皇︶・昭和時代︵昭和天皇︶・平成時代︵明仁︶・令和時代︵徳仁︶と呼ばれている。これらのうち、明治維新から1947年︵昭和22年︶5月2日までの時代︵明治時代・大正時代・戦前昭和時代︶を﹁大日本帝国時代﹂と、政体︵憲法︶に因んで呼ぶ例もある[2]。また、北海道・北東北、南西諸島などの周縁部については、→日本史時代区分表︶。 また、文化面に着目して、縄文文化・弥生文化・古墳文化・飛鳥文化・白鳳文化・天平文化・弘仁・貞観文化・国風文化・院政期文化・鎌倉文化・北山文化・東山文化・桃山文化・元禄文化・化政文化などが用いられる。原始
旧石器時代



縄文時代

弥生時代


古代
古墳時代

飛鳥時代
奈良時代


平安時代

中世
鎌倉時代


南北朝時代


室町時代


戦国時代


近世
安土桃山時代



江戸時代




近現代
明治時代
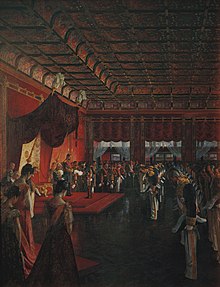
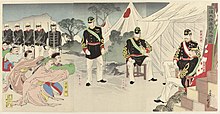

 イタリア、
イタリア、 アメリカ合衆国、
アメリカ合衆国、 フランス、
フランス、 オーストリア=ハンガリー帝国海軍、
オーストリア=ハンガリー帝国海軍、 日本海軍、
日本海軍、 ドイツ帝国海軍、
ドイツ帝国海軍、 イギリス海軍、
イギリス海軍、 ロシア帝国海軍
1889年から1900年にかけて清で義和団の乱が発生、西太后は日本や西洋列強国に宣戦布告、その影響で日本は八カ国連合軍に加わり、勝利した。清に再び勝利した日本の権益は増加することになる。
1891年には日本を訪日していたロシア帝国の皇帝ニコライ二世が警備にあたっていた警察官・津田三蔵に暗殺未遂で終わる大津事件が発生した。
1904年に開戦した日露戦争ではロシア帝国側の艦隊がほぼ全滅するといった反面、日本側の損害は駆逐艦1大破、水雷艇数隻沈没で、主力艦は中破すらなく、ほとんど無傷であったという異例の結果を残した。
日本の勝利後、ロシア帝国から賠償金を得られず大きな負債が残ったが、ロシア帝国が清国から受領していた大連と旅順の租借権獲得、東清鉄道の一部である南満洲鉄道を獲得するなど、満洲における権益を得ることとなった。当時としては非白人国として唯一列強諸国の仲間入りをし、アジア諸国の中で唯一ほぼ全ての不平等条約改正を達成、欧米諸国と対等の国家となり、のちには﹁五大国﹂の一角をも占めることとなり、日清戦争と日露戦争に連続的に勝利したことで下関条約やポーツマス条約といった日本側が有益になる条約を締結した。
さらに大韓帝国においてロシアの脅威がなくなったことで日本は保護国化を決行する。1905年︵明治38年︶には第二次日韓協約締結後大韓帝国の外交権は日本に接収された。同年には韓国統監府を設立、1910年︵明治43年︶の日韓併合条約の締結により、大韓帝国は日本に正式に併合された。
明治末期の1912年にはスウェーデンで行われたストックホルムオリンピックに初めて出場した。これはアジア諸国で初である。
ロシア帝国海軍
1889年から1900年にかけて清で義和団の乱が発生、西太后は日本や西洋列強国に宣戦布告、その影響で日本は八カ国連合軍に加わり、勝利した。清に再び勝利した日本の権益は増加することになる。
1891年には日本を訪日していたロシア帝国の皇帝ニコライ二世が警備にあたっていた警察官・津田三蔵に暗殺未遂で終わる大津事件が発生した。
1904年に開戦した日露戦争ではロシア帝国側の艦隊がほぼ全滅するといった反面、日本側の損害は駆逐艦1大破、水雷艇数隻沈没で、主力艦は中破すらなく、ほとんど無傷であったという異例の結果を残した。
日本の勝利後、ロシア帝国から賠償金を得られず大きな負債が残ったが、ロシア帝国が清国から受領していた大連と旅順の租借権獲得、東清鉄道の一部である南満洲鉄道を獲得するなど、満洲における権益を得ることとなった。当時としては非白人国として唯一列強諸国の仲間入りをし、アジア諸国の中で唯一ほぼ全ての不平等条約改正を達成、欧米諸国と対等の国家となり、のちには﹁五大国﹂の一角をも占めることとなり、日清戦争と日露戦争に連続的に勝利したことで下関条約やポーツマス条約といった日本側が有益になる条約を締結した。
さらに大韓帝国においてロシアの脅威がなくなったことで日本は保護国化を決行する。1905年︵明治38年︶には第二次日韓協約締結後大韓帝国の外交権は日本に接収された。同年には韓国統監府を設立、1910年︵明治43年︶の日韓併合条約の締結により、大韓帝国は日本に正式に併合された。
明治末期の1912年にはスウェーデンで行われたストックホルムオリンピックに初めて出場した。これはアジア諸国で初である。
大正時代




昭和時代






平成時代






令和時代


歴史認識・歴史叙述
脚注
注釈
出典
参考文献
●堤, 隆﹃ビジュアル版・旧石器時代ガイドブック﹄新泉社︿シリーズ﹁遺跡を学ぶ﹂別冊第2巻﹀、2009年8月25日。ISBN 9784787709301。 ●松藤, 和人﹃日本列島人類史の起源-﹁旧石器の狩人﹂たちの挑戦と葛藤-﹄雄山閣、2014年5月22日。ISBN 9784639023135。 ●堤, 隆﹃旧石器時代研究への視座 No.2-特集:4万年前以前日本列島に人類はいたのか-﹄ 2巻、2020年11月5日。doi:10.24484/sitereports.86546。 ●﹃朝日百科 日本の歴史﹄ 全12巻、朝日新聞社 ●﹃岩波講座 日本通史﹄ 全21巻・別巻4巻、岩波書店、1993年 - 1996年 ●﹃日本の歴史﹄ 全26巻、講談社、2000年 - 2003年 ●﹃日本の歴史﹄ 全32巻、小学館、1973年 - 1976年 ●﹃大系日本の歴史﹄ 全15巻、小学館、1987年 - 1989年 ●﹃日本の歴史﹄ 全26巻・別巻5巻、中央公論社、1965年 - 1967年 ●﹃講座日本歴史﹄ 全13巻、東京大学出版会、1984年 - 1985年 ●﹃日本歴史大系﹄ 全6巻 山川出版社、1984年 - 1990年 ●﹃日本の時代史﹄ 全30巻、吉川弘文館、2002年 - 2004年 ●﹃国史大辞典﹄ 全15巻、吉川弘文館、1979年 - 1993年 ●﹃日本史大事典﹄ 全7巻、平凡社、1992年 - 1994年 ●﹃日本歴史大事典﹄ 全3巻、小学館、2000年 - 2001年 ●その他、Portal:歴史学/日本史も参照のこと。関連項目
- 歴史学
- 考古学
- 古文書
- 日中関係史
- 日朝関係史
- 日露関係史
- 日米関係史
- 朝鮮の歴史
- 台湾の歴史
- 沖縄県の歴史
- 日系アメリカ人の歴史
- アイヌの歴史
- 郷土史
- 日本の軍事史
- 日本の経済史
- 日本教育史
- 日本法制史
- 日本建築史
- 日本近代建築史
- 日本美術史
- 日本の文化
- 日本写真史
- 日本の女性史
- 日本の首都
- 日本の官制
- 日本の古代道路
- 日本の税金
- 日本史学史
- 日本史時代区分表
- 日本史の出来事一覧
- 各年の日本の一覧
- 日本の合戦一覧
- 日本が関与した戦争一覧
- 日本の神社一覧
- 日本の寺院一覧
- 令制国一覧
- 日本の元号一覧
- 日本の史跡一覧
- 天皇の一覧
- 皇室の系図一覧
- 摂政・関白の一覧
- 内閣総理大臣の一覧
- 日本国歴代内閣
- 戦前の政治家一覧
外部リンク
- 日本史年表(戦国・安土桃山)
- 日本の歴史ガイド
- 『日本誕生 -民族の歴史-』《→YouTube版》 - 『科学映像館』より。1967年に養命酒製造の企画の下で製作された短編映画。
《先土器時代から弥生時代にかけての日本民族の生活・文化について触れている。湯浅譲二音楽、日映科学映画製作所制作》 - 日本史に関する文献を探すには(主題書誌) - 調べ方案内(国立国会図書館)

