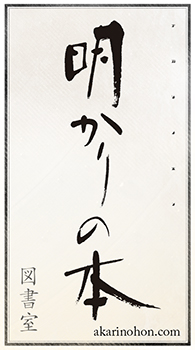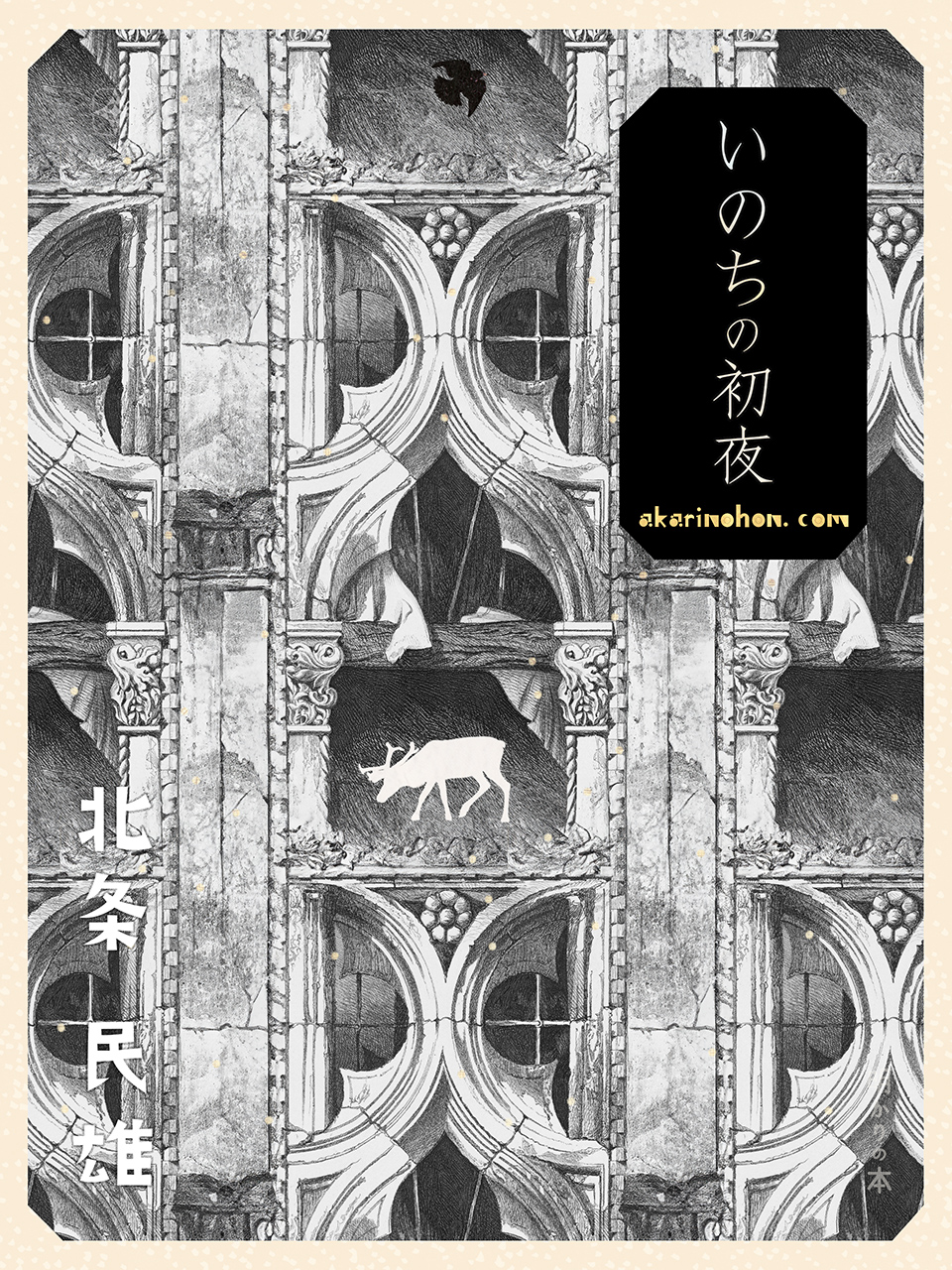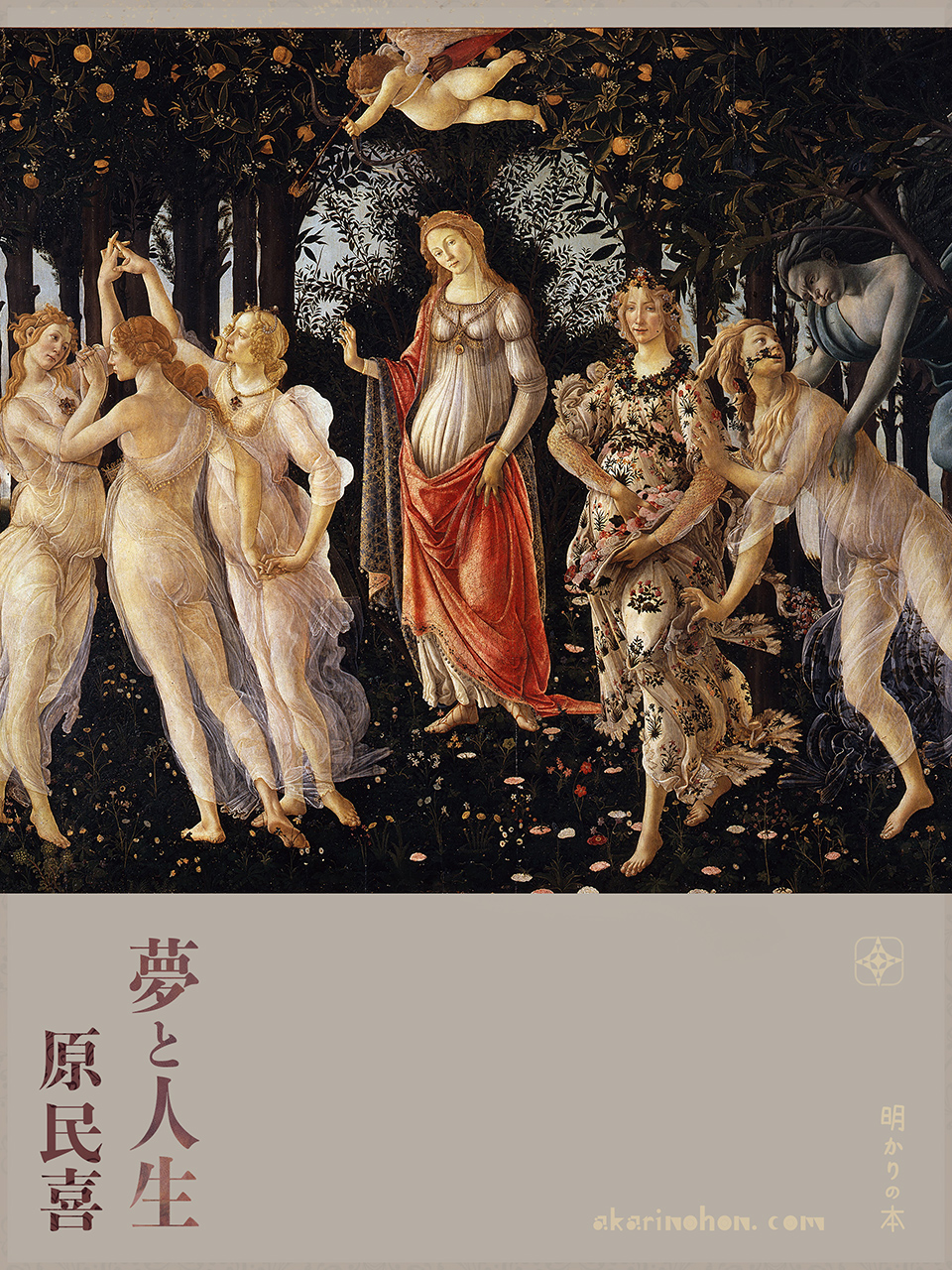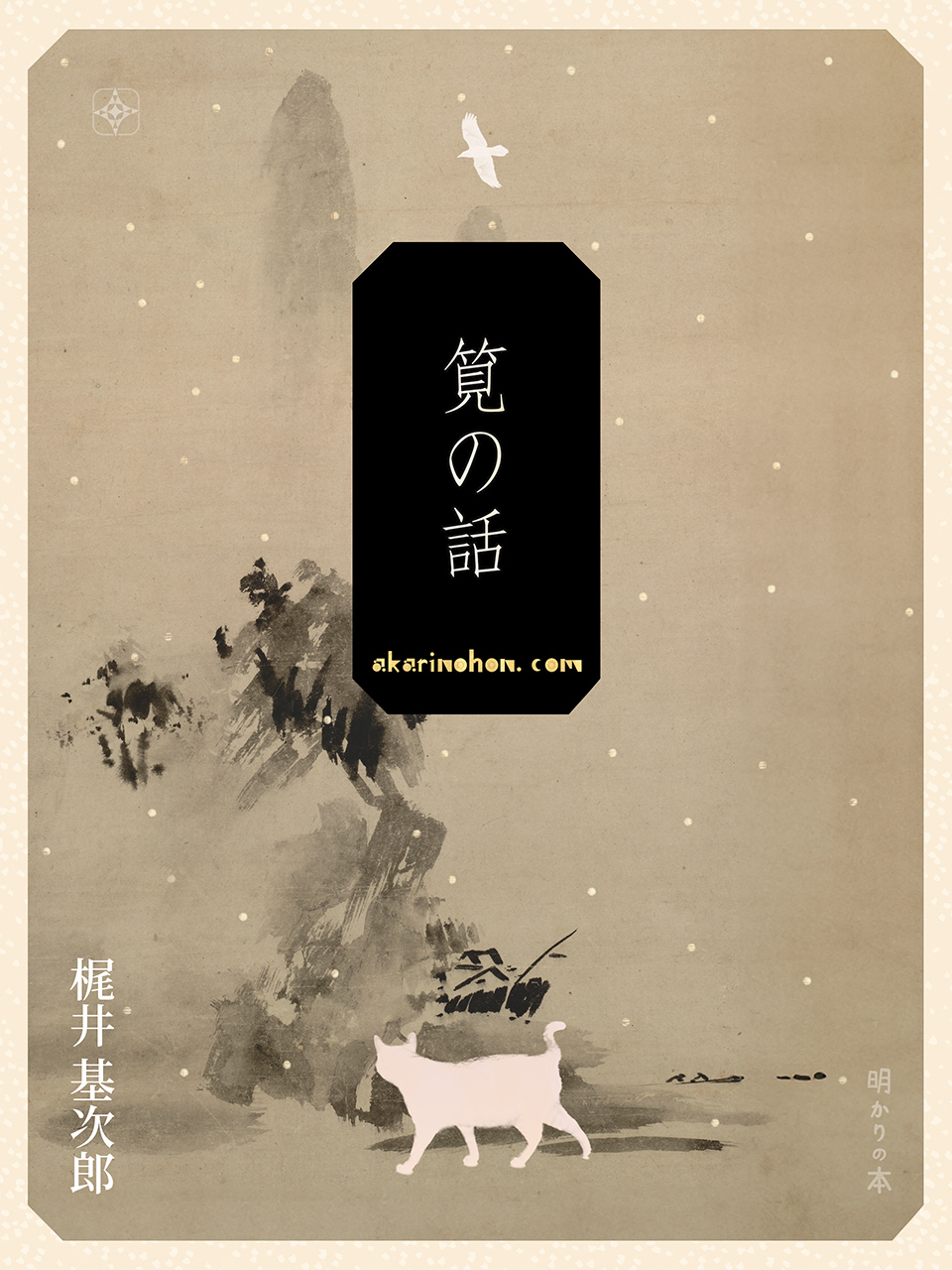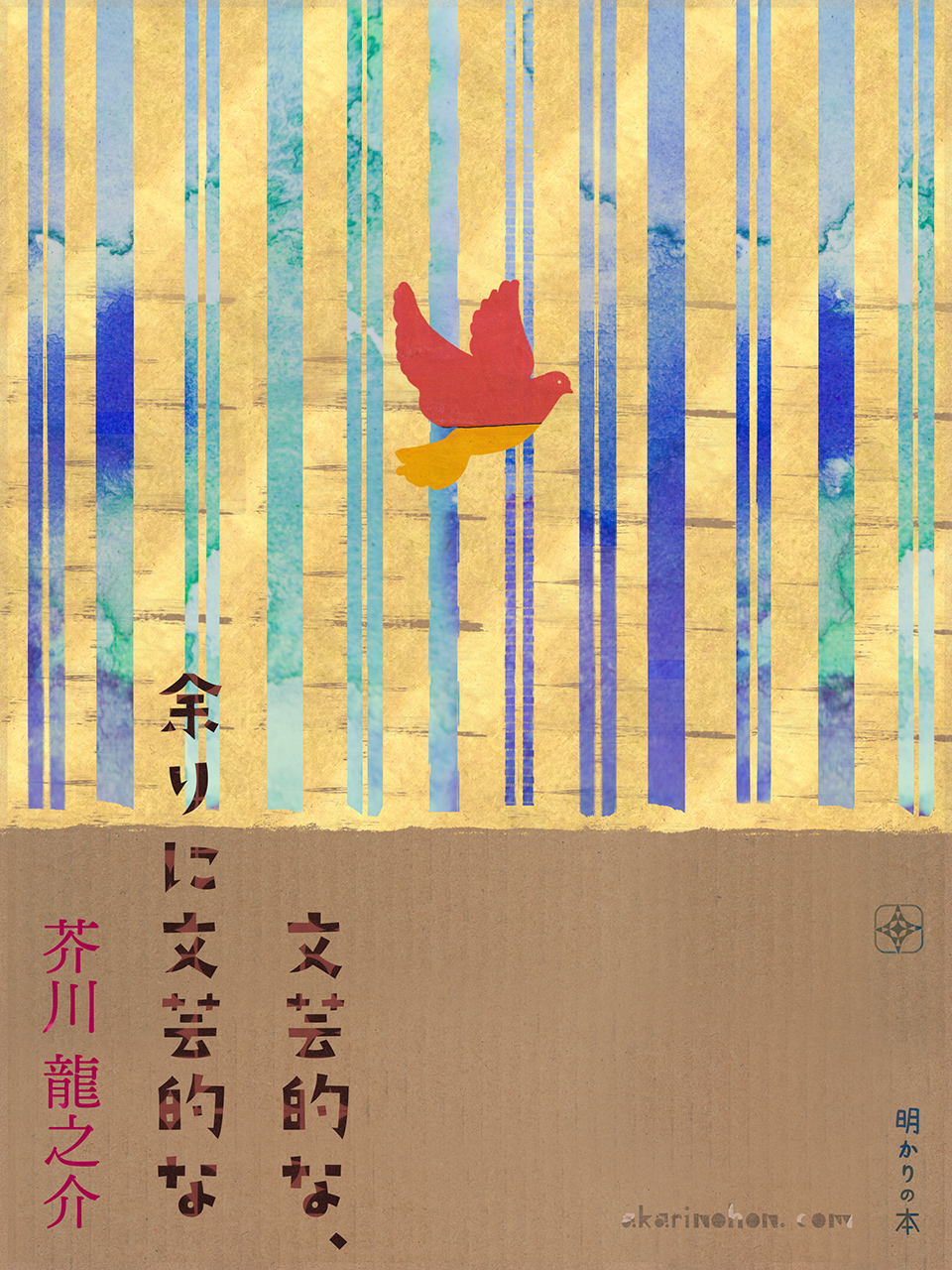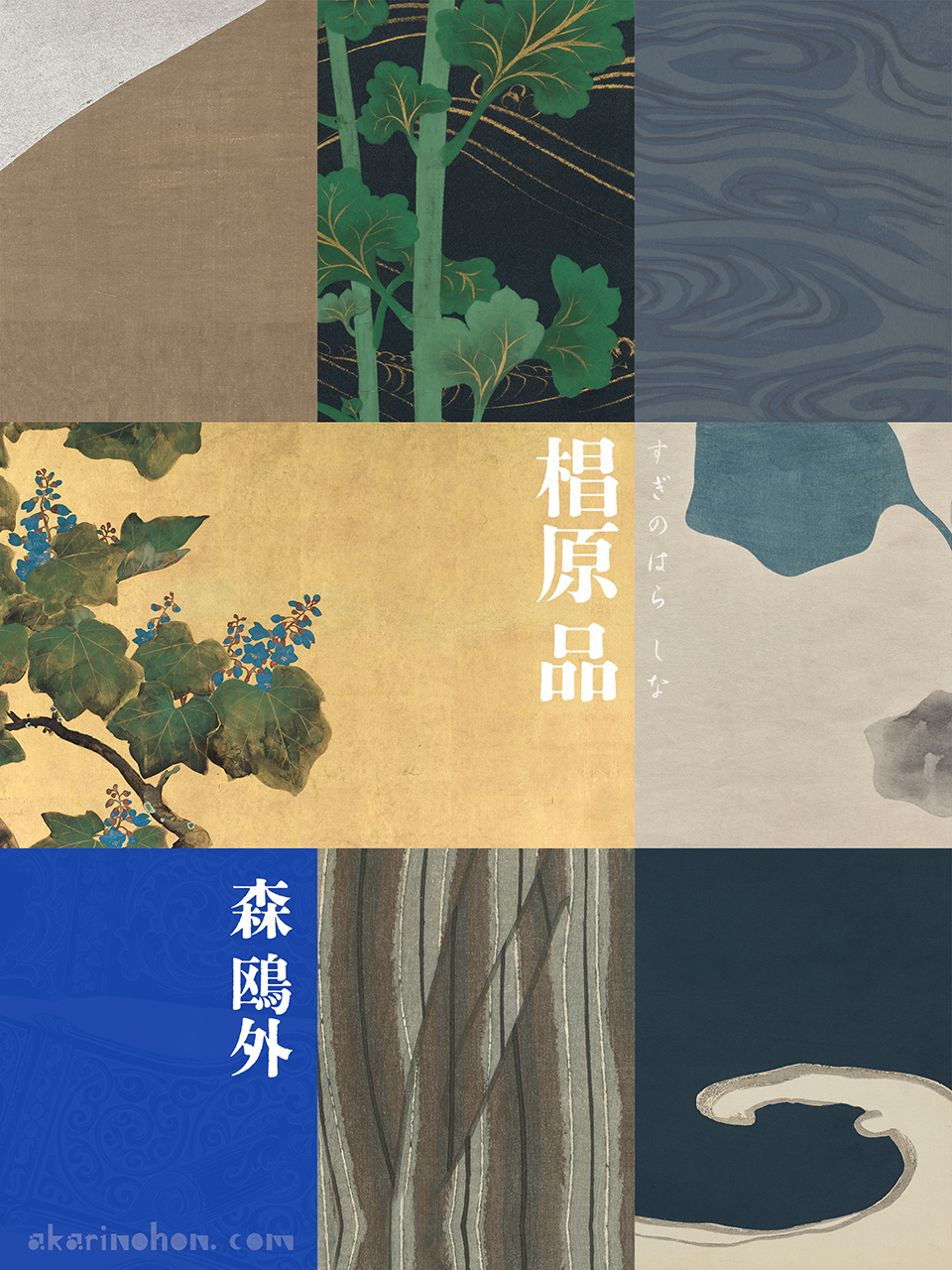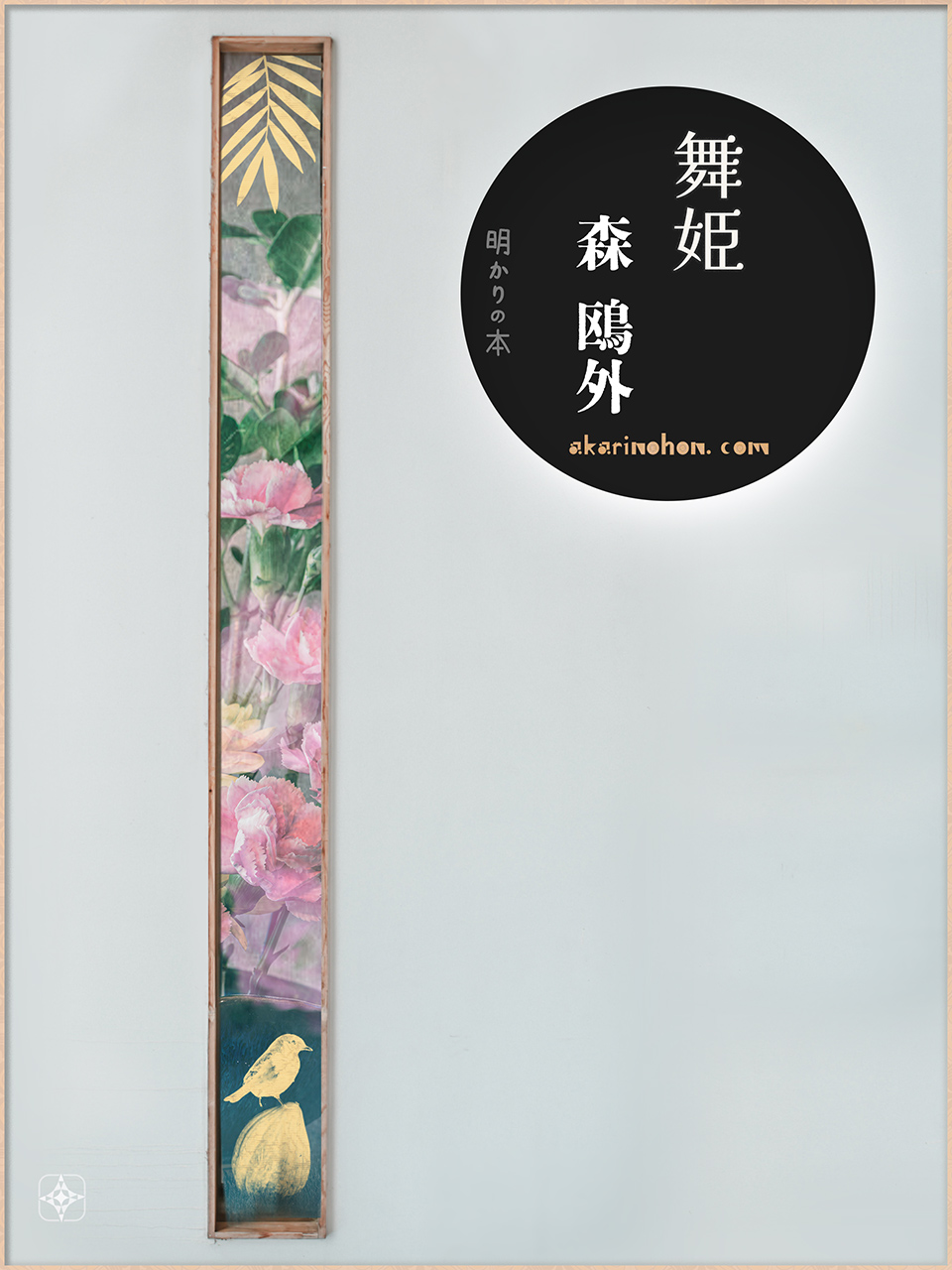今日は、北条民雄の「いのちの初夜」を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。
子どものころに感動した本を、大人になってから再読するのは緊張するんですが、本作は読みやすい文体で構成された、児童文学としても愛読されうる作品に思いました。
病者仲間の手にしている義眼の描写がみごとで魅入られました。北条民雄にとっての文学は、この義眼や松葉杖のような存在だったのでは、と思いました。序盤で自死と生と木々のことについて書くのですが、これは聖書の死生観の影響も色濃いのでは、と思ったのですが、作者の北条民雄はヨブ記を愛読していて、この物語との共通項があるように思いました。中盤から後半にかけて苦悶の描写が展開されて凄絶な心情が記されてゆき、そこから闘病記に閉塞せずに、いのちの詩と生命論に進んでゆくのがもの凄い作品に思いました。病の体験と、聖書のヨブの文学性が混交したような独特な文学でした。これは発表当時から文学界でも広く読まれた作品なんです。若いころに病で苦しんだ現実の記憶と、この本に描かれた文学上の記憶が、心中で入り混じってゆくという読書体験をした、1936年ごろの読者は多かったのでは、と思いました。 「いのちの初夜」という言葉は、師の川端康成に添削してもらってつけた題名なんだそうです。
装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約5秒)