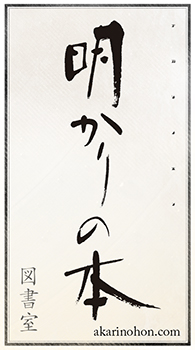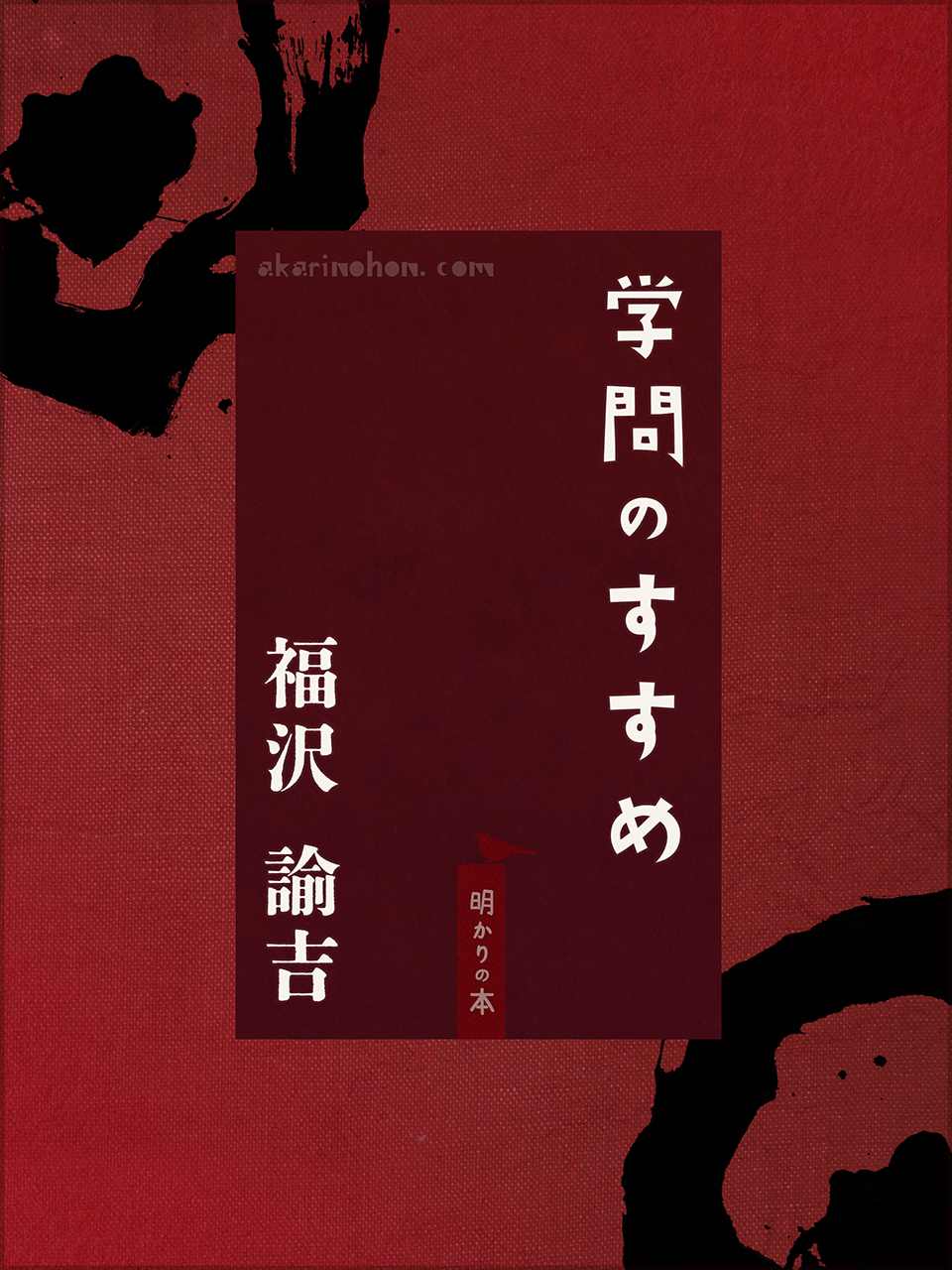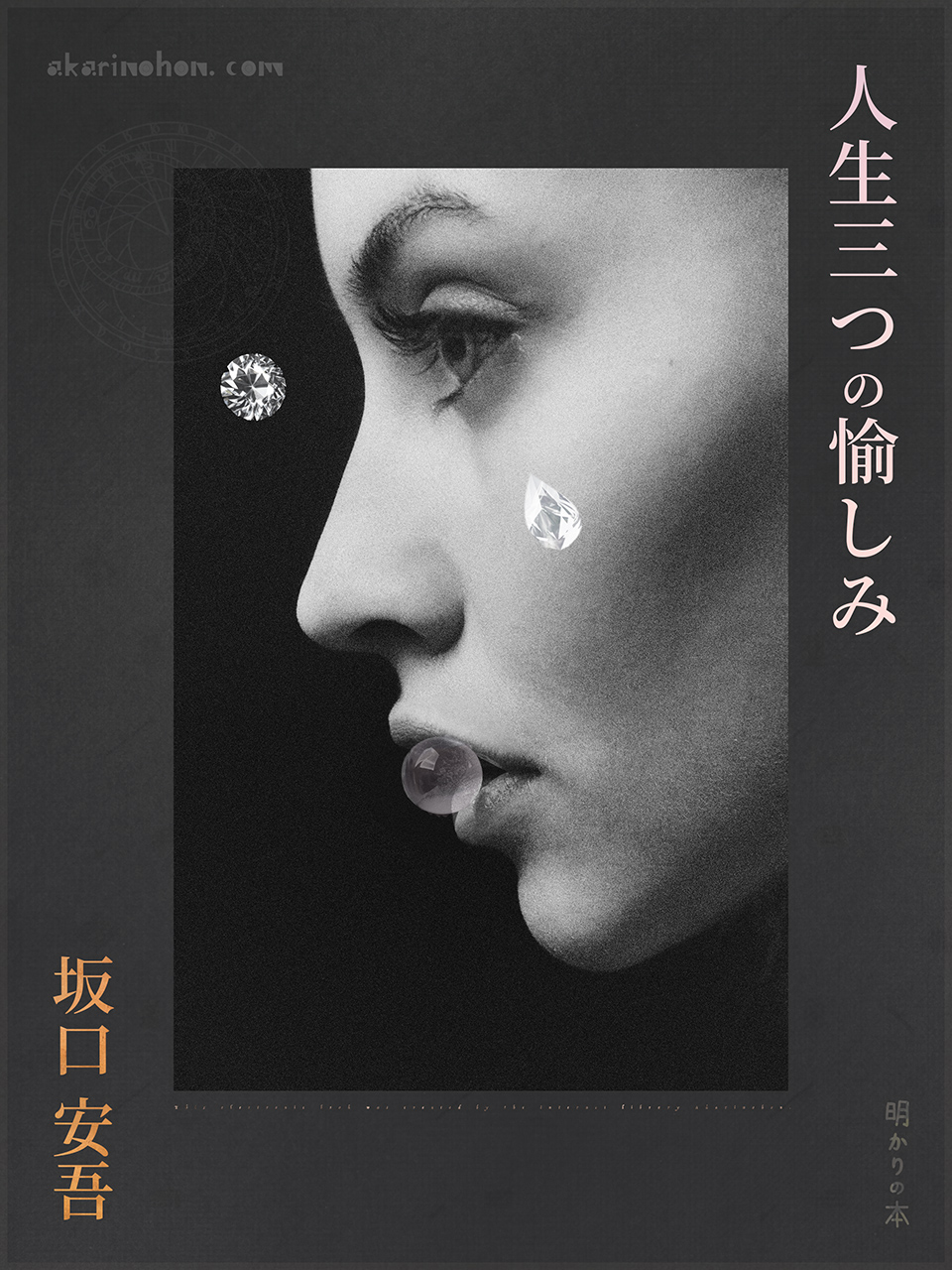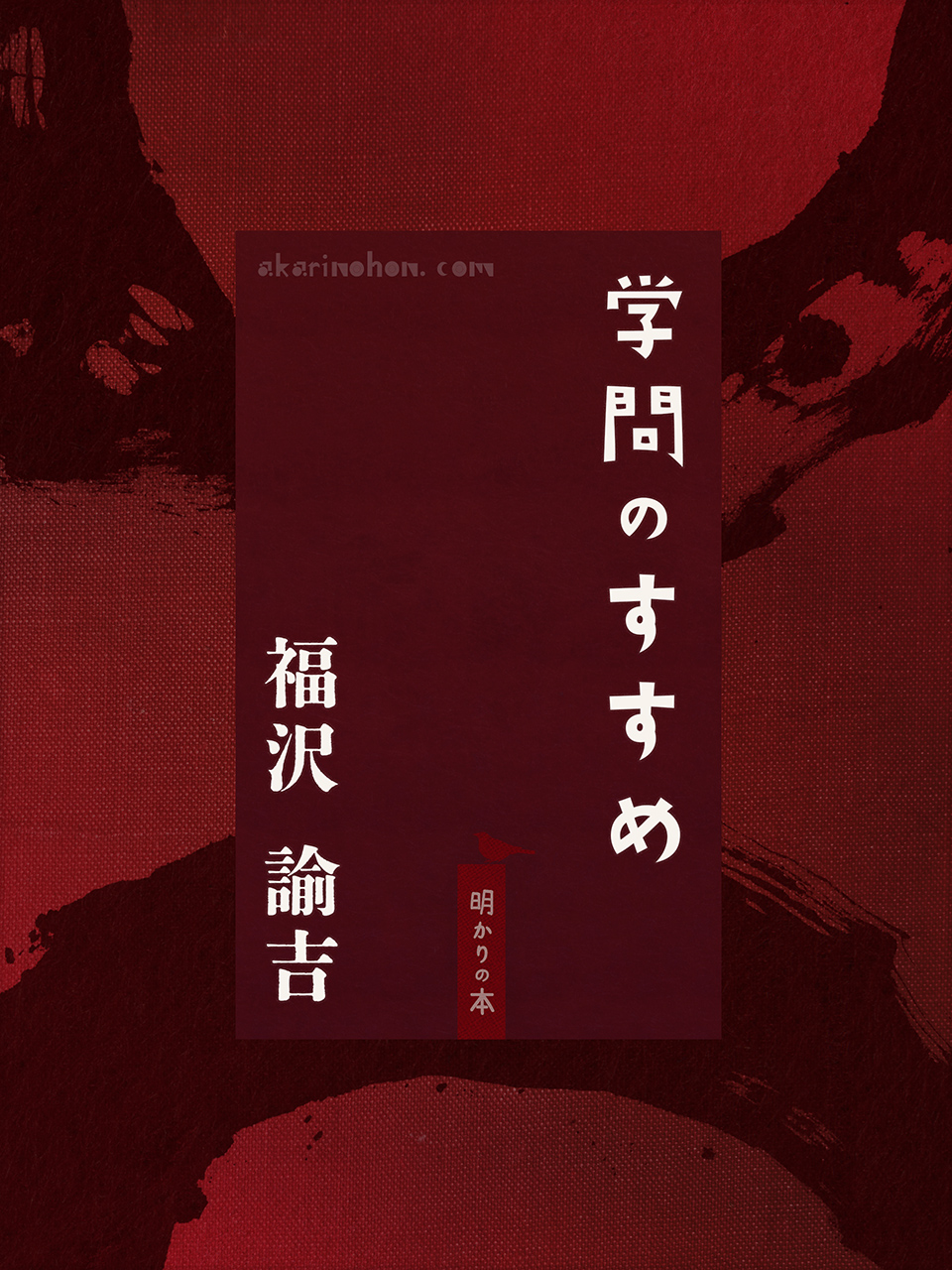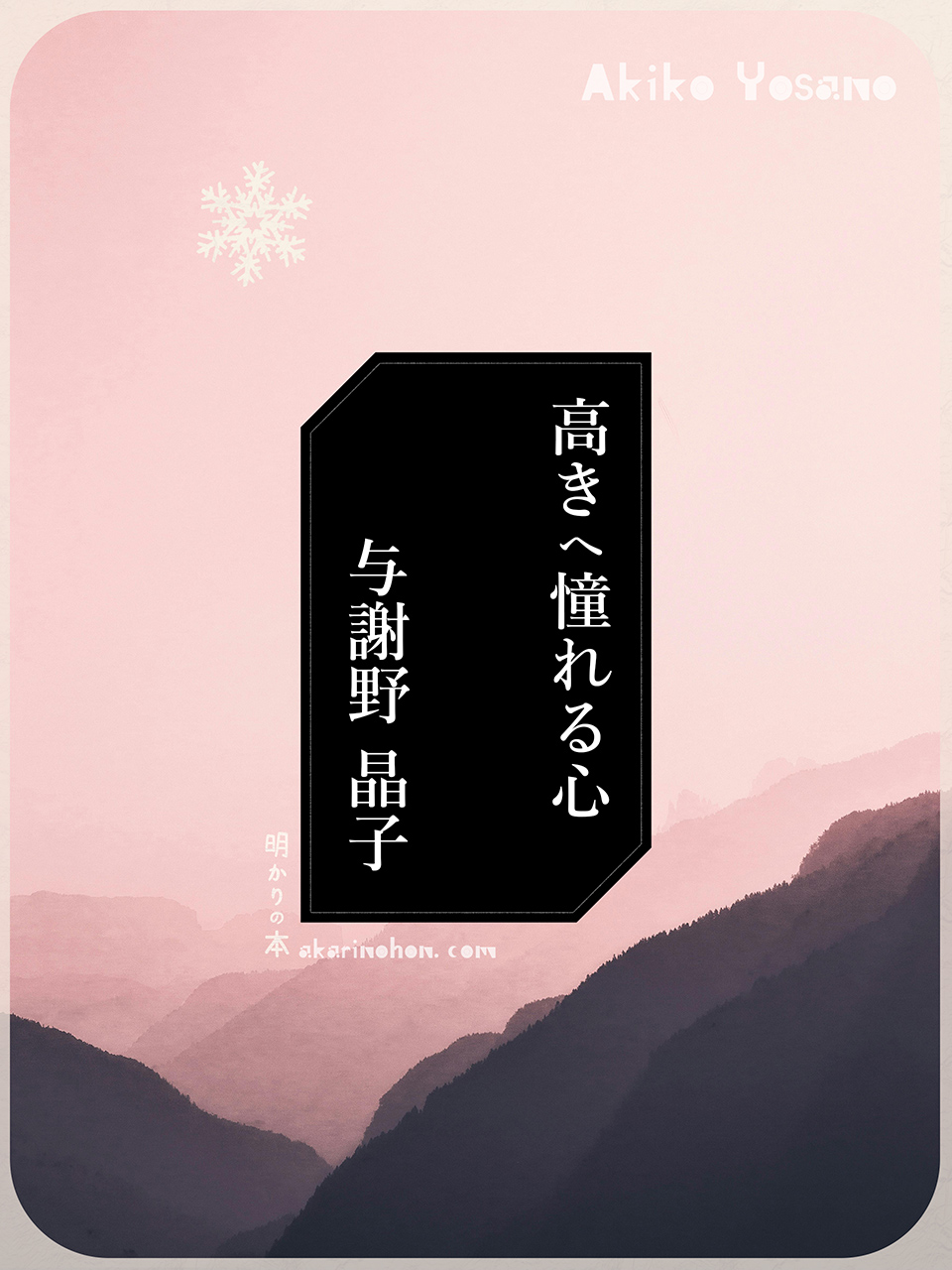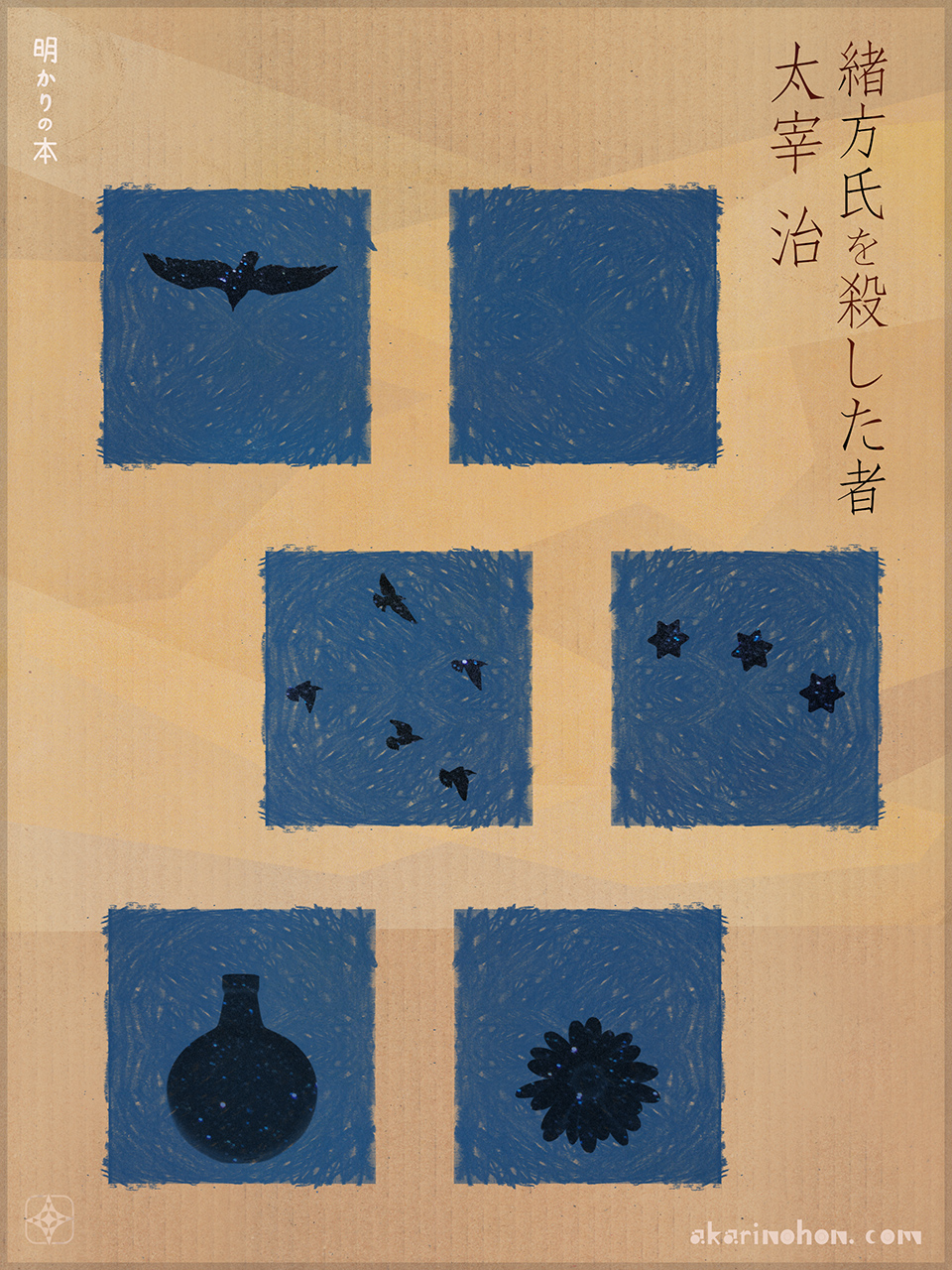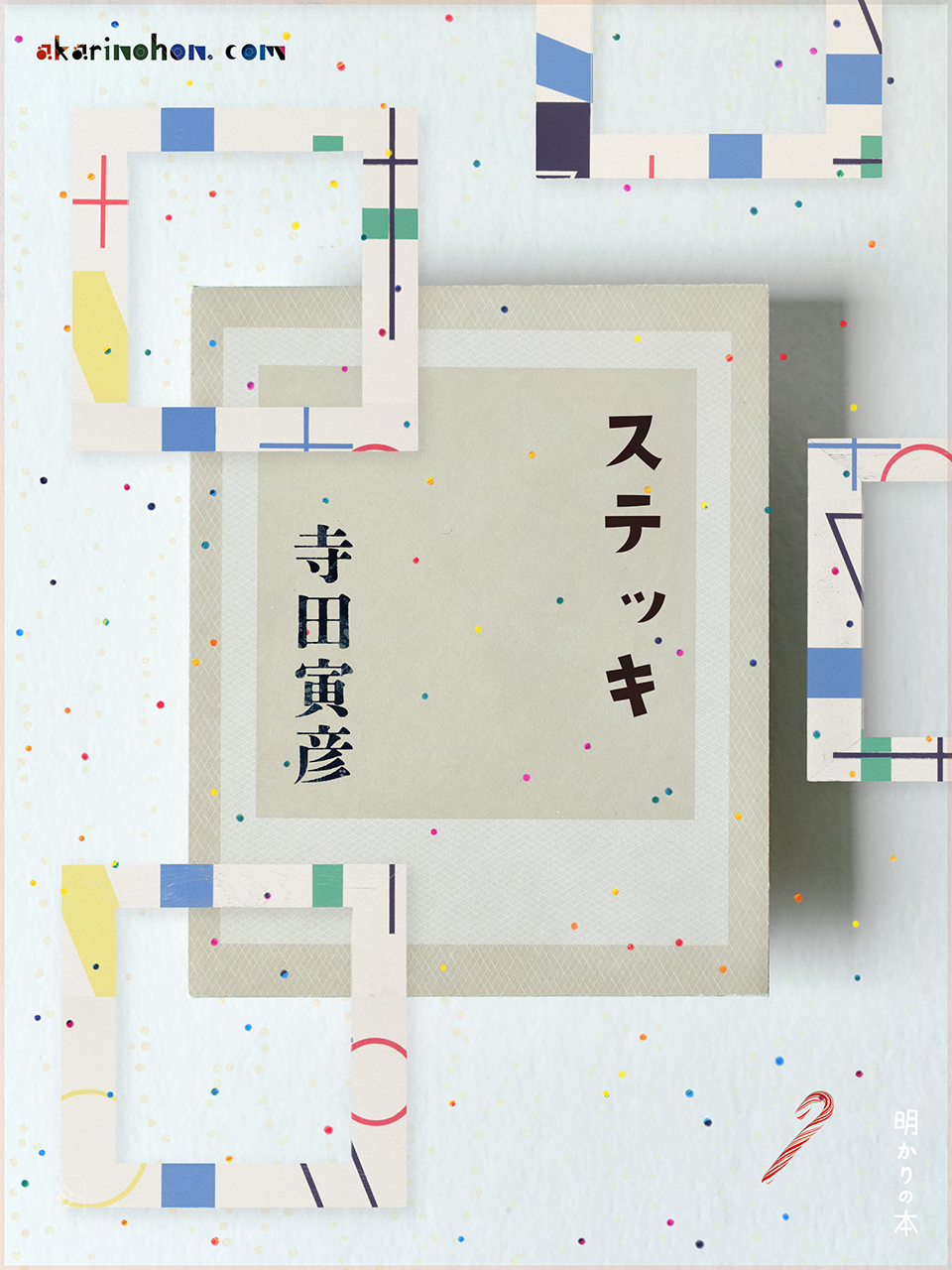今日は、福沢諭吉の「学問のすすめ」その13を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。
こんかいは怨望について論じていました。後半でこの問題をまとめた箇所があってそれは「人間最大の禍は怨望にありて、怨望の源は窮より生ずるもの」ということで人類でいちばんの不幸は怨みをつのらせることで、これは閉鎖的な状況によって作り出される。だから他人の言論の自由は重要だし、他人の経済的な自由も重要になる。不幸が起きている現場では、この経済的自由と言論の自由が壊されている。中世日本で言うところの、殿様の御殿に囲われた女中たちが直面した、不合理な賞罰制度と不自由と、そこから生ずる怨みのことが例示されていました。福沢諭吉の、怨望の解決案としては、言論の自由と経済の自由を拡張する、ということを述べていました。本文こうです。![]()
自由に言わしめ、自由に働かしめ、富貴も貧賤もただ本人のみずから取るにまかして、他よりこれを妨ぐべからざるなり。![]()
凶悪な犯罪の場合は、壊れた発言と壊れた金力というのが中心にあるようにも思うんですが、他人の言論の自由を豊かにしてゆく、というのがどうも重要なんだろうと、思いました。
装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約3秒)
★ 『学問のすすめ』第一編(初編)から第一七編まで全文を通読する
追記 現代のAI到来時代にも通用することを、福沢諭吉は論じているように思いました。福沢諭吉は「人間最大の災いは怨みにある、怨みの源は窮から生ずる」と述べています。AIが進化して労働者が減ってゆく現代に、あらゆる人の「自由に言わしめ、自由に働かしめ」ということを実現するには、運輸業をすべてAIが担当するころに、1%の超富裕者層からの税金を使ってベーシックインカム制度を導入する必要があるのでは、と思いました。