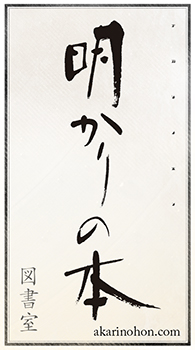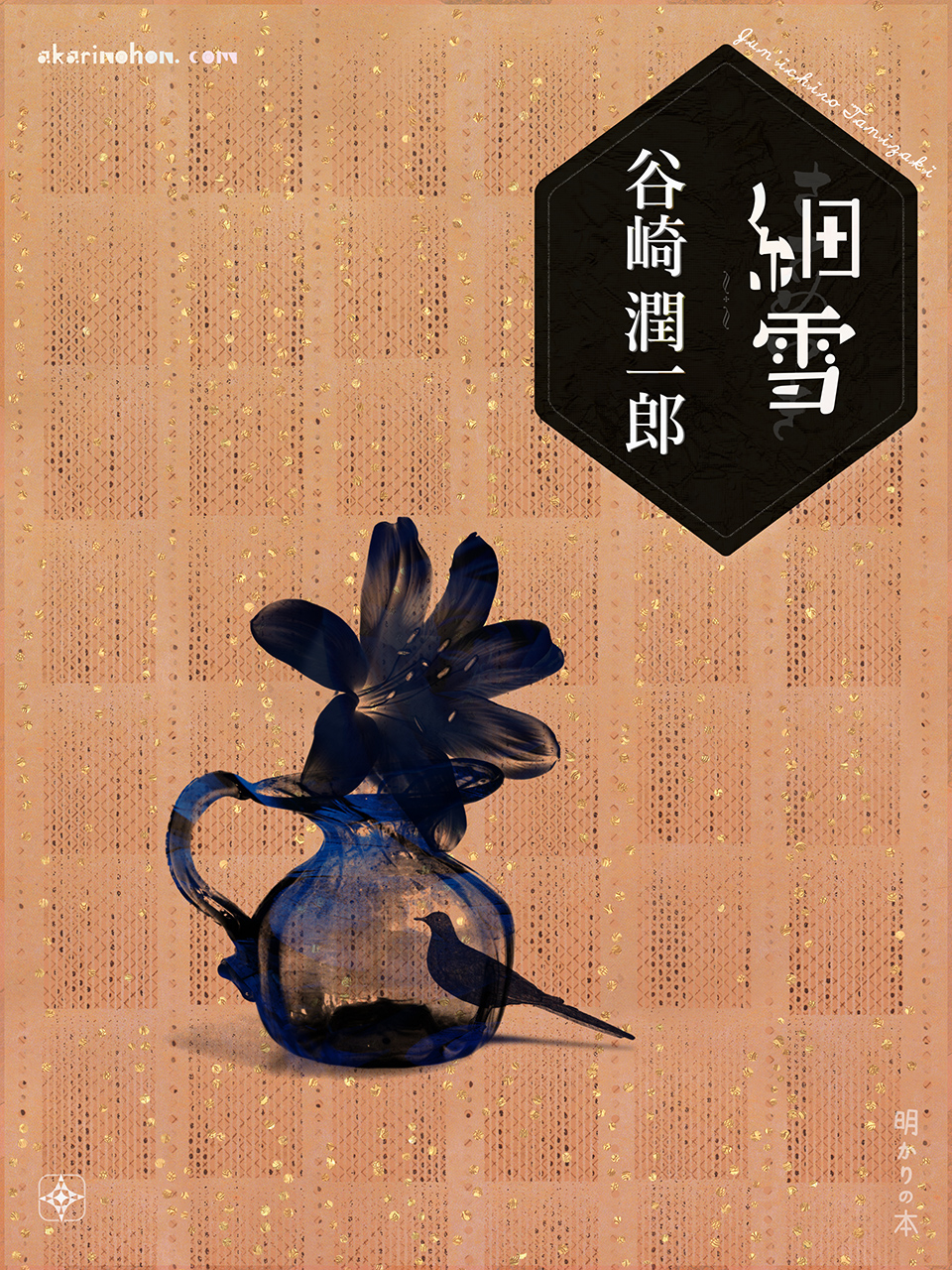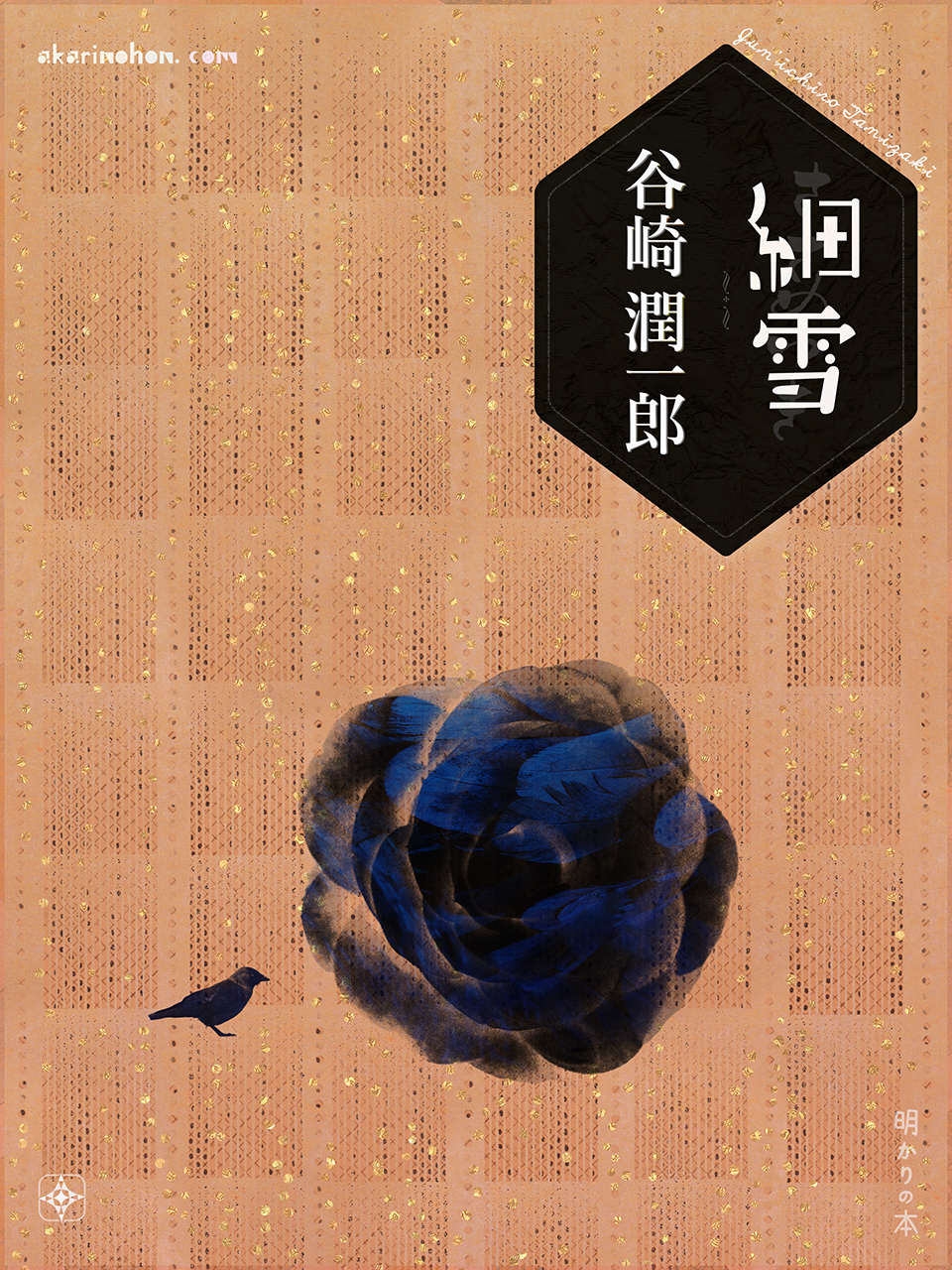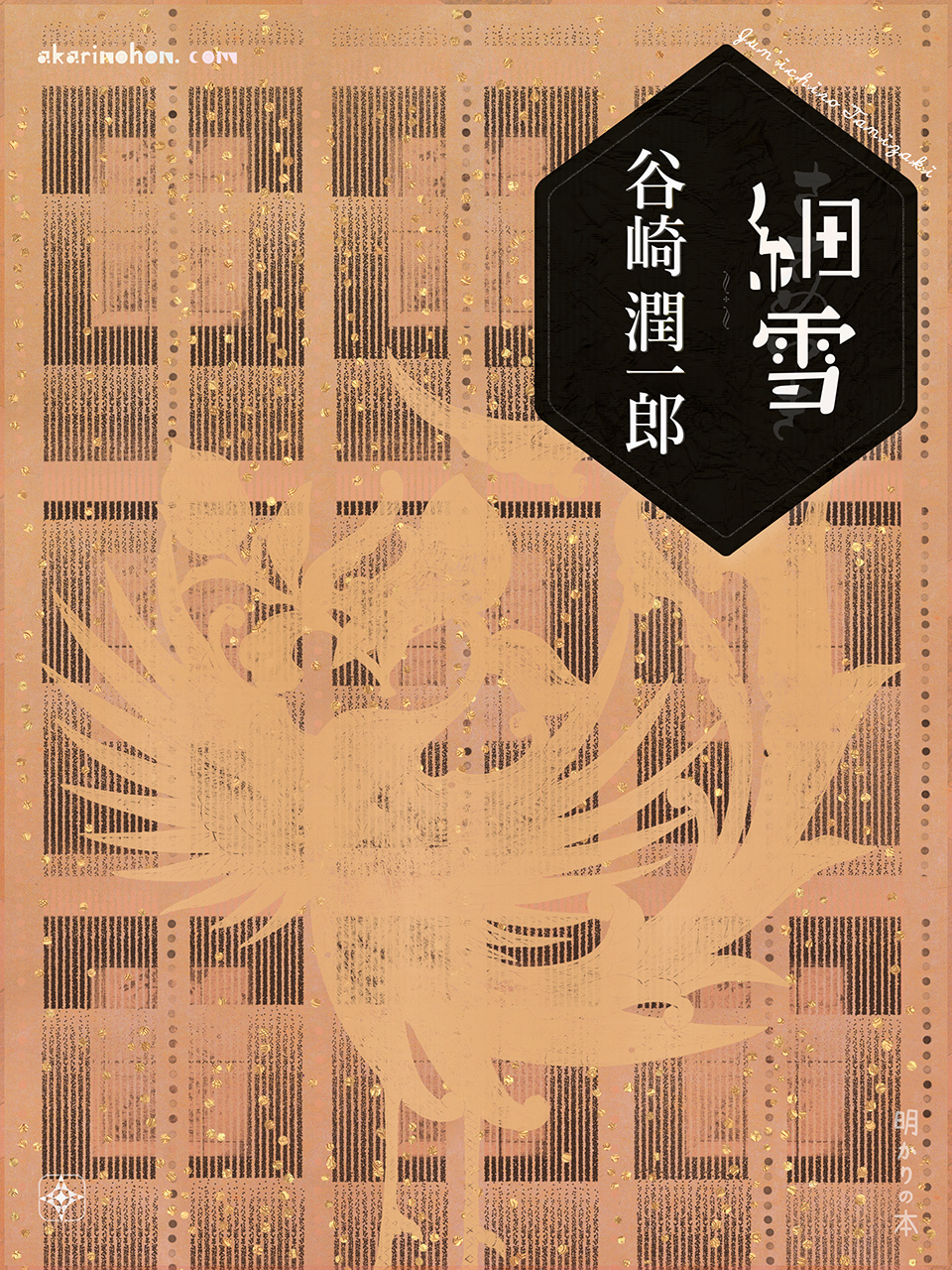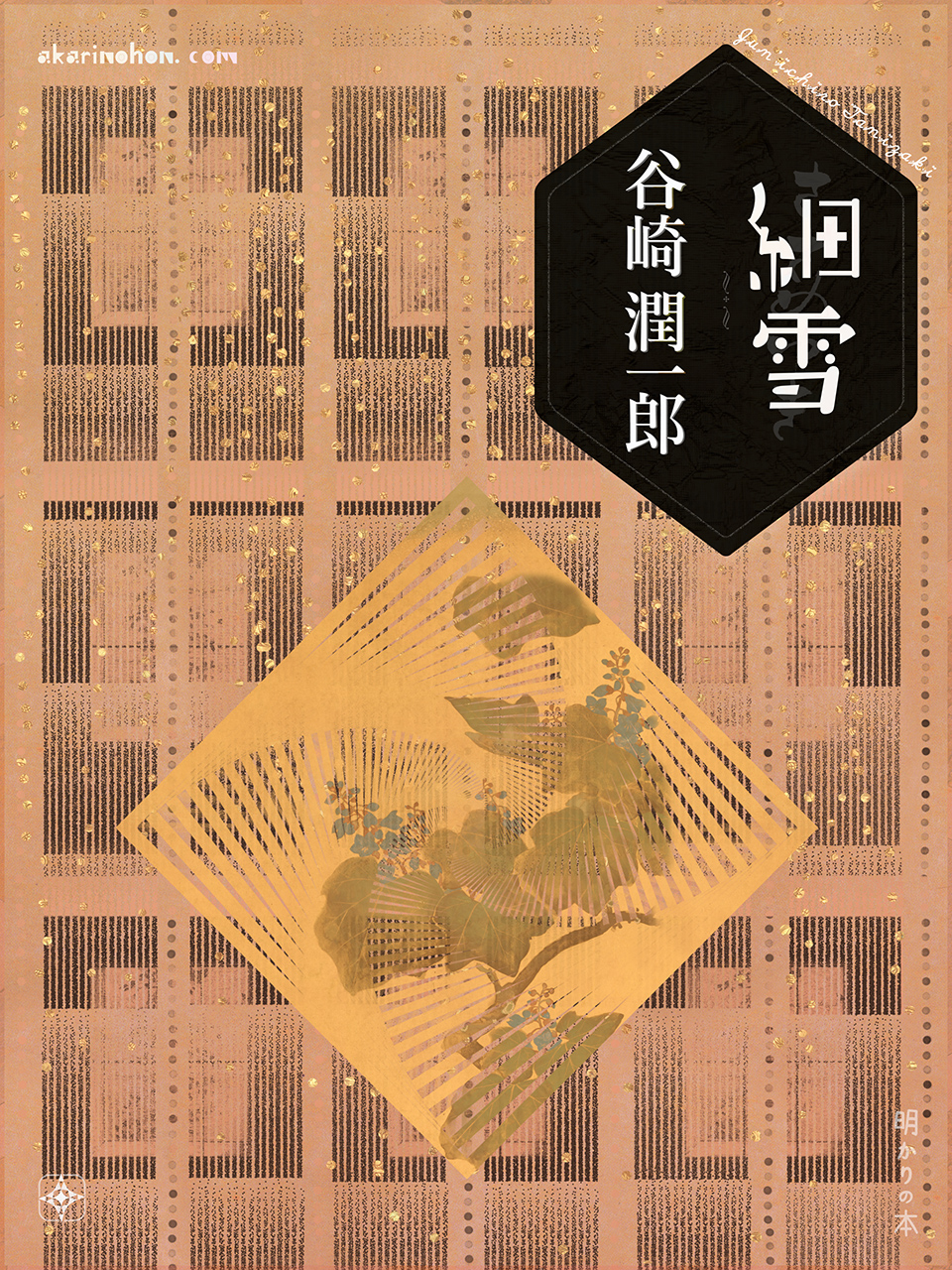今日は、谷崎潤一郎の「細雪」その41を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。
舞の師匠を見舞う妙子の描写がありました。おさく師匠の訃を聞いた妙子の、心情と行動が記されてゆきました。本文こうです。![]()
葬儀も残暑の厳しい日に、阿倍野でほんの小人数で営まれたが、その人達が殆どそっくり居残って隣の火葬場へ送って行き、お骨が焼けるのを待っている間に故人を偲ぶいろいろの話が出た。![]()
この前後の描写が静謐で、これが第二次大戦が終結した敗戦後すぐの二十世紀中盤に「陰翳礼賛」とともに世界中で読まれた日本文学なんだというように思いました。次回に続きます。
装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約20頁 ロード時間/約3秒)
当サイトでは『細雪 中巻一』を通し番号で『細雪 三十』と記載しています。『中巻三十五』は通し番号で『六十四』と表記しています。
「細雪」の上中下巻、全巻を読む。(原稿用紙換算1683枚)
谷崎潤一郎『卍』を全文読む。 『陰翳礼賛』を読む。
■登場人物
蒔岡4姉妹 鶴子(長女)・幸子(娘は悦ちゃん)・雪子(きやんちゃん)・妙子(こいさん)