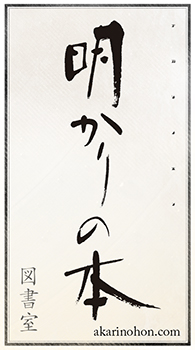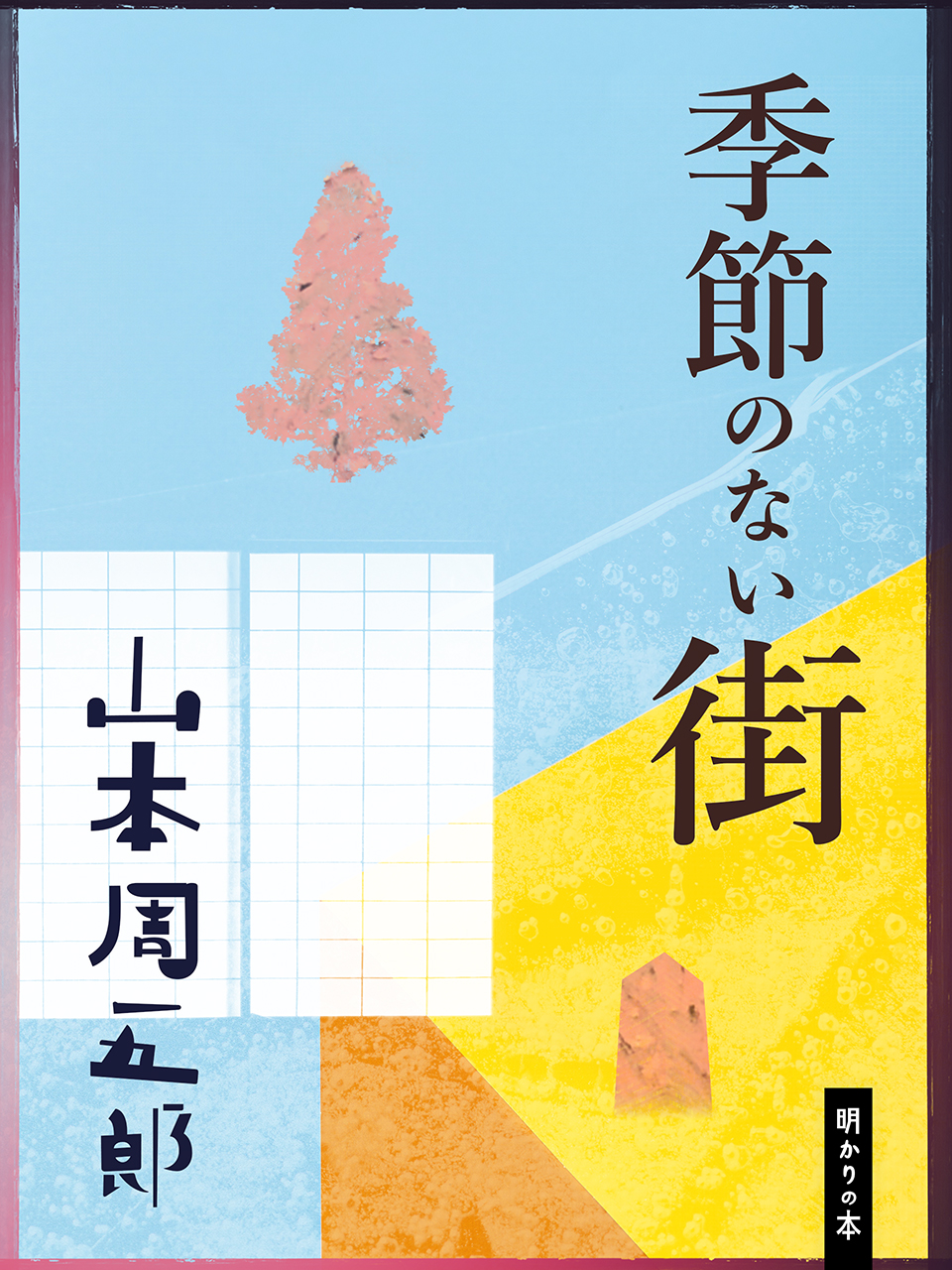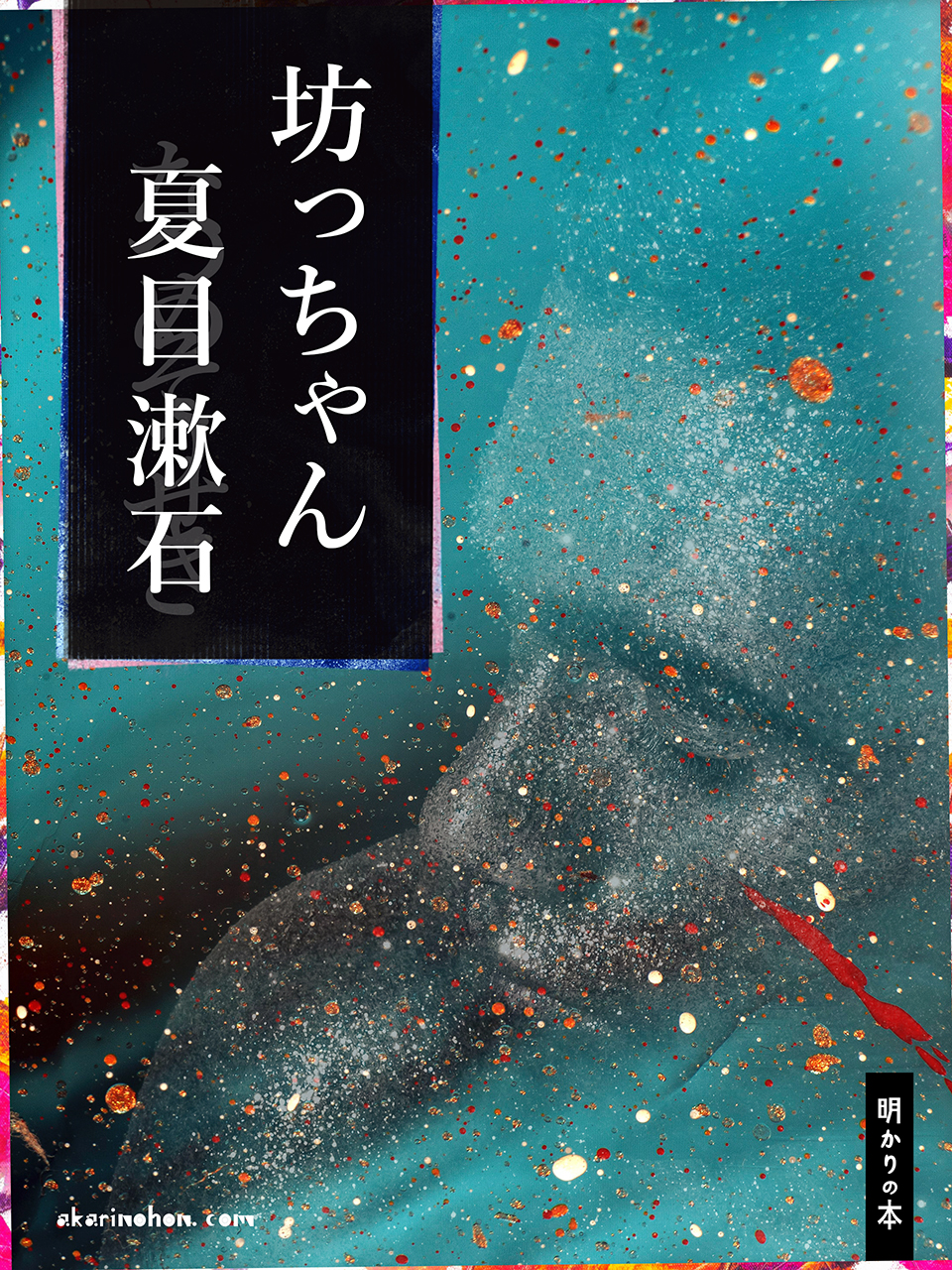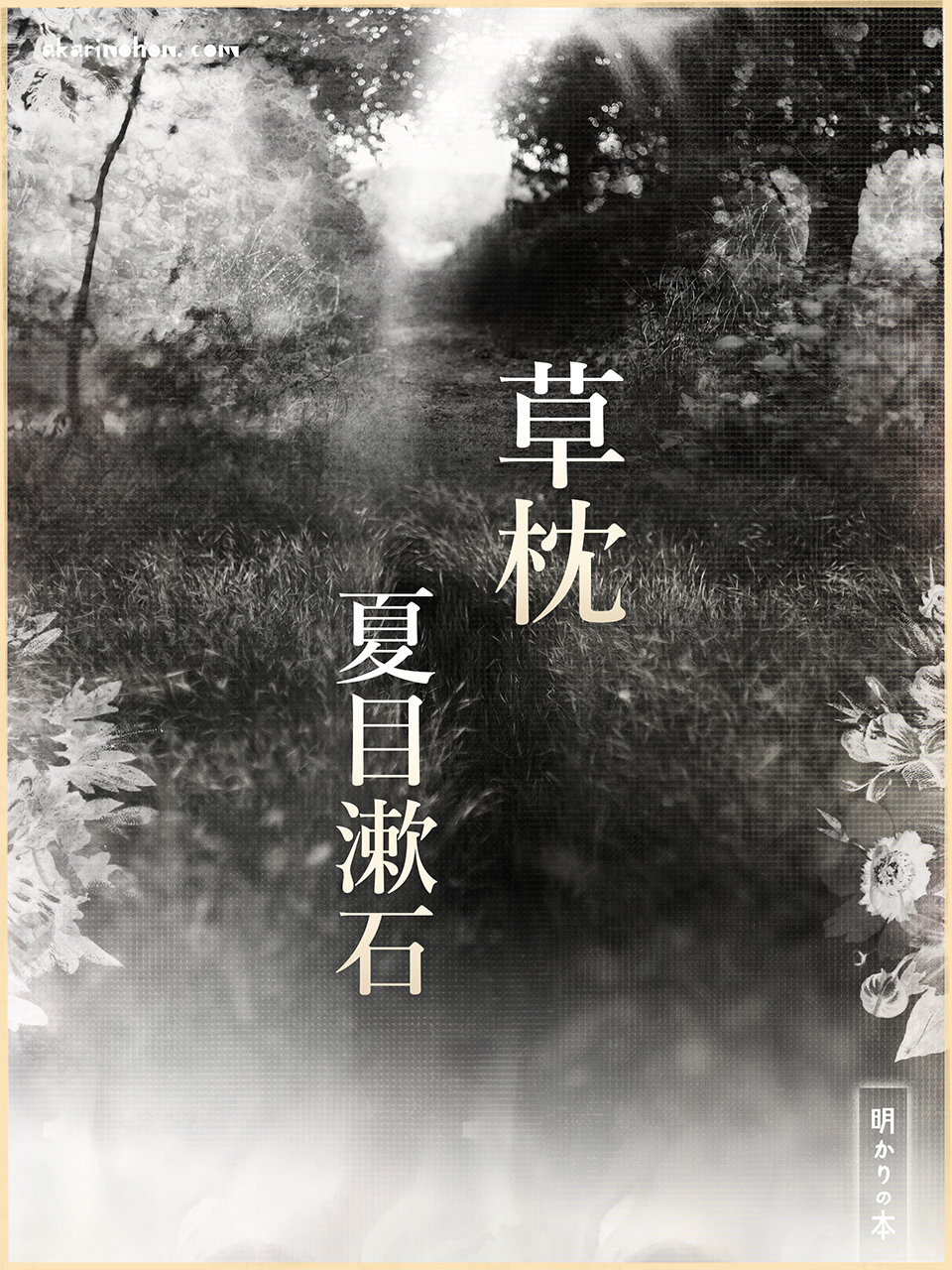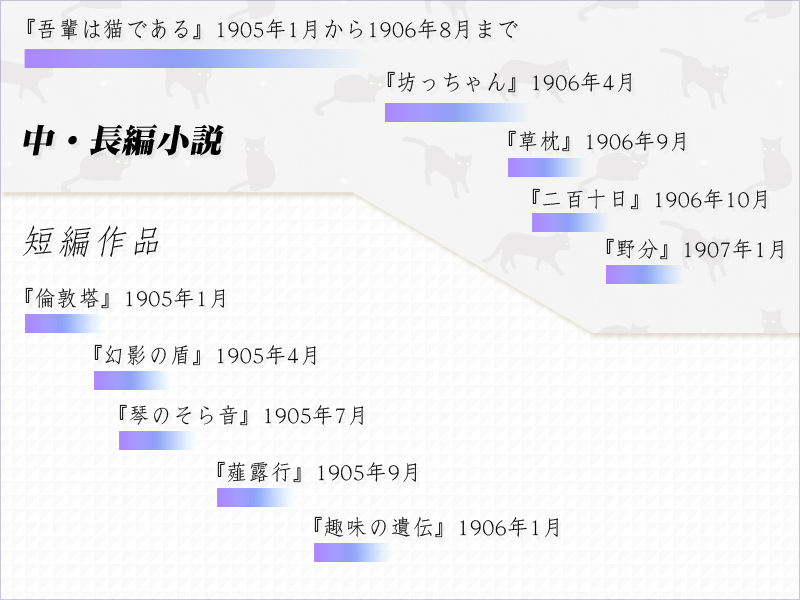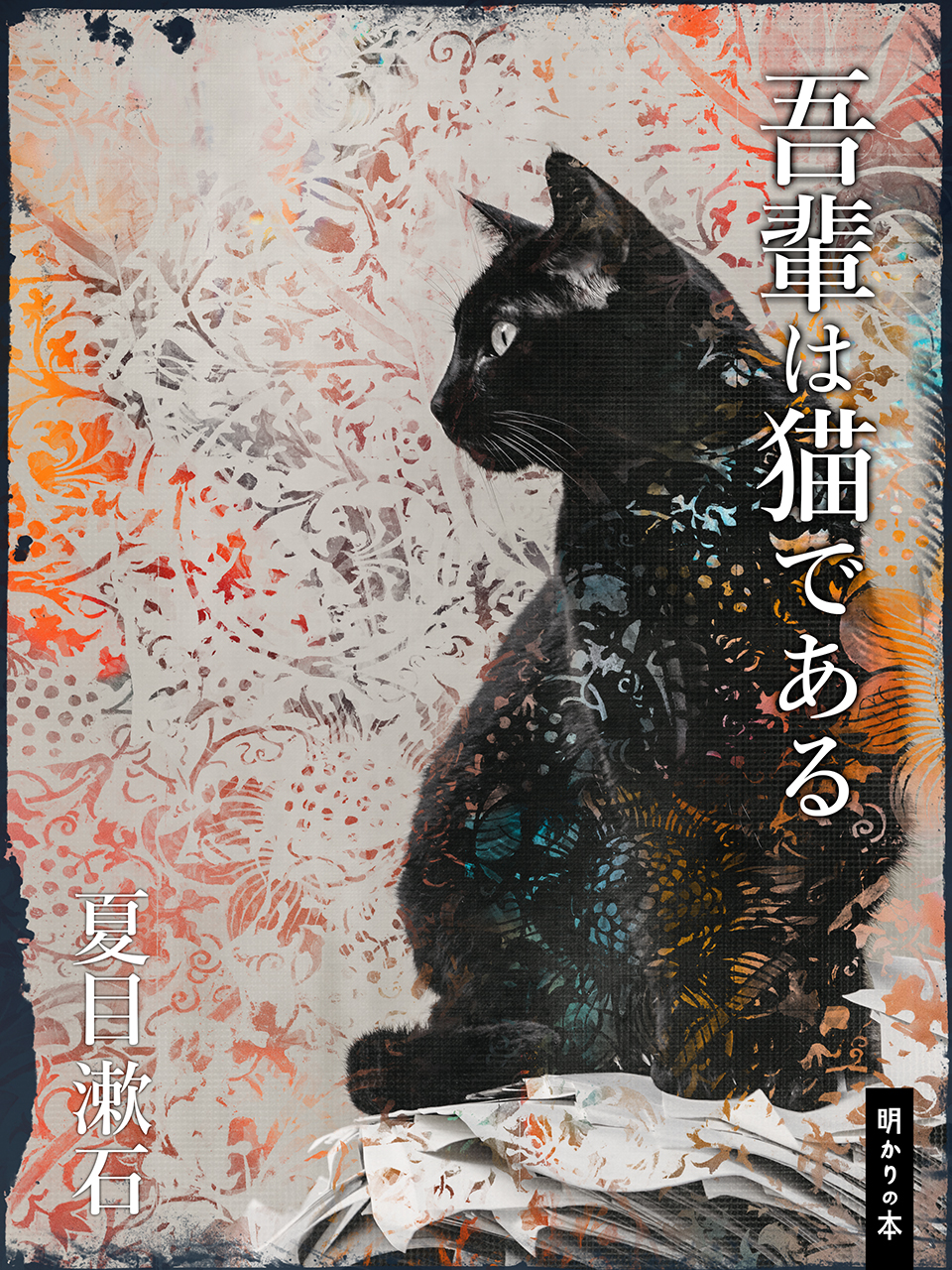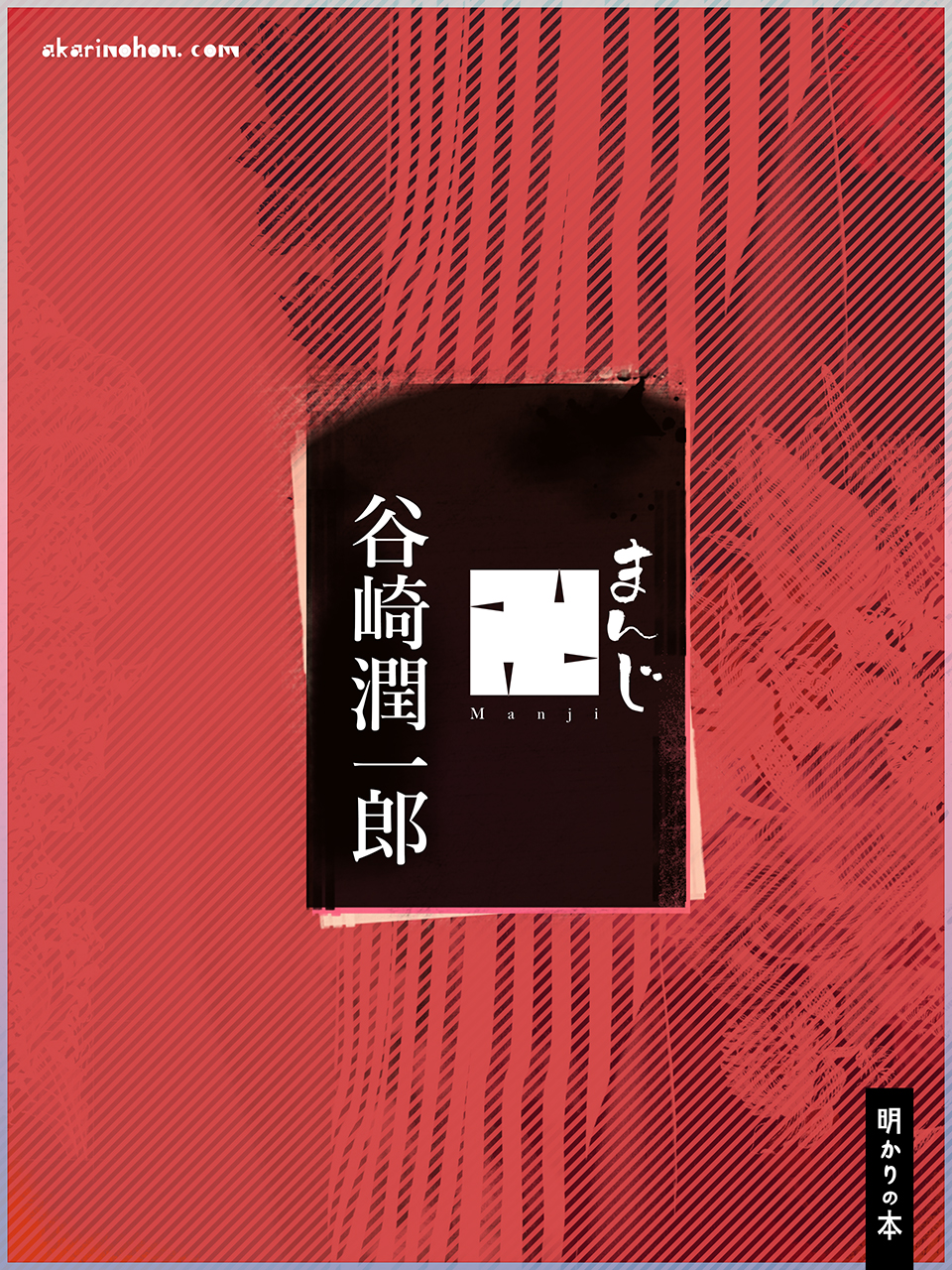今日は、谷崎潤一郎の「吉野葛」を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。
今日から6回に分けて、この小説を読んでゆこうと思います。谷崎潤一郎と言えば「痴人の愛」と「卍」がぼくは大好きなんですが、今回の小説はちょっとけっこう難解なことが書いてあって、ようするにある小説家が、奈良は吉野の南北朝時代に生きた「自天王」と五鬼のことを調査している。吉野の側からみた南北朝時代における伝説についていろいろ論じている。
ところでぼくは知らなかったのですが、五鬼継という家系は今もあって、wikipediaにも掲載されているのでした。
奈良は生駒に鬼取町という村があって、そこでかつて捕らえられた五鬼の子孫……というのが吉野に生きてきたと……。
古い本に書かれた鬼というのはモンスターのことでは無く、人のことをどうも書いているようです。じゃあ古事記の黄泉の国にいる鬼はなんだったんだ、とか思いました。
装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約3秒)
※「吉野葛」全文をはじめから最後まで通読する(大容量で重いです)