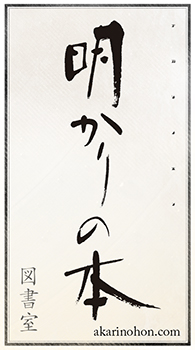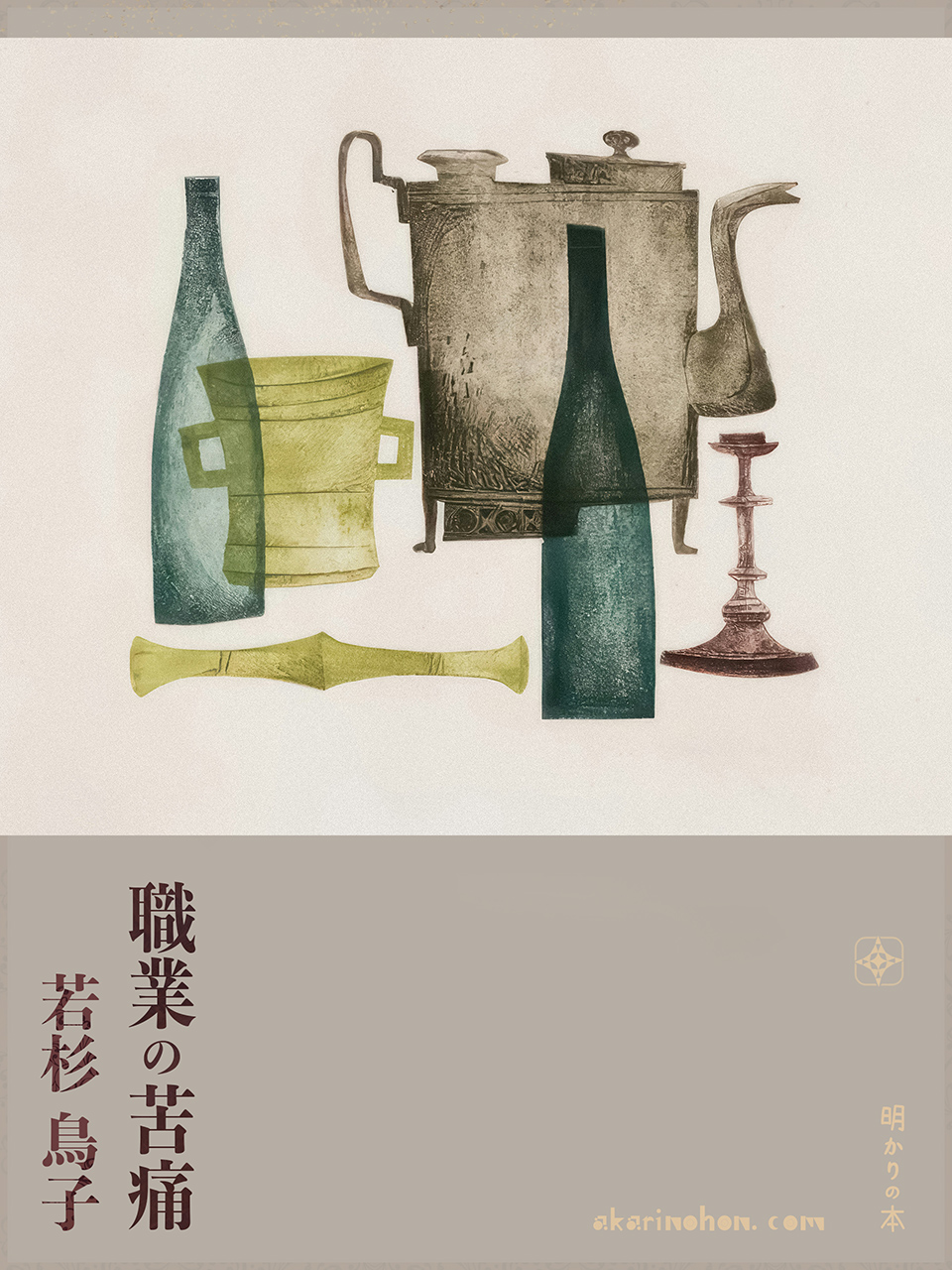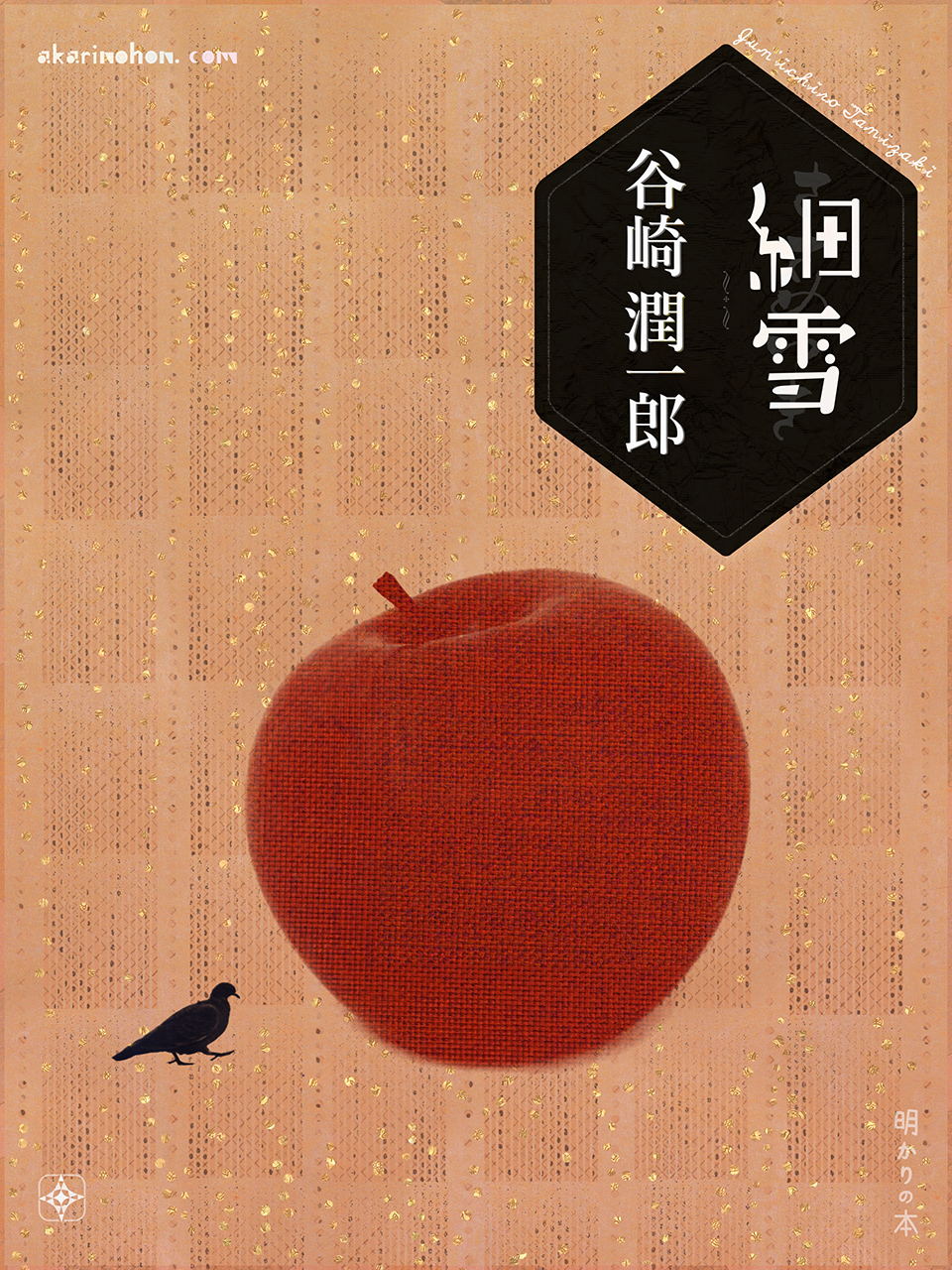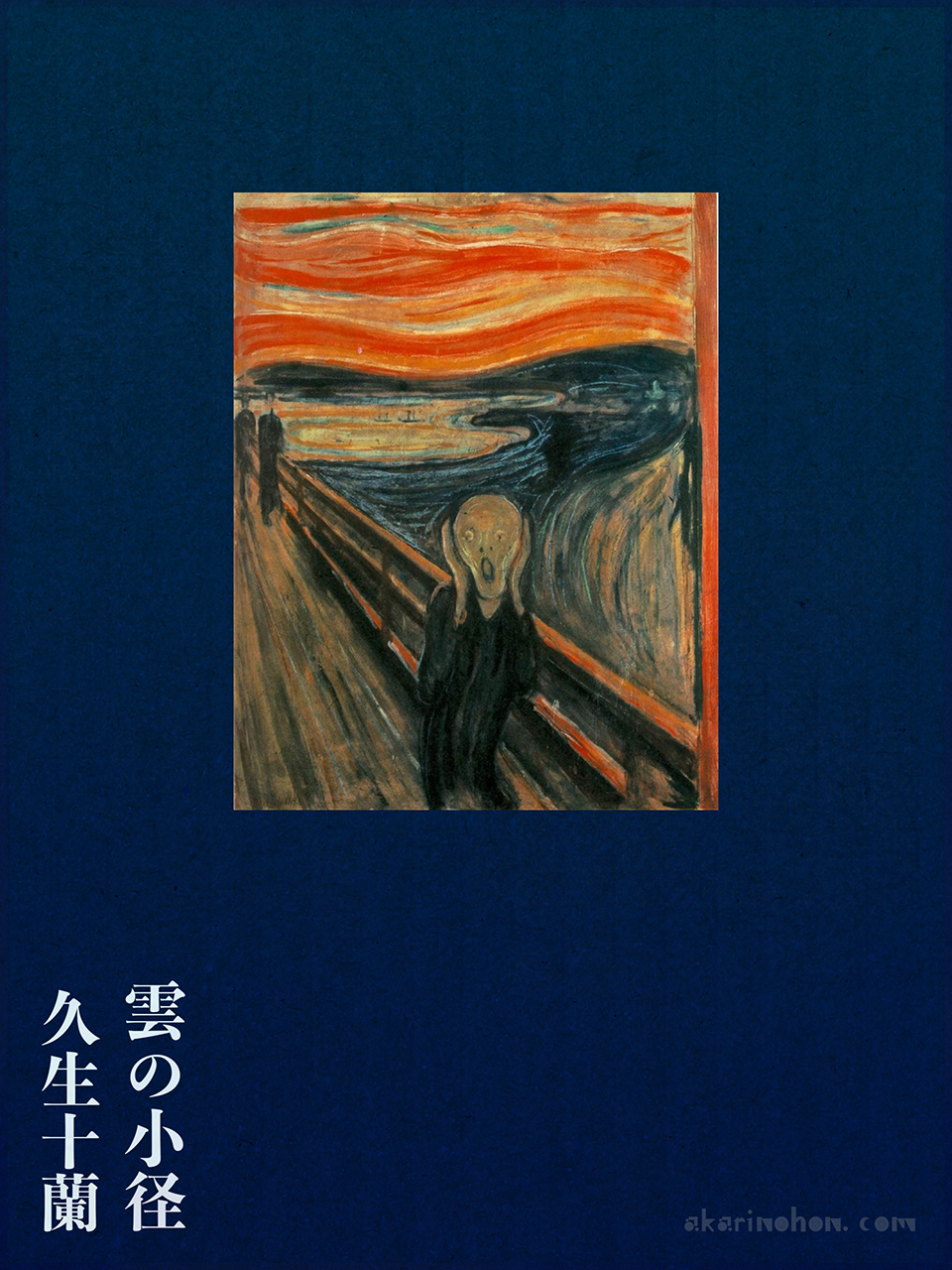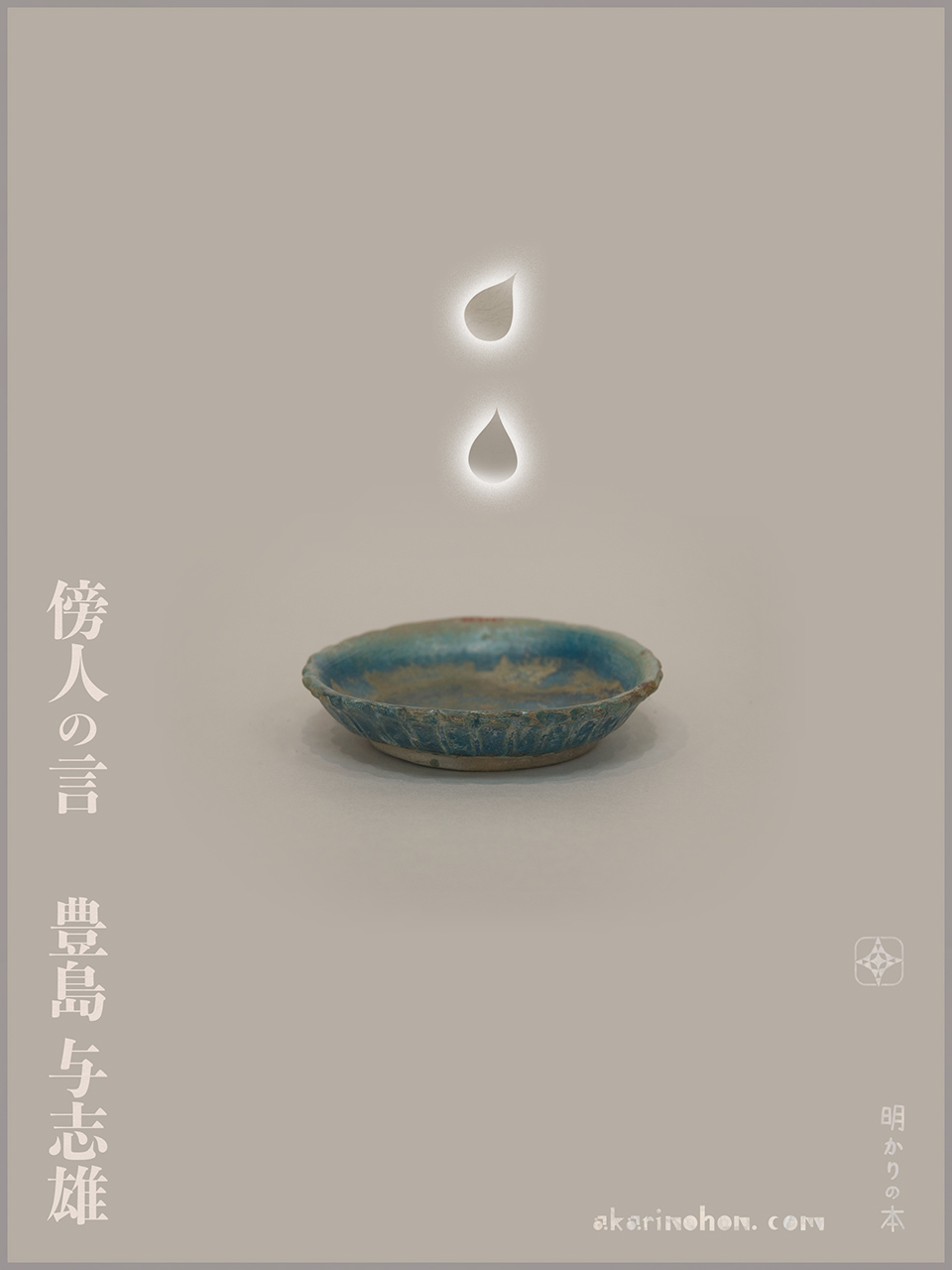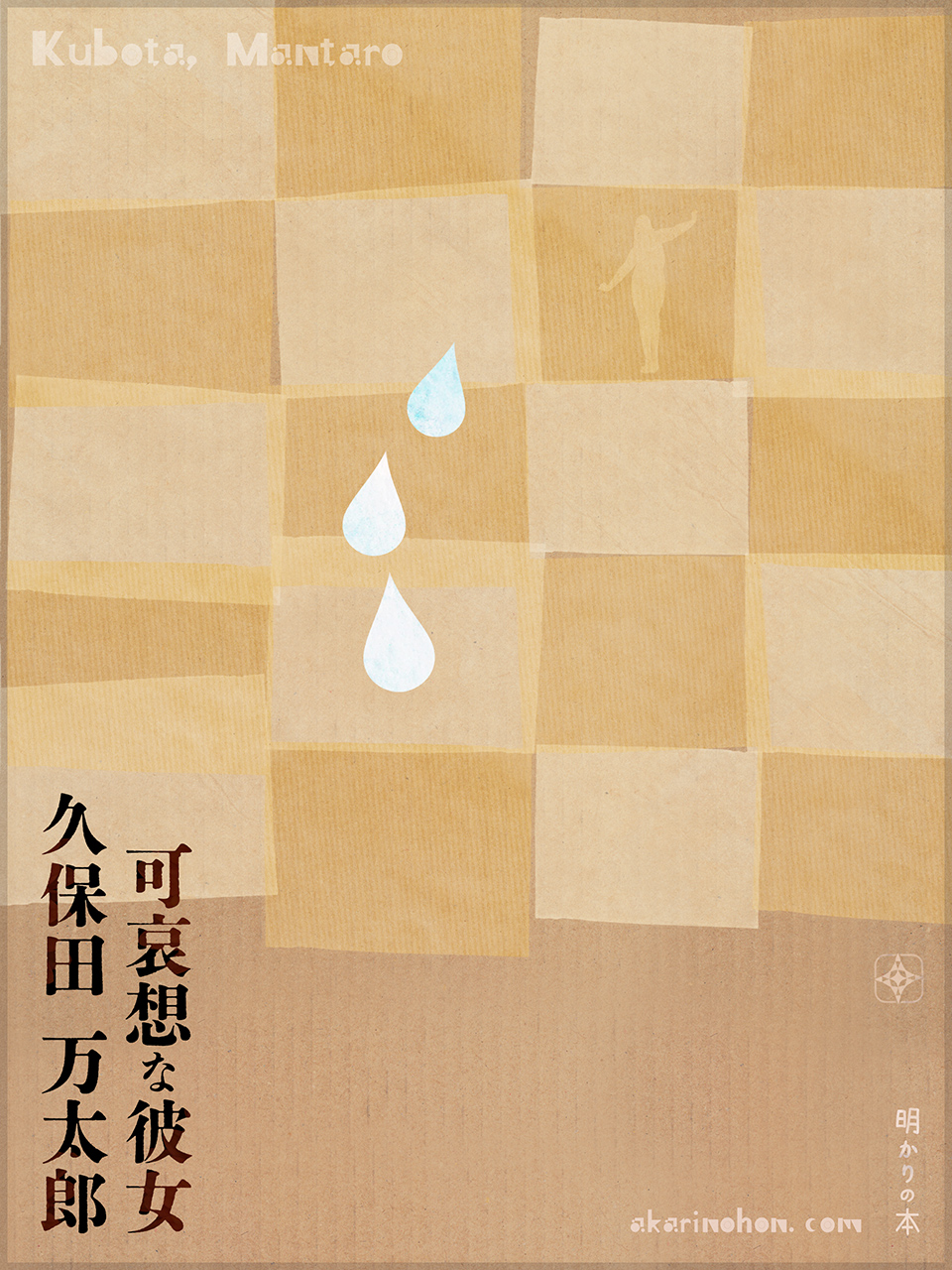今日は、久生十蘭の「雲の小径」を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。
これは飛行機に乗る男を描きだすところからはじまる小説で……「この三年、白川幸次郎は、月に三回、旅客機で東京と大阪をいそがしく往復している」
ある日、白川のところに病院から電話がかかってきて、長らく親交があった「妻の香世子」のことで妙なことを言われるんです。白川は「私には家内なんかありません」と事実を答えるのですが、とにかく病院で手続きをすることとなった。その体験があって、白川は霊との交信に深い興味を持つようになってしまった。作中に記載されているように「西洋の降霊術」を参照して書かれた作品なのでした。
装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)
(総ページ数/約10頁 ロード時間/約5秒)
追記 あまりにもリアルな幻視体験のために、ある男がこの「霊の友会」の悪影響を受け、霊にひっぱられるかたちで、事件が起きてしまった。「霊の友会」はこの事件によって解散となった。それから白川は飛行機で東京と大阪を行き来するようになった。ある日、香世子と仲の悪かった柚子と偶然にも飛行機内で出会ってしまう。このあと、事件の真相究明編が、柚子によって解き明かされてゆくのでした。柚子はとつぜん姿が変貌して香世子になる、という幻視の描写がありました。白川はやっともともとの霊媒を見つけ出して、香世子の霊と話し込むのでした。香世子は死後もまだ犠牲者を求めていた。「おれは死にたくないのだ、助けてくれと叫んだところで、ふっと現実にたちかえった。」で終わる、読後感の悪い小説でした。